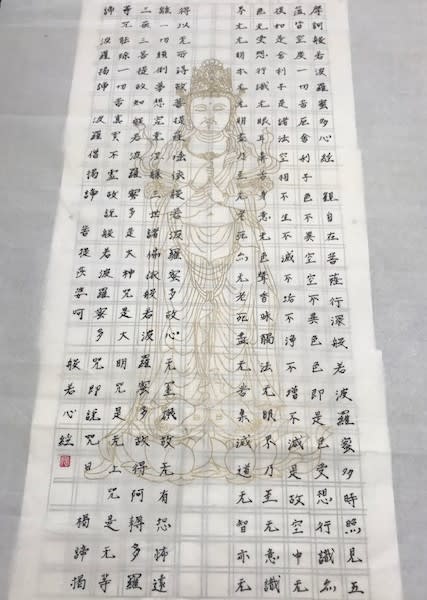大船鉾の軸先に飾られる竜頭が大丸京都店のウインドーにディスプレー
祇園祭の前祭の山鉾巡行が17日に行われ、後祭に引き継がれた。その後祭の山鉾建てが18日から行われ、本日21日から23日までが宵山。そして24日はクライマックスの山鉾巡行。11基が御池通から河原町通を南下し四条通を巡行し、また、傘鉾や馬長稚児、児武者などは四条通を巡行し八坂神社へ。
24日は還幸祭として3基の神輿が四条御旅所を出発し八坂神社に還幸し、神霊を本社に戻す。そして31日に八坂神社で疫神社夏越祭が行われ、鳥居に大茅輪を設け、参拝者は茅輪をくぐり、厄を祓い護符を授かる。この夏越祭を最後に1カ月の行事が終了し祇園祭の幕が下ろされる。
三年ぶりの山鉾巡行ということで、大丸京都店では、京都新聞の協力のもと、祇園祭をより
知っていただこうと懸装品や錺金具などに施された動物をパネル展示で紹介。その写真(パネルを複写)を紹介する。
動く美術館と称される山鉾を飾る「懸装品」は祇園祭の見どころひとつである。京都の絵師が下絵を手掛けた懸装品や、海外から伝来した織物など数多くの装飾品を飾り、それぞれの山鉾が競うかのように飾りたてる。
その中には、たくさんの生き物が存在し、その数130種類以上といわれている。めでたさを象徴する鳳凰や龍といった空想上の珍獣たちが飾られている。それらは山鉾ならではの豪華絢爛の装飾に一役を担っている。それを楽しむのも祇園祭である。
大丸京都店に展示されていたものを改めて紹介する。
- 蝙蝠 木賊山
木賊山の欄縁金具には黒漆仕上げの蝙蝠。金の雲の中を舞い幸福を呼ぶ縁起物とされている

- 鶴 放下鉾
屋根の下の欄縁金具には鶴が飾られ、めでたい縁起物として飾られている

- 蟷螂 蟷螂山
からくり仕掛けの蟷螂は愛嬌たっぷりに飾られている

- 虎 保昌山
円山応挙の下絵で虎が2匹刺繍されている

- 飛龍 太子山
飛龍の錺金具は迫力がある

- 鶏 函谷鉾
関所・函谷関で斉の君子孟嘗君が家来に鶏の鳴声をさせ開門させ難を逃れた故事にまつわり鶏を刺繍に

- 兎 月鉾
屋根の下の欄縁金具には神聖なものの象徴として兎が飾られている

- 鷹 鷹山
200年近くぶりに巡行復帰。懸装品は新調し鉾の名前にちなんで鷹が刺繍された

- 鳳凰 長刀鉾
鳳凰は空想上の生き物で縁起物として数多く使用されている

- 麒麟 山伏山
鳳凰と同様に、空想上の生き物として多く刺繍に使用されている

リポート&写真/ 渡邉雄二 写真/ 大丸京都店で展示されてあるパネル展示を撮影 資料/ 京都新聞祇園祭特集
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
尾道・文化紀行 https://asulight0911.com/hiroshima_onomichi/