
76歩 34歩 22角不成!
その瞬間、あなたは何を思うだろうか。
(あるいは思わないだろうか)
対局が進むとわかってくる。ああ、この棋士は不成の人なのだ。恐らくは完全に必要不可欠でない限り、角を飛び込む時(ほぼ同何かの時)には不成だということがわかってくる。
成っても成らなくても取る一手ならばほぼ(結果は)同じ。
一方で駒は強く使うことが通常だ。角と馬ではその差は歩とと金ほどではない。たとえ取る一手だとしても、歩を不成で使うケースは希だろう。また、銀、桂、香の場合は成れば必ず強くなるとも限らない。不成が現れて何か自然でないと感じるとすれば、圧倒的に角なのだ。たった3手目で実現できるのも角のみだ。
ソフトの桂不成などはおなじみだ。どう考えても成った方がいいと思える場面でも、不成を選択する場面がある。
(取り返す一手ならば同じこと)
合理的に考える人はそう結論づけることができるかもしれない。だが、ソフトと血の通った人間のすることでは、別の意味があると思う人も多いだろう。アナログとデジタルの違いもある。実際の盤では、駒を反転させて成るという行為は、明らかに一手間かかる。秒を読まれてやむなく不成になったという局面はいくらでもある。
将棋ウォーズの場合はどうだろう? 右か左か、どちらも手間は変わらない。むしろ、ほぼ成った方が正解なのであれば、そちら側に癖がついていても自然だろう。完全に手間が同じであるなら、その角不成を棋士はあえて選んで指しているということだ。(面倒で成らないというアナログ的主張は成立しない)
(取る一手ならば同じこと)
同じであるということは、どちらでもいいというになる。問題は何も存在しないとも言える。
どちらでもいい。どうでもいい。これは同じことだろうか?
同じであるはずなのに、決まって不成……
「棋士は、それによって何かを表現しているのではないか」
不成の棋士と対戦した後、僕はぼんやりとそんなことを考えていた。
アナログの名残、弾丸における時間切迫の演出、何らかの怒り、0.1秒と合わせての威圧、合理主義者の矜持、そうした何か、またはそのすべてを語ろうとしている。
あるいは、(表現している)と思わせることに狙いの本質がある場合もあるだろう。もしも、対局中に「表現」などについて考えてしまったとしたら……。それは棋理とはまるでかけ離れすぎている。余計なことを考える内に指し手が乱れ、まともな将棋が指せなくなってしまうことだってあり得るのではないか。
盤を離れてからあれこれ思うことは別に悪くはない。けれども、対局中は局面にだけ集中すべきだ。心の裏まで読み取ろうとする試みには、将棋を壊してしまう危険も潜んでいると知っておきたい。















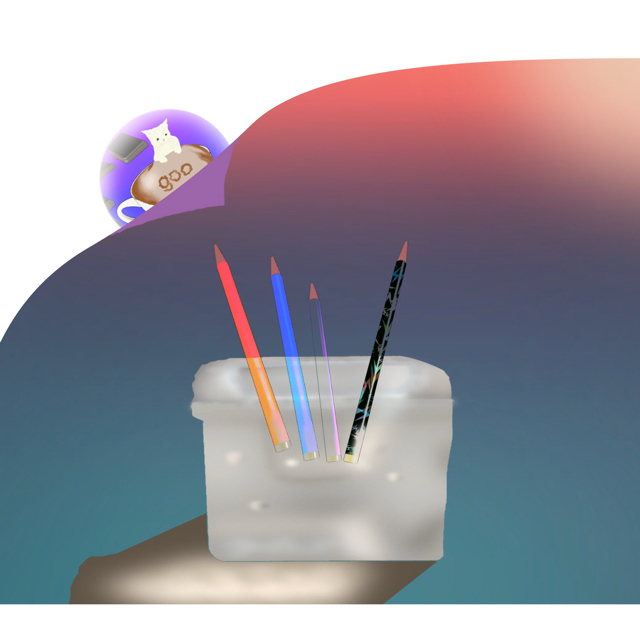

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます