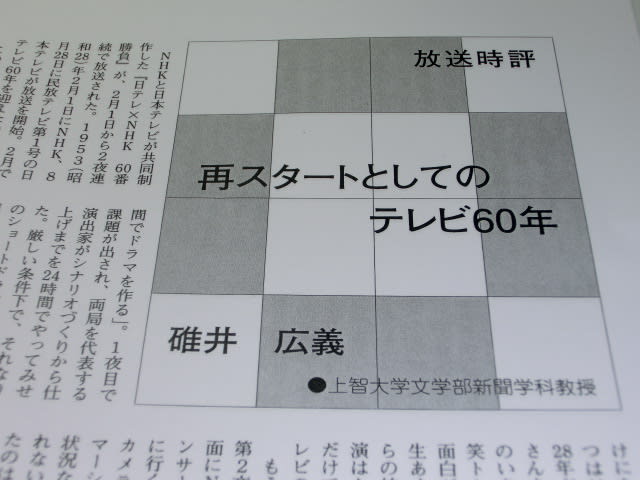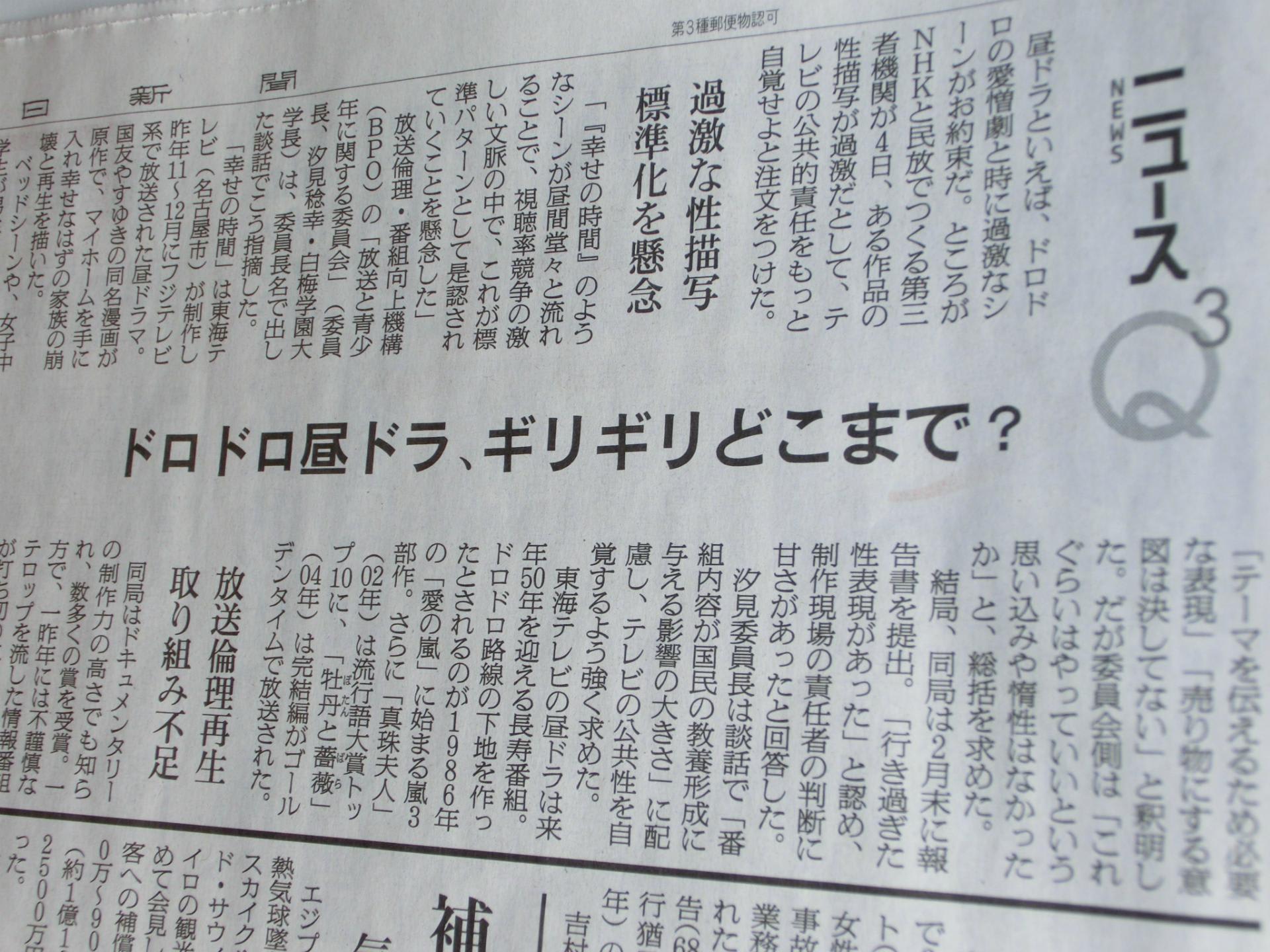橋場先生と事務局の皆さん
この3月で定年を迎える文学部の先生方を「お送りする会」が開かれました。
新聞学科教授の橋場義之先生も、そのお一人。
毎日新聞出身である先生の薫陶を受けて、活字ジャーナリズムの世界に進んだ学生も多い。
厳しく教育すべきところはビシッとする一方で、学生たちと、とことんつき合って下さった橋場先生。
おつかれさまでした。
そして、ありがとうございました!



「月刊民放」3月号の放送時評。
今回は、テレビ60年をテーマに書いています。
再スタートとしてのテレビ60年
NHKと日本テレビが共同制作した『TV60 日テレ×NHK 60番勝負』が、2月1日から2夜連続で放送された。1953(昭和28)年2月1日にNHK、8月28日に民放テレビ第1号の日本テレビが放送を開始。2月でテレビ60年だ。
この特番の目玉企画は「24時間でドラマを作る」。1夜目で課題が出され、両局を代表する演出家がシナリオ作りから仕上げまでを24時間でやってみせた。厳しい条件下で、それなりのショートドラマを作った制作陣には敬意を表すが、当然のことながらやや寒い内容だった。
それよりも、見ていて釘づけになった場面が2つある。1つはNHKが放送した第1夜、28年ぶりの出演だという明石家さんまがスタジオに現れ、過去のいきさつをネタに展開した爆笑トークだ。出演した「クイズ面白ゼミナール」で、さんまが生あくびをしていたと視聴者からの抗議が殺到。以降、本格出演はなかったというのだ。裏話だけでなく、当時の視聴者とテレビの関係性が興味深かった。
もう1つの釘づけシーンは第2夜の冒頭、日本テレビの画面にNHKの有働由美子アナウンサーが登場した時だ。CMに行くタイミングで有働アナがカメラに向かって、「はい、コマーシャル!」とやった。この状況なら当たり前の演出かもしれないが、見ていてドキドキしたのは事実だ。
この2つの場面の面白さを支えていたのは、まず生放送というスタイルだろう。わが家とは別空間であるはずのスタジオの空気や時間を、画面を通じて共有しているという感覚。つながっているという気分である。次に、NHKにいるはずのないさんま、日本テレビで見るはずのない有働アナを目撃したという驚きだ。テレビという日常の中に異分子が混入したことによる非日常性が見る側を興奮させた。人はそこにあるはずのないもの、見るはずのないものに遭遇したら目が離せなくなるのだ。
60年前の草創期、現在とは比べようもないレベルの画質や音質だったにも関わらず、テレビが見る人たちを惹きつけた。それはスポーツ中継であれバラエティーであれ、何が起きるか(飛び出すか)わからない生放送による特別な時間と、テレビでなければ見られないものを目撃する特別な体験だったからではないか。そして、こうしたテレビの力は現在も失われてはいないし、逆にテレビ60年をきっかけに、原点に返るという意味で再考に値するのではないか。この記念特番を見ながら、そんなことを思った。
もちろん、現在のテレビはのんきに還暦を祝っていられる状況ではない。ネットの台頭。視聴者のテレビ離れ。広告収入の減少。加えて原発事故をめぐって広まったテレビ報道への不信感もある。しかし、もしもテレビが劣化していると言うなら、それはテレビそのものではなく、テレビに関わる人たちの劣化かもしれないのだ。あえて青臭いことを言えば、テレビに関わる人間の志の問題である。
ここで思い浮かぶのが、1974年の秋から翌年3月まで放送された、フジテレビのドラマ『6羽のかもめ』のことだ。その最終回「さらばテレビジョン」の劇中劇で、政府は国民の知的レベルを下げることを理由に(セリフでは「これ以上の白痴化を防ぐために」)、国民に対してテレビ禁止令を出す。テレビ局は全て廃止。各家庭のテレビは没収。禁酒法時代の酒と同じ扱いとなるという設定だ。ドラマの終盤、山崎努演じる放送作家が酒に酔った勢いでカメラに向かって自分の思いをぶつける。あの伝説の名セリフが飛び出すシーンだ。脚本は倉本聰さん。
「だがな一つだけ言っとくことがある。(カメラの方を指さす)あんた!テレビの仕事をしていたくせに、本気でテレビを愛さなかったあんた!(別を指さす)あんた!――テレビを金儲けとしてしか考えなかったあんた!(指さす)あんた!よくすることを考えもせず偉そうに批判ばかりしていたあんた!あんた!! あんたたちにこれだけは言っとくぞ!何年たってもあんたたちはテレビを決してなつかしんではいけない。あの頃はよかった、今にして思えばあの頃テレビは面白かったなどと、後になってそういうことだけは言うな。お前らにそれを言う資格はない。なつかしむ資格のあるものは、あの頃懸命にあの情況の中で、テレビを愛し、闘ったことのある奴。それから視聴者――愉しんでいた人たち」
倉本さんが、ドラマの中のドラマという二重構造に仕込んで投げつけた時限爆弾は、テレビ60年を迎えた現在も、そのカウントダウンを続けている。
(月刊民放 2013年3月号)
東京新聞に連載中のコラム「言いたい放談」。
今回は、tvkのドキュメンタリードラマ『希望の翼~あの時、ぼくらは13歳だった』について書きました。
時間と国境を越えた友情
二日の夜、ドキュメンタリードラマ『希望の翼~あの時、ぼくらは13歳だった』を見た。tvk(テレビ神奈川)と韓国KBSの共同制作によるものだ。
一九四五年、日本の植民地支配下にあった朝鮮半島で二人の中学生が出会う。実在の日本人、寒河江正(さかえ・ただし)と韓国人の羅逸星(ナ・イルソン)だ。当時、校内で朝鮮語は禁じられていたが、羅はつい口にしてしまう。非難する日本人の同級生たち。その時、寒河江が叫ぶ。「朝鮮の人たちが朝鮮語を話して何が悪い!」
こうして始まった友情も日本の敗戦で途切れてしまう。再会できたのは四十一年後のことだ。寒河江は音楽プロデューサーに、羅は天文学者になっていた。一昨年、二人は対談と記録で構成された共著『あの時、僕らは13歳だった~誰も知らない日韓友好史』を上梓したが、それがこのドラマの原作である。
主演、国広富之。総合監督は『岸辺のアルバム』の大山勝美だ。描かれる戦時中のエピソードはもちろんだが、韓国で日本文化が開放される以前から寒河江たちが続けてきた、音楽による民間交流の取り組みも見どころだ。そこには互いの歴史と文化に対する敬意がある。
二十三日の午後二時からBS-TBSでも放送される。Tvkは二十七日午後七時から再放送。若者を含む幅広い年代の人たちに見てもらえたらと思う。
(東京新聞 2013.03.06)
3月21日(木)に開催する「放送批評懇談会シンポジウム2013」
まで、あと2週間となりました。
参加申込みの締切が13日(水)ですので、ご注意ください。
放送批評懇談会シンポジウム2013
ローカルパワーの創り方
ローカルパワーの創り方
<開催趣旨>
2013年は日本でテレビ放送が始まってから60周年にあたります。また東日本大震災から2年が経ち、被災地の放送局の地デジ化も完了して、文字通り日本のテレビはデジタル・メディアの一員となりました。この間、政治や経済はもちろん、メディアの世界も大きく動いてきました。特にソーシャルメディアを中心とするウェブの積極的な活用は、放送界においても日常化していますが、まだまだ手探りの状態が続いています。
中でもローカル局における課題は山積するばかりです。地方経済の冷え込みの中で、地デジ化の経済的負担は解消されていません。自社制作番組というコンテンツ作りも成功事例ばかりではありません。データ放送の活用、オンデマンドやアプリの開発などの取り組みも簡単には進みません。しかし、各地域の住民と直接コミュニケーションを行っているローカル局の活性化なくして、今後の放送界の発展を望むことができないのも事実です。
そこで放送批評懇談会シンポジウム2013は、「ローカルパワーの創り方」をテーマに、番組コンテンツから放送外収入まで、ローカル局が抱える課題を取り上げ、これと向き合い、一緒に考えたいと思います。放送というメディアのあり方そのものが問われる時代だからこそ、“ローカル局の明日”へのヒントを探っていきます。
<日 時> 2013年3月21日(木曜日)13:00~17:00
<会 場> 海運クラブ 2階ホール (東京都千代田区平河町)
<主 催> NPO法人放送批評懇談会
<対 象> 民放、NHK。番組制作会社。企業のメディア担当者。通信事業者。衛星放送事業者。ケーブルTV。インターネット関連会社。広告会社。新聞社、出版社。官公庁。自治体。各種権利団体。大学・研究者ほか。
放送批評懇談会シンポジウム2013
ローカルパワーの創り方
【基調講演】
デジタル時代の放送哲学
~ローカリズムとデジタルヒューマニズム~
テレビマンユニオン会長
ゼネラルディレクター 取締役
重延 浩
【特別講演】
ローカルパワーを応援!
~全国47都道府県芸人移住プロジェクト~
よしもとクリエイティブエージェンシー
代表取締役副社長
泉 正隆
【プレゼンテーション】
ローカルパワーで挑む新ビジネス
テレビドキュメンタリーの劇場展開
東海テレビ放送プロデューサー
阿武野勝彦
デジタルサイネージで新たな収入構築
北陸朝日放送コンテンツ企画部
伊藤祐介
ローカル発のVOD事業をリードする
北海道テレビ放送取締役
上杉一紀
地場産業と歩む放送局
MBC開発代表取締役社長
陶山賢治
独立局コンテンツの“創意工夫”
テレビ神奈川編成局長
関 佳史
司会/碓井広義 上智大学教授
ローカルパワーの創り方
【基調講演】
デジタル時代の放送哲学
~ローカリズムとデジタルヒューマニズム~
テレビマンユニオン会長
ゼネラルディレクター 取締役
重延 浩
【特別講演】
ローカルパワーを応援!
~全国47都道府県芸人移住プロジェクト~
よしもとクリエイティブエージェンシー
代表取締役副社長
泉 正隆
【プレゼンテーション】
ローカルパワーで挑む新ビジネス
テレビドキュメンタリーの劇場展開
東海テレビ放送プロデューサー
阿武野勝彦
デジタルサイネージで新たな収入構築
北陸朝日放送コンテンツ企画部
伊藤祐介
ローカル発のVOD事業をリードする
北海道テレビ放送取締役
上杉一紀
地場産業と歩む放送局
MBC開発代表取締役社長
陶山賢治
独立局コンテンツの“創意工夫”
テレビ神奈川編成局長
関 佳史
司会/碓井広義 上智大学教授
<受講料>
放送批評懇談会正会員(個人)5,000円 維持会員(法人)15,000円 一般20,000円/いずれも資料つき
*維持会員社の社員・職員の方は、維持会員枠でお受付いたします。
<振込先>
三井住友銀行新宿通支店 普通口座7955764
口座名=特定非営利活動法人放送批評懇談会
<定員>
200名(先着順受付)
<申込締切>
3月13日(水曜日)(ただし、定員になり次第、締め切らせていただきます)
朝日新聞の「ニュースQ3」コーナー。
昼ドラ「幸せの時間」をめぐる、BPOと制作した東海テレビの動きを報じていました。
この記事の中で、コメントしています。
ドロドロ昼ドラ、ギリギリどこまで?
昼ドラといえば、ドロドロの愛憎劇と時に過激なシーンがお約束だ。ところがNHKと民放でつくる第三者機関が4日、ある作品の性描写が過激だとして、テレビの公共的責任をもっと自覚せよと注文をつけた。
■過激な性描写、標準化を懸念
「『幸せの時間』のようなシーンが昼間堂々と流れることで、視聴率競争の激しい文脈の中で、これが標準パターンとして是認されていくことを懸念した」
放送倫理・番組向上機構(BPO)の「放送と青少年に関する委員会」(委員長、汐見稔幸・白梅学園大学長)は、委員長名で出した談話でこう指摘した。
「幸せの時間」は東海テレビ(名古屋市)が制作し昨年11~12月にフジテレビ系で放送された昼ドラマ。国友やすゆきの同名漫画が原作で、マイホームを手に入れ幸せなはずの家族の崩壊と再生を描いた。
ベッドシーンや、女子中学生が男性の前で服を脱ぐ場面などの描写が週刊誌やネットで話題になった。BPOには「行き過ぎではないか」など3桁に近い数の批判が寄せられ、「放置できない」(汐見委員長)として審議していた。
■必要主張の局、指摘受け反省
局側は当初、性描写を「テーマを伝えるため必要な表現」「売り物にする意図は決してない」と釈明した。だが委員会側は「これぐらいはやっていいという思い込みや惰性はなかったか」と、総括を求めた。
結局、同局は2月末に報告書を提出。「行き過ぎた性表現があった」と認め、制作現場の責任者の判断に甘さがあったと回答した。
汐見委員長は談話で「番組内容が国民の教養形成に与える影響の大きさ」に配慮し、テレビの公共性を自覚するよう強く求めた。
東海テレビの昼ドラは来年50年を迎える長寿番組。ドロドロ路線の下地を作ったとされるのが1986年の「愛の嵐」に始まる嵐3部作。さらに「真珠夫人」(02年)は流行語大賞トップ10に、「牡丹(ぼたん)と薔薇(ばら)」(04年)は完結編がゴールデンタイムで放送された。
■放送倫理再生、取り組み不足
同局はドキュメンタリーの制作力の高さでも知られ、数多くの賞を受賞。一方で、一昨年には不謹慎なテロップを流した情報番組が打ち切りになった。
元同局社員の磯野正典・金城学院大教授(メディア論)は「再生への取り組みが現場でできていない。より意外性のある過激さで話題作りを狙ったのでは」。
実際、「幸せの時間」は次回予告に過激シーンを入れ、番組ホームページでは「このドラマの過激さはギリギリ限界」とPRした。フジテレビ関係者は「ちょっとしたことにも敏感な時代だということは認識すべきだったかもしれない」。他系列の名古屋局プロデューサーは「性描写が直接的で、昼間に地上波でやる内容じゃなかった」と語る。
東海テレビは4日、「不快な思いをされた視聴者の皆様には深くおわび申し上げます」とコメントを発表。担当取締役の役員報酬を1カ月10%カット、制作局の責任者やプロデューサーを減給や厳重注意とする処分を公表した。
碓井広義・上智大教授(メディア論)は「表現を巡る議論を深めることが必要なのに、処分はタブー化を招く。現場が萎縮する恐れはないか」と話す。
(高橋昌宏)
朝日新聞 2013.03.05

日刊ゲンダイに連載中の「TV見るべきものは!!」。
今週は、NHK「マイケル・サンデルの白熱教室@東北大学」について書きました。
マイケル・サンデルの白熱教室@東北大学
「思考と議論の道場」だ
「思考と議論の道場」だ
日本でもすっかりお馴染みになったハーバード大学のマイケル・サンデル教授。先週末、NHKでシリーズ最新作「マイケル・サンデルの白熱教室@東北大学」が放送された。サブタイトルは「これからの復興の話をしよう」。学生と市民、1000人が集まった。
過去の「白熱教室」では架空の課題を設定していたが今回は違う。「自主避難と補償」「人命救助と犠牲」など話は極めて具体的だ。まず感心するのは、会場にいる人たちを議論に巻き込んでいく手腕だ。二者択一の質問を投げかけ、参加者に選択の理由を述べてもらう。また反論や再反論の合間に論点を素早く整理し、議論が堂々巡りにならないよう配慮するのだ。
最も盛り上がったのは、復興に際して合意とスピードのどちらを優先させるかという議論だった。若者が住民の意見を一致させることの必要性を主張すると、シニア世代の男性が「それは絵に描いた餅」と反論。さらに別の男性が「合意というより納得が大事。それには時間も必要」と訴える。最後に教授は、他者の意見を理解し、敬意をもって議論することの大切さを説いていた。
自分の頭で考え、それを言語化する。同時に他者の意見に耳を傾ける。その上で自ら判断を下さなくてはならない時代。サンデル教授とこの番組は、「思考と議論の道場」としてかなり有効だ。
(日刊ゲンダイ 2013.03.05)
ああ、そういえば、以前はビニールのカバーをまとった本が、よく書店に並んでいたなあ。
ジャズ評論家・寺島靖国さんの近刊『JAZZ偏愛主義』(DU BOOKS)を手にとって、そんなことを思った。
これ、大きさは文庫本サイズで、厚さは2センチくらい。前述の透明な
ビニールカバーがかけられている。ちょっと懐かしい感触だ。
こういうのって、やはり、人の手で1冊ずつ作業するんだろうか。
ならば、ご苦労さまです。
200枚のJAZZレコード、じゃなくてCDを紹介している。新譜中心で。
寺島さんのウンチク、独断と偏見、いや偏愛を楽しむ一冊です。

さて、今週の「読んで、書評を書いた本」は、以下の通りです。
小林信彦
『私の東京地図』 筑摩書房
石村博子
『孤高の名家 朝吹家を生きる 仏文学者・朝吹三吉の肖像』
角川書店
ウンベルト・エーコ リッカルド・アマディ:訳
『歴史が後ずさりするとき』 岩波書店
円堂都司昭
『ディズニーの隣の風景~オンステージ化する日本』 原書房
* 上記の本の書評は、
発売中の『週刊新潮』(3月7日号)
Bookworm欄に掲載されています。
北海道新聞に連載している「碓井広義の放送時評」。
今回は、この冬の連ドラについて書きました。
早いもので、今期も、すでに終盤。
やや、どんぐりのナントカみたいな状況ですが(笑)、それぞれ健闘中ではあります。
そんな中から、3本をピックアップしました。
注目すべき冬ドラマ
今という時代の人間像体現
今という時代の人間像体現
今期の連続ドラマもあと数回を残すのみとなった。起承転結でいえば最終コーナーを回るところだ。目立つようなヒット作はないものの、注目すべきドラマが何本かある。
まずは『最高の離婚』(フジテレビ―UHB)だ。尾野真千子と瑛太、真木よう子と綾野剛。人気の女優と俳優の組み合わせだが、それだけではない。物語の中で飛び交う結婚と離婚に関する本音が刺激的なのだ。
「妻って結局、鬼嫁になるか、泣く妻になるのかの二択しかないのよ」と尾野が叫び、夫である瑛太は、「結婚は3Dです。打算、妥協、惰性。そんなもんです」とつぶやく。どちらの夫婦にも子供はなく、いわば緩衝材のないまま互いと向き合う危うさがある。恋愛と結婚の違い。男女間の目線の落差。一昨年の『それでも、生きてゆく』で芸術選奨新人賞を受けた坂元裕二の脚本が光っている。
次が架空の高級住宅地を舞台としたミステリードラマ『夜行観覧車』(TBS―HBC)である。平均的サラリーマンの宮迫博之と鈴木京香が娘と共に引っ越してきたのが2009年のことだ。4年後、向かいに住む開業医の家で惨劇が起きる。夫が何者かに殺され、妻の石田ゆり子と次男が姿を消す。4年の間に何があったのか。犯人は誰なのか。過去と現在を往復する巧みな構成が効いている。
原作は『告白』の湊かなえの小説だ。『最高の離婚』と違って、ここでは子供との確執や地域との軋轢もテーマになっている。住宅街の主(ぬし)とも言える自治会婦人部長・夏木マリの怪演も見逃せない。
そして、もう1本が『まほろ駅前番外地』(テレビ東京―TVH)。一昨年映画化された『まほろ駅前多田便利軒』(原作・三浦しをん)の続編であり、映画の続きとしてドラマが作られる逆パターンは珍しい。キャストは映画と同じ瑛太と松田龍平だ。瑛太は東京郊外の「まほろ市」で便利屋を営む。中学時代の同級生である松田は、瑛太の事務所に居候しながら仕事を手伝っている。
大きな事件が起きるわけではない。また彼らはいわゆるヒーローでもない。むしろ困った大人たちである。しかし、ストーリーもさることながら、ワケあり男2人の微妙な間合いや、周囲の人たちとの関係から生まれる空気感が実に心地いいのだ。特に瑛太の飄々としていながらどこか芯がある行動や、にじみ出るユーモアは一見の価値がある。『最高の離婚』と併せて、今という時代、この世代の人間像を体現しているからだ。
(北海道新聞 2013.03.04)
2008年4月に始めた、この「碓井広義ブログ」。
トータルのアクセス数が、300万に達しました。
ありがとうございます!
完全に自分の生活の中に組み込まれているので、書かないで眠ろうとして、忘れ物に気づいたように飛び起きたりします。
それに、最近では、少し前のことも覚えていなかったりするので(大丈夫か、私)、こうして記録が残されているのは、とても有難い。
また、初めてお会いする方に、「ブログ、以前から拝見しています」と言われたりすると、嬉しかったり。
まあ、そんなこんなで、これからも専門であるテレビををはじめ、あれやこれやについて書いていきますので、引き続き、どうぞよろしく、
お願いいたします。
急に、すごく太い字の書ける万年筆が欲しくなって、パイロット・カスタム74の「特太」というのを入手。
「太字」、「極太」とあって、その上が「特太」なのだ(笑)。
カスタム74自体は、まあ、ごく普通の万年筆なのですが、先日、テレビでパイロットの社内や仕事の様子を見る機会があり、「うーん、パイロット、真面目だなあ」と思ったので、パイロットにしたのです。

インクは、この万年筆にはブルーを入れたかったので、同じパイロットの「asa-gao 朝顔」にしました。
ボトルのデザインも美しい。
これが、かなりいい色で、今、慣らし運転中にもかかわらず、ずんずん書いています。

ああ、びっくりした。
「インターFM」を聴いていたら、ホキ徳田さんが出てきたのだ。
でもね、あの「北回帰線」の、あのヘンリー・ミラーの、奥さんだった「ホキ徳田」さんですよ。
そのホキさんが、ラジオでピアノを弾きながら、ジャズを歌っているのだ(だってジャズ歌手だもん)。
ヘンリー・ミラーって、確か生誕120年とか、没後30年とかも過ぎてるはずで、失礼ながら、その元奥さまが、お元気だとは知らなかった。
しかも、ラジオ番組まで持っていらして、「ホキ徳田のYUMMY MUSIC」(土曜24:00~25:00)。
いや、ほんと失礼しました。
そういえば、ホキ徳田さんがヘンリー・ミラーと結婚した時、2人は45歳くらい離れていて、それが話題になったんだもんなあ(笑)。
ホキさんがお元気でも、何らおかしくないわけで、私の完全な思い込みでしたね。
この番組、来週も聴いてみよっと。
発売中の「週刊新潮」最新号で、NHK朝ドラ「純と愛」で放送された、「火事場シーン」についてコメントしました。
記事は以下の通りです。
燃え盛る家屋に飛び込むとは
非常識なり「純と愛」
非常識なり「純と愛」
轟々と燃え盛る、ホテル「里や」。寝タバコによる2階からの失火は、たちまち3階建ての建物全体に広がる――そんな光景が放映されたのは、NHK連続テレビ小説「純と愛」第120回、2月22日のことだった。
燃えゆく「里や」を呆然と見つめるひとびと。ふと、板前の藍田忍(田中要次)が気づく。「里や」女将・サト(余貴美子)の亡夫の形見である三線(さんしん)がないのだ。
藍田は制止を振り切り、赤々とした屋内へ。焼けた梁が落ちる。
だが藍田はすぐに飛び出してきた。三線を抱えたその顔は、煤けていた・・・。
もちろんこれはドラマだ。現実にはありえないことが起きても構わない。だがアクションドラマじゃあるまいし、猛火の中に飛び込むなんて非常識なのでは?
「“火事場の馬鹿力”なんて言葉はありますが、あのシーンは、危険を冒して飛び込んでいくのが納得できる状況ではありませんよ」
と言うのは、碓井広義・上智大学教授(メディア論)。
「東日本大震災での教訓は“災害に遭ったらまず逃げろ”です。ましてこの場面、人命ではなく“モノ”を救い出すために無茶をしている。これはあまりにリアリティのない自己犠牲で、“無謀の二乗”としか言いようがありません」
このドラマ、ヒロインの純(夏菜)が、祖父が沖縄で経営していた“魔法の国”のような理想のホテルを目指して奮闘する、というストーリーなのだが、実家のホテルはなくなり、就職した一流ホテルは買収され、父親は事故死。
「ヒロインの居場所が次々に消えるという流れになっています。そして今度は、居場所そのものを焼き払った。意外性を求めすぎて、かえって作為を感じさせますね」(同)
“火事現場への飛び込み”はその顕著な例、というところか。すでにクランクアップし、放送も残り1ヶ月、果たして純に“居場所”はできるのだろうか・・・。
(週刊新潮 2013.03.07号)