デジタル化の行方 第3部 溶ける公教育③ 命を守る力つくのか
和光大学の制野俊弘准教授(体育科教育学)は、宮城県東松島市の中学校教師時代、水泳では「進む」こと中心ではなく、「呼吸」に中心をおいたドル平(どるひら)と呼ばれる泳法の指導に力を入れました。同県を巨大な津波が襲った2011年の東日本大震災。教え子の一人は津波で川に流されドル平で九死に一生を得ました。一方、津波で命を落としたなかに授業でドル平を教えきれなかった子どもがいました。
制野さんは「水泳の授業で自分の命を守る力を子どもたちにつけることは、公教育の最低限の使命」と胸に刻みます。
実施せず
小中学校のプールを徐々に廃止し、企業や区立の学校外プールへ移行すると決めた東京都葛飾区。これまでほぼ全学校で実施してきた水難事故を想定した着衣泳が、今年度は学校外プールを利用した12の小中学校では実施されませんでした。区の担当者は、着衣泳は学習指導要領で必修とされておらず、着衣泳を拒否した民間1施設を除き、実施しなかったのは各学校の判断だといいます。
同区の場合、学校外プールでは企業のインストラクターが指導に当たります。現場でインストラクターに教師が指示を出すと偽装請負になります。区の担当者は、教師が立てた授業計画に基づき事前に複数回打ち合わせしており、民間の専門性が生かされ教師の負担軽減にもなっているといいます。民間の専門性を活用して個別最適な教育を実現する、という政府方針にも符合しますが…。
「教育委員会に提出する書類作業などに追われ昨日も学校を出たのは夜の11時。企業と事前に打ち合わせする時間なんて教師にありません。体育主任は顔合わせくらいしているかもしれないけど」
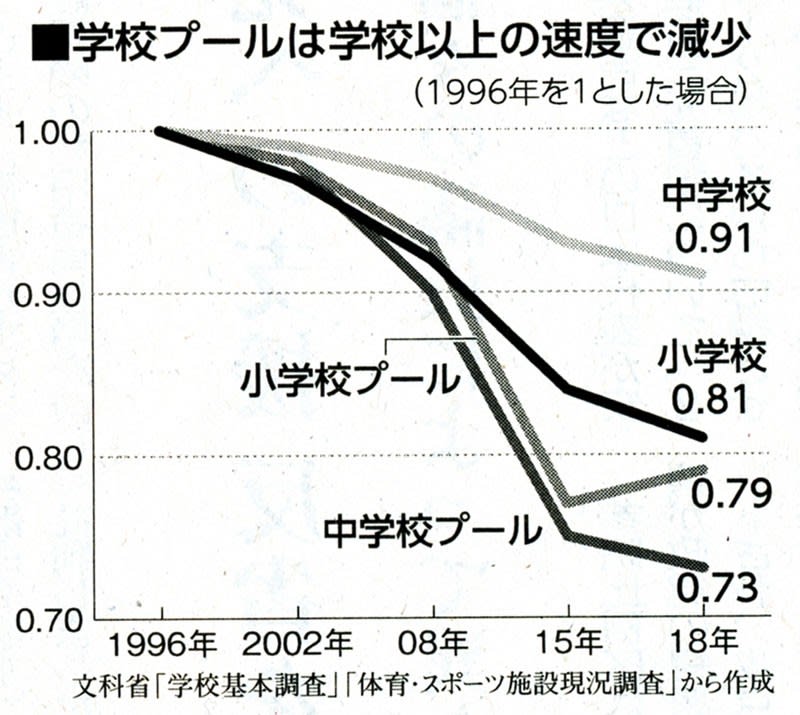

プール送迎のために待機するバス。T字路の停止線から駐車し、2台目と3台目はT字路を挟んで駐車=6月1日、東京都葛飾区
丸投げに
民間プールへ移行した小学校のベテラン教師は、授業の実態は企業丸投げだと断言します。泳力ごとに子どもをグループ分けし、教師は泳ぎの苦手なグループの補助に入るため、得意な子のグループの様子は見られず「成績も一人ひとりの細かな評価はできない」と言います。泳ぎの指導法などインストラクターから教師が学ぶことも多いとしつつ、こう語ります。
「水泳の日は登校してすぐバス移動。子どもたちをとにかくせかす。遅刻する子やトラブルで出発が遅れたり、渋滞につかまったりもある。置き去りがないかなど、行き帰りでの子どもの確認にも神経を使う。忘れ物があってもすぐ取りにいけない。プールから帰ってから朝の会をやるので授業時間が削られるし、子どもも移動とプールで疲れるので、次の授業時間は集中する内容は組めない」
制野准教授は、水泳授業には本来、水中という異質な環境に置かれることによる体や心の変化、不安を共有することで子ども同士が協力し合うようになるなど、学級づくりのうえでも重要なカギとなる機能があるといいます。企業への丸投げでは、そうした可能性は開かれず、競泳に特化した指導で“落ちこぼれ”をつくりだす危険もあると語ります。
「教師の負担軽減の名で進む公教育の民間委託で、真っ先に標的になっているのが水泳や部活動です。教える機会が減っていけば泳げない教師も出てくるでしょう。単なる合理化で民間に受け渡すことは反対です。負担軽減というなら、教育委員会が押し付けてくる書類業務など削るべきものはほかにたくさんあります」(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2022年10月19日付掲載
小中学校のプールを徐々に廃止し、企業や区立の学校外プールへ移行すると決めた東京都葛飾区。これまでほぼ全学校で実施してきた水難事故を想定した着衣泳が、今年度は学校外プールを利用した12の小中学校では実施されなかった。区の担当者は、着衣泳は学習指導要領で必修とされておらず、着衣泳を拒否した民間1施設を除き、実施しなかったのは各学校の判断だと。
制野准教授は、水泳授業には本来、水中という異質な環境に置かれることによる体や心の変化、不安を共有することで子ども同士が協力し合うようになるなど、学級づくりのうえでも重要なカギとなる機能があると。企業への丸投げでは、そうした可能性は開かれず、競泳に特化した指導で“落ちこぼれ”をつくりだす危険もあると。
和光大学の制野俊弘准教授のいうドル平泳法。50年以上前、僕が小中学生だったころから推奨されてきました。
和光大学の制野俊弘准教授(体育科教育学)は、宮城県東松島市の中学校教師時代、水泳では「進む」こと中心ではなく、「呼吸」に中心をおいたドル平(どるひら)と呼ばれる泳法の指導に力を入れました。同県を巨大な津波が襲った2011年の東日本大震災。教え子の一人は津波で川に流されドル平で九死に一生を得ました。一方、津波で命を落としたなかに授業でドル平を教えきれなかった子どもがいました。
制野さんは「水泳の授業で自分の命を守る力を子どもたちにつけることは、公教育の最低限の使命」と胸に刻みます。
実施せず
小中学校のプールを徐々に廃止し、企業や区立の学校外プールへ移行すると決めた東京都葛飾区。これまでほぼ全学校で実施してきた水難事故を想定した着衣泳が、今年度は学校外プールを利用した12の小中学校では実施されませんでした。区の担当者は、着衣泳は学習指導要領で必修とされておらず、着衣泳を拒否した民間1施設を除き、実施しなかったのは各学校の判断だといいます。
同区の場合、学校外プールでは企業のインストラクターが指導に当たります。現場でインストラクターに教師が指示を出すと偽装請負になります。区の担当者は、教師が立てた授業計画に基づき事前に複数回打ち合わせしており、民間の専門性が生かされ教師の負担軽減にもなっているといいます。民間の専門性を活用して個別最適な教育を実現する、という政府方針にも符合しますが…。
「教育委員会に提出する書類作業などに追われ昨日も学校を出たのは夜の11時。企業と事前に打ち合わせする時間なんて教師にありません。体育主任は顔合わせくらいしているかもしれないけど」
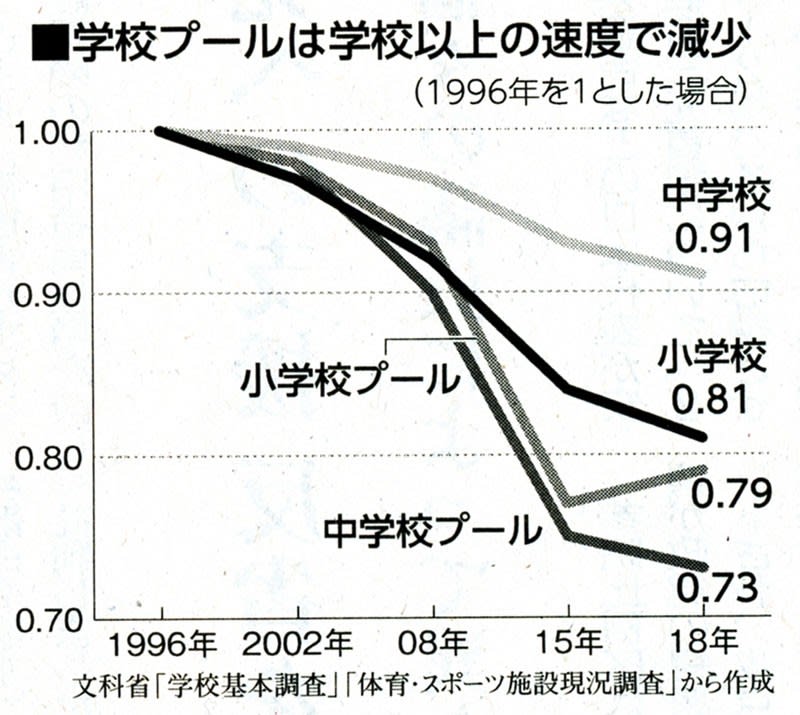

プール送迎のために待機するバス。T字路の停止線から駐車し、2台目と3台目はT字路を挟んで駐車=6月1日、東京都葛飾区
丸投げに
民間プールへ移行した小学校のベテラン教師は、授業の実態は企業丸投げだと断言します。泳力ごとに子どもをグループ分けし、教師は泳ぎの苦手なグループの補助に入るため、得意な子のグループの様子は見られず「成績も一人ひとりの細かな評価はできない」と言います。泳ぎの指導法などインストラクターから教師が学ぶことも多いとしつつ、こう語ります。
「水泳の日は登校してすぐバス移動。子どもたちをとにかくせかす。遅刻する子やトラブルで出発が遅れたり、渋滞につかまったりもある。置き去りがないかなど、行き帰りでの子どもの確認にも神経を使う。忘れ物があってもすぐ取りにいけない。プールから帰ってから朝の会をやるので授業時間が削られるし、子どもも移動とプールで疲れるので、次の授業時間は集中する内容は組めない」
制野准教授は、水泳授業には本来、水中という異質な環境に置かれることによる体や心の変化、不安を共有することで子ども同士が協力し合うようになるなど、学級づくりのうえでも重要なカギとなる機能があるといいます。企業への丸投げでは、そうした可能性は開かれず、競泳に特化した指導で“落ちこぼれ”をつくりだす危険もあると語ります。
「教師の負担軽減の名で進む公教育の民間委託で、真っ先に標的になっているのが水泳や部活動です。教える機会が減っていけば泳げない教師も出てくるでしょう。単なる合理化で民間に受け渡すことは反対です。負担軽減というなら、教育委員会が押し付けてくる書類業務など削るべきものはほかにたくさんあります」(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2022年10月19日付掲載
小中学校のプールを徐々に廃止し、企業や区立の学校外プールへ移行すると決めた東京都葛飾区。これまでほぼ全学校で実施してきた水難事故を想定した着衣泳が、今年度は学校外プールを利用した12の小中学校では実施されなかった。区の担当者は、着衣泳は学習指導要領で必修とされておらず、着衣泳を拒否した民間1施設を除き、実施しなかったのは各学校の判断だと。
制野准教授は、水泳授業には本来、水中という異質な環境に置かれることによる体や心の変化、不安を共有することで子ども同士が協力し合うようになるなど、学級づくりのうえでも重要なカギとなる機能があると。企業への丸投げでは、そうした可能性は開かれず、競泳に特化した指導で“落ちこぼれ”をつくりだす危険もあると。
和光大学の制野俊弘准教授のいうドル平泳法。50年以上前、僕が小中学生だったころから推奨されてきました。



















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます