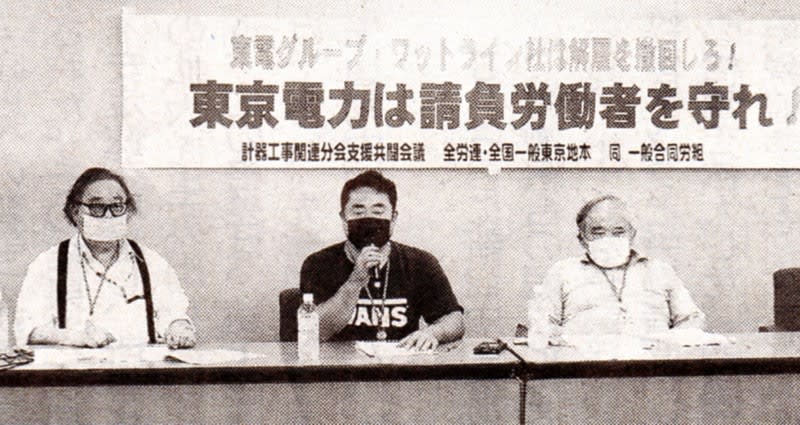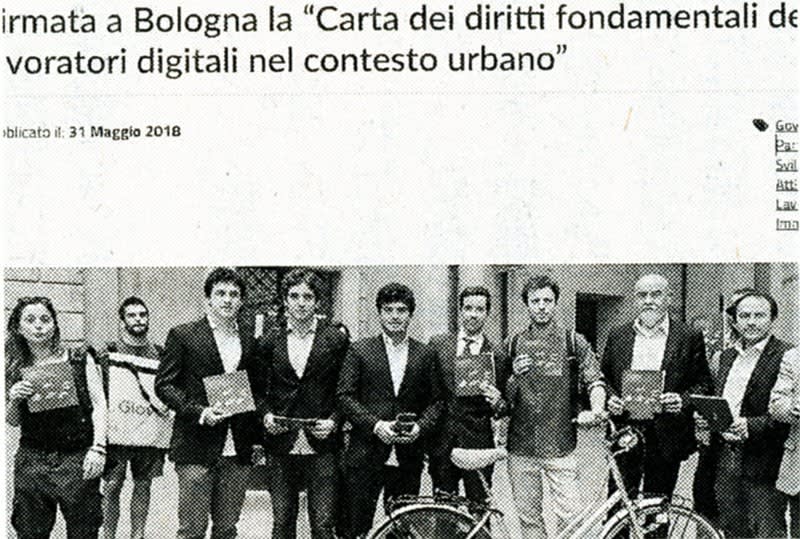税と新自由主義② 勝者GAFAが総取り
政治経済研究所理事 合田寛さん
―グローバル化と新自由主義によって税制の具体的なあり方はどう変わりましたか。
英国のサッチャー政権と米国のレーガン政権は新自由主義思想を本格的に実践した政権でした。1979年に政権に就いたサッチャー首相は、83%程度だった個人所得税の最高税率を一気に40%に引き下げました。法人税率も52%から35%に下げました。81年に政権に就いたレーガン大統領も同様の大減税を行いました。
これ以降、富裕層減税の競争が世界的な潮流となりました。現在、所得税の最高税率は、米国37%、英国45%、日本45%と、80年代のほぼ半分の水準になっています。法人税率(国税)も、米国21%、英国19%、日本23・2%と、80年代の半分程度に低下しました。
法人税の減税は税引き後の企業利益を増やし、配当の増額や株価の高騰を通じて、大量の株式を保有する富裕層の資産をさらに増やします。所得税の最高税率の引き下げと相まって、富裕層をますます富裕にしました。
他方、逆進的な社会保険料(給与税)や消費税(付加価値税)の引き上げで、低・中所得層の所得に対する税負担率は重くなりました。税制が貧困と不平等を広げています。
一握りの富豪に
―不平等の広がりを数値でみるとどうなります
か。
世界不平等研究所の『世界不平等レポート2018』が最新動向を計測し、表にしています。1980年以降の約40年間で、世界の総所得の伸びのうち、どの所得グループがどのくらいの割合を得たかを示したものです。
それによると、世界の所得上位0・1%の個人が13%を得ており、下位50%が得た12%を上回っています。わずか0・1%の富裕者が、世界の半数の人々よりも多く所得を増やしたわけです。さらに、上位1%の個人は27%を勝ち得ています。世界の所得の伸びの4分の1以上を1%の富裕者が得たことになります。
近年の不平等の特徴は、ごく一握りの富裕者に富が集中していることです。米誌『フォーブス』の世界長者番付によると、1987年に10億ドル以上の資産を保有する人(ビリオネア)は140人おり、資産総額は2950億ドルでした。2021年にはビリオネアが2755人と約20倍に増え、資産総額は13兆1000億ドル(約1500兆円)と約44倍に増えました。世界の不平等の拡大は歴然としています。
1980~2016年に全人口が得た所得の伸びを100としたとき、その100のうち各所得階層の人びとが得た割合(%)
『世界不平等レポート2018』から作成
強大な権限手中
―GAFA(グーグル、アップル、フェイスブック〈現メタ〉、アマゾン)など米国のIT(情報技術)企業の創業者が長者番付の上位に並んでいます。
GAFAは市場を支配する現代の巨大独占企業として、異常な高収益を得ています。これらのIT企業はデジタル革命の成果を取り入れて台頭しました。デジタル革命は、あらゆる情報を0とーの列として記号化し、「完全・瞬時・無料」で複製・伝達することを可能にしました。IT企業はほとんど追加コストなしでサービスを無限に拡大できます。
GAFAはこの成果を生かし、無数の売り手と買い手をインターネット上で結びつけるプラットフォーム(基盤)型ビジネスを創出しました。例えばグーグルは、無料の検索サービスを提供して膨大な利用者を抱え込む一方、これら利用者の関心に応じて表示される広告の枠を事業者に売り、収入を得ます。
囲い込む顧客が多いほど収益が増えるため、GAFAは10年ほどの間に数百社の競争企業を買収してきました。各分野で圧倒的なシェアを握り、その分野の情報を独占・支配・管理する強大な権限を得ています。
競争は短期間で勝者総取りに終わり、独占が形成されました。GAFAはプラットフォームを主宰する立場を使って自己を優先させ、略奪的価格を設定し、排他的な行為で独占を強めています。進出先の国々で巨額の税を逃れることも高収益の大きな要因です。
グローバル化と新自由主義がもたらしたものは、公平な市場競争ではなく、不公平な独占と不平等な富の集中だったのです。
(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2021年11月11日付掲載
近年の不平等の特徴は、ごく一握りの富裕者に富が集中していることです。米誌『フォーブス』の世界長者番付によると、1987年に10億ドル以上の資産を保有する人(ビリオネア)は140人おり、資産総額は2950億ドルでした。2021年にはビリオネアが2755人と約20倍に増え、資産総額は13兆1000億ドル(約1500兆円)と約44倍に増えました。世界の不平等の拡大は歴然と。
政治経済研究所理事 合田寛さん
―グローバル化と新自由主義によって税制の具体的なあり方はどう変わりましたか。
英国のサッチャー政権と米国のレーガン政権は新自由主義思想を本格的に実践した政権でした。1979年に政権に就いたサッチャー首相は、83%程度だった個人所得税の最高税率を一気に40%に引き下げました。法人税率も52%から35%に下げました。81年に政権に就いたレーガン大統領も同様の大減税を行いました。
これ以降、富裕層減税の競争が世界的な潮流となりました。現在、所得税の最高税率は、米国37%、英国45%、日本45%と、80年代のほぼ半分の水準になっています。法人税率(国税)も、米国21%、英国19%、日本23・2%と、80年代の半分程度に低下しました。
法人税の減税は税引き後の企業利益を増やし、配当の増額や株価の高騰を通じて、大量の株式を保有する富裕層の資産をさらに増やします。所得税の最高税率の引き下げと相まって、富裕層をますます富裕にしました。
他方、逆進的な社会保険料(給与税)や消費税(付加価値税)の引き上げで、低・中所得層の所得に対する税負担率は重くなりました。税制が貧困と不平等を広げています。
一握りの富豪に
―不平等の広がりを数値でみるとどうなります
か。
世界不平等研究所の『世界不平等レポート2018』が最新動向を計測し、表にしています。1980年以降の約40年間で、世界の総所得の伸びのうち、どの所得グループがどのくらいの割合を得たかを示したものです。
それによると、世界の所得上位0・1%の個人が13%を得ており、下位50%が得た12%を上回っています。わずか0・1%の富裕者が、世界の半数の人々よりも多く所得を増やしたわけです。さらに、上位1%の個人は27%を勝ち得ています。世界の所得の伸びの4分の1以上を1%の富裕者が得たことになります。
近年の不平等の特徴は、ごく一握りの富裕者に富が集中していることです。米誌『フォーブス』の世界長者番付によると、1987年に10億ドル以上の資産を保有する人(ビリオネア)は140人おり、資産総額は2950億ドルでした。2021年にはビリオネアが2755人と約20倍に増え、資産総額は13兆1000億ドル(約1500兆円)と約44倍に増えました。世界の不平等の拡大は歴然としています。
1980~2016年に全人口が得た所得の伸びを100としたとき、その100のうち各所得階層の人びとが得た割合(%)
| 中国 | 欧州 | インド | ロシア | 米国・カナダ | 世界 | |
| 全人口 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 所得下位50% | 13 | 14 | 11 | -24 | 2 | 12 |
| 中位40% | 43 | 38 | 23 | 7 | 32 | 31 |
| 上位10% | 43 | 48 | 66 | 117 | 67 | 57 |
| 所得上位1% | 15 | 18 | 28 | 69 | 35 | 27 |
| 上位0.1% | 7 | 7 | 12 | 41 | 18 | 13 |
| 上位0.01% | 4 | 3 | 5 | 20 | 9 | 7 |
| 上位0.001% | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 4 |
強大な権限手中
―GAFA(グーグル、アップル、フェイスブック〈現メタ〉、アマゾン)など米国のIT(情報技術)企業の創業者が長者番付の上位に並んでいます。
GAFAは市場を支配する現代の巨大独占企業として、異常な高収益を得ています。これらのIT企業はデジタル革命の成果を取り入れて台頭しました。デジタル革命は、あらゆる情報を0とーの列として記号化し、「完全・瞬時・無料」で複製・伝達することを可能にしました。IT企業はほとんど追加コストなしでサービスを無限に拡大できます。
GAFAはこの成果を生かし、無数の売り手と買い手をインターネット上で結びつけるプラットフォーム(基盤)型ビジネスを創出しました。例えばグーグルは、無料の検索サービスを提供して膨大な利用者を抱え込む一方、これら利用者の関心に応じて表示される広告の枠を事業者に売り、収入を得ます。
囲い込む顧客が多いほど収益が増えるため、GAFAは10年ほどの間に数百社の競争企業を買収してきました。各分野で圧倒的なシェアを握り、その分野の情報を独占・支配・管理する強大な権限を得ています。
競争は短期間で勝者総取りに終わり、独占が形成されました。GAFAはプラットフォームを主宰する立場を使って自己を優先させ、略奪的価格を設定し、排他的な行為で独占を強めています。進出先の国々で巨額の税を逃れることも高収益の大きな要因です。
グローバル化と新自由主義がもたらしたものは、公平な市場競争ではなく、不公平な独占と不平等な富の集中だったのです。
(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2021年11月11日付掲載
近年の不平等の特徴は、ごく一握りの富裕者に富が集中していることです。米誌『フォーブス』の世界長者番付によると、1987年に10億ドル以上の資産を保有する人(ビリオネア)は140人おり、資産総額は2950億ドルでした。2021年にはビリオネアが2755人と約20倍に増え、資産総額は13兆1000億ドル(約1500兆円)と約44倍に増えました。世界の不平等の拡大は歴然と。