チェは異邦人戦士であることを自覚していた。キューバ革命政府では人材不足という厳しい現実があり、フィデルに乞われれば一定期間留まらざるを得ないと覚悟していたが、権力に興味はなく、いつ自由になれるかが問題だったようだ。ソ連を中心とする共産主義社会の連帯にも、分業という美名の下に貧富の差が固定化され、資本主義経済に似た覇権主義的構造にある(それでも貧しいキューバはソ連に頼らざるを得ない)ことに絶望し、高い理想と裏切られた現実のはざまで、祖国・アルゼンチンの解放という見果てぬ夢に向かって、予備演習的なコンゴ遠征に続き、ボリビアでの反帝国主義闘争へと、ゲリラとして死ぬことを半ば覚悟し半ば夢見つつ、自らを追い込んでいく。
キューバを出て行くチェの心情について、米国人ジャーナリストで作家のIF・ストーンは、サルトル夫妻がチェに会ったのと前後してキューバを訪問し、回想記の中にしたためている。「チェは単に男前というだけでなく美しいと私が感じた最初の男だった。縮れた赤っぽい髭の彼は、林野牧畜の神ファウヌスと、日曜学校で配られるキリストの複製画の交じり合ったような風貌だった。私を最も驚かせたのは、彼が突然手にした権力によって変わりもせず腐敗もせず中毒にも罹っていない事実だった。彼の発言には共産主義の陳腐な言葉はなかった。米国人記者が感じ取るべきは、彼の抱く深い対米不信だろう。その理由はいろいろあるが、彼は、米国を西半球(米州)での競争相手と見做しているアルゼンチンの市民なのだ」「チェは癒されたいという気持ちを醸し、人はチェに苦しむ者への同情を感じ取るだろう。彼の政治的関心はメキシコからアルゼンチンまでのアメリカ(ラテンアメリカ)にあった。我々米国人が自国を指して〈アメリカ〉と言うときに忘れているアメリカだ。チェはカストロ体制について〈我々はカリブ海のチトーになろうとしている。米国はチトーと折り合いをつけた。我々とも徐々に折り合えるようになるはずだ〉と言った」。そしてチェがキューバを去ったことについて、「私は驚かなかった。彼は常に革命家だった。彼の味覚にとって、キューバさえも味気なくなっていたのだろう。革命は権力を握ったことで(道徳的な)罪に陥ったのだろう。無垢な価値が徐々に荒廃して行ったことにチェは我慢がならなかった、と容易に想像できる。彼はキューバ人でなかったため、ラテンアメリカの中で一国だけ米帝国主義から解放されたことに満足できなかった。彼は大陸規模で考えていた」と語っている。
キューバ革命戦争中、反乱軍司令の中で最大の軍功を収めた人物とされ、フィデルやチェと知的応酬の出来る数少ない論客でもあったウベール・マトスは、自らの反共主義によってフィデルと路線対立し、禁固20年の刑に服し、1979年に出所してマイアミに移住した。2002年に出版した自伝の中でチェのことに触れて、次のように述べている。「フィデルはチェを酷使した。ソ連の援助が不可欠になるや、反ソ傾向のあったチェを切り離さねばならなかった。だからボリビアに行った。悲しいのは、見捨てられたのをチェが感知していたことだ。チェが犠牲になるや、フィデルはチェを宣伝に使った。思想の隔たりはあったが、チェとは友人だった。チェは優れたゲリラではなく、平凡なゲリラだった。チェは冒険好きで勇気があった。活躍できる場を求めていた。チェはキューバ革命の象徴というよりも犠牲者だ」。立場上、ジャーナリストのように中立かあるいは多少の興味なりシンパシーがあるのと比べれば、些か手厳しい見方だが、現実だろう。実際、マトスは革命政権の書いた正史から抹殺されたという。ハバナ入城時にカミーロ(革命軍の参謀長)とともにフィデルを挟んでいる有名な写真からマトスの姿は消されたらしいのだ(逆にマトスの著書の表紙は、まさにフィデル、カミーロと並んでのハバナ入城の写真だという)。
驚いたことに、チェは父親と同い年であることに気づいた。日本とラテンアメリカという状況が違うと随分生きざまが変わるものだ。他に同級生は(どうでもいい話だが)、フランス文学者・澁澤龍彦、民主カンボジア首相のポル・ポト、未来学者アルビン・トフラー、漫画家・手塚治虫、言語学者ノーム・チョムスキーがいる。鬼籍に入った方が多く、生きていればそういう年齢なのだ。その2つ下のジェームス・ディーンが亡くなったときの24歳のままのイメージでいるのと同じで、チェは39歳の若さで伝説になったまま冷凍保存された。チェには、(やや広い意味での)同時代ということでのシンパシーと、そうは言っても今となっては時代背景が違い、置かれた環境も違うことから来る違和感とがない交ぜになる。その空気の一端を吸っているだけに、複雑な気持ちになる。それでも、写真展「写真家チェ・ゲバラが見た世界」で感じた、戦いの狭間に見せるナイーブなほどに優しいまなざし、超人的な勇気や行動力と人間的な弱さの背後にある、私心の無い大義に殉じる無垢さは、永遠に人々の心を惹きつけてやまないことだろう。89歳になる彼が生きていたら・・・とは俄かに想像がつかない(笑)。
キューバを出て行くチェの心情について、米国人ジャーナリストで作家のIF・ストーンは、サルトル夫妻がチェに会ったのと前後してキューバを訪問し、回想記の中にしたためている。「チェは単に男前というだけでなく美しいと私が感じた最初の男だった。縮れた赤っぽい髭の彼は、林野牧畜の神ファウヌスと、日曜学校で配られるキリストの複製画の交じり合ったような風貌だった。私を最も驚かせたのは、彼が突然手にした権力によって変わりもせず腐敗もせず中毒にも罹っていない事実だった。彼の発言には共産主義の陳腐な言葉はなかった。米国人記者が感じ取るべきは、彼の抱く深い対米不信だろう。その理由はいろいろあるが、彼は、米国を西半球(米州)での競争相手と見做しているアルゼンチンの市民なのだ」「チェは癒されたいという気持ちを醸し、人はチェに苦しむ者への同情を感じ取るだろう。彼の政治的関心はメキシコからアルゼンチンまでのアメリカ(ラテンアメリカ)にあった。我々米国人が自国を指して〈アメリカ〉と言うときに忘れているアメリカだ。チェはカストロ体制について〈我々はカリブ海のチトーになろうとしている。米国はチトーと折り合いをつけた。我々とも徐々に折り合えるようになるはずだ〉と言った」。そしてチェがキューバを去ったことについて、「私は驚かなかった。彼は常に革命家だった。彼の味覚にとって、キューバさえも味気なくなっていたのだろう。革命は権力を握ったことで(道徳的な)罪に陥ったのだろう。無垢な価値が徐々に荒廃して行ったことにチェは我慢がならなかった、と容易に想像できる。彼はキューバ人でなかったため、ラテンアメリカの中で一国だけ米帝国主義から解放されたことに満足できなかった。彼は大陸規模で考えていた」と語っている。
キューバ革命戦争中、反乱軍司令の中で最大の軍功を収めた人物とされ、フィデルやチェと知的応酬の出来る数少ない論客でもあったウベール・マトスは、自らの反共主義によってフィデルと路線対立し、禁固20年の刑に服し、1979年に出所してマイアミに移住した。2002年に出版した自伝の中でチェのことに触れて、次のように述べている。「フィデルはチェを酷使した。ソ連の援助が不可欠になるや、反ソ傾向のあったチェを切り離さねばならなかった。だからボリビアに行った。悲しいのは、見捨てられたのをチェが感知していたことだ。チェが犠牲になるや、フィデルはチェを宣伝に使った。思想の隔たりはあったが、チェとは友人だった。チェは優れたゲリラではなく、平凡なゲリラだった。チェは冒険好きで勇気があった。活躍できる場を求めていた。チェはキューバ革命の象徴というよりも犠牲者だ」。立場上、ジャーナリストのように中立かあるいは多少の興味なりシンパシーがあるのと比べれば、些か手厳しい見方だが、現実だろう。実際、マトスは革命政権の書いた正史から抹殺されたという。ハバナ入城時にカミーロ(革命軍の参謀長)とともにフィデルを挟んでいる有名な写真からマトスの姿は消されたらしいのだ(逆にマトスの著書の表紙は、まさにフィデル、カミーロと並んでのハバナ入城の写真だという)。
驚いたことに、チェは父親と同い年であることに気づいた。日本とラテンアメリカという状況が違うと随分生きざまが変わるものだ。他に同級生は(どうでもいい話だが)、フランス文学者・澁澤龍彦、民主カンボジア首相のポル・ポト、未来学者アルビン・トフラー、漫画家・手塚治虫、言語学者ノーム・チョムスキーがいる。鬼籍に入った方が多く、生きていればそういう年齢なのだ。その2つ下のジェームス・ディーンが亡くなったときの24歳のままのイメージでいるのと同じで、チェは39歳の若さで伝説になったまま冷凍保存された。チェには、(やや広い意味での)同時代ということでのシンパシーと、そうは言っても今となっては時代背景が違い、置かれた環境も違うことから来る違和感とがない交ぜになる。その空気の一端を吸っているだけに、複雑な気持ちになる。それでも、写真展「写真家チェ・ゲバラが見た世界」で感じた、戦いの狭間に見せるナイーブなほどに優しいまなざし、超人的な勇気や行動力と人間的な弱さの背後にある、私心の無い大義に殉じる無垢さは、永遠に人々の心を惹きつけてやまないことだろう。89歳になる彼が生きていたら・・・とは俄かに想像がつかない(笑)。














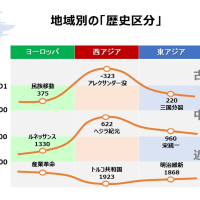




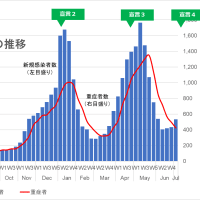






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます