死者行方不明合わせて100名以上とは

先日、アメリカ東海岸を襲ったハリケーンよりも被害は甚大と言うことのようです。
あちらは早々に住民達は皆避難をしていましたが・・・
日本もどうにかならなかったのでしょうか

「すべてノロノロ台風が原因で、雨の量は想定外だった」というお話が
お役所辺りから聞こえてきますが、自然相手の「想定外」というのはありえないと、
東日本大震災で思い知ったはず・・・
ちょっと残念ですね。
被害に遭われた方々には、心よりお見舞いを申し上げます。
台風から遠く離れた南関東も一週間近く不安定なお天気が続き、
連日の突然の雨にはウンザリしましたが、ようやく明るい太陽が照り出しました

ツクツクボウシが鳴きだし、朝晩に吹く風はもうすっかり秋の気配ですが、
我が家の夏の思い出をまだ全部紹介していませんでしたので、UPします。
8月15日「箱根・ガラスの森美術館」
 |
8月15日~16日、息子一家と恒例の「箱根旅行」に行ってきました。
現地集合、現地解散の気ままな箱根行きです。
宿は今年の冬に新年会で集まった、息子の会社の保養所・・・
我等夫婦は宿の近くの「ガラスの森美術館」でランチ&美術鑑賞をしようと、
朝8時半に我が家を出発


普段は1時間半位で行けるルートですが、お盆休みのこの時期は倍の3時間かかりました

午前中なので駐車場もスムースに停められましたが、入り口は大勢の入場者で溢れていました。
「こういう作り物に人が殺到する事態が信じられない」
自然の中を歩くのが好きな我々はそう呟きながら中に入りました。
 |
中に入ると目の前に、イタリアの「貴族の館」風の建物が広がっていました。
 |
日本初の本格的なヴェネチアン・グラス美術館として、1996年にオープン。
私は出来て間もない頃、仕事仲間たちと来ましたので15年ぶりの来園、主人は初めてです。
 |
晴れてはいるものの、今年の夏特有の雲の多さで、
正面に見えるはずの「大涌谷」も霞んでいるようです。
 |
水の都「ヴェネチア」と言うよりは、イギリス辺りの田園風景という感じですが・・・
 |
そろそろお昼、お腹も空きました。
私たちはカフェ・レストラン「テラッツァ」へ直行・・・
10分待ちで席に案内されました。
 |
歌声が聞こえてきました。
イタリア人歌手によるカンツォーネの生演奏です。
青春時代に観た映画「恋愛専科」の主題歌「アルディラ」が懐かしい・・・
美男美女のトロイ・ドナヒューとスザンヌ・プレシェットが素敵でした

 |  |
| 1日5回の生演奏があります♪ | カボチャのスープと野菜とチーズの前菜 |
 |  |
冷製の海鮮パスタが美味しい | デザート付きランチのお任せセット頂きました。 |
 |
窓の向うは中世のヴェネチア・・・
カンツォーネの明るい歌声を聴きながら美味しいお食事が楽しめました。
軽井沢で果たせなかった「お洒落なイタリアンランチ」
箱根で果たせて満足で~す

 |
「カフェ」の他、広い庭園には「ヴェネチアン・グラス館」「現代ガラス館」
「ミュージアム・ショップ」などが点在しています。
 |
木の橋を渡って歩み入れば、そこはアドリア海の王女と謳われた往時のヴェネチア。
 |  |
| 橋にかけられたキラキラ輝くトンネルも | 池に浮ぶ豪華な花もガラスです |
 |
美術館の広間では演奏会が開かれていました。
グラスの縁を指でこするとガラス特有の良く澄んだ音を発します。
それを楽器とした「グラス・ハープ」と言うのでしょうか?
澄み切った神秘的な音色が、心癒してくれました。
会場の皆で歌った「箱根の山は天下のけん(嶮)、函谷關(かんこくかん)もものならず
 」も
」も楽しい思い出として残りましたが・・・
私はこの難しい歌詞がスムースに出てきませんでした

 |  |
| 中世のヴェネチア貴族の館を再現した | 優雅な美術館内には・・・ |
 |  |
| 15世紀~18世紀ヨーロッパ貴族を熱狂させた | ヴェネチアン・グラス100点余りが並んでいる |
 |  |
| まさに卓越した技を尽くした美の極み | 繊細優美な輝きですね  |
 |  |
| 19世紀に復活した現代ヴェネチアン・グラス | ガラスの無限の可能性を秘めた斬新さですね |
「ミュ-ジアム・ショップ」にはヴェネチアン・グラスはもちろん、
世界各国のガラス製品が約100.000点!
 |  |
| ガラス細工やアクセサリ-などが並ぶ | 女性好みの空間です  |
 |
夫と一緒ではユックリお買い物をする気にもなれず、ざっと廻ってから外に出て
庭の散策をしました。
 |  |
| 辛うじて残っていたバラ | この西欧庭園に相応しいで花です |
他に「紫陽花の小道」もあって、初夏が良いかも知れませんね。
「思ったより楽しめたな~、二箇所の音楽が特に良かった
 」
」束の間のイタリアを味わえた3時間半でした。
 |
こちらは我が家の「ヴェネチアングラス」です。
1995年にご近所の親しい仲間4人で行った「イタリア旅行」のヴェネチアで、
皆同じこのペアのワイングラス買ってきました。
深い赤色のガラスが、この派手な金の模様を落ち着いた感じに仕上げていますね。
アノ頃は夫たちも皆そろって働き盛りのサラリーマン・・・
休日にはよく4軒のどなたかのお宅に夫婦共々集まり、お料理を持ち寄っての食事会を催し
その時は必ずこのグラスを持参し、4夫婦8人で乾杯しましたよ


それもこれも懐かしい思い出ですね。












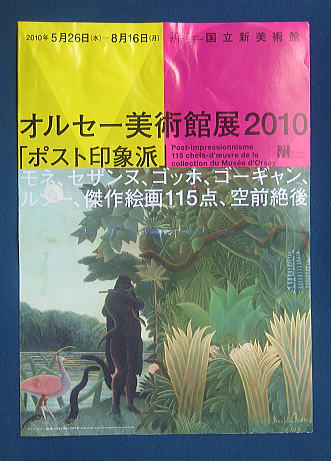
 」
」










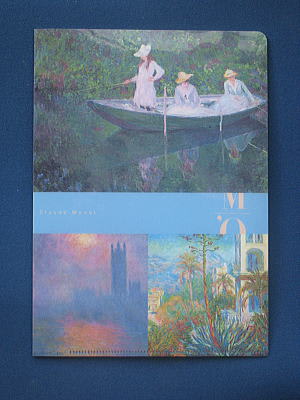














 >
>





















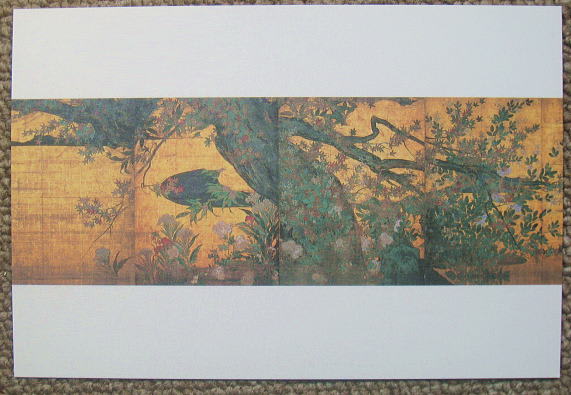











 >
>
 >
>











 >
>

















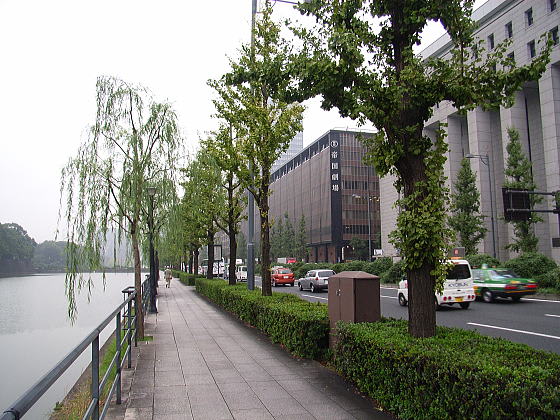




 、六つのセクションの絵画はそれぞれに興味深いものでした。
、六つのセクションの絵画はそれぞれに興味深いものでした。





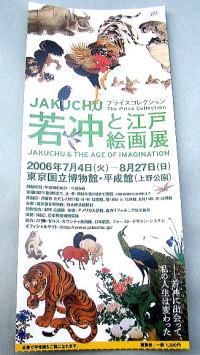
 、ロケットのように飛び出して行く好奇心は半端でなく
、ロケットのように飛び出して行く好奇心は半端でなく 、それが3人3様で方向が違うので、面白いと言えば面白いのですが
、それが3人3様で方向が違うので、面白いと言えば面白いのですが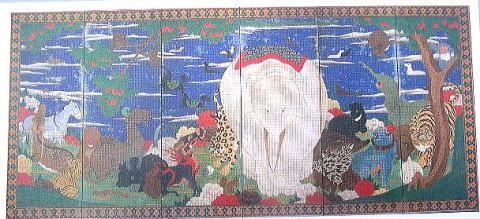
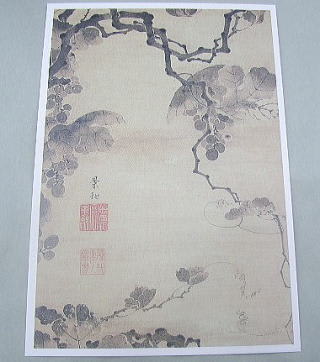



 こちらが若冲の代表的な作品「紫陽花双鶏図」
こちらが若冲の代表的な作品「紫陽花双鶏図」



