先日、車で明午橋通りを味噌天神方面へ向かって走っていた時、新屋敷の大井手をわたるところで信号停車した。ふと大井手の方に目をやると川端柳が見えた。近頃、川端柳を見る機会が減った。昔はもっと川や井手沿いに多くの川端柳が植わっていたものだが。この大井手沿いには辛うじて昔の風情が残っている。
そんなことを考えているとつい「東雲節」の一節が口をついて出る。
「♪ なにをくよくよ川端柳 こがるるなんとしょ」
これは坂本龍馬の作とも高杉晋作の作ともいわれる都々逸である。「柳に風」なんていうことわざもあるが、要するに「しなやかに おだやかに生きましょう」ということを言っているのだろうと勝手に解釈している。この歳になると妙にその言葉が胸に染みるのである。
この都々逸は、熊本ゆかりの俗謡「東雲節(ストライキ節)」にも歌い込まれていてなじみ深い。
〽なにをくよくよ川端柳 こがるるなんとしょ
水の流れを見てくらす
東雲の暁の鐘 ごんとつきゃ辛いね
てなことおっしゃいましたかね

大井手の川端柳(金剛寺の裏あたり)
そんなことを考えているとつい「東雲節」の一節が口をついて出る。
「♪ なにをくよくよ川端柳 こがるるなんとしょ」
これは坂本龍馬の作とも高杉晋作の作ともいわれる都々逸である。「柳に風」なんていうことわざもあるが、要するに「しなやかに おだやかに生きましょう」ということを言っているのだろうと勝手に解釈している。この歳になると妙にその言葉が胸に染みるのである。
この都々逸は、熊本ゆかりの俗謡「東雲節(ストライキ節)」にも歌い込まれていてなじみ深い。
〽なにをくよくよ川端柳 こがるるなんとしょ
水の流れを見てくらす
東雲の暁の鐘 ごんとつきゃ辛いね
てなことおっしゃいましたかね

大井手の川端柳(金剛寺の裏あたり)










 三味線音楽の大御所・本條秀太郎さんが創始された俚奏楽のなかで、僕が一番好きな曲、それが「島めぐり」である。大まかに言うと伊豆諸島や小笠原諸島に古くから残る唄つづりとでも言ってよかろう。しかし、何度も聞いていると実に巧みに構成されていることに気付く。随分前に本條秀美さんにいただいた歌詞(下記)を見てみると、赤い角括弧でくくられた部分が、ト書きでもあり曲のメインストリームにもなっていて、そこに各島唄を入れ子とした構造になっている。実はこの赤い角括弧部分もどこかの島の古謡を使ってあるのかと思っていたが、どうやらそうではないことが段々わかって来て、先般、東京での稽古に行かれた本條秀美さんに確認してきていただいた。やはり本條秀太郎さん自ら作られた歌詞なのだそうだ。こうした工夫が俚奏楽の本旨である、失われそうな鄙唄の再生につながるのだろう。
三味線音楽の大御所・本條秀太郎さんが創始された俚奏楽のなかで、僕が一番好きな曲、それが「島めぐり」である。大まかに言うと伊豆諸島や小笠原諸島に古くから残る唄つづりとでも言ってよかろう。しかし、何度も聞いていると実に巧みに構成されていることに気付く。随分前に本條秀美さんにいただいた歌詞(下記)を見てみると、赤い角括弧でくくられた部分が、ト書きでもあり曲のメインストリームにもなっていて、そこに各島唄を入れ子とした構造になっている。実はこの赤い角括弧部分もどこかの島の古謡を使ってあるのかと思っていたが、どうやらそうではないことが段々わかって来て、先般、東京での稽古に行かれた本條秀美さんに確認してきていただいた。やはり本條秀太郎さん自ら作られた歌詞なのだそうだ。こうした工夫が俚奏楽の本旨である、失われそうな鄙唄の再生につながるのだろう。







 九州東海大学の片野学先生が亡くなられて今年でもう10年になる。自然農法や有機農業の権威だった先生とは、僕は15年前、一度だけお会いしたことがある。僕の知人で洋菓子店経営をされている方から、阿蘇で無農薬の果樹栽培をしたいので専門家の指導を受けたいという相談を受けた。たまたま僕の知人に片野先生の奥様と親しい方がおられたので、僕が間を取り持つ形で先生の指導を受けることになった。会食しながらということで、僕も同席することになったが、とてもざっくばらんな先生で、面白い話が次から次に出て、時の経つのも忘れるほどだった。その席で先生が言われた言葉で一番印象深かったのは「適地適作」ということだった。阿蘇は火山灰地だから作物は限られる。とりあえずブルーベリーを始められたらいかが、というような話だった。先生とは機会があればもう一度お目にかかりたいと思っていたがかなわなかった。
九州東海大学の片野学先生が亡くなられて今年でもう10年になる。自然農法や有機農業の権威だった先生とは、僕は15年前、一度だけお会いしたことがある。僕の知人で洋菓子店経営をされている方から、阿蘇で無農薬の果樹栽培をしたいので専門家の指導を受けたいという相談を受けた。たまたま僕の知人に片野先生の奥様と親しい方がおられたので、僕が間を取り持つ形で先生の指導を受けることになった。会食しながらということで、僕も同席することになったが、とてもざっくばらんな先生で、面白い話が次から次に出て、時の経つのも忘れるほどだった。その席で先生が言われた言葉で一番印象深かったのは「適地適作」ということだった。阿蘇は火山灰地だから作物は限られる。とりあえずブルーベリーを始められたらいかが、というような話だった。先生とは機会があればもう一度お目にかかりたいと思っていたがかなわなかった。






 昨日は八月朔日。藤崎八旛宮に八朔詣りに行った。節供なので拝殿でお詣りした後、境内の末社をお詣りして廻った。その間の暑さといったら…。八朔というのはもともと旧暦での節供で、新暦では今年の場合、9月3日になるようだ。その頃になると、稲穂が頭を垂れ始める頃で、摘んだ御初穂を神に供える習わしがあったので、八月朔日を「ほづみ(穂摘)」ともいうようになったそうだ。
昨日は八月朔日。藤崎八旛宮に八朔詣りに行った。節供なので拝殿でお詣りした後、境内の末社をお詣りして廻った。その間の暑さといったら…。八朔というのはもともと旧暦での節供で、新暦では今年の場合、9月3日になるようだ。その頃になると、稲穂が頭を垂れ始める頃で、摘んだ御初穂を神に供える習わしがあったので、八月朔日を「ほづみ(穂摘)」ともいうようになったそうだ。
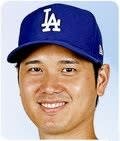 一昨日、テレビ熊本(TKU)夕方のニュース情報番組「TKU Live News」で大谷翔平選手と寝具メーカー西川の共同企画「大きな夢を見よう!プロジェクト」が紹介された。
一昨日、テレビ熊本(TKU)夕方のニュース情報番組「TKU Live News」で大谷翔平選手と寝具メーカー西川の共同企画「大きな夢を見よう!プロジェクト」が紹介された。