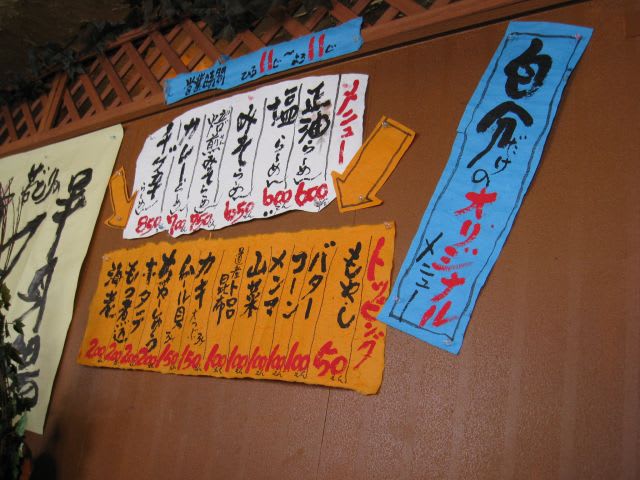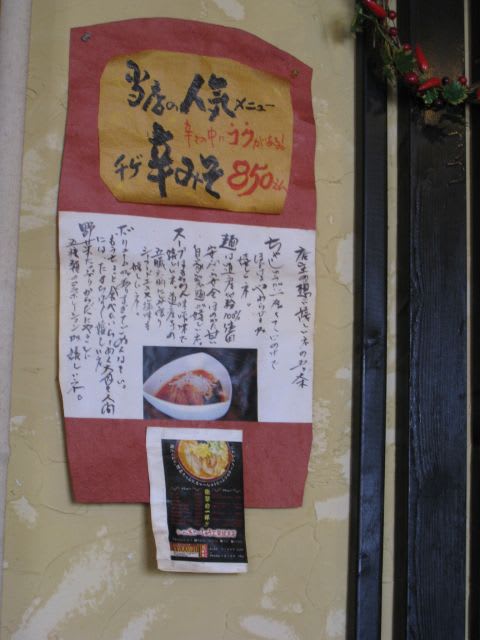ヒトはなぜ夢を見るのか 脳の不思議がわかる本, 千葉康則, PHP文庫 ち-3-3, 1998年
・脳についての素朴な疑問に、脳生理学の専門家が回答する一問一答集。一問につき、3~4ページずつの読みきり形式。一般人でも気軽に読める内容です。それぞれの質問に真正面から答えるのではなく、一般に広まっている脳についての誤ったイメージを正し、正確な学問的解釈を示す回答が目立ちます。本当ならズバズバ回答できればいいのでしょうが、脳の研究は、そこまではまだまだ至らない状況です。
・「要するに、この本は脳生理学の知識や見解を使って、応用問題を解くという形のものです。」p.4
・「ところで、脳についていえば、それは10分の1しか使っていないとか、その記憶容量は一京(兆の一万倍)ビット以上である、というような計算もあります。それなりに興味ある計算ですが、後に説明するように、脳の働きは神経網の中の一種の信号活動ですから、神経細胞の数とかその接続点であるシナップスの数とか、その組み合わせの様式数という具合に、数で表せるものではないのです。しいて数でいえば無限大といえます。」p.16
・「「使えば使うほどよくなる」という現象を専門的には「用不用の法則」といい、生物の特性とされています。つまり、機械や無生物は使うほど磨耗しますが、生体は使うほど発達する、ということです。」p.18
・「一日一〇万個ずつ神経細胞が死んでゆく、というような話もありますが、その分だけ無駄がなくなり、身軽になると考えた方がいいでしょう。(中略)一〇万個といっても、百数十億個といわれる神経細胞の十数万分の一である、という計算もしてみて下さい。」p.24
・「脳はもともと集中的にはたらくものだけれども、それは決して機械のように定常的なものでないことがわかります。集中の対象が次々と変わったり、集中の程度の強弱が波動的に変化します。」p.39
・「視野の中になにかが飛び込んできたりすると、無意識に手が動いて、それを振り払ったりします。これでわかるように、情報が送り込まれて、脳がそれに反応するということと、その情報が本人に感じられるということは、必ずしも同じ現象ではないのです。」p.48
・「すぐれたひらめきが生まれるのは、散歩中とか就眠前とか入浴中のような、どちらかというとあまりものを考えていないときであることも、経験的にわかっています。」p.52
・「脳が創造的にはたらくのは、外に向かって行動するときです。環境の変化を探り、それに対応し、効果的に行動するためには常に工夫が必要です。従って、空腹で食物を求めなければならないときや、敵と戦うときには、脳は創造的にはたらきます。」p.58
・「アイディアというのはものごとや問題を視点を変えてみつめて、新しいとらえ方をするところから生まれます。そのためには、ものごとや問題の全体をとらえなければなりません。」p.60
・「アイディアを次々と生みだす人間になりたいと願うのであれば、かりに先にいる人がいても、その模倣をするという安易な道を選ばないという心掛けが必要でしょう。」p.62
・「記憶力の弱い人というのは、むしろものごとを理解しない人、ものごとに強い関心を持てない人である場合が多いのです。ものごとを大きな全体としてとらえている人は、忘れたことでもたぐりよせることができるし、仮に間違えてもでたらめな間違いはしません。」p.66
・「要するに、脳のはたらきの最大の特性はその変動の柔軟性であり、バランスです。それを自在性ということもできます。脳機能を固定的にとらえるのは無意味です。」p.72
・「人間が言語を駆使できるようになったのは、(中略)口のまわりの筋肉を器用に素速く動かせるようになったからです。そのために、短い音を素速く組み合わせることによって無数の言葉をつくることができるようになりました。」p.78
・「赤とダイダイは近い色ですが、赤と青が違うように別の色なのです。このように、連続しているものでも区切ってしまう言語機能の性質を分節性といいます。このために、事象を細分化して分類整理することができるわけですが、言語機能が事象の全体を見失ってしまうのも分節性のためです。」p.79
・「一般に、ことばの学問というと文学などを指すことが多いのですが、算数とか数学こそことばの学問ということができます。」p.80
・「脳に言語機能がつけ加わって、人間は人間になり得た、という説はかなり根拠のあるものです。この本で動物と共通した非言語機能と人間独自の言語機能に分けて脳機能を論じているところが多いのも、そのためです。」p.101
・「脳のはたらきはリズムを持っており、人間の行動はそのリズムに乗り、また行動のリズムが脳のリズムもつくる、という関係があるので、そこに音楽が参加する意味が生まれるのです。」p.122
・「戦いとか逃走とか、行動しているときには感情という心の変化はみられず、行動を抑えているときには感情が高まるという関係に気づきます。」p.126
・「このように考えると、「男はみんなオオカミ」とか「イヌ畜生にも劣る」というようないい方は動物にたいする侮辱罪にあたるかもしれません。性善説と性悪説にしても、どちらといい切れるものではありませんが、どちらかというと性善説の方が正しいといえます。」p.160
・「理科系に進学する女性はたしかに少数派です。これは、むしろ女性は言語機能が苦手ということなのでしょうが、相対的に非言語機能に頼るところが大きいともいえます。」p.165
・「人間にも非言語的な伝達能力はありますが、言語機能があるので、動物ほどには敏感に機能しにくいという事情があるわけです。」p.169
・「失敗しても、脳のはたらきが発達するためには失敗が必要なのだ、とたかをくくっていればいいのです。」p.193
・「要するに、脳は使ってみなければそのよしあしはわからない、というのが正解でしょう。ただし、むきになればいいというのではなく、使い方が問題です。」p.203
・「睡眠は脳が完全に休息してしまう現象ではなく、それも脳のひとつの働きです。目ざめているときに活動している部分を抑制する力がはたらいているという状態です。」p.208
・「いわゆる「ひらめき」で、われながら名案と感動するような思いつきも、夢と同じように忘れやすいものです。思いつきもそのままでは行動と結びつきませんから、しばらくして消えてしまうのです。従って、創造的な仕事をしている人はいつも筆記道具を持ち歩いて、思いついたところで書き残しておく心掛けが必要です。」p.220
・脳についての素朴な疑問に、脳生理学の専門家が回答する一問一答集。一問につき、3~4ページずつの読みきり形式。一般人でも気軽に読める内容です。それぞれの質問に真正面から答えるのではなく、一般に広まっている脳についての誤ったイメージを正し、正確な学問的解釈を示す回答が目立ちます。本当ならズバズバ回答できればいいのでしょうが、脳の研究は、そこまではまだまだ至らない状況です。
・「要するに、この本は脳生理学の知識や見解を使って、応用問題を解くという形のものです。」p.4
・「ところで、脳についていえば、それは10分の1しか使っていないとか、その記憶容量は一京(兆の一万倍)ビット以上である、というような計算もあります。それなりに興味ある計算ですが、後に説明するように、脳の働きは神経網の中の一種の信号活動ですから、神経細胞の数とかその接続点であるシナップスの数とか、その組み合わせの様式数という具合に、数で表せるものではないのです。しいて数でいえば無限大といえます。」p.16
・「「使えば使うほどよくなる」という現象を専門的には「用不用の法則」といい、生物の特性とされています。つまり、機械や無生物は使うほど磨耗しますが、生体は使うほど発達する、ということです。」p.18
・「一日一〇万個ずつ神経細胞が死んでゆく、というような話もありますが、その分だけ無駄がなくなり、身軽になると考えた方がいいでしょう。(中略)一〇万個といっても、百数十億個といわれる神経細胞の十数万分の一である、という計算もしてみて下さい。」p.24
・「脳はもともと集中的にはたらくものだけれども、それは決して機械のように定常的なものでないことがわかります。集中の対象が次々と変わったり、集中の程度の強弱が波動的に変化します。」p.39
・「視野の中になにかが飛び込んできたりすると、無意識に手が動いて、それを振り払ったりします。これでわかるように、情報が送り込まれて、脳がそれに反応するということと、その情報が本人に感じられるということは、必ずしも同じ現象ではないのです。」p.48
・「すぐれたひらめきが生まれるのは、散歩中とか就眠前とか入浴中のような、どちらかというとあまりものを考えていないときであることも、経験的にわかっています。」p.52
・「脳が創造的にはたらくのは、外に向かって行動するときです。環境の変化を探り、それに対応し、効果的に行動するためには常に工夫が必要です。従って、空腹で食物を求めなければならないときや、敵と戦うときには、脳は創造的にはたらきます。」p.58
・「アイディアというのはものごとや問題を視点を変えてみつめて、新しいとらえ方をするところから生まれます。そのためには、ものごとや問題の全体をとらえなければなりません。」p.60
・「アイディアを次々と生みだす人間になりたいと願うのであれば、かりに先にいる人がいても、その模倣をするという安易な道を選ばないという心掛けが必要でしょう。」p.62
・「記憶力の弱い人というのは、むしろものごとを理解しない人、ものごとに強い関心を持てない人である場合が多いのです。ものごとを大きな全体としてとらえている人は、忘れたことでもたぐりよせることができるし、仮に間違えてもでたらめな間違いはしません。」p.66
・「要するに、脳のはたらきの最大の特性はその変動の柔軟性であり、バランスです。それを自在性ということもできます。脳機能を固定的にとらえるのは無意味です。」p.72
・「人間が言語を駆使できるようになったのは、(中略)口のまわりの筋肉を器用に素速く動かせるようになったからです。そのために、短い音を素速く組み合わせることによって無数の言葉をつくることができるようになりました。」p.78
・「赤とダイダイは近い色ですが、赤と青が違うように別の色なのです。このように、連続しているものでも区切ってしまう言語機能の性質を分節性といいます。このために、事象を細分化して分類整理することができるわけですが、言語機能が事象の全体を見失ってしまうのも分節性のためです。」p.79
・「一般に、ことばの学問というと文学などを指すことが多いのですが、算数とか数学こそことばの学問ということができます。」p.80
・「脳に言語機能がつけ加わって、人間は人間になり得た、という説はかなり根拠のあるものです。この本で動物と共通した非言語機能と人間独自の言語機能に分けて脳機能を論じているところが多いのも、そのためです。」p.101
・「脳のはたらきはリズムを持っており、人間の行動はそのリズムに乗り、また行動のリズムが脳のリズムもつくる、という関係があるので、そこに音楽が参加する意味が生まれるのです。」p.122
・「戦いとか逃走とか、行動しているときには感情という心の変化はみられず、行動を抑えているときには感情が高まるという関係に気づきます。」p.126
・「このように考えると、「男はみんなオオカミ」とか「イヌ畜生にも劣る」というようないい方は動物にたいする侮辱罪にあたるかもしれません。性善説と性悪説にしても、どちらといい切れるものではありませんが、どちらかというと性善説の方が正しいといえます。」p.160
・「理科系に進学する女性はたしかに少数派です。これは、むしろ女性は言語機能が苦手ということなのでしょうが、相対的に非言語機能に頼るところが大きいともいえます。」p.165
・「人間にも非言語的な伝達能力はありますが、言語機能があるので、動物ほどには敏感に機能しにくいという事情があるわけです。」p.169
・「失敗しても、脳のはたらきが発達するためには失敗が必要なのだ、とたかをくくっていればいいのです。」p.193
・「要するに、脳は使ってみなければそのよしあしはわからない、というのが正解でしょう。ただし、むきになればいいというのではなく、使い方が問題です。」p.203
・「睡眠は脳が完全に休息してしまう現象ではなく、それも脳のひとつの働きです。目ざめているときに活動している部分を抑制する力がはたらいているという状態です。」p.208
・「いわゆる「ひらめき」で、われながら名案と感動するような思いつきも、夢と同じように忘れやすいものです。思いつきもそのままでは行動と結びつきませんから、しばらくして消えてしまうのです。従って、創造的な仕事をしている人はいつも筆記道具を持ち歩いて、思いついたところで書き残しておく心掛けが必要です。」p.220