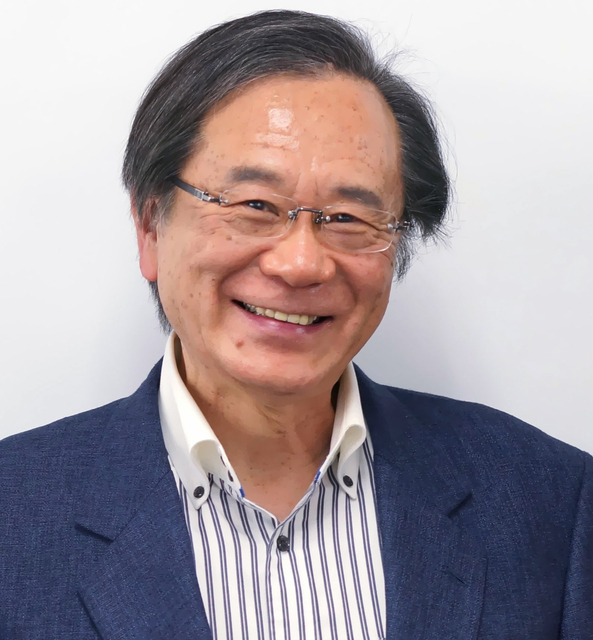痺れた、全身が痺れた。
めくるめくような感動に目頭が熱くなった。
昨日のジョナサン・ノットのショスタコーヴィチ交響曲5番「革命」は、曲のイデー・意味を深く了解させる空前の名演奏で、心底感心し、精神的な興奮が冷めず、今朝は早朝に目覚めてしまった。東響の能力もまた見事。弦には清涼感や透明感があり、コンサートマスターの水谷さんの音の美しさと表現力には心打たれた。木管も見事だし、金管も健闘していた。
一曲目のブリテン渾身の力作であるヴァイオリン協奏曲も適任の大物ダニエル・ホープをソリストに充実の名演だったが、ショスタコーヴィチと並べて演奏されると、作曲家としての次元の違いが際立ってしまう。ブリテンに限らず英国の作曲家は、どうしても「経験論」の世界でcommon sense(常識・良識)の精神風土にあるために、創造者としては限界があることが明瞭になる。一夜のプログラムとしてのまとまりとしては、同じショスタコーヴィチのヴァイオリン協奏曲1番の方がよいはずだが、異なる世界を見せるにはノットの選曲でよいのだろう(とても優れた演奏家や指揮者を排出する英国だが、作曲家=創造者はあまり出ない)。
交響曲5番「革命」は、スターリン主義の官僚独裁政府から批判を浴びていたショスタコーヴィチが放った「社会主義リアリズム」に則った交響曲で、当局からも歓迎され、彼は自身の危機を救ったが、しかし、それは騙しであり、この曲には巧妙に隠された意図があって、メトロノームの速度変更に伴う楽曲の読みにより、表層的な浅薄さとは全く異なる世界を持つ。
従来の西側諸国の有名な指揮者とオケによる演奏は、無邪気なハリウッド映画の交響曲バージョンのような演奏で、かつて名演と呼ばれたものは全てそう。ソ連から生まれた洗練されないドラマとしての交響曲。
それがスターリン死後の彼自身の言葉や1979年のソ連の音楽家ソロモンによる「証言」(その真偽については多くの論争がある)を踏まえた後では、この曲が20世紀の最高の作品(少なくともその一つ)であることを示す名演奏も現れはじめた。
ショスタコーヴィチと深く親交があり、多くの初演を手掛けたムラヴィンスキーは、彼が育てた手兵のレニングラードフィル(当時は世界最高の能力をもつスーパーオケ)と共にこの曲の決定盤と言われる鋼のような強靭な名演を残してしるが、それは、従来の解釈通りの演奏で、演奏が見事な分、内容空疎で退屈な部分もあちこちに散見する。1973年の東京公演でも従来通りの解釈(ムラヴィンスキーの演奏はすべて「証言」前の演奏なので致し方ないが、作曲者と親しかったので期待してしまう)。
ところが、1990年にシュスタコーヴィチの息子マキシム・ショスタコーヴィチがロンドン交響楽団と入れたCDでは、とりわけ問題視された終曲(4楽章)が引きづるような重いテンポで、異様なほどの深い感銘を与える演奏になっている。また、1999年の高齢のクルト・ザンデルリンクによるアムステルダム(ロイヤル)コンセルトヘボーとのライブも従来とはまるで異なる遅いテンポの見事な演奏。1楽章から全曲を通して、さすがの名指揮者に感動する。彼は、若い時にはムラヴィンスキーの元で研鑽を積んだ人で、作曲家との交流をもつ。
ただし、最近でも従来の演奏を踏襲したような演奏が多く、例えば、高評価を受けた小澤征爾・サイトウキネンでは、イデー・意味の希薄な音響美の音楽になっている。
さて、いよいよ昨日の演奏だが、1楽章冒頭から意味に満ちた内容の濃い見事な音楽が鳴る。ノットの曲のつかみは、かつてない明瞭さで、Shostakovichが楽曲に込めた思いを透視して目前に提示するかのごとく。しかも深い共感と愛がある。身体的かつ知的な興奮を誘い、グングンと惹かれる。2楽章も3楽章もみな、内容が濃くて、豊かで強いイデーが立ち現れる。おわってほしくない、という気持ちになる。終曲は遅いテンポで深く沈む込むよう、もの凄い迫力だが、一つも浮いたとことはなく、ムラヴィンスキーにあった平板な個所もない。この曲が、どれほどのものかが痛いほど分かる。20世紀世紀最高の名曲(少なくともその一つ)であることがヒシヒシと実感される。全編にみなぎる寂しさや哀しさは、20世紀の抒情性そのものだし、それは今日も同じ。カタルシスにより浄化され、痺れに痺れた。ただ感動あるのみ。
写真は、演奏会終了後、興奮冷めやらぬ私(撮影は西山裕天君)
サントリーホール