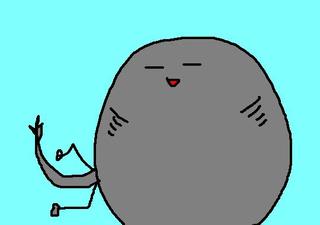
あまりのストレスで足が生えてしまったわたくし
「ヒトラー 最期の12日間」とか「アドルフの画集」といった作品は、基本的に啓蒙的な意味を持っているのであろう。日本ではあまりそうではないが、ヒトラーを普通の人間として把握すること自体が、啓蒙されなければ問題として存在を許されない状態があるからである。たぶん。ただ、問題はそう簡単ではなく、明らかに当時を知らない人間が多くなってきたことと関係があるに違いない。また、ヒトラーを反ユダヤ主義者の権化に祭り上げておかないと、世界にかなりの数居ると思われる反ユダヤ主義(者、ではない)的な人びとを抑圧出来ないという当為も、必要上存在してきたとも思われる。例えば、「スターウォーズ」のダースベーダーにしたところで、彼が普通の人間であることなど自明の理に過ぎず、だからこそことさらに明言してはならないものだったのである。問題は、罪と罰の問題であって、人間性の問題ではないからである。ヒトラーを「悪魔」と切って捨てることは、戦前戦後においては、そういわずにはいられないものであっても、自明の前提ではなかったはずである。たぶん、観念的に自明になったのは最近であって、だからこそ、その概念崩しが必要になってしまう訳である。そうだとすれば、悪人も人間でした、といった姿勢が、進歩とは限らない。啓蒙だからしょうがないかもしれないが、上の映画には、戦後必死に積み上げられてきた、ファシズムやヒトラーの研究、あるいは、当時の芸術運動と労働運動、ナショナリズムとの関係をさぐる研究は、あまり生かされていなかった気がする。
「アドルフの画集」は、第一次大戦の現実をくぐり抜けた者達が、芸術を現実(政治)運動として再生させる理念が当時あったことを強調していたように思う──だからこそ、若きヒトラーは画家として認められないことが事実として突きつけられても、それを政治運動へと観念的に昇華できたというわけで……。いや、そうではない、映画のなかでの若きヒトラーは、画家として何故かだめな自分の悲しみや怒りをそのまま演説の中で活かしていた、つまり、ほとんど彼の演説は「泣き怒る」体をなしていた。これは、あまりにも自意識過剰な側面を強調しすぎであったと思われる。そうすると、彼が考えていた「政治+芸術=力」という観念は、ただ導きの糸であったに過ぎないということであろうか。ことはたぶんそれほど単純ではなかったはずである。ファシズムの問題は、根無し草になった人間の不安から直接に導かれるものではないし、反ユダヤ主義の問題は、またそれとは別である。映画の製作者も無論それは分かっており、映画の結末で、ややトリッキーなことをやっていた……。これは映画の落とし前であって、現実は違うだろう。
「ヒトラー 最期の12日間」で面白かったのは、ベルリンのシェルターで追いつめられたヒトラーが「無能な将軍達をスターリンみたいにちゃんと粛正しとけば良かった」、「ドイツを守るために若者が死ぬのは当然である」、「ドイツ国民が今回滅びても、ドイツは残る」とか叫んでいたことである。たしかにトチ狂っているとも言える訳だが、彼の夢は歴史を超越した純粋アーリア人の住むドイツという夢なので、ユダヤ人の粛正だけでなく、消耗戦を嫌う現実的な軍人達や、いまある命を惜しむ不純な人間たちも滅びて当然という理屈はある意味彼にとっては当然なのである。そしてこの映画も、ヒトラーが自分を芸術家だと思っていたこととこの純粋志向を結びつけたがっていた。したがって、この程度の志向は、ヒトラーでなくても十分起こりうるから、観客は自分の内なるヒトラーに気付くという訳であろう。しかし、だからなんなのだ?卓越した人間は純粋だとでも言いたいのか?いかにも出世主義者の言い訳じみている。そもそも、芸術家でもヒトラーでもない(なりたくもない人びとがほとんであろうが)人間が、勝手に彼らの内面を推測してよいものであろうか。この映画は、晩年のヒトラーの秘書の回想録が原作であり、最後に彼女自身が画面に登場し「当時はいろんなことが見えなかった。しかししっかり見ようと思えば真実が見えたはずだ」と語っていた。この発言が悔恨か保身か、それは分からないが、しっかり見ても分からないものは分からないのではないか。世界では思いもかけないことが起こっていて、実際よく知っていると思っている近親者に関してもまったく同じことである。こういうことは、常に厳しく勉強していないとなかなか分かってこないことであって、半端に勉強したあと啓蒙ばかりやっているとそれが見えなくなってくる。そういう人間の末路は悲惨であり、すべてにおいて自分の見栄を優先し他人にいろいろな意味で暴力をふるうようになる。……思うに、こういうのは、ヒトラーみたいに現実の戦争や政治に忙しいやつよりは、暇な人間に起こる現象であるように思われるのであるが……。









