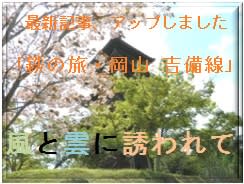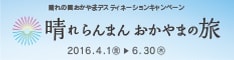昔は「祝祭日」などと言い、この日は休日だ、休館だ、休業だなどとした
ものだが、最近ではこの「祝祭日」と言う言い方は余り聞かれなくなった。

実はこの事が少し気になって、8月に「山の日」が制定されたことを機に、
「国民の祝日に関する法律」を紐解いてみた。
とは言っても長文難解でも無いので、調べると言っても左程の事は無い。
この法律は、昭和23(1948)年7月に制定されていて、二つの条文から出
来ている。

その第一条では、『自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習
を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民
こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づ
ける』とある。
そしてその第二条で「国民の祝日」として具体的に16の祝日と、その制定趣
旨を述べている。

この法律では定めた16日を、はっきりと「国民の祝日」と定義付け、「祝祭
日」との表現はどこにも書かれていない。
更に調べてみるとこの「祭日」と言うのは皇室で祭事が行われる日のことで、
この法律が制定される以前まではその一部が休日となっていた事が解った。

つまり戦後、皇室の祭祀令が廃止され、この法律が制定されて以降は、
国法上では「祝祭日」と言う言い方は制度上無くなったと言うことである。

これは思うに、親世代が戦前から引き継いだ日常会話を、戦後生まれが
耳伝えにそのまま聞き覚えて来た結果であろう。
法律上ではとっくに「国民の祝日」と定義付けられているのに、言葉だけが
連綿と残り続いてきたと言うことらしい。
そういえば昔、親たちは「祝祭日」になると、その日のことを「今日は旗日」
などとも言っていた。(続)

(写真:境港・水木しげるロード 本文とは無関係)
ホームページ「風と雲に誘われて」
最新記事アップしました。
「鉄の旅・岡山 吉備(桃太郎)線」
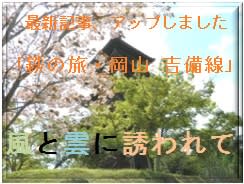
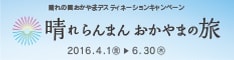

 にほんブログ村
にほんブログ村
ものだが、最近ではこの「祝祭日」と言う言い方は余り聞かれなくなった。

実はこの事が少し気になって、8月に「山の日」が制定されたことを機に、
「国民の祝日に関する法律」を紐解いてみた。
とは言っても長文難解でも無いので、調べると言っても左程の事は無い。
この法律は、昭和23(1948)年7月に制定されていて、二つの条文から出
来ている。

その第一条では、『自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習
を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民
こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づ
ける』とある。
そしてその第二条で「国民の祝日」として具体的に16の祝日と、その制定趣
旨を述べている。

この法律では定めた16日を、はっきりと「国民の祝日」と定義付け、「祝祭
日」との表現はどこにも書かれていない。
更に調べてみるとこの「祭日」と言うのは皇室で祭事が行われる日のことで、
この法律が制定される以前まではその一部が休日となっていた事が解った。

つまり戦後、皇室の祭祀令が廃止され、この法律が制定されて以降は、
国法上では「祝祭日」と言う言い方は制度上無くなったと言うことである。

これは思うに、親世代が戦前から引き継いだ日常会話を、戦後生まれが
耳伝えにそのまま聞き覚えて来た結果であろう。
法律上ではとっくに「国民の祝日」と定義付けられているのに、言葉だけが
連綿と残り続いてきたと言うことらしい。
そういえば昔、親たちは「祝祭日」になると、その日のことを「今日は旗日」
などとも言っていた。(続)

(写真:境港・水木しげるロード 本文とは無関係)
ホームページ「風と雲に誘われて」
最新記事アップしました。
「鉄の旅・岡山 吉備(桃太郎)線」