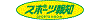福岡3区(福岡市早良区・西区・城南区の一部、糸島市)

山内 康一
山内康一ブログ 『 蟷螂の斧 』
暮らしと経済
安倍政権6年半をふり返る(3):格差が成長を妨げる
2019年 07月06日
クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)
安倍政権6年半をふり返るシリーズ第3弾です。安倍政権の経済政策の基本は、経済成長重視です。公平な分配より、成長を重視する姿勢です。大企業や富裕層が先に豊かになれば、その利益がしたたり落ち(トリクルダウン)、中所得層や貧困層もそのうち豊かになるという発想がアベノミクスの根底にあります。
しかし、近年の研究によれば、格差の拡大は経済成長を阻害します。むしろ再分配政策で格差を是正することが、経済成長につながることがわかっています。アベノミクスの異次元緩和は「2年以内のデフレ脱却」に見事に失敗し、理論的問題があることは明らかです。格差是正を放置して、経済成長を優先することは理論的にも否定されつつあります。約3年前の2016年4月12日付ブログを再掲します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
格差が成長をさまたげる
安倍総理は、消費税増税を延期するためのお墨つきを得るため、国際金融経済分析会合にポール・クルーグマン教授を呼びました。ノーベル経済学賞を受賞したクルーグマン教授は、一般向けにわかりやすい本を書く才能もあり、私も20年以上前の学生時代からクルーグマン教授の著書を愛読してきました。
クルーグマン教授は、消費税増税に否定的な意見も言いましたが、その他にもいろんな意見を発表しています。安倍総理は、クルーグマン教授の他の意見のほうにも耳を傾けてほしいと思います。
クルーグマン教授は「格差是正と経済成長の間でトレードオフはない」と言います。これは経済学の常識が変わりつつあることを意味します。
これまでリベラル派は「経済成長率の低下という犠牲を払っても、低所得者への支援が必要である」と主張してきました。他方、保守派は「富裕層の税率を引き下げ、低所得者への支援を削減し、経済を成長させて全体のパイを拡大すれば、結果的に低所得者の所得も増える(トリクルダウン理論)」と主張してきました。左も右も(=リベラル派も保守派も)「格差是正と経済成長の間にトレードオフがある」という点では一致していました。以前の私もそう思っていました。
クルーグマン教授は、この従来の見方を否定し、「格差が極端になり過ぎると経済成長を損なう」と言います。富の再分配(富裕層への課税強化と低所得層への支援の拡大)は、むしろ経済成長率を上昇させると言います。国際通貨基金(IMF)や国際労働機関(ILO)、経済協力開発機構(OECD)の調査でも、そのことが裏付けられています。国際機関の調査では、日本でも格差拡大が経済成長の足を引っ張っていることが示されています。富裕層をさらに豊かにすることが経済成長につながるわけではなく、貧困を緩和することが経済成長につながることが、だんだん証明されてきています。
極端な経済格差は、人材の有効活用をさまたげ、長期の経済成長に悪影響を与えます。低所得の家庭の子どもが教育を受ける機会を奪われると、将来の労働力の質は低下します。人口減少社会においては、教育への投資は、もっとも高収益の投資です。子どもの貧困が深刻になり、子どもの教育機会が奪われることは、長期の経済成長にマイナスです。所得格差を縮小する政策は、労働力の質を高め、長期の経済成長率の上昇につながります。単に「子どもたちがかわいそうだから、子どもの貧困をなくさなければいけない」という公平性の観点だけではなく、「経済成長を実現するために子どもの貧困をなくさなければいけない」という経済的な視点も重要です。
恥ずかしながら自分の不見識さを告白しますが、私自身も10年ほど前は「上げ潮」路線(トリクルダウン理論)は、日本では有効だと思っていました。しかし、その後の世界中の格差拡大についての調査研究を見て、これまでの経済学の常識が変わりつつあることに気づき、考えを改めました。多くの経済学者や政府関係者も考え方を改めつつあります。
いまの日本で必要な経済政策は、上げ潮(トリクルダウン)志向のアベノミクスではなく、再分配政策の強化です。格差の縮小は経済成長や社会の安定にとって重要です。富裕層を優遇しても経済成長率は下がることが明らかになってきました。再分配政策を強化して、より公平な経済をつくることが、実は経済成長率をあげることになります。格差拡大で社会の分断が進んでいる今こそ、クルーグマン教授の再分配強化の提案に耳を傾けるべき時期だと思います。
*参考:ポール・クルーグマン、2014年、「社会の足を引っ張る格差」(『現代ビジネス』)
関連記事
 ホーム
ホーム
山内康一ブログ 『 蟷螂の斧 』
社会と市民活動、NPO
安倍政権6年半をふり返る(2):ピント外れの子どもの貧困対策
2019年 07月05日
クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)
安倍政権6年半をふり返るシリーズの第2弾です。日本は先進国の中でも子どもの貧困が深刻な国です。ひとり親世帯の貧困率の高さは先進国トップです(特に父子家庭より母子家庭の貧困が深刻です)。
子どもの貧困は、政治の貧困そのものです。子どもの貧困は子どもの責任ではなく、社会全体で取り組むべきです。政府は税金を使って貧困に取り組むのが当然ですが、安倍政権はピント外れな政策を打ち出しました。2016年4月5日付ブログ「国家が寄付を集めるべきか?」の再掲です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
安倍政権の子どもの貧困対策はピント外れです。政府は、鳴り物入りで2015年10月に「子供の未来応援基金」というのをつくり、民間に寄付を呼びかけています。「目的は正しいけれど、手段が間違っている」という政策の典型例です。この政策は官と民の役割分担という観点から問題があります。基本的な発想も間違っているし、費用対効果も最悪です。
1.費用対効果の悪さ
民進党の蓮舫代表代行が予算委員会で費用対効果の悪さを指摘しました。2億円以上の税金を使って寄付を呼びかけて、集まった寄付金は約2千万円だったそうです。2億円の広報費を使って、2千万円の寄付を集めるのは、誰が考えても費用対効果が悪いです。
一般に民間財団やNPOが寄付を呼びかけるときの経費は、寄付金でカバーします。寄付を集めるための広報費は、NPO業界の常識でいえば寄付金額の2割以内がふつうで、1割くらいで済めば優秀な部類です。つまり寄付金を集めるための広報費に2千万円くらい使って、2億円の寄付を集めるといったバランスが、NPO業界の相場観です。集まった寄付金の金額よりも、寄付金集めの広報費が大きいというのは、明らかに失敗です。
せっかく寄付してもその大半が広報費に消えるのでは寄付者は納得しません。NPOは、知恵をしぼって広報費を抑え、なるべく事業費に回す努力をします。政府の「子供の未来応援基金」は、おそろしくバランスが悪く、非効率な事業です。私が寄付者の立場だったら、「子供の未来応援基金」に寄付するより、地元の子ども支援NPOに寄付する方を選びます。
2.官と民のすみ分け
問題は費用対効果だけではありません。そもそも「政府が寄付金を集めるべきか?」という本質的な問題があります。寄付という行為は、民間の発意と善意に基づくべきです。
安倍政権では、何でも国家が口を出そうとします。国家が市場に介入したり、市民社会の領域に介入したり、余計なお世話が多いです。寄付という純粋に民間セクターの行為にまで、国家が介入するのはおかしいです。
国が子どもの貧困対策に資金が必要だと判断したら、税収から予算を確保するのが当然です。国は、寄付を呼びかけるよりも、徴税すればいいわけです。
もちろん民間の力で子どもの貧困問題に取り組むのはたいせつです。しかし、国が音頭をとって民間の企業やNPOをリードしようという姿勢に問題があります。安倍政権では「国民運動」にしたいそうですが、その発想自体が全体主義国家的です。市民の主体的な参画による「市民運動」こそが、21世紀の自由で民主的な社会では望ましいと思います。
3.本来、国がやるべきこと
政府が子どもの貧困対策のために本来やるべきことは、再分配政策の見直しや母子家庭への支援の拡充、貧困家庭への児童手当の増額、就学支援等です。政治の責任で子どもの貧困に取り組むべきであり、税金を投入して当然です。子どもの貧困のような問題にこそ国費を投じるべきです。わざわざ国が寄付を呼びかけるという発想自体がおかしいです。
国が果たすべき役割は、子どもの貧困対策に貢献している企業やNPOの支援のために税金で助成することです。国は資金を出すけれど、市民の自発性は尊重する、という助成が望ましいです。
また、寄付税制を拡充して、NPOが寄付金を集めやすい環境づくりに力を入れるべきです。日本に寄付文化が根付きにくいのは、税制にも原因があります。寄付金控除の手続きを簡素化したり、寄付金の控除額を増やしたりと、寄付しやすい環境を整えるべきです。
安倍政権は、これまでもNPOや市民団体に冷淡で、どんなテーマでも国家が前面に出ようとします。国家主義的、家父長的な態度がにじみ出ています。お上に何でも依存する社会や国家が主導する社会よりも、市民が主体的に課題に取り組む社会が望ましいと私は思います。
関連記事


山内康一ブログ 『 蟷螂の斧 』
平和と外交
安倍政権6年半をふり返る(1):安倍政権の軍事化政策
2019年 07月04日
クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)
参議院選挙の争点は「安倍政権をどう評価するか」だと思います。
そこで安倍政権の6年半をふり返る意味で、過去のブログを引っ張り出すシリーズを始めます。第1回目は2017年10月15日付ブログ「安倍政権の軍事化政策をふり返る」です。以下、再掲です。なお、このブログの後で軍事援助はさらに拡大していることを申し添えます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
安倍政権のタカ派的な政策のなかでは、集団的自衛権や共謀罪の問題は注目され、批判をあびてきました。一方で、目立たない形で粛々とそして着実に日本の「軍事化」が進んでいます。法改正が必要な事項であれば国会で審議され、野党も声をあげる機会があります。しかし、閣議決定だけで静かに進む「軍事化」は目立たないため、あまり国民の目につくことなくいつの間にか進行します。
安倍政権の「軍事化」路線を象徴する4つの事例を取り上げます。なお、以下の事例は少しは報道されましたが、報道が断片的だったこともあり、さほど議論を呼びませんでした。
2013年12月17日「国防の方針」に代えて「国家安全保障戦略」を閣議決定
2014年4月1日「武器輸出三原則」に代えて「防衛装備移転三原則」を閣議決定
2015年2月10日「ODA大綱」に代えて「開発協力大綱」を閣議決定
2016年5月2日 海上自衛隊機(TC90)のフィリピン海軍への貸与に合意
この4つの事例は、国際紛争に積極的に関わろうとする安倍政権の姿勢を象徴しています。これを見れば「積極的平和主義」というよりも、「積極的軍事主義」であることは明らかです。それぞれの含意を見ていきます。
1.大学における軍事研究の解禁
2013年12月17日「国防の方針」に代えて「国家安全保障戦略」を閣議決定しました。そのなかの「知的基盤の強化」という項目で「高等教育機関における安全保障教育の拡充・高度化、実践的な研究の実施等を図る」と述べ、防衛省と大学との共同研究の実施を打ち出しました。大学における軍事研究を促進する狙いです。
これを踏まえ防衛省は2015年から安全保障に関する基礎研究に資金を配分する「安全保障技術研究推進制度」をスタートし、豊橋技術科学大学や東京工業大学などの計9件の研究が選ばれました。一部の大学の研究者としては、研究資金の不足を防衛省の研究費で補おうという意図だったのかもしれません。その後、日本学術会議が大学における軍事研究に慎重な姿勢を見せたこともあり、大学での軍事研究は下火になりました。日本学術会議の見識ある声明のおかげで、安倍政権の意図はくじかれましたが、危ういところでした。
2.武器輸出の解禁と積極的な売り込み
2014年4月1日「武器輸出三原則」に代えて「防衛装備移転三原則」を閣議決定しました。条件付きながら、武器輸出が可能となりました。そしてオーストラリアへの海上自衛隊の潜水艦(そうりゅう)の売り込みに政府は力を入れました。結果的には入札で負けたため潜水艦輸出は成立しませんでしたが、もし実現していれば数千億円(あるいは数兆円)の売り上げになったことでしょう。
アベノミクスの陰の柱のひとつは武器輸出といえます。日本が「死の商人」として国際社会に打って出ることは、日本の平和国家としてのイメージを大きく損ない、長い目で見れば国益を毀損します。紛争に巻き込まれる可能性も高まります。さらに日本が輸出した武器が非人道的な目的に使用された場合には、倫理的・道義的責任を問われます。武器輸出で稼ごうという発想は誤りです。
3.ODAによる他国軍隊援助の解禁
2015年2月10日「ODA(政府開発援助)大綱」に代えて「開発協力大綱」が閣議決定されました。この決定によりODAを使って他国の軍隊を支援することが可能になりました。具体的には「民生目的、災害救助等非軍事的目的の開発協力に相手国の軍又は軍籍を有する者が関係する場合には、その実質的意義に着目し、個別具体的に検討する。」という文言です。民生支援や災害支援に関しては軍隊への支援も可能になります。
しかし、軍隊へのODA供与には問題があります。軍隊の非軍事部門(民生支援や災害支援)の援助であっても、結果的に軍事力増強に役立ちます。第一に日本からODAで援助してもらった分だけ予算が浮きます。浮いたお金を別の軍事的用途に流用できます。
第二に、軍隊が実施する人命救助には、軍事的な意味があります。軍は航空機を使って海洋における人命救助を行いますが、単に人道的な理由でやっているわけではありません。平時は純粋に人道的な理由で人命救助を行うのでしょうが、戦時には撃墜された味方の戦闘機等のパイロットを救い出すために人命救助用の航空機を用意しているわけです。パイロットの救命体制を整えるのは、戦力と士気を維持する上で重要です。戦闘機のパイロットを養成するには莫大な予算と時間がかかり、パイロットの救出は軍事的に重要な意味があります。
第三に、軍の工兵隊(自衛隊では施設科と呼びます)の災害復旧能力は、戦闘で壊れた施設を復旧する能力と同じです。従って、軍の工兵隊の災害援助の能力を強化することは、戦闘能力を強化することと同義です。
軍が行う活動には、すべて軍事的な意味があるといえます。他国の軍隊をODAで支援すれば、当然ながら当該国の敵国(仮想敵国)から恨まれます。百歩譲っても、軍隊へのODA支援が許容されるのは、停戦監視や人道援助に関わるPKO活動への支援だけだと思います。それ以外の軍隊へのODAによる支援はやめた方がよいと思います。
4.他国への軍事援助の解禁
2016年5月2日海上自衛隊の練習機(TC90)をフィリピン海軍に貸与することで合意しました。海洋の警戒監視に使用することが想定されています。南シナ海で中国と領有権を争うフィリピンを支援し、中国をけん制する狙いといわれています。自衛隊装備の他国への供与第一号となります。フィリピン側はP-3C対潜哨戒機を希望していたものの、維持費や技術的な問題もあり、TC90で落ち着きました。日本側は運用に必要な機材を供与し、パイロットや整備士を訓練します。
他国の軍隊に航空機を与え、パイロットや整備士を訓練すれば、まぎれもない軍事援助です。練習機とはいえ、警戒・監視に使うのなら、やはり軍用機です。機関銃やミサイルを装備していなくても、軍用機と見られます。世界の空軍や海軍の偵察機や警戒機には、レーダーやカメラを搭載しているだけで、武装していない航空機もたくさんあります。それでも軍用機と見られます。
中国側は、「日本海軍がフィリピン海軍に軍事援助して、中国の南シナ海進出を食い止めようとしている」と受け取ります。東アジアの軍事的緊張を高めることにつながる可能性は否定できません。最初に南シナ海の軍事的緊張を高めたのは中国かもしれませんが、それに対抗して日本が前のめりに軍拡競争に加わるのがよいことなのか疑問です。
第二次大戦後の中国は、何度も隣国と国境紛争を起こしてきました。領土問題をめぐって中国は、旧ソ連、インド、ベトナムと大規模な武力衝突を起こしています。すべての事例で中国側が先に手を出しています。超大国ソ連との国境紛争でも中国側が先制パンチを浴びせています。中国という国は、いざという時には武力行使をためらわない、という点を理解する必要があります。
フィリピンの大統領が人気取りのために過激な行動をとり、中国との武力衝突のきっかけをつくる可能性がないとは言い切れません。日本が貸与した海自機が、南沙諸島(スプラトリー諸島)で中国軍機に撃墜されたらどうなるでしょうか。日本が中国とフィリピンの国境紛争に巻き込まれる可能性が出てくるのなら、慎重に判断すべきです。南シナ海の航海の自由は重要ですが、そのことと中国・フィリピン間の紛争に自ら進んで関与しようとすることは別問題です。フィリピン海軍への航空機の貸与はやめた方がよいと思います。
以上のように、安倍政権の軍事化の歩みは着実です。安倍政権は、目立たないように、粛々と軍事化を進めています。多くの国民が気づいたときには手遅れになっている、という可能性も十分考えられます。そういう意味でも安倍政治を終わらせないと、本当に戦争に突き進んでしまいます。
「害交の安倍」では?
韓国向け輸出規制は、大きな問題です。いわゆる「徴用工問題」は、日韓の二国間の問題であり、限定的な国際問題です。もっと言えば、徴用工裁判という韓国の司法の問題であり、韓国の行政府(外務省含む)にとって手を出しにくい領域の問題です。
しかし、輸出規制はWTO提訴を招きかねず、国際社会の注目を集め、多国間の問題に飛び火しやすいため、国際社会の日本に対する目線が厳しくなる可能性があります。輸出規制は「徴用工問題の多国間問題化」につながるリスクがあります。
徴用工問題は、多国間の議論になると圧倒的に日本が不利です。国際社会は、ドイツが企業の拠出金で基金をつくって強制労働被害者に賠償した例を知っています。欧米のメディアや政治家は「なぜ日本はドイツと同じことをしないのか?」という素朴な疑問を持つことでしょう。
徴用工問題は、日韓の二国間の問題にとどめておくのが賢明です。多国間の問題に広げるのは日本にとって不利です。しかし、安倍政権は輸出規制によって国際社会の注目を集めてしまいそうです。自ら進んで不利な土俵を設定しているようにしか見えません。
しかも輸出規制は日本企業にも悪影響が及びます。自らの首を絞めることになりかねません。輸出規制対象の品目は日本企業に圧倒的な強みがある分野ですが、韓国企業をはじめ各国企業が危機感をもって自給を目指せば日本企業の競争相手が生まれます。長い目で見れば、日本企業の競争相手を利する規制になりかねません。
輸出規制発表のタイミングも気になります。大阪のG20は目立った成果もなく、参院選の支持率アップに貢献しませんでした。金正恩とトランプの電撃首脳会談に注目が集まり、安倍総理の影が薄くなりました。G20で支持率アップという思惑が外れたので、別の手を考えた結果、輸出規制という強硬な手段を用いたのかもしれません。
おそらく韓国に強硬な態度をとれば「右バネ」がきくという安易な考えが背景にあるのではないかと思います。参院選の真っ最中に排外的なナショナリズムに訴える政策を打ち出すのは危険な火遊びです。ナショナリズムを為政者が煽ることは許されません。歴史の教訓によると、ナショナリズムをもてあそぶとコントロールできなくなります。そういう意味でも現政権のやり方には問題があります。
また、日本は国際捕鯨委員会(IWC)から脱退し、国際社会の厳しい批判を浴びています。IWCには問題があると思います。しかし、だからといって問答無用に脱退するのは、日本のイメージにマイナスの影響を与えます。戦前の国際連盟脱退のミニ版のような印象を受けた方も多いと思います。これも「右バネ」に引っ張られた外交的判断だと思います。安倍政権は日本外交の基盤を崩しつつあります。
勇ましく騒がしい言葉でナショナリズムに訴える外交は、日本のソフトパワーを低下させる一方です。「外交の安倍」だと思っているのは、ご本人と排他的なナショナリストだけだと思います。北方領土交渉も行き詰まり、北朝鮮には無視され、イラン訪問は無駄足に終わり、八方ふさがりです。これでは「害交の安倍」ではないでしょうか。
世論の支持を集めるために、排他的なナショナリズムに訴える政治家がもっとも国益を損ないます。歴史をふり返ると、ナショナリズムに訴える政治家ほど、国益を損なうというパラドックスが見られます。中庸で健全な愛国心を持ちつつも、おだやかな言葉で世界と冷静に交渉できるリーダーが必要です。トランプのミニ版のような外交はやめた方がいいと思います。
前にも引用しましたが、中曽根康弘元首相の言葉で締めくくりたいと思います。昔の自民党の首相は、外交感覚があったものだと今になって感心します。
中庸で健全であるべき愛国心に対して、偏狭なナショナリズムが反作用的に出てくるのはありがちな話だが、国益を長期的観点から考え、短期的に起こる過度のナショナリズムに対して身を以て防波堤としてこれを抑えるのは政治の役割である。当然のことながら、相手国の言動や行動に刺激され、日本のナショナリズムを扇動するようなことがあってはならないし、国民への丁寧な説明と熟慮を重ねた冷静な外交こそが求められる。
*出典:中曽根康弘「宰相に外交感覚がない悲劇」新潮45 2012年11月号
<趣旨>
板垣英憲「オフレコ会」~情報4重構造「表・裏・陰・闇」を解析する。マスメディアの表面に登場して来ない門外不出の「陰と闇」の情報、ブログはもちろん通常の勉強会では語れない内容を取り上げ、少数の参加者の皆様と共に、懇談形式による勉強会を開催いたします。
日 時 7月20日(土)13時~16時まで
会 場 都内某所
(懇談会プログラム)
12:30~13:00 受付
13:00~14:30 講演
14:30~14:45 休憩
14:45~15:50 懇談(質疑応答)
※プログラムのお時間は多少前後いたします。
人数 18名様(申込先着順)
参加費 5000円
お申込みはこちら
本日の「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」
「安倍1強独裁」が、いよいよ中国化し、国民有権者を弾圧、安倍晋三首相は、トランプ大統領提案の「中東地域、海域に有志連合軍派遣」に無条件参加を表明する可能性が大である
◆〔特別情報1〕
「安倍1強独裁」が、いよいよ中国化し、国民有権者を弾圧してきた。安倍晋三首相が7月15日午後4時40分ごろ、JR札幌駅前で、選挙カーの上から自民党公認候補の応援演説を始めた直後、聴衆男性1人が「安倍やめろ、帰れ」などと連呼し始めた途端、北海道警の制服、私服の警官5、6人が男性を取り囲み、服や体をつかんで数十メートル後方へ移動させた。「増税反対」と叫んだ女性1人も強制的に移動させたという。20日には、秋葉原駅近くで、選挙運動期間最後の演説を行う予定というけれど、警視庁は、「安倍やめろ、帰れ」コールが始まれば、一斉に強制排除に乗り出し、場合によっては、続々逮捕に踏み切るのであろうか。軍事的には、憲法9条に「自衛隊」(陸海空軍、宇宙軍)を明記、「男女平等の徴兵制」新設、あるいは、トランプ大統領提案の「中東地域、海域に有志連合軍派遣」に無条件参加を表明する可能性が大である。
つづきはこちら→「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」*有料サイト(申し込み日から月額1000円)
携帯電話からのアクセスはこちら→「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」*有料サイト(申し込み日から月額1000円)
携帯電話から有料ブログへのご登録
「板垣英憲情報局」はメルマガ(有料)での配信もしております。
お申し込みはこちら↓

板垣英憲マスコミ事務所からも配信しております。
お申し込みフォーム
南北首脳会談から米朝会談を経て南北統一へ、そして中国の民主化のシナリオが書かれています。このときから始まっていました。必読です。
 |
日本の覚悟 イルミナティ解体 「新機軸」発動 人類補完計画 この一大事に世界を救う盟主となる |
| クリエーター情報なし | |
| ヒカルランド |
 |
中国4分割と韓国消滅 ロスチャイルドによる衝撃の地球大改造プラン 金塊大国日本が《NEW大東亜共栄圏》の核になる (超☆はらはら) |
| 板垣 英憲 | |
| ヒカルランド |
その改訂版がこれ。併せてお読み頂きたい。
 |
[新装完全版]ロスチャイルドによる衝撃の地球大改造プラン 米国とイスラエルの力を借りて皇国の理念「NEW八紘一宇とNEW大東亜共栄圏」の実現へと向かうNIPPON! |
| クリエーター情報なし | |
| ヒカルランド |
オフレコ懇談会
2019年7月20日(土)13時~16時
元毎日新聞記者・政治経済評論家歴45年!
板垣英憲が伝授する「必勝!」のための情報キャッチ術・情勢判断学~情報4重層「表・裏・陰・闇」とジレンマ情勢予測秘術
会 場 都内某所
参加費 5,000円
【『一由倶楽部 鉄板会』】
令和元年7月31日 (水)14時~16時
会 場 都内某所
参加費 5,000円
イラン沖有志連合が日本に突きつけたもうひとつの踏み絵
果たして日本はどのような形で参加するのだろう。
安保法を強行採決して集団的自衛権の行使を可能にしたのだから、早々と戦争協力できるはずだ。
しかし、これまでの報道では、安倍政権にそうする気配はない。
憲法9条違反の日米同盟であるが、その要請に従って実際に憲法9条違反を行うかどうかは、大きな踏み絵なのである。
そして、ここにきて、もう一つの踏み絵が出て来た。
きょうの各紙が報じている。
イランが日本に対して有志連合に参加しないように促した事がわかったというのだ。
「伝統的な友好国」を売りものにし、とくに父の安倍晋太郎外相が築いたイランとのパイプを大切にする安倍首相は、あっさりとイランの要請を裏切ることが出来るのか。
イランの不参加要請は、安倍首相にとってもうひとつの踏み絵となるとメディアは報じている。
しかし、である。
安倍政権ならずとも、これまで日本は何度も米国の圧力に負けてイランを裏切って来た。
結論から言えば、踏み絵をあっさり踏んで、安倍政権は有志連合に参加するほかない。
日本にとって、日米同盟の前には、いかなる踏み絵も、踏み絵にならないのだ。
憲法9条違反すら踏み絵にならない。
新聞が勝手に「踏み絵を踏まされる」と書いているだけなのである(了)
社会2019年7月19日掲載

特定危険指定暴力団の元幹部だった中本さん。暴力団を離脱し、現在はうどん店を営む()
一段落してきた感のある、吉本興業の芸人らによるいわゆる「闇営業」問題。この報道で頻繁に耳にした「反社会的勢力」だが、彼らと仮に出会うことがあった場合、一般人が事前に察知したり、あるいは見て「おかしい」と気付くことはできるのだろうか。世の中にはファッションでタトゥー入れている善良な人は数多くいる。パンチパーマだって本来、その手の人の専売特許ではない。一方で見るからに善人そうな人、真面目なサラリーマン風の人が実は半グレということだってある。知らないでつきあったら、足をすくわれることにもなりかねない。
速報「靖国神社」を揺るがすセクハラ動画 幹部職員が部下にお触り、被害者は複数人
速報また魔の3回生 自民「石崎徹」議員が秘書にパワハラ、暴行…音声公開
数多くの暴力団関係者や暴力団離脱者からの聞き取りをして、「暴力団博士」の異名を持つ社会学者の廣末登氏(久留米大学非常勤講師)は、こう解説する。
「20年前なら、暴力団関係者は見た目で判断できたでしょうね。代紋をジャケットにつけていたりと、見るからにヤクザだとわかるように振る舞っていましたから。しかし、暴力団排除条例が施行されてからは、どんどん彼らも普通の人に紛れるようになっていきました。見た目もごく普通です。
かなりの人数に会ってきた私でも、ちょっと会って話したくらいでは、区別なんかできません。ましてや、芸人さんたちにすぐ気付けというのは無理がある気もします。
知り合いの元暴力団員から聞いたこんな話があります。彼はカタギになるために組をやめて、会社の営業マンになった。一所懸命に働いていたら、ある時、邪魔な商売敵を『さらってこい』と命じられた。それを拒否したらボコボコにされて、そこでようやく『ここも暴力団関係だった!』と気づいた、というのです。会社はカモフラージュしていたから、就職時にはわからなかったそうです。
暴力団に限りません。オレオレ詐欺集団のメンバーだって、多くは見た目は普通です。特に出し子(預金を引き出す役)なんかは、本当に普通の子がやっていることが多い。
見た目で気付け、というのはちょっと無理があるのではないでしょうか。まあ、そもそも気付いたとして毅然とした態度を取るのもまた難しいでしょうし……」
多くの離脱者からの聞き取りをしてきた廣末氏が懸念しているのは、仮に知らなかったとはいえ反社会的勢力と交際した場合にどの程度の制裁が課されるべきか、という問題だ。目下、数多くの芸人が「無期限謹慎」などの厳しい処分を受けている。交際すること自体が非常識だ、というのが一種の社会的コンセンサスになっているのは事実だろう。だから、昔のように「芸能と裏社会は切っても切れない関係」なんて言い分は通用しない。
しかし、それが社会の安定につながるのかは、長い目で見た場合、簡単な話ではない。
「正義感の強い方ほど、『そんなやつらはどうなっても知ったことか』と厳しい意見を述べるのかもしれません。暴力団排除条例などもそういう考えのもとに作られたため、暴力団を離脱してから5年は銀行口座新規開設ができない、インフラ(水道・電気など)を除く契約行為(不動産の賃貸契約など)ができない、生命保険他に加入できない、などの制約が課せられることになっています」
廣末氏の著作『ヤクザの幹部をやめて、うどん店はじめました。――極道歴30年中本サンのカタギ修行奮闘記』は、九州で組幹部までつとめた男性が、カタギを志して地元でうどん店を開業するまでの苦闘を描いたドキュメントだ。組を抜けた直後には、口座開設も賃貸契約もままならなかったものの、地域の人々に支えられて更生を果たし、現在も店は繁盛しているという。これは一種の心温まるストーリーになっているが、もしも地元の人たちの温かい支援が無ければ、どうなっていただろう。
もちろん、ある程度の壁は当然の報いだ、と厳しい見方も必要だろう。が、最近では、警察も、離脱者にあまりに高いハードルを課すことは逆効果になりかねない、という視点を持つようになってきたのだという。
「結局、追い詰めすぎると、カタギには戻らず、また悪の道に戻る。また、カモフラージュが巧みになっていくので、さきほどもお話ししたように、一般人に紛れてしまう。それが長期的に見た場合に、本当に社会のためになるのかは冷静に考えたほうがいいのではないでしょうか。
2010年~2017年度で、警察の支援で暴力団を離脱したのが4170人で、そのうち、把握されている就労者は2.6%ほどです。『ざまあみろ、当然の報いだ』と思われるかもしれませんが、残りの人が何をしているのか。あるいはカタギに戻ろうとして挫折したとき、どこへ向かうのか。そこを見る必要があります。暴力団員とそこからもはぐれたアウトローとどちらが危険なのか、ということです。
これは芸能界の話にも通じるかもしれません。薬物に手を出した芸能人、あるいは今回の芸人たちが、一定のペナルティを課されるのは仕方ないでしょう。でも、廃業するまでに追い詰めることがいいのかは議論の余地があるのではないでしょうか」
手弁当で、犯罪少年や暴力団離脱者の更生に尽力している「暴力団博士」の言葉には耳を傾ける価値があるのではないか。
18歳・三上紗也可、記憶障害乗り越え東京五輪内定4号「運命の競技」…女子板飛び込み
◆世界水泳第7日(18日、韓国・光州)
【光州(韓国)18日=ペン・太田倫、カメラ・竜田卓】女子板飛び込み準決勝で、三上紗也可(18)=米子DC=が307・95の7位で12人で争う決勝(19日)に進出し、東京五輪を事実上内定させた。決勝で順位が確定次第、正式に出場権を得る。高校卒業後、進学や就職をせず、飛び込み一本に懸ける生活を送ってきた“浪人ダイバー”。けがによる引退危機を乗り越え、今大会の飛び込み陣では、4人目の五輪内定者となった。
覚悟の強さが、きれいな入水を導き出した。三上の準決勝3本目。予選で失敗した305B(前逆宙返り2回半エビ型)を練習通りに決めた。67・50のハイスコア。コーチが両手を天に突き上げた。「今は実感はそんなになくてフワフワしている感じ」。ヤマ場を乗り越え、307・95の7位。東京五輪へのチケットを事実上、手に入れると、白い歯がやっとのぞいた。
今春の高校卒業後、進学や留学という憧れを一時封印し、飛び込み一本に懸けている。練習は高校時代から安田千万樹(ちまき)コーチ(48)とマンツーマン。地元・鳥取県に合宿費用などの支援を受け、アルバイトさえもせずに競技に打ち込む。「覚悟を決めました。五輪に行かないと恩返しできない」。実家から通う飛び込み練習は1日6時間。それ以外の時間も、体のケアや筋力トレーニングに充てる生活だ。
浪人ダイバーとなったのは、安田コーチのバックアップがあったから。現役時代は1994年広島アジア大会3メートル板飛び込み銅メダルという安田コーチから、高校2年の時に勧められた道だ。「三上は器用じゃない。圧倒的な力はない。退路を断って、何かを捨てないと集中できない」。練習時間や環境を最大限確保するためだった。熱意に打たれた三上一家が首を縦に振った。
ずぬけた脚力を持っていた三上は中3で腰椎分離症を患うなど、故障が多かった。昨夏は引退危機に陥った。合宿中に飛び板に後頭部を強打し、17針縫う裂傷。脳しんとうで一時的に記憶障害、健忘症に陥った。「5分ごとに記憶をなくすんです。すぐ前にあったことを忘れてしまう。どうしたらいいのか、と」。安田コーチは責任を感じ、両親に「これ以上指導は無理」と伝えた。だが、逆に「お願いします」と頭を下げられ、師弟関係は続いた。幸い約1か月で競技に復帰し、後遺症はない。「絶対五輪でメダルを取りたい気持ちがあったから、乗り越えられた」と、三上も振り返る。
今大会、飛び込み陣の内定者は寺内健、坂井丞、荒井祭里に次ぎ4人目。19日の決勝に臨む、18歳がこんなセリフを吐くと説得力がある。「飛び込みという競技が、自分にとって運命の競技だった」
◆三上 紗也可(みかみ・さやか)2000年12月8日、鳥取・米子市生まれ。18歳。小学2年の時、学校で飛び込み教室の案内が配られたのをきっかけに、競技を始める。中学時代は腰のけがなどに悩まされるが、米子南高1年時には高校総体で優勝するなど頭角を現した。昨夏のジャカルタ・アジア大会では3メートル板飛び込みで4位。155センチ、53キロ。
18歳・三上紗也可、記憶障害乗り越え東京五輪内定4号「運命の競技」…女子板飛び込み
◆世界水泳第7日(18日、韓国・光州)
【光州(韓国)18日=ペン・太田倫、カメラ・竜田卓】女子板飛び込み準決勝で、三上紗也可(18)=米子DC=が307・95の7位で12人で争う決勝(19日)に進出し、東京五輪を事実上内定させた。決勝で順位が確定次第、正式に出場権を得る。高校卒業後、進学や就職をせず、飛び込み一本に懸ける生活を送ってきた“浪人ダイバー”。けがによる引退危機を乗り越え、今大会の飛び込み陣では、4人目の五輪内定者となった。
覚悟の強さが、きれいな入水を導き出した。三上の準決勝3本目。予選で失敗した305B(前逆宙返り2回半エビ型)を練習通りに決めた。67・50のハイスコア。コーチが両手を天に突き上げた。「今は実感はそんなになくてフワフワしている感じ」。ヤマ場を乗り越え、307・95の7位。東京五輪へのチケットを事実上、手に入れると、白い歯がやっとのぞいた。
今春の高校卒業後、進学や留学という憧れを一時封印し、飛び込み一本に懸けている。練習は高校時代から安田千万樹(ちまき)コーチ(48)とマンツーマン。地元・鳥取県に合宿費用などの支援を受け、アルバイトさえもせずに競技に打ち込む。「覚悟を決めました。五輪に行かないと恩返しできない」。実家から通う飛び込み練習は1日6時間。それ以外の時間も、体のケアや筋力トレーニングに充てる生活だ。
浪人ダイバーとなったのは、安田コーチのバックアップがあったから。現役時代は1994年広島アジア大会3メートル板飛び込み銅メダルという安田コーチから、高校2年の時に勧められた道だ。「三上は器用じゃない。圧倒的な力はない。退路を断って、何かを捨てないと集中できない」。練習時間や環境を最大限確保するためだった。熱意に打たれた三上一家が首を縦に振った。
ずぬけた脚力を持っていた三上は中3で腰椎分離症を患うなど、故障が多かった。昨夏は引退危機に陥った。合宿中に飛び板に後頭部を強打し、17針縫う裂傷。脳しんとうで一時的に記憶障害、健忘症に陥った。「5分ごとに記憶をなくすんです。すぐ前にあったことを忘れてしまう。どうしたらいいのか、と」。安田コーチは責任を感じ、両親に「これ以上指導は無理」と伝えた。だが、逆に「お願いします」と頭を下げられ、師弟関係は続いた。幸い約1か月で競技に復帰し、後遺症はない。「絶対五輪でメダルを取りたい気持ちがあったから、乗り越えられた」と、三上も振り返る。
今大会、飛び込み陣の内定者は寺内健、坂井丞、荒井祭里に次ぎ4人目。19日の決勝に臨む、18歳がこんなセリフを吐くと説得力がある。「飛び込みという競技が、自分にとって運命の競技だった」
◆三上 紗也可(みかみ・さやか)2000年12月8日、鳥取・米子市生まれ。18歳。小学2年の時、学校で飛び込み教室の案内が配られたのをきっかけに、競技を始める。中学時代は腰のけがなどに悩まされるが、米子南高1年時には高校総体で優勝するなど頭角を現した。昨夏のジャカルタ・アジア大会では3メートル板飛び込みで4位。155センチ、53キロ。』
三上紗也可選手の此までの苦労が報われ、女子板飛び込みの東京オリンピックでのメダル獲得をお祈り申し上げます。