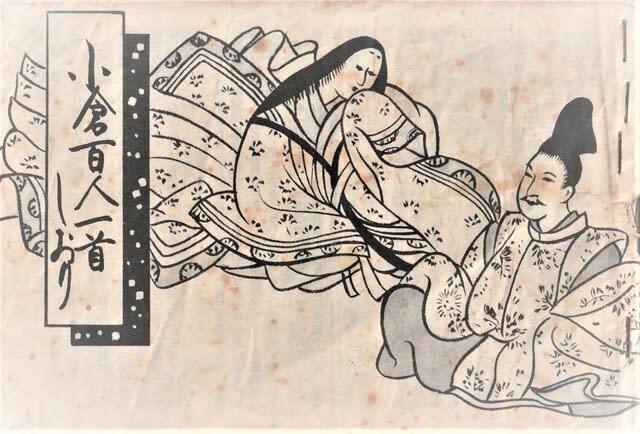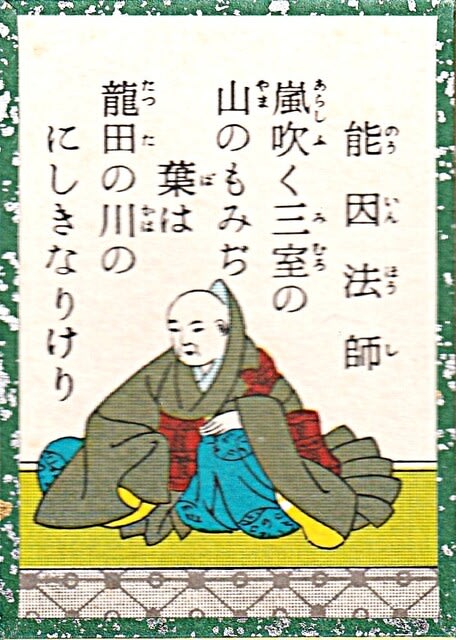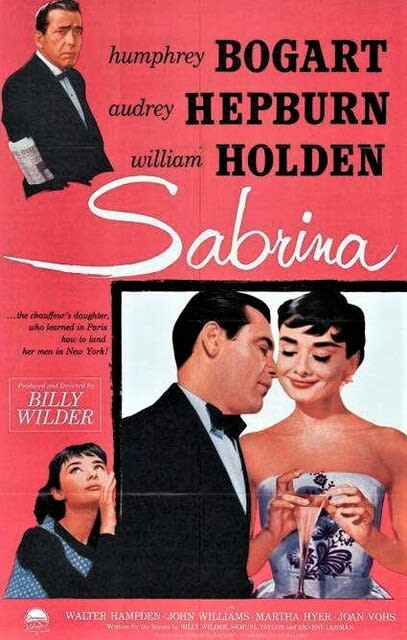草花にも超疎い爺さん、ブログを始めた頃までは、我が家の庭に咲く花であろうが、道端、空き地、畑地、川原等で蔓延っている野草であろうが、公園や植物園等で鑑賞出来る草木であろうが、まるで関心も興味も無しで、見ても、花名も知らず、分からず、覚えられずで、ほとんど珍紛漢紛だった気がする。数多のブログを拝見するようになってから、その無知ぶりを痛感、初めて、花名等を知ろうという気になったものだったが、教えてもらっても、自分で調べても そのそばから忘れてしまう老脳、出来る限り、写真を撮ってきて、ブログ・カテゴリー「爺さんの備忘録的花図鑑」に書き込むことで、少しづつだが、分かる草花が増えてきたように実感している。草花に詳しい人からは、「なーんだ、そんな花も知らなかったの?」と笑われそうだが、爺さんにとっては、新情報、新知識、後日、また忘れてしまった時等に、確認したりするのに役に立つ存在になっている。花名を調べたり、知ったところで、ナンボになる分けでも無しだが、脳トレ、ボケ防止の一助になるかも知れない等と、勝手に思い込みながら・・・
先日、散歩・ウオーキングの途中で見掛けて撮っていた「サフラン」。
「サフラン」という花名だけは、かなり以前から知っていた気がするが、
詳しく知るはずもなく、これまで知った、「イヌサフラン」、「クロッカス」等とも
混同してしまっており、未だに、サッとは、花名同定出来ないでいる。
2020年11月7日、散歩・ウオーキングの途中で見掛け撮っていた「サフラン」


2024年11月13日、散歩・ウオーキングの途中で見掛け撮っていた「サフラン」

サフラン
アヤメ科、クロッカス属、多年草、
別名「薬用サフラン」、「秋クロッカス」
地中海地方では、青銅器時代から栽培されていたとされる植物で、
紀元前から、雌しべを、香辛料、染料、香料、薬用として利用された。
原産地 地中海沿岸、小アジア
日本には、江戸時代、薬用として渡来。
草丈 20cm~30cm、
花色 紫色、
赤くて長い3本の雌しべと、3本の黄色の雄しべが特徴。
開花時期 10月頃~11月頃、
花言葉 「歓喜」「過度を慎め」「濫用するな」
「サフラン」と「クロッカス」の違い・見分け方
「サフラン」 「クロッカス」
◯開花時期 10月頃~11月頃 2月頃~4月頃
◯花色 紫色のみ 黄色、紫色、白色等 多種
◯雄しべ・雌しべ 赤色の3本の長い雌しべと 黄色の雄しべが真ん中に固まる
黄色の3本の雄しべ
◯別名 「薬用サフラン」 「花サフラン」
「秋咲きサフラン・秋クロッカス」
「番紅花」
「爺さんの備忘録的花図鑑」・「クロッカス」
👇️
こちら