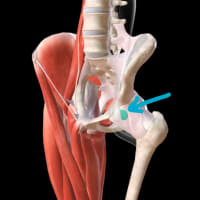各疾患の治療法や各部位ごとの技法の講義をしていると、
時折若い参加者から
「このテクニックであれば何日間痛みを止められますか?」
といった質問を受けることがあります。
これは真面目に考えると考えるほどに、返答に困ってしまう質問なのです。
私は
「3日もたすことができたら、少なくともその治療の方向性は間違っていないと考えていいのではないでしょうか。」
と答えるようにしています。
なぜそんな回りくどい言い方をするのかと言うと、私はテクニック自体が痛みを消す力を持つものではないと考えているからです。
たとえ話をします。
物語なんかで伝説の聖剣を持つとどんな敵でもバッタバタと倒してゆく…
みたいな話があるじゃないですか。
でも実際はどんなに優れた剣でも、使う人間の技量によって敵を倒せるかどうかが決まるものでしょう!?
北斗神拳という拳法が強いのではなく、ケンシロウやラオウが強いって言えばイメージがつく方もいるかも。
ジャギでしたっけ!?兄弟の中でも弱いキャラもいたでしょう!?
治療の技も同じで、その技法が「強い」のではなく、
「強い」結果に結びつけるには使う技師の判断力が大事なんです。
痛みは日常頻回に取られる姿勢や動作によって身体に癖が付き、
負荷が強く集まる箇所ができてしまったり、関節の動きがガタついてしまったりしたことで
局所的に筋肉が痙攣を生じてしまったり、関節周辺の組織が傷付いてしまったり、
などといった経緯で出てきます(他にも痛みが生じるシチュエーションはあるでしょうが...)。
なので「痛み」を止めるには、
何による痛みなのか(炎症か?循環不全か?痙攣か?など)?
を判断し、取りうる対応を考えます。
炎症性の問題であれば患部に急性期の対応(安静・冷却・圧迫・挙上)をし、患部が落ち着くのを待たなければいけません。
痙攣や循環不全による痛みであればすぐさま患部に手を入れることもできます。
これを東洋医学では「表治:ひょうち」と言います。(ふふふ、鍼灸師っぽいでしょう!?)
痛みに対する直接的な対処を指します。
そして、その一方で、
どうして傷害をおった局所にばかり負担が集まってしまうのか?
を読み解いて、
負担を除くためにできることななにか?
を考えて、
その負担を除くための行程をたどるためにどの技法が適しているのか判断し、対処してゆきます。
つまり、痛みが出るおおもとの問題にテコ入れをしてゆくということです。
これを東洋医学では「本治:ほんち」と言います。(むふふ、鍼灸師っぽいでしょう!?)
ちなみにこれは慢性期だけでなく急性期にも行うことのできる分野です。
例えば、捻挫や肉離れといった急性期の問題であれば急性期の対応(安静・冷却・圧迫・挙上)をし、
患部が落ち着くのを待たなければいけないのは当たり前のことですが、
そうした最中でも、患部への負担を集めてしまう周辺の要素(姿勢やコントロールの問題など)には手を入れることはできるでしょう!?
なぜそうするかって、患部の負担が減ればそれだけ治りが早いからです。
東洋医学ではこれらを同時に行うことを「表本同治:ひょうほんどうち」と呼び、
本来の治療としています。(ぐふふ、鍼灸師っぽいでしょう!?)
ま、それはいいとして、治療手技ありきではなく、身体を読み解く評価に基づいて治療は始まるのです。
つまり、テクニックは思い描いた「治るための道筋」に向けた変化を導くための「道具」なのです。
どんなに良い道具でも、使い道が定まらなめれば結果を出すことができません。
なので、先ほどの「3日もてば…」や「聖剣」の話となったのです。
徒手医学の技法にはその変化に驚かされるものもゴロゴロしています。
ですので、学生時代の私も前出の先生のように考えた時期もありました。
そうした誤解も臨床を通じて正されてゆくものだと思います。
先の先生も、これからきっといつか解る時が来るでしょう。
なんとなく、「わっかるかなぁ~!?わっかんねぇ~だろ~なぁ~ いえ~い!」by松鶴家千とせ師匠
的なやり取りになってしまって気になってしまって…
ここで書いてもどうかとも思いつつ、書いてみました。
名前も解らないけど、読んでくれると良いな。