存在としての建築 隈研吾
三段落 ⑫~⑮
⑫ あるものが、それが存在する場所と幸福な関係を結んでいるときに、我々は、ものを自然であると感じる。自然とは関係性である。自然な建築とは、場所と幸福な関係を結んだ建築のことである。〈 場所と建築との幸福な結婚 〉が、自然な建築を生む。
⑬ では幸福な関係とは何か。場所の〈 景観 〉となじむことが、幸福な関係であると定義する人もいる。しかし、〈 この定義 〉は、〈 建築を表象として捉える建築観 〉に、依然としてとらわれている。場所を表象として捉えるとき、場所は、景観という名で呼ばれる。表象としての建築と、景観という表象とを調和させようという考えは、ひと言で言えば他人事として建築や景観を評論するだけの、傍観者の議論である。表象として建築を捉えようとしたとき、我々は場所から離れ、視覚と言語にとらわれ、場所という具体的でリアルな存在から浮遊していく。コンクリートの上に、仕上げを貼りつけるという方法で表象を操作し、「景観に調和した建築」をいくらでも作ることができる。表象の操作の不毛に気づいたとき、僕は景観論自体が不十分であることを知った。
⑭ 〈 場所に根を生やし 〉、場所と接続されるためには、建築を表象としてではなく、存在として、捉え直さなければならない。単純化して言えば、あらゆる物は作られ(生産)、そして受容(消費)される。表象とはある物がどう見えるかであり、その意味で受容のされ方であり、受容と消費とは人間にとって同質の活動である。一方、存在とは、生産という行為の結果であり、存在と生産とは不可欠で一体である。どう見えるかではなく、どう作るかを考えたとき、初めて幸福とは何かがわかってくる。
⑮ 二十世紀には存在と表象とが分裂し、表象をめぐるテクノロジーが肥大した結果、存在(生産)は極端に軽視された。どうあるか、どう作られているかではなく、どう見えるかのみが注目された。〈 二十世紀は広告代理店の世紀であった 〉と要約した人がいるが、表象の操作を繰り返せば、広告だけは無限に作り出すことができ、それなりの感動も驚きも作り続けることはできる。しかし、〈 それ 〉は人間の本当の豊かさとは関係ない。広告代理店にとっての豊かさではなく、人間にとっての豊かさを探りたければ、建築をどう生産するかに対して、我々は再び着目しなければならない。
Q19「景観」とはどのようなものだと筆者は述べているか。15字以内で答えよ。
A19 場所を表象として捉えたもの
Q20「この定義」とは何か。25字程度で答えよ。
A20 建築が場所の景観となじむことを幸福な関係とすること。
Q21「建築を表象として捉える建築観」に基づいて作られるものは何か。11字で抜き出せ。
A21「景観に調和した建築」
「場所に根を生やし」について、
Q22「場所に根を生やし」とは、何が、どうなることか。本文の言葉を用いて、30字以内で記せ。
A22 建築が、表象ではなく具体的でリアルな場所と接続すること。
Q23 22のようになった状態を比喩的にどう述べていたか。12字で抜き出せ。
A23 場所と建築との幸福な結婚
Q24 23のために、何を考えなければならないのか。16字で抜き出せ。
A24 どう見えるかではなく、どう作るか
Q25「二十世紀は広告代理店の世紀であった」とあるが、この状態をもたらした要因は何か。20字以内で抜き出して記せ。
A25 表象をめぐるテクノロジーが肥大した
Q26「それ」とは何か。40字以内で記せ。
A26 表象の操作によって生まれた無限の広告により、人々に感動を驚きを与えていること。
⑫ あるもの
↓↑ 幸福な関係 → ものを自然であると感じる
存在する場所
∥
建築
↓↑ 幸福な関係 → 自然な建築
場所
⑬ 景観……場所の表象
↓↑
建築……表象としての建築
∥
「景観に調和した建築」
↓
存在から浮遊していく
↑
↓
⑭ 場所……具体的でリアルな場所
↓↑
建築……存在としての建築
∥
自然な建築
↓
場所に根を生やし 場所と接続
表象……どう見えるか=受容・消費
↑
↓
存在……どう作るか=生産 → 幸福
Q27「場所と建築との幸福な結婚」とはどういうことか。(70字以内)
A27 建築物が、
どう見えるかよりもどう作るかを優先して生産され、
具体的でリアルな場所から浮遊することなく接続し、
自然な状態で存在していること。
⑮二十世紀
存在と表象とが分裂
表象のテクノロジーが肥大
↓
存在(生産)の軽視
∥
どう見えるかのみが注目
二十世紀……広告代理店の世紀
∥
表象を操作する人が時代の主役
∥
広告代理店の豊かさ
↑
↓
人間の本当の豊かさ
Q28「二十世紀は広告代理店の世紀であった」とはどういうことか。(50字以内)
A28 もの自体の作り手ではなく
ものの表象を操作する人間が、
二十世紀の経済活動の主役であったということ。
三段落 ⑫~⑮
⑫ あるものが、それが存在する場所と幸福な関係を結んでいるときに、我々は、ものを自然であると感じる。自然とは関係性である。自然な建築とは、場所と幸福な関係を結んだ建築のことである。〈 場所と建築との幸福な結婚 〉が、自然な建築を生む。
⑬ では幸福な関係とは何か。場所の〈 景観 〉となじむことが、幸福な関係であると定義する人もいる。しかし、〈 この定義 〉は、〈 建築を表象として捉える建築観 〉に、依然としてとらわれている。場所を表象として捉えるとき、場所は、景観という名で呼ばれる。表象としての建築と、景観という表象とを調和させようという考えは、ひと言で言えば他人事として建築や景観を評論するだけの、傍観者の議論である。表象として建築を捉えようとしたとき、我々は場所から離れ、視覚と言語にとらわれ、場所という具体的でリアルな存在から浮遊していく。コンクリートの上に、仕上げを貼りつけるという方法で表象を操作し、「景観に調和した建築」をいくらでも作ることができる。表象の操作の不毛に気づいたとき、僕は景観論自体が不十分であることを知った。
⑭ 〈 場所に根を生やし 〉、場所と接続されるためには、建築を表象としてではなく、存在として、捉え直さなければならない。単純化して言えば、あらゆる物は作られ(生産)、そして受容(消費)される。表象とはある物がどう見えるかであり、その意味で受容のされ方であり、受容と消費とは人間にとって同質の活動である。一方、存在とは、生産という行為の結果であり、存在と生産とは不可欠で一体である。どう見えるかではなく、どう作るかを考えたとき、初めて幸福とは何かがわかってくる。
⑮ 二十世紀には存在と表象とが分裂し、表象をめぐるテクノロジーが肥大した結果、存在(生産)は極端に軽視された。どうあるか、どう作られているかではなく、どう見えるかのみが注目された。〈 二十世紀は広告代理店の世紀であった 〉と要約した人がいるが、表象の操作を繰り返せば、広告だけは無限に作り出すことができ、それなりの感動も驚きも作り続けることはできる。しかし、〈 それ 〉は人間の本当の豊かさとは関係ない。広告代理店にとっての豊かさではなく、人間にとっての豊かさを探りたければ、建築をどう生産するかに対して、我々は再び着目しなければならない。
Q19「景観」とはどのようなものだと筆者は述べているか。15字以内で答えよ。
A19 場所を表象として捉えたもの
Q20「この定義」とは何か。25字程度で答えよ。
A20 建築が場所の景観となじむことを幸福な関係とすること。
Q21「建築を表象として捉える建築観」に基づいて作られるものは何か。11字で抜き出せ。
A21「景観に調和した建築」
「場所に根を生やし」について、
Q22「場所に根を生やし」とは、何が、どうなることか。本文の言葉を用いて、30字以内で記せ。
A22 建築が、表象ではなく具体的でリアルな場所と接続すること。
Q23 22のようになった状態を比喩的にどう述べていたか。12字で抜き出せ。
A23 場所と建築との幸福な結婚
Q24 23のために、何を考えなければならないのか。16字で抜き出せ。
A24 どう見えるかではなく、どう作るか
Q25「二十世紀は広告代理店の世紀であった」とあるが、この状態をもたらした要因は何か。20字以内で抜き出して記せ。
A25 表象をめぐるテクノロジーが肥大した
Q26「それ」とは何か。40字以内で記せ。
A26 表象の操作によって生まれた無限の広告により、人々に感動を驚きを与えていること。
⑫ あるもの
↓↑ 幸福な関係 → ものを自然であると感じる
存在する場所
∥
建築
↓↑ 幸福な関係 → 自然な建築
場所
⑬ 景観……場所の表象
↓↑
建築……表象としての建築
∥
「景観に調和した建築」
↓
存在から浮遊していく
↑
↓
⑭ 場所……具体的でリアルな場所
↓↑
建築……存在としての建築
∥
自然な建築
↓
場所に根を生やし 場所と接続
表象……どう見えるか=受容・消費
↑
↓
存在……どう作るか=生産 → 幸福
Q27「場所と建築との幸福な結婚」とはどういうことか。(70字以内)
A27 建築物が、
どう見えるかよりもどう作るかを優先して生産され、
具体的でリアルな場所から浮遊することなく接続し、
自然な状態で存在していること。
⑮二十世紀
存在と表象とが分裂
表象のテクノロジーが肥大
↓
存在(生産)の軽視
∥
どう見えるかのみが注目
二十世紀……広告代理店の世紀
∥
表象を操作する人が時代の主役
∥
広告代理店の豊かさ
↑
↓
人間の本当の豊かさ
Q28「二十世紀は広告代理店の世紀であった」とはどういうことか。(50字以内)
A28 もの自体の作り手ではなく
ものの表象を操作する人間が、
二十世紀の経済活動の主役であったということ。










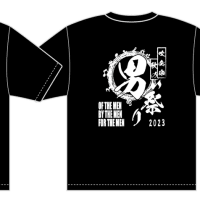





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます