評論文では意味段落ごとに解いていくように、小説は場面ごとに解いていきます。
場面とは何か。
何らかの出来事が生成する状況が描かれたひとまとまりのことです。シーンとも言いますね。
a時間とb空間、そしてc登場人物で規定されます。
第一場面を見てみましょう。
譜面をパートごとに練習して、セクションごとに音として仕上げていくのは、山から石を切り出す作業だが、そのごろごろした石がようやくしっかりとした石組みになろうとしていた。森勉が細やかに出す指示は、石と石の接続面をぴったりと合わしていく仕事だった。
この日、何度目かで「くじゃく」をさらっていた時、克久はばらばらだった音が、一つの音楽にまとまる瞬間を味わった。スラブ風の曲だが、枯れ草の匂いがしたのである。斜めに射す入り陽の光が見えた。それは見たことがないほど広大な広がりを持っていた。いわく言い難い哀しみが、絡み合う音の底から湧き上がっていた。悔しいとか憎らしいとか、そういういらいらするような感情は一つもなくて、大きな哀しみの中に自分がいるように感じた。つまり音が音楽になろうとしていた。地区大会前日だった。
地区大会の前日の場面ですね。場所は音楽室でしょう。
その日、主人公の克久は「音が音楽になろうとす」る瞬間を体験します。
問2 傍線部A「音が音楽になろうとしていた」とあるが、それはどういうことか。その説明として最も適当なものを選べ。
① 指揮者の指示のもとで各パートの音が融(と)け合い、具象化した感覚や純化した感情を克久に感じさせ始めたこと。
② 指揮者に導かれて克久たちの演奏が洗練され、楽曲が本来もっている以上の魅力を克久に感じさせ始めたこと。
③ 練習によって克久たちの演奏が上達し、楽曲を譜面通りに奏でられるようになったと克久に感じさせ始めたこと。
④ 各パートの発する複雑な音が練習の積み重ねにより調和し、圧倒するような迫力を克久に感じさせ始めたこと。
⑤ 各パートで磨いてきた音が個性を保ちつつ精妙に組み合わさり、うねるような躍動感を克久に感じさせ始めたこと。
「音が音楽になる」とは、どういうことでしょうか。
選択肢を見ると、
「②演奏が洗練され、楽曲が本来もっている以上の魅力を克久に感じさせ始めた」
「④練習の積み重ねにより調和し、圧倒するような迫力を克久に感じさせ始めた」
「⑤音が個性を保ちつつ精妙に組み合わさり、うねるような躍動感」
などとありますが、どれも正解のように見えませんか。
実際に、このような意味合いで「音が音楽になる」と言われることはよくあります。
「③楽曲を譜面通りに奏でられるようになった」の意味ではあまり用いられないでしょうか。
「譜面通りに吹くだけじゃ、音楽にならないんだよ!」と怒られることさえありますから。
傍線部と選択肢を見るだけでは、この問題は解けません。
場面全体をふまえましょう。
さらに傍線部の「つまり」にも注意しましょう。
「つまり」は言い換えですから、「つまり」の前後は「=(イコール)」の関係です。
克久はばらばらだった音が、一つの音楽にまとまる瞬間を味わった。
∥
枯れ草の匂いがしたのである。入り陽の光が見えた。
大きな哀しみの中に自分がいるように感じた。
∥
つまり「音が音楽になろうとしていた」
演奏から、具体的イメージがわき、感情がわきあがってきます。
それを、選択肢①では「具象化した感覚や純化した感情」と言い換えています。
①が正解です。
「各パートの音が融け合い」も、本文の「ばらばらだった音が、一つの音楽にまとまる」と対応してます。
問2を間違えた人は、
1 場面で解くという意識が欠けている
2「具象化」が何のことかわからなかい
3「つまり」をチェックしていない
が、原因のはずです。123のような状態の人を専門用語で「テキトーに解く人」とよんでいます。
問3 傍線部B「怒られるたびに内心で『ちゃんとやってるじゃないか』とむくれていた気持ちがすっかり消えた」とあるが、それはなぜか。その理由として最も適当なものを選べ。
① 日々の練習をきちんと積み重ねているつもりでいた一年生だったが、地区大会で他校の優れた演奏を聴いて、めざすべき演奏のレベルが理解できたと同時に、まだその域に達していないと自覚したから。
② 地区大会での他校の演奏を聴いて自信を失いかけた一年生だったが、演奏を的確に批評するOBたちが自分たちの演奏を音に厚みがあると評価したので、あらためて先輩たちへの信頼を深めたから。
③ それまでばらばらだった自分たちの演奏が音楽としてまとまる瞬間を地区大会で初めて経験した一年生は、音と音楽との違いに目覚めると同時に、自分たちに求められている演奏の質の高さも実感したから。
④ 地区大会で他校のすばらしい演奏を聴いて刺激を受けた一年生は、これからの練習を積み重ねていくことで、音楽的にさらに向上していこうという目標を改めて確認し合ったから。
⑤ 自分たちとしては十分に練習をしてきたつもりでいた一年生だったが、地区大会での他校の堂々とした演奏を聴き、自信をもって演奏できるほどの練習はしてこなかったと気づいたから。
これを解くためにも、場面を把握する必要があります。
問6で問題にもなっていますが、お話は時系列どおりには進んでいません。
第一場面も含めて整理すると、
a 地区大会前日 克久の「音→音楽」体験
b 地区大会翌日以降 克久含む一年生……先輩の言うことを聞くようになる
c 地区大会当日 他の中学校の演奏を聴く
→(克久の)「胸のうさぎ」が躍り上がる音
→部員達……「負けた」
→一年生たち……自分たちの未熟さを思い知る
d 地区大会の夜 克久と百合子(母)のやりとり
e 地区大会翌日以降 一年生……先輩に叱られなくなる
時の流れは、a→cd→beですね。
b(結果)の理由は、cd(原因)にあるはずです。
正解は、①「地区大会で他校の優れた演奏を聴いて、めざすべき演奏のレベルが理解できたと同時に、まだその域に達していないと自覚したから」しかありません。
場面とは何か。
何らかの出来事が生成する状況が描かれたひとまとまりのことです。シーンとも言いますね。
a時間とb空間、そしてc登場人物で規定されます。
第一場面を見てみましょう。
譜面をパートごとに練習して、セクションごとに音として仕上げていくのは、山から石を切り出す作業だが、そのごろごろした石がようやくしっかりとした石組みになろうとしていた。森勉が細やかに出す指示は、石と石の接続面をぴったりと合わしていく仕事だった。
この日、何度目かで「くじゃく」をさらっていた時、克久はばらばらだった音が、一つの音楽にまとまる瞬間を味わった。スラブ風の曲だが、枯れ草の匂いがしたのである。斜めに射す入り陽の光が見えた。それは見たことがないほど広大な広がりを持っていた。いわく言い難い哀しみが、絡み合う音の底から湧き上がっていた。悔しいとか憎らしいとか、そういういらいらするような感情は一つもなくて、大きな哀しみの中に自分がいるように感じた。つまり音が音楽になろうとしていた。地区大会前日だった。
地区大会の前日の場面ですね。場所は音楽室でしょう。
その日、主人公の克久は「音が音楽になろうとす」る瞬間を体験します。
問2 傍線部A「音が音楽になろうとしていた」とあるが、それはどういうことか。その説明として最も適当なものを選べ。
① 指揮者の指示のもとで各パートの音が融(と)け合い、具象化した感覚や純化した感情を克久に感じさせ始めたこと。
② 指揮者に導かれて克久たちの演奏が洗練され、楽曲が本来もっている以上の魅力を克久に感じさせ始めたこと。
③ 練習によって克久たちの演奏が上達し、楽曲を譜面通りに奏でられるようになったと克久に感じさせ始めたこと。
④ 各パートの発する複雑な音が練習の積み重ねにより調和し、圧倒するような迫力を克久に感じさせ始めたこと。
⑤ 各パートで磨いてきた音が個性を保ちつつ精妙に組み合わさり、うねるような躍動感を克久に感じさせ始めたこと。
「音が音楽になる」とは、どういうことでしょうか。
選択肢を見ると、
「②演奏が洗練され、楽曲が本来もっている以上の魅力を克久に感じさせ始めた」
「④練習の積み重ねにより調和し、圧倒するような迫力を克久に感じさせ始めた」
「⑤音が個性を保ちつつ精妙に組み合わさり、うねるような躍動感」
などとありますが、どれも正解のように見えませんか。
実際に、このような意味合いで「音が音楽になる」と言われることはよくあります。
「③楽曲を譜面通りに奏でられるようになった」の意味ではあまり用いられないでしょうか。
「譜面通りに吹くだけじゃ、音楽にならないんだよ!」と怒られることさえありますから。
傍線部と選択肢を見るだけでは、この問題は解けません。
場面全体をふまえましょう。
さらに傍線部の「つまり」にも注意しましょう。
「つまり」は言い換えですから、「つまり」の前後は「=(イコール)」の関係です。
克久はばらばらだった音が、一つの音楽にまとまる瞬間を味わった。
∥
枯れ草の匂いがしたのである。入り陽の光が見えた。
大きな哀しみの中に自分がいるように感じた。
∥
つまり「音が音楽になろうとしていた」
演奏から、具体的イメージがわき、感情がわきあがってきます。
それを、選択肢①では「具象化した感覚や純化した感情」と言い換えています。
①が正解です。
「各パートの音が融け合い」も、本文の「ばらばらだった音が、一つの音楽にまとまる」と対応してます。
問2を間違えた人は、
1 場面で解くという意識が欠けている
2「具象化」が何のことかわからなかい
3「つまり」をチェックしていない
が、原因のはずです。123のような状態の人を専門用語で「テキトーに解く人」とよんでいます。
問3 傍線部B「怒られるたびに内心で『ちゃんとやってるじゃないか』とむくれていた気持ちがすっかり消えた」とあるが、それはなぜか。その理由として最も適当なものを選べ。
① 日々の練習をきちんと積み重ねているつもりでいた一年生だったが、地区大会で他校の優れた演奏を聴いて、めざすべき演奏のレベルが理解できたと同時に、まだその域に達していないと自覚したから。
② 地区大会での他校の演奏を聴いて自信を失いかけた一年生だったが、演奏を的確に批評するOBたちが自分たちの演奏を音に厚みがあると評価したので、あらためて先輩たちへの信頼を深めたから。
③ それまでばらばらだった自分たちの演奏が音楽としてまとまる瞬間を地区大会で初めて経験した一年生は、音と音楽との違いに目覚めると同時に、自分たちに求められている演奏の質の高さも実感したから。
④ 地区大会で他校のすばらしい演奏を聴いて刺激を受けた一年生は、これからの練習を積み重ねていくことで、音楽的にさらに向上していこうという目標を改めて確認し合ったから。
⑤ 自分たちとしては十分に練習をしてきたつもりでいた一年生だったが、地区大会での他校の堂々とした演奏を聴き、自信をもって演奏できるほどの練習はしてこなかったと気づいたから。
これを解くためにも、場面を把握する必要があります。
問6で問題にもなっていますが、お話は時系列どおりには進んでいません。
第一場面も含めて整理すると、
a 地区大会前日 克久の「音→音楽」体験
b 地区大会翌日以降 克久含む一年生……先輩の言うことを聞くようになる
c 地区大会当日 他の中学校の演奏を聴く
→(克久の)「胸のうさぎ」が躍り上がる音
→部員達……「負けた」
→一年生たち……自分たちの未熟さを思い知る
d 地区大会の夜 克久と百合子(母)のやりとり
e 地区大会翌日以降 一年生……先輩に叱られなくなる
時の流れは、a→cd→beですね。
b(結果)の理由は、cd(原因)にあるはずです。
正解は、①「地区大会で他校の優れた演奏を聴いて、めざすべき演奏のレベルが理解できたと同時に、まだその域に達していないと自覚したから」しかありません。










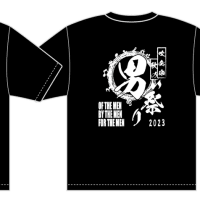





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます