□ これも剪定に漏れたアブラハム・ダービー(ER)
秋薔薇とは言えません、大きさも3分の2くらい
◇ かつて学生時代から三十歳辺りですから、つい最近まで(!?)、
川端康成や三島由紀夫や谷崎潤一郎や辻邦生の小説のように、
これぞ日本語とうなずけるような、美しい文章に触れていたくて、
彼らの小説を憑かれたように読破していきました。

◇ 1992年か今年2007年のお正月頃まででしたか…。
延々15年かけて塩野七生さんの超大作、ライフワークの「ローマ人の物語」全15巻を
毎年1冊ずつ、刊行される度に、待ちかねたように読み続けてきました。
ユリウス・カエサルの偉大さに、心打たれたのが約10年前。
古代ローマの繁栄、パックス・ロマーナにも少しずつボロが見え出します。
2~3世紀辺りを、塩野さんは「終わりの始まり」(第11巻)と銘打ちました。
シンプル・イズ・ベストの見事さにプロフェッショナルの心意気を感じたものです。
それも、五賢帝の最後の哲人皇帝、マルクス・アウレリウス帝の世に…。
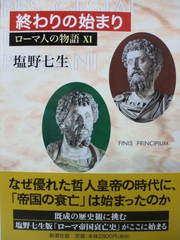
◇ あらら、すみません。
もっとも興味あるジャンルのことですから、話が横道に反れてしまいそうした。

□ アブチロンはうつむいてばかり。アオイ科アプチロン属の常緑小低木。
◇ 私は念願の「源氏物語」を、たとえ注釈はあっても原文のまま読み通してみたいです。
そのあと、瀬戸内静寂さんや円地文子さん、与謝野晶子や谷崎潤一郎の現代語訳の
どれかを読んでみたいなと思います。
いづれの御時にか 女御・更衣あまたさぶらひたまひける中に
いとやむごとなき際にはあらぬが すぐれて時めきたまふ ありけり。
↑
※ のっけから、主語がないですね。
英語は、日記以外は大抵主語くらいはありますし、
イタリア語は、固有名詞以外は主語がなくても、
動詞の活用で推測できます。
源氏物語の冒頭は、↑の部分にあるのです。
別に透明人間でも、Ms.Spaceでもありません。
私が想像力と注釈を頼りに、もちろんあまり使いたくなくても
場合によっては、通常枕代わりの古語辞典も必要です。
古語辞典を使い始めると、読破するのにいつまでかかることやらと
いうことに、間違いなく陥ってしまいますから、
少々はすっ飛ばしても、スピード違反にならん程度に走りましょう。
今は「秋の交通安全運動」の真っ最中です???

◇ ところで、日本古来?の言葉で掛け値なく美しい言葉。
自分の好きな言葉が、たとえば、二十四節気と源氏物語の五十四帖です。
もっとも二十四節気は、中国からの輸入品だそうですが…もうすぐ「秋分」。

(二十四節気)
春 立春(りっしゅん) 雨水(うすい) 啓蟄(けいちつ)
春分(しゅんぶん) 清明(せいめい) 穀雨(こくう)
夏 立夏(りっか) 小満(しょうまん) 芒種(ぼうしゅ)
夏至(げし) 小暑(しょうしょ) 大暑(たいしょ)
秋 立秋(りっしゅう) 処暑(しょしょ) 白露(はくろ)
秋分(しゅうぶん) 寒露(かんろ) 霜降(そうそう)
冬 立冬(りっとう) 小雪(しょうせつ) 大雪(たいせつ)
冬至(とうじ) 小寒(しょうかん) 大寒(たいかん)

(源氏物語)
桐壺(きりつぼ) 帚木(ははきぎ) 空蝉(うつせみ)
夕顔(ゆうがお) 若紫(わかむらさき) 末摘花(すえつむはな)
紅葉賀(もみじのが) 花宴(はなのえん) 葵(あおい)
賢木(さかき) 花散里(はなちるさと) 須磨(すま)
明石(あかし) 澪標(みおつくし) 蓬生(よもぎう)
関屋(せきや) 絵合(えあわせ) 松風(まつかぜ)
薄雲(うすぐも) 朝顔(あさがお) 少女(おとめ)
玉鬘(たまかずら) 初音(はつね) 胡蝶(こちょう)
螢(ほたる) 常夏(とこなつ) 篝火(かがりび)
野分(のわき) 行幸(みゆき) 藤袴(ふじばかま)
真木柱(まきばしら) 梅枝(うめがえ) 藤裏葉(ふじのうらば)
若菜上(わかな じょう) 若菜下(わかな げ) 柏木(かしわぎ)
横笛(よこぶえ) 鈴虫(すずむし) 夕霧(ゆうぎり)
御法(みのり) 幻(まぼろし) 雲隠(くもがくれ)
匂宮(におうのみや) 紅梅(こうばい) 竹河(たけかわ)
橋姫(はしひめ) 椎本(しいがもと) 総角(あげまき)
早蕨(さわらび) 宿木(やどりぎ) 東屋(あずまや)
浮舟(うきふね) 蜻蛉(かげろう) 手習(てならい)
夢浮橋(ゆめのうきはし)
※ 以上は宇治十帖と呼ばれています。

◇ 源氏物語の世界と私のつながりの、きっかけ?といえるものは、
遥か小学6年生まで遡ります。
その頃は切手収集が流行ってまして、私もと思って、
最初に郵便局で買い求めた切手が、源氏物語絵巻の「宿木」でした。
だから、中学卒業か高校入学後あたりまでは、
源氏物語って絵巻物みたいに思ってました。
それが、約千年も前の一大長編恋愛小説、それも紫式部という女性が書き綴った、
世界に誇れる抒情詩でもあると知って、腰は抜けませんでしたが、
切手とはあまりに結びつかないものでしたので、わけもわからず驚きました。

◇ 中学3年生の担任は国語の先生でしたが、
君らには源氏物語は読めない、読んでもわからない!
なぜか、そう決め付けられました。
なるほど、いづれの御時にかや、いとやむごとなき際にはあらぬが、
なんてのっけから難し過ぎました。
エロありグロありオカルトありの54帖らしいです。
それでも数十年の間、君らには読めないと決め付けられたときの反発が、
私にはしぶとく残ってます。

◇ まずは、桐壺から松風まで、文庫本で3冊分ですが、
おっちらおっちらと、諦めずに読んでいきたいと思います。
まあ、54帖を1年に1帖では、私は除夜の鐘みたいな年になってしまいます。
1年間かけてというのが、良いところではないでしょうか。

◇ さて、古文の教科書に必ず取り上げてある、「須磨」の帖の一部分。
学生時代を神戸で過ごしただけに、須磨浦の海岸を思い浮かべます。
源氏の物語の中では、名文中の名文という評価らしいですね。
千年もの間、そのような評価が延々と続いていると言うのも驚きです。
須磨には、いどど心づくしの秋風に、海はすこし遠けれど、
行平の中納言の、関吹き越ゆるといひけむ浦波、
夜々はげにいと近く聞こへて、
またなくあはれなるものは、かかる所の秋なりけり。
須磨では、いっそう嘆きを尽くさせる秋風の頃となって、
海は少し遠いけれども、
行平の中納言が、「関吹き越ゆる」と詠んだという浦波が、
夜ともなると歌どおり耳のすぐ側に聞こえて、
ほかにないほど寂しいのは、こういう所の秋であった。
旅人は袂すずしくなりにけり 関吹きこゆる須磨の浦風
在原行平(818-93)(続古今集)

◇ ビリーのブーキャンで、きつかったら手をぶらぶらしても、水分補給してもいい。
でも絶対に最後まで諦めないことを、実際にこの年で学んでいる最中です。
8月8日から始めましたから、7週間目に入りました。
物理的にできないこと、興味の湧かないことは無理してまではやる気がしませんが、
自分に合っていて、やればできるということには、私は変な凝り性を発揮します。
遣り出したら、たとえ細々とでも、一休みしながらでも、続けることに
価値を見い出すのです。
源氏物語をこれから読み続けるのも、そこにあります。

◇ 継続は力なり。
そして、明日は明日の風が吹く。
だから希望をもって「良かった探し」をしながら、たとえつまづいても、
お腹以外がへこんでも生きていけるのでしょう。

◇ そして学生時代、教養部の経済学の講義で先生が教えてくれた言葉。
これもずっと私の支えです。
古典の世界とはやや外れますが…順番も逆かもしれません。
Cool Head, but Warm Heart!


(The End)
秋薔薇とは言えません、大きさも3分の2くらい
◇ かつて学生時代から三十歳辺りですから、つい最近まで(!?)、
川端康成や三島由紀夫や谷崎潤一郎や辻邦生の小説のように、
これぞ日本語とうなずけるような、美しい文章に触れていたくて、
彼らの小説を憑かれたように読破していきました。

◇ 1992年か今年2007年のお正月頃まででしたか…。
延々15年かけて塩野七生さんの超大作、ライフワークの「ローマ人の物語」全15巻を
毎年1冊ずつ、刊行される度に、待ちかねたように読み続けてきました。
ユリウス・カエサルの偉大さに、心打たれたのが約10年前。
古代ローマの繁栄、パックス・ロマーナにも少しずつボロが見え出します。
2~3世紀辺りを、塩野さんは「終わりの始まり」(第11巻)と銘打ちました。
シンプル・イズ・ベストの見事さにプロフェッショナルの心意気を感じたものです。
それも、五賢帝の最後の哲人皇帝、マルクス・アウレリウス帝の世に…。
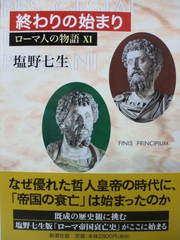
◇ あらら、すみません。
もっとも興味あるジャンルのことですから、話が横道に反れてしまいそうした。

□ アブチロンはうつむいてばかり。アオイ科アプチロン属の常緑小低木。
◇ 私は念願の「源氏物語」を、たとえ注釈はあっても原文のまま読み通してみたいです。
そのあと、瀬戸内静寂さんや円地文子さん、与謝野晶子や谷崎潤一郎の現代語訳の
どれかを読んでみたいなと思います。
いづれの御時にか 女御・更衣あまたさぶらひたまひける中に
いとやむごとなき際にはあらぬが すぐれて時めきたまふ ありけり。
↑
※ のっけから、主語がないですね。
英語は、日記以外は大抵主語くらいはありますし、
イタリア語は、固有名詞以外は主語がなくても、
動詞の活用で推測できます。
源氏物語の冒頭は、↑の部分にあるのです。
別に透明人間でも、Ms.Spaceでもありません。
私が想像力と注釈を頼りに、もちろんあまり使いたくなくても
場合によっては、通常枕代わりの古語辞典も必要です。
古語辞典を使い始めると、読破するのにいつまでかかることやらと
いうことに、間違いなく陥ってしまいますから、
少々はすっ飛ばしても、スピード違反にならん程度に走りましょう。
今は「秋の交通安全運動」の真っ最中です???

◇ ところで、日本古来?の言葉で掛け値なく美しい言葉。
自分の好きな言葉が、たとえば、二十四節気と源氏物語の五十四帖です。
もっとも二十四節気は、中国からの輸入品だそうですが…もうすぐ「秋分」。

(二十四節気)
春 立春(りっしゅん) 雨水(うすい) 啓蟄(けいちつ)
春分(しゅんぶん) 清明(せいめい) 穀雨(こくう)
夏 立夏(りっか) 小満(しょうまん) 芒種(ぼうしゅ)
夏至(げし) 小暑(しょうしょ) 大暑(たいしょ)
秋 立秋(りっしゅう) 処暑(しょしょ) 白露(はくろ)
秋分(しゅうぶん) 寒露(かんろ) 霜降(そうそう)
冬 立冬(りっとう) 小雪(しょうせつ) 大雪(たいせつ)
冬至(とうじ) 小寒(しょうかん) 大寒(たいかん)

(源氏物語)
桐壺(きりつぼ) 帚木(ははきぎ) 空蝉(うつせみ)
夕顔(ゆうがお) 若紫(わかむらさき) 末摘花(すえつむはな)
紅葉賀(もみじのが) 花宴(はなのえん) 葵(あおい)
賢木(さかき) 花散里(はなちるさと) 須磨(すま)
明石(あかし) 澪標(みおつくし) 蓬生(よもぎう)
関屋(せきや) 絵合(えあわせ) 松風(まつかぜ)
薄雲(うすぐも) 朝顔(あさがお) 少女(おとめ)
玉鬘(たまかずら) 初音(はつね) 胡蝶(こちょう)
螢(ほたる) 常夏(とこなつ) 篝火(かがりび)
野分(のわき) 行幸(みゆき) 藤袴(ふじばかま)
真木柱(まきばしら) 梅枝(うめがえ) 藤裏葉(ふじのうらば)
若菜上(わかな じょう) 若菜下(わかな げ) 柏木(かしわぎ)
横笛(よこぶえ) 鈴虫(すずむし) 夕霧(ゆうぎり)
御法(みのり) 幻(まぼろし) 雲隠(くもがくれ)
匂宮(におうのみや) 紅梅(こうばい) 竹河(たけかわ)
橋姫(はしひめ) 椎本(しいがもと) 総角(あげまき)
早蕨(さわらび) 宿木(やどりぎ) 東屋(あずまや)
浮舟(うきふね) 蜻蛉(かげろう) 手習(てならい)
夢浮橋(ゆめのうきはし)
※ 以上は宇治十帖と呼ばれています。

◇ 源氏物語の世界と私のつながりの、きっかけ?といえるものは、
遥か小学6年生まで遡ります。
その頃は切手収集が流行ってまして、私もと思って、
最初に郵便局で買い求めた切手が、源氏物語絵巻の「宿木」でした。
だから、中学卒業か高校入学後あたりまでは、
源氏物語って絵巻物みたいに思ってました。
それが、約千年も前の一大長編恋愛小説、それも紫式部という女性が書き綴った、
世界に誇れる抒情詩でもあると知って、腰は抜けませんでしたが、
切手とはあまりに結びつかないものでしたので、わけもわからず驚きました。

◇ 中学3年生の担任は国語の先生でしたが、
君らには源氏物語は読めない、読んでもわからない!
なぜか、そう決め付けられました。
なるほど、いづれの御時にかや、いとやむごとなき際にはあらぬが、
なんてのっけから難し過ぎました。
エロありグロありオカルトありの54帖らしいです。
それでも数十年の間、君らには読めないと決め付けられたときの反発が、
私にはしぶとく残ってます。

◇ まずは、桐壺から松風まで、文庫本で3冊分ですが、
おっちらおっちらと、諦めずに読んでいきたいと思います。
まあ、54帖を1年に1帖では、私は除夜の鐘みたいな年になってしまいます。
1年間かけてというのが、良いところではないでしょうか。

◇ さて、古文の教科書に必ず取り上げてある、「須磨」の帖の一部分。
学生時代を神戸で過ごしただけに、須磨浦の海岸を思い浮かべます。
源氏の物語の中では、名文中の名文という評価らしいですね。
千年もの間、そのような評価が延々と続いていると言うのも驚きです。
須磨には、いどど心づくしの秋風に、海はすこし遠けれど、
行平の中納言の、関吹き越ゆるといひけむ浦波、
夜々はげにいと近く聞こへて、
またなくあはれなるものは、かかる所の秋なりけり。
須磨では、いっそう嘆きを尽くさせる秋風の頃となって、
海は少し遠いけれども、
行平の中納言が、「関吹き越ゆる」と詠んだという浦波が、
夜ともなると歌どおり耳のすぐ側に聞こえて、
ほかにないほど寂しいのは、こういう所の秋であった。
旅人は袂すずしくなりにけり 関吹きこゆる須磨の浦風
在原行平(818-93)(続古今集)

◇ ビリーのブーキャンで、きつかったら手をぶらぶらしても、水分補給してもいい。
でも絶対に最後まで諦めないことを、実際にこの年で学んでいる最中です。
8月8日から始めましたから、7週間目に入りました。
物理的にできないこと、興味の湧かないことは無理してまではやる気がしませんが、
自分に合っていて、やればできるということには、私は変な凝り性を発揮します。
遣り出したら、たとえ細々とでも、一休みしながらでも、続けることに
価値を見い出すのです。
源氏物語をこれから読み続けるのも、そこにあります。

◇ 継続は力なり。
そして、明日は明日の風が吹く。
だから希望をもって「良かった探し」をしながら、たとえつまづいても、
お腹以外がへこんでも生きていけるのでしょう。

◇ そして学生時代、教養部の経済学の講義で先生が教えてくれた言葉。
これもずっと私の支えです。
古典の世界とはやや外れますが…順番も逆かもしれません。
Cool Head, but Warm Heart!


(The End)

















