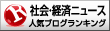「大変や大変や后の宮さんが・・・・」
突然、御所が揺れに揺れ、大騒ぎになっていた。
「早く御匙・・早くやっ!」
典侍が叫び、女官や侍従らが駆け回る。
顔色が真っ青の后の宮はすぐさま、ソファに寝かされ口元の血が拭われる。
「ああ、后の宮さん、しっかりしはって!」
后の宮は突然ご自分が吐血された事に驚き、ソファに寝かされてもまだ心臓がどきどきされているようだった。
「一体、何があったのだ」
飛び込んで来たお上は后の宮の手をとり、「早く医者を呼ばぬか」と珍しく語気を荒げる。
「お上・・お上、私は大丈夫です」
后の宮はそうお答えになり起き上がる。
「起きはっても平気どすか?」
「ええ。自分の部屋に行きます。ああ・・床を汚してしまったのね」
「そんなもん、掃除したらよろしいわ。お戻りさんになるんなら侍医が参ってから」
「その方がいいのかしら」
后の宮は自分で判断するのをやめてしまったようにぐったりともう一度ソファに横になる。
慌てて駆け付けた侍医がすぐさま脈をとり、丁寧に診察した。
「吐血は腸壁が破れた結果と存じ上げます。出血が治まるまでお食事は控えらえ、点滴にいたしましょう。今までにも何度か鼻出血なされていますし、過度な精神的なお疲れが原因かと思います」
「それでは大事ないのだな」
「はい。見た目ほどは。ただ、これは心の問題が原因のようでございますので、なるべくストレスのかからない環境を」
「私が愚痴を言ったばかりに」
お上はつい先日、后の宮に女一宮について話した事を後悔した。
いつも后の宮は真面目に受け止める癖があるからこうなのだ・・・もっとご自分がしっかりしなくてはと思われたのだった。
それでも帝の心はささくれ立ってしまう。
なぜ東宮は参内しない?東宮妃は一体何を気に入らないというのか。
二言目には「皇室の決まりごとが時代遅れ」とののしるが、確かにそういうものに苦しめられてきたことは事実だが・・・
后の宮もまた静養に赴いても少しもお気が晴れないようだった。
(東宮妃は私に似ている)
后の宮そう思うと背筋が凍る思いをされた。
そうではない。似てなんかいない。私があの頃、流産をきっかけに気が塞いでしまったのは、先帝の元に参内するのが嫌だったのは、他の妃殿下達から虐められていたからよ。
あの当時は時代が変わっていた。
旧皇族や華族が臣下となり、財産の多くを手放す一方、成り上がりがアメリカなどとの貿易で資産を築く。伝統や格式よりも、財産を持っているかいないかの方が重要だった。
后の宮はまさにそんな時代における成功者の一族だった。
旧皇族の血を受けていない、華族の称号を持ったこともない、上流階級のしきたりも伝統も知らなかった。
けれど、后の宮は裕福に育ち、絵のような西洋館に住んでお手伝いさんがいるような家庭で、女性としては珍しくも大学まで出して貰い、美しい着物もドレスも欲しいまま。
誰もがうらやむ生活を送っていたのだ。
それなのに宮中に入った途端、それらの生き様が全て否定された。
先帝の后の宮を始め、妃殿下方の冷たい視線は忘れない。
いつか乗り越える、いつか上に立ってやるのだ・・・とそれだけを思って今日まで生きて来た。
それが嫁にこのような思いをさせられようとは。
そして、その嫁がよりによって合わせ鏡のような存在とは。
后の宮の病状はすぐに公に発表され、数日、葉山の別邸で静養する事が決まった。
二宮からはすぐに連絡が入り、すぐにお見舞いに伺いたいとの旨があったが、東宮家からはそのような申し出がなかったので、后の宮は「慌てなくていい」とお断りになった。
東宮家はいつも通り春スキーにでかけてしまい、そのあまりにも人情味のない行動に回りは呆れてものが言えなかったが誰も批判しなかった。
「紀宮」(きのみや)は東宮家に気を遣いつつも、やはり后の宮が心配で子供達を連れて参内したが、その事が東宮家に伝わると妃はまた心が傷ついたと言って参内しなかった。
后の宮はいら立ちながら思わず「紀宮」(きのみや)に「余計なことをしないで頂戴。あちらの人は神経質なのだから。私の面目を潰さないで」と八つ当たりしてしまった。
二宮家では「なんでうちのお妃さんが叱られなあかんの」と侍女達が怒りで喧喧囂囂と言い合っていたが、二宮も「紀宮」(きのみや)も何も言わなかった。
そんな両親の姿を見つつ、大姫と中姫はそれぞれ中等科と高等科に進学した。
二人とも、両親が大きなストレスを抱えていることはわかっていたし、自分達もまたその巻き添えになっている事も知っていた。
「東宮の伯母上はどうしても好きになれないわ。勿論、女一宮は可愛いけど。でも、あんな風に嘘をついていいのかしら」
中姫の素朴な疑問は当然の事だったろう。
「身分が上の方には逆らえないのよ。伯母上はご病気なんだから」
大姫が慰める。日々、笑顔が可愛らしくなって来た若宮は姉たちにとってはぬいぐるみのようなもので、始終抱っこしていても飽きないし、お世話をするのも楽しい。
いつかこの若宮が大きくなった時、「陛下」と呼ばれるその日まで見守っていかなくてはならないのだ。
「病気なら女一宮もでしょう」
「中姫ったら。そんな事を言ったらお母さまたちが悲しまれるわよ」
「悲しいのは私の方よ。私、若宮の事は可愛いし大好き。こんな風に抱っこしていると癒されるもん。でも、お母様が贔屓なさっているようで少し悲しい」
「あら、やきもちをやいているのね。そうね、中姫はついこの間まで赤ちゃんだったんだものね」
「そんな事ないわ。私、ずっとお姉さんよ。お姉さまはご優秀でお父様やお母さまの期待もあるけど、私はスケートをやったり、踊ったりの方が好きだから・・・もしかしたらそういうところが合わないのかな」
「どなたと」
「お母さまたちと」
「あら、あなたには手話があるじゃない。あなたの手話はとっても綺麗よ。もっともっとお勉強なさいよ」
「そうね・・・お姉さま。人間は正直で真面目に生きなくてはならないとお父様はおっしゃったわ。特別な才能がなくてもよい。皇族として生まれた以上は与えられた務めを果たし、コツコツと自分を磨く事が大事だと。言葉遣いや身のこなしも大切だから私達、小さい頃からそりゃあ厳しく言われて来たじゃない?」
「そうね」
「学校でもお家でも、私達は一時だって気を抜いたことなんかないわ」
「ええ」
「でも東宮の伯母上は何も出来ないじゃない。お辞儀だってできやしない。それなのにどうして素晴らしいって雑誌に書かれたりするの?そして若宮が生まれたら、どうして私達、悪く言われるの?」
中姫のストレートな物言いに大姫は答えることが出来なかった。
「ずるいと思うの。卑怯だと思うの。東宮の伯父上だっておじい様やおばあ様がどんなに心を痛めているか少しもわからないであの伯母上の言いなりだし」
「それは私もわかってるけど、それをおとう様やお母さまに申し上げたからって何がどうなるものではないわ。何を言われても潔白なら黙っていなさいと言われるのがオチ。言い訳をすると余計に疑われるからって。私だって週刊誌なんかの見出しをみるとぞっとするのよ。怖いわ。まるで日本中が私達を憎んでいるみたいに思うこともある。だけど我慢しないといけないのよ」
「訴えちゃダメなの?」
「ダメなの。私達は我慢しなくちゃ」
「私達が適応障害になればいいんじゃない?お母さまが倒れるとか」
「それじゃやることが東宮の伯母上と一緒じゃないの。そういうのを同じ穴のムジナというのよ。同じところに落ちてはいけない。それが私達のプライドよ」
「よくわからない。難しいもの。毎日、週刊誌の見出して女一宮が天皇になるのか若宮なのかって・・学校でも聞かれたりするし。なんていうか・・悪意を感じるのよ」
「私達、なるべく距離を取らなくてはね」
二宮家の姫達が、実はこんなに傷ついて、矛盾と戦いつつある事に、残念な事に「紀宮」(きのみや)達は気づいていなかった。
というより、今は毎日の公務で精一杯の状態で、子供達の細かな心の動きまでは図りかねていたのだ。
特に「紀宮」(きのみや)はあからさまになりつつある、自分への誹謗中傷に対し、必死に知らない顔をしていなければならず、それだけで精神的にも肉体的にもかなりきつかったのだった。
最近の、后の宮の態度の変化も気になることだし。
でも、それを口に出す事は出来ないし・・嫁として宮家の妃としての苦悩は大きかった。
そんなこんなで毎日が続いていき、いよいよ雨が降り出し梅雨入りも間近という頃、東宮家に大問題が起き上がった。
なんと、東宮の胃にポリープが見つかってしまったのだった。