「一体どうしたというの」
ただならぬ中姫の様子に「紀宮」(きのみや)はベッドサイドに座り込んだ。
中姫は泣くまいと必死にこらえていたがその声は震えている。
「私は生まれてくるべきじゃなかったって言ってるのよ」
中姫の声はうわずっている。
「どうしてそんな事を。誰が?」
「クラスのお友達。お母さまたちから聞いたって。私が生まれる時にお母さまは色々な事を言われたって。東宮妃様に」
子供の世界はなんと残酷な事だろう。話題にしていい事と悪い事の区別がつかない。それは全て大人の世界の鏡のようなものなのに。
「私は女だったからよかったけど、もし男だったら。そしてもし今度生まれてくる子が女の子で、いいえ、男の子だったら」
「だったら?」
「わからないわ。でもみんな東宮妃様がお可哀想っていうのよ」
「ああ!」
「紀宮」(きのみや)は思わず中姫を抱きしめた。
「私もお父様もあなたが生まれて来た事をとっても喜んでいるのよ。あなたが女だろうが男だろうが」
「でも・・・でも・・・」
「あのね。中姫。人がこの世に生まれてくるという事はとても大切で大きなことなの。さっきお局が言っていたわ。子供というのは親の体を食らって生まれてくると」
「そんな・・・怖い」
「そうね。でもその通りなんだと思う。虫や魚でも自分の体をエサにして子孫を残すものはいるわ。人間でも、出産で命を落とす人は決して少なくないの。それでも子供は欲しいの。生まれてきてほしいの。お母さまもお父様も、あなた達を決して生まれてこなければいいと思ったことなどないわ。もし、ほんの少しでもそんな事を考えたら罰があたる。あなた達は皇祖皇宗の血を引いている大切な体。私のお腹を借りて生まれて来ただけよ。それだけ尊いのよ」
「お母さま・・・・」
中姫はもう耐えられなくなって「紀宮」(きのみや)にすがりつき、なきじゃくり始めた。
そんな様子を部屋の外から見守る二宮の顔も歪み、今にも落涙しそうな目で、苦しそうに見つめる。
「それからね・・それから。私にあの大きな遊園地に連れて行ってって言われたの。お友達に」
「まだ小学生じゃないの。そんな事駄目よ」
「そうじゃないの。女一宮みたいに、私と行けばどんな乗り物でも優先的に乗れるでしょうっていうのよ」
「・・・・」
今度は「紀宮」(きのみや)は言葉も出なかった。
「こ・・皇族をそんな風に利用しようとする人はもうお友達じゃないわ。お付き合いをやめなさい」
厳しくそれだけ言った。
中姫は「お母さまが懐妊されてから、何だか辛い事ばかりよ。クラスの中で冷やかされたり、東宮妃様がお可哀想と言われたり。どうしてそんな事を言われなくちゃいけないのかさっぱりわからなくて。お姉さまにも聞いてみたけど、わからないって。私もお姉さまも弟か妹を可愛がってあげたいだけなのに」
「それでいいのよ。中姫はお姉さまになるのだから、いつまでもつまらない事で泣いていないで着替えてお食事を摂りましょう」
中姫はやっと母から離れて涙を拭いた。
「わかりました・・・お母さま。もう言いません。でもやっぱりおかしいと思う。本当にお母さまのおっしゃる通りなら、間違っているのはお可哀想という人たちでしょう?でも雑誌でもネットでもそんな話ばかりじゃない。外の世界では違うの?」
「中姫」
入って来たのは二宮だった。
「世の中には間違いを流布する連中がいるのは確かだ。しかし、それに惑わされてはいけない。もう少し大きくならないとわからない事もある。その時になったら教えるから」
「はい」
中姫はおとなしく引き下がった。「紀宮」(きのみや)は二宮に支えられて立ち上がる。娘が全然納得していない事は一目瞭然だったが、今はそれでごまかすしかないのだ。
「お母さま」
部屋を出る時、中姫は言った。
「赤ちゃんのお世話は私に任せてね。ちゃんとお勉強するから。手作りのおもちゃを作っても上げる。でもその代わり」
「その代わり・・・?」
「赤ちゃんばかり可愛がらないでね」
「紀宮」(きのみや)は「当たり前でしょう」と言って娘を抱きしめた。
「こんなにいい子なのに可愛がらずにいれると思う?」
そう言われて中姫はほっとした様子だった。
「私達は権力がありません。後ろ盾も。そんな私達が挑戦しようとしている事は子供達を苦しめることになるのでしょうか」
「それでもこれが運命と思うしかないだろう。あなたを娶った時にはこんな事態になるとは思わなかった。私達は筆頭宮家として役割を果たし子供達を育て、好きな研究に没頭する。そんな幸せな構図を描いていたのだ。まさか皇位継承に絡む事になろうとは。どのような勢力が東宮家を押して女帝への道を開こうとしているのかわからない。けれど、これは私の勘でしかないが、女一宮に皇位継承権を与えてしまったらその時点で皇室は終わる。そうでなくても終わるかもしれない。私達はそれを少しでも長く誇りをもって食い止める事しか出来ないのだ」
「存じております。ただ。子供達が可哀想で。大姫も中姫もよく育っていると思いますのに、世の中の猜疑心や権力争いなどを経験させたくはありません」
「仕方ない。私達の味方はもういないも同然。孤独な戦いであれば家族は一蓮托生」
「紀宮」(きのみや)はふらりとして慌てて二宮に支えられた。
「疲れたのかい?大丈夫か?」
「平気です。私は負けません」
「その笑顔は私の救いだよ」
「紀宮」(きのみや)はまだ頑張れると思った。二宮が自分を愛してくれている限り、どんな事があっても無事に子供を産まなくてはならないと決心した。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「いやだもん」
女一宮は幼稚園に入ってからというもの、このセリフを言わない日はなかった。
おふくは何とかきちんと時間を守って幼稚園に連れて行こうとするのだが、女一宮の昼夜逆転現象はなかなか改善されなかった。
「今日はお友達と踊りを踊るんですって。お弁当もお好きなものが入っていますから」
おふくはぐずる女一宮をなんとか車に乗せ幼稚園に向かう。
おふくは知っていた。幼稚園の行事のありとあらゆることが女一宮にとってハードルが高いことを。
4歳児というのは自我も芽生えるが少しずつ社会性が出来て、回りと一緒に行動出来るようになる。ましてやこの幼稚園は皇族が入る名門中の名門。
一般の子供よりも優秀な子が揃っている。おふくは毎日子供達の様子を見ているが歳のわりにはきはきと大人の質問に答える子や、何でも自分でできる子など、さすがに受験してまで入って来た子達と思うこともしばしば。
しかし、女一宮は朝のあいさつもろくに出来ない。
家庭の中で「あいさつ」という躾がされていないからだ。父親は朝の7時に食卓に着いているが母親は昼になるまで起きて来ない。
東宮は「おはよう。女一宮」と声をかけてくれるが、娘の方は知らん顔。
知らん顔をしていてもちょっと観察していれば女一宮がお父様を大好きという感情はわかるのだが。
幼稚園の子供達同士の挨拶、先生への挨拶、保護者達への挨拶。朝の挨拶は何度もするものだが、女一宮は全く興味を示さないし、下手に挨拶を強要するとひっくり返って泣き出すのでそれも出来ない。
一番の課題はお弁当かもしれない。
幼稚園では躾の一環として、4歳までお箸を使えるようにすることを義務付けている。しかし、女一宮はそれが出来ないので「皇族特権」でフォークを使っている。それが他の子供達から見ると奇異に映るようで、時々「変なの」という言葉も聞こえてくる。
みんなで並んで席に着くとか、みんなで同じ行動をとるというのが今の女一宮には苦痛でしょうがない。
「お可哀想に・・・」とおふくは思う。
普通の子なら無理して幼稚園に通わせなくてもいい筈なのに。
エリート意識の強い子供達に囲まれて競争社会の中で常にトップを走らされる。身の丈に合ってないのは一目瞭然なのに、独り歩きを始めた「ご優秀伝説」に踊らされ、実像より虚像の方が大きくなる。
「おふくさん!」
と、待機室に控えるおふくを呼びに来たのは女一宮の担任だった。
「大変なんです。宮様が粗相をなさって」
「わかりました」
おふくはすぐに大きなバッグを抱え、教室に向かった。
教室では子供達が大騒ぎをしていた。それを他の先生たちが「お外で遊びましょう」と全員を整列させて出ていこうとする。でも興奮した子供達はなかなか言うことをきかなかった。
「宮がおもらしした」と誰かが叫ぶと、他の子達もはやし立てる。
女一宮はそんな子供達の中で一人無表情だった。
異様な光景だったが、おふくは構わず女一宮を抱き上げると保健室に走る。
自分の服も汚れているのはわかったが、今はそんな事を考えている暇はない。
保健室ですぐにバッグから着替えとおむつを取り出して着替えさせる。
女一宮の顔は紅潮していた。
「宮様・・・宮様!」
なんと、おでこにさわると熱いではないか。
「侍医を侍医を呼んでください」
おふくは叫んだ。












 どんなに検査しても抑えられてないのが韓国なのに、まるで模範の国みたいに報道するのはやめて欲しい。
どんなに検査しても抑えられてないのが韓国なのに、まるで模範の国みたいに報道するのはやめて欲しい。
 眠れなくて・・・やっぱり電車の中で「厚生省からの・・・」にすごくショックを受けたのかなと。今は有事というけれどまさにそうですよね。
眠れなくて・・・やっぱり電車の中で「厚生省からの・・・」にすごくショックを受けたのかなと。今は有事というけれどまさにそうですよね。
 休業補償を成立させたら、国会を一ヶ月程度休会にしてくれ
休業補償を成立させたら、国会を一ヶ月程度休会にしてくれ 国会議員というのは、有事の時こそ頑張って働かないといけないのでは?安倍総理が前回、病気で総理を続けられなかった時、散々「健康管理ができてない」と責め立てましたよね。
国会議員というのは、有事の時こそ頑張って働かないといけないのでは?安倍総理が前回、病気で総理を続けられなかった時、散々「健康管理ができてない」と責め立てましたよね。






















 5月24日から幼稚園を休んでいた愛子内親王は25日から登園
5月24日から幼稚園を休んでいた愛子内親王は25日から登園




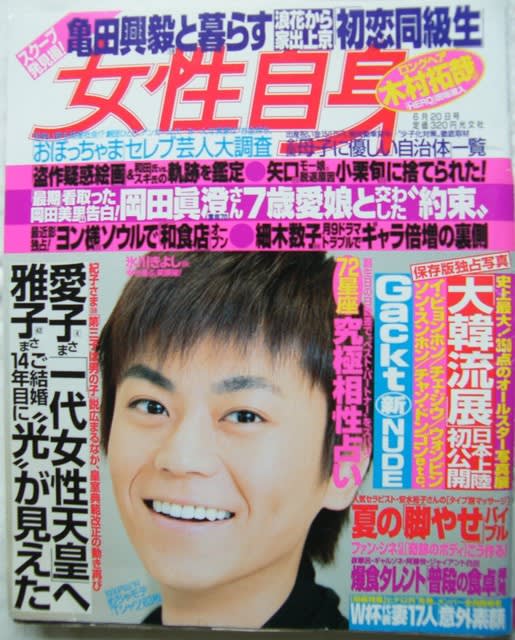















































 お騒がせなヘンリーとメーガンは正式に4月1日からロイヤルじゃなくなるけど、「HRH」の敬称は付けたりつけなかったりするそうです。でも「サセックスロイヤル」の商標は使ってはいけないらしい。
お騒がせなヘンリーとメーガンは正式に4月1日からロイヤルじゃなくなるけど、「HRH」の敬称は付けたりつけなかったりするそうです。でも「サセックスロイヤル」の商標は使ってはいけないらしい。














