「紀宮」(きのみや)にも意地はあった。
清貧の学者の家に生まれ浮世離れした生活を送って来た「紀宮」(きのみや)は世の中の「損得」や「利害関係」「根回し」などを知らずに「愛」のみで二宮に嫁いだ。
だから、初めて東宮妃を見た時、その立ち居振る舞いや言葉に衝撃を受け、どのように対処したらよいかわからなかった。
東宮妃は「将来は女性総理大臣」との覚えもある程の才媛と言われていた。
6年もの間、東宮からの求婚を断り続け、それなのになぜかまた会い・・を繰り返し、いつの間にか外国からの報道で「東宮妃」に内定した。
それから、宮中はがらりと変わってしまった。
何がって、いうなれば上が下に、日が西から昇るような、今まで経験した事のない経験をするハメになってしまったのだ。
「紀宮」(きのみや)が小さい頃から教えられ、自ら学んで来たことをことごとく否定され、感情的な東宮妃の言葉が全て正しいとされた。
「なぜ義母(はは)宮はあのように東宮妃をお庇いになるのかしら」
最初にそう思ったのは大宮様が崩御された時、東宮妃が「風邪のようなもの」で葬儀に出席しなかった時。
冠婚葬祭というのはどんな国の王族でも出席は義務だし、もしそれを破ればきついお咎めがある筈なのに、東宮妃は責められることはなかった。
理由はわかっていた。
あの時は「紀宮」(きのみや)もその場にいたのだから。
大宮は60年以上も先帝に仕えた皇族出身のお方。今上の母上であるから、その葬儀の手はずを整える為に皇后は奔走していたのだ。
どんな小さなことも目ざとくご注意になる皇后さまには「紀宮」(きのみや)始め、他の女性皇族方もみな緊張していた。
ある小さな事で皇后が「そこは・・・」と東宮妃におっしゃった途端、東宮妃は顔色を変えて「えっ」と小さくおっしゃった。
別に皇后は叱ったわけではない。「ご注意」あるいは「お口添え」をなさっただけだったが、何がお気に召さなかったのか東宮妃は真っ青になってがたがた震え始めたのだった。
皇后も「紀宮」(きのみや)も驚いて「どうなさいましたの」と声をかける。
すると、東宮妃は恐ろしい目で「紀宮」(きのみや)を睨みつけると「あなたとは違うの」とおっしゃるなり部屋を飛び出して行かれたのだった。
「紀宮」(きのみや)は一瞬、何を言われたのか分からず、回りを見たけれどみな黙っている。
一体、何が「あなたとは違う」のかしら。どうしたらいいのかしら。追いかけるべきなのかしら。
「紀宮」(きのみや)が困っていると、皇后は「困った事ね」とおっしゃり、何事もないように打ち合わせをお進めになる。先帝の二宮妃も、他の宮妃方もみな一斉にしらけたお顔をされていた。
そして葬儀の日、東宮妃は「風邪のようなもの」で欠席したのだった。
表の役人達は懸命に「欠席」の理由を「風邪のようなもの」から「夏バテのようなもの」としたり、「体調が・・・」と言葉を濁したり必死にとりつくろったけれど、その違和感はずっと「紀宮」(きのみや)の心に残っていた。
それでも、東宮妃は東宮妃。身分の上下が全ての宮中では下の者が上に忠告する事など出来ない。だから勿論、あの時なぜ東宮妃が「あなたとは違うの」とおっしゃったのかわからない。今も・・・
どんな時も、二宮の妃として「紀宮」(きのみや)は二人の姫を育て、公務に励み、ライフワークの学問に勤しんでいればそれで幸せだった。
しかし、決定的な出来事は起こってしまった。
それは昨年の冬。
今上の女一宮がご降嫁なされ、めでたい日の次の月に天長節がやって来た。
その日は一日中儀式三昧で、「紀宮」(きのみや)も二宮と共に参内し、祝賀を述べ、さらに一般参賀にも参加。
大姫と中姫は夕方、宮中に古くから伝わるしきたり通りの「御地赤」と呼ばれる着物を着せて参内させた。
丁度、4歳の女一宮も可愛いドレスを着て参内し、お上にお祝いを申し上げる筈だった。
歳の順で大姫が一歩、お上の元に出た時、突如、女一宮が
「あれ!あれ!」とおっしゃった。東宮妃が懸命に止めるのを振り切って大姫に近づくと、御地赤の袖を引っ張る。
大姫も中姫もびっくりして「ダメよ。今はダメ」といい、必死に袖を引きはがそうとする。
しかし、無理に離されると女一宮はより一層「あれ!」と叫びだし、今度は中姫の裾を引っ張ろうとしがみつくのであった。
もう大騒ぎであった。東宮と東宮妃は「いい子だから」となだめすかそうとし、女官や侍従も巻き込んで「ご挨拶を先にいたしましょう」と言い聞かせる。
しかし、女一宮はまるでほんの赤子のように泣き叫び、柔らかな絨毯の上にひっくり返って泣きわめき始めた。
皇后は少しぞっとしたように「どうしたのでしょう」とおっしゃったが、東宮妃にはそれが詰問のように聞こえたらしく、「だって・・大姫や中姫が綺麗な着物を着てくるからだわ」と言い返しなさった。
名前を出された大姫や中姫は頬を赤くしてご両親の方へ逃げようとする。二宮は娘たちを自分の方に引き寄せ、「お早く女一宮をあちらへ」と言った。
お上も少し不愉快な顔をされて「どんな理由があってもこのように取り乱すとは」とお怒りをあらわになさる。
すると東宮妃はさらに興奮して「女一宮はその赤い着物に触りたかっただけなのに、何で触らせてくれないの。それでも年上なの?大姫、中姫、小さな子を泣かせて罪悪感ないの」と責め立てた。
東宮はおろおろとひっくり返って泣いている女一宮を抱き上げ、女官に控えの間に連れていかせようとした。
「紀宮」(きのみや)は思わず、「それは言いがかりです・・」と言いかけたのだが、その前に皇后が「本日の子供達の服装について打ち合わせをしなかったのですか。お伺いは立てたの?」と「紀宮」(きのみや)を見つめておっしゃった。
「はい。あの、てっきり女一宮様も御地赤をお召しになると思い」
「陛下、子供達の服までは揃える必要がないでしょう。私達はしきたり通りにしているだけです」と二宮は「紀宮」(きのみや)の前にお出になったが、皇后は首を横に振られた。
「でも現実に女一宮は悲しんで泣いているのよ。自分より綺麗な着物を着ている大姫たちをみて」
「こんな小さな子に着物なんて着せられるはずないわ。なのに、思わせぶりに派手な赤い着物を着て私の子を刺激するなんて。なんて恐ろしいの」
東宮妃は大姫たちにつかみかからんばかりになったので、「紀宮」(きのみや)は思わず膝を折った。
「申し訳ありません。私達の配慮が足りませんでした」
場はシーンとなってしまった。
東宮は「もういいじゃないか。「紀宮」(きのみや)も悪かったと言っているのだし」ととりなしにかかる。
「ひどいわ。小さな子が泣いて暴れているからって陛下に叱られるなんて。こんなの、普通じゃない。子供なのよ。大姫や中姫のような大きな子じゃないのよ」
と今度は東宮妃が泣き出し、どしどしと東宮の御胸を叩く。お上も言葉を失い皇后をご覧になり、「もう挨拶の儀は終わりにしよう」とおっしゃった。
東宮家、二宮家の「お祝い御膳」の時間が迫っていたのだ。
侍従はほっとしてお上を、控えの間にお連れする。
その後ろを皇后も黙ってついて行かれた。振り返りもせず。
女官長が「お祝い御膳のお時間です。お子様方はそれぞれお帰りに」
というと、大姫も中姫も不安そうな顔をしご両親を窺う。
母宮がご自分達を庇って謝られたのだと思うと、大姫達は涙が出そうになったがそれをじっとこらえて「ごきげんよう。伯父上様。伯母上様」といい、部屋を出て行った。
女一宮は帰ろうとする姫宮達を追いかけようと起き上がったが、それをぐいっと東宮妃に抱き上げられ「私は一旦東宮御所に帰ります」と言った。
「でも、これからお祝い御膳だし。教育係に任せたら」と東宮は言ったが、妃は聞いていなかった。
「私、この子と戻ります」と言うなり、さっさと部屋を出て行ってしまったのだ。
「じゃあ、待っているからね」と妃の後ろ姿に東宮は声をかけたが一切無視だった。
気まずい空気を察した女官長は「ささ、食堂へ」と促した。
すでに降嫁されたお上の女一宮、未草の君(ひつじぐさの君)がご夫君とおいでになっていたがただならぬ雰囲気に「どうなさったの?」と兄宮や「紀宮」(きのみや)に尋ねる。
でも皆、すでに疲れ切っていた。
食堂にお上と皇后が入られ、東宮と二宮、「紀宮」(きのみや)、未草の君と御夫君が席に着いたが、東宮妃は現れない。
「先に始めましょう」と明るく東宮は言ったが、皇后は「それでは東宮妃が可哀想ではありませんか」とお止めになった。
「東宮御所に連絡をして、急いでこちらに来るように言いなさい」と侍従にお命じになり、言われた侍従は走って連絡を取りに行ったのだが、中々帰って来ない。お祝い御膳が始まる時間からすでに30分以上も経ち、その間、二宮も「紀宮」(きのみや)も黙っている。
「皇后陛下。お上をお待たせするのはどうかと思いますわ」と未草君(ひつじぐさの君)が意見すると、皇后は微笑まれ「その通り。でも東宮妃が戻って来た時に私達が先に食べ始めていたら気まずい思いをするでしょう」
「東宮妃はお具合でも悪くなさったの?」
「そうではないけど、女一宮の調子が悪くてね。お上、お待たせして申し訳ありませんわ。でもここはもう少し」
もう少し・・・もう少しと言いながら1時間が過ぎる。
東宮もばつが悪いのか、必死に話題を提供し、一人で二宮や未草君(ひつじぐさの君)の御夫君に話しかける。
「東宮妃殿下は、女一宮様を寝かしつけてから参られます」
「東宮妃殿下は女一宮様をお風呂に入れていらっしゃるとかで・・・」
そんなよしなしことを報告されつつ、皆のイライラも募りそうな時、突如、皇后が立ち上がられた。
「私、東宮妃が来るまで玄関で待ちましょう」
(え?)未草君(ひつじぐさの君)も「紀宮」(きのみや)もぎょっとした。
「それは・・皇后陛下、お風邪を召されては大変です。それなら私が参ります」と「紀宮」(きのみや)はすっくと立ちあがり、ドアを開けようとする。
「私も」と未草君(ひつじぐさのきみ)も立ち上がった。
二人はその場にいたたまれないように廊下に飛び出し、冷たい風が吹く玄関へと歩いて行った。二人とも無言だった。未草君(ひつじぐさのきみ)は義姉の思いを理解し、心の中でご自分だけが臣下へ逃げた事に罪悪感を抱いていた。
「紀宮」(きのみや)は唇を真一文字に結び、お長服の裾が隙間風に吹かれるのも構わずひたすら背中をまっすぐにして待っていた。
東宮妃が現れたのはそれからさらに1時間も後だった。
東宮妃はすっかり普段着に着替えていて、「紀宮」(きのみや)達を見ると悪びれもせず「どうも」と言い、食堂へ入って行った。
「東宮のお姉さま」と未草君(ひつじぐさのきみ)が言いかけたその時、がたっと崩れ落ちる音がしてはっと振り返った。
冷たい壁に寄りかかるようにして立った「紀宮」(きのみや)の瞳から大粒の涙が流れ落ちていた。
「お姉さま・・・お姉さま」優しい義妹の腕に支えられ、何とかしっかり立ち上がった「紀宮」(きのみや)だったが、初めて感じる人と言うものへの憎しみにおののいていた。
(私には私の意地がある。誇りがある。私はどす黒い思いを認めない。決して。どこまでもひたすらにこの道を歩んでいくんだわ)
「紀宮」(きのみや)は感情を振り払って頭を上げた。もう弱くない。
 チャーター機の1便で帰国した2人が検査を拒否。もめにもめて政府側が折れてしまったらしいですね。どうして拒否するんでしょうか?
チャーター機の1便で帰国した2人が検査を拒否。もめにもめて政府側が折れてしまったらしいですね。どうして拒否するんでしょうか?


































 上皇后が非常ブザーを押して侍医を呼ぶ
上皇后が非常ブザーを押して侍医を呼ぶ 上皇はいびきをかいているような感じだったけど、処置をしている間に意識を取り戻す
上皇はいびきをかいているような感じだったけど、処置をしている間に意識を取り戻す 30日にMRI検査をするもどうして倒れたのか原因となる初見は見つからない
30日にMRI検査をするもどうして倒れたのか原因となる初見は見つからない 30日には朝食もとられている
30日には朝食もとられている 驚きました。
驚きました。 こんなんで3月にお引越しなんか出来るんでしょうか?
こんなんで3月にお引越しなんか出来るんでしょうか? 華子妃殿下が31日=2月5まで検査入院
華子妃殿下が31日=2月5まで検査入院 婦人科系の精密検査を受ける為
婦人科系の精密検査を受ける為 こちらも大変心配です。年齢的には色々出てきてもしょうがないのですが、華子妃にはいつまでもお元気でいらして欲しい。
こちらも大変心配です。年齢的には色々出てきてもしょうがないのですが、華子妃にはいつまでもお元気でいらして欲しい。
































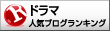

 小泉進次郎が「育休は休みじゃない。育児っていうお仕事してます」と言ったとか。
小泉進次郎が「育休は休みじゃない。育児っていうお仕事してます」と言ったとか。


























 他人事ではあるんですけど。
他人事ではあるんですけど。
 滝クリの資産は3億円
滝クリの資産は3億円










