結構「面白い」って言われてしまい・・・ついつい・・・
第一回目は こちら
 韓国史劇風小説 「天皇の母」連載 第 2 回
韓国史劇風小説 「天皇の母」連載 第 2 回 
(フィクションだよ・・フィクション)
年の瀬が迫っていた。
「また女かもしれない」
誰かがつぶやき「そんな事を言うな」と遮る。
そうは言っても天皇と皇后の間にはすでに4内親王が生まれている。
皇位継承権があるのは男子のみで、このまま生まれなかったらどうなるか。
不安で不安でしょうがないのであった。
だから、月満ちて、未来の天皇がが生まれた時、堰を切ったように日本中が
喜びにあふれた。
「何っ!男!本当に男なのかっ!ナニはあるかっ!」
時の総理大臣は知らせを聞くなり叫んだ。
ぶしつけな物言いに女官長は怒りそうになったが、まあ、目出度い事だしと
「ございます」と答えた。
すると大臣は、いきなりはらはらと大粒の涙を流し始めたではないか。
「まさに日本は神の国だ」
今まで心の重しになっていた事が一瞬にして吹き飛んでいくような素晴らしさ。
冬なのに清々しい風が吹き渡る・・・まるで春が来たかのように。
「天皇陛下万歳。皇太子殿下万歳」
その場にいた人達はみな合わせたかのように万歳三唱を続けるのだった。
皇后は生まれたばかりの男の子を見て優しく微笑んだ。
傍らの天皇は「ありがとう。よく頑張ったね」とねぎらった。
「思えば遠い道のりだったような気がするよ」
二人の胸に去来したのは、婚約以来の山あり谷ありの人生。
天皇がまだ皇太子時代。
父帝は生まれつき体が弱く、政務を取るにつれさらに身も心も弱らせていった。
次第に回りの期待は皇太子に集中するようになる。
「摂政宮」となり、父の代わりに政務に携わる、そして、宮家の女王と婚約。
当時はまだ付き合ったりするような時代ではない。
その結婚を決めたのは時の天皇と皇后であった。
すぐに女王は女学校を中退し、お妃教育に励むようになり、
皇太子もまた妻を迎える準備を進めようとしていた。
まさにその時、いきなり「婚約を破棄すべきである」という意見が
政府から出たのだ。
たまたま女王の弟が軍隊に入る為に身体検査を受けた時
「色弱」の結果が出た。
そこで大騒ぎである。よくよく調べたら女王の母方に色盲の気が
ある事が発覚。発病しているのはその弟君だけだったのであるが
それでも高貴な血筋にそのような遺伝はダメだと反対する勢力が現れた。
それに敢然と立ち向かったのは女王の父宮。
「一度決めた婚約を破棄するなど前代未聞。もし、そんな事をなさるなら
私は娘と一緒に自害します」
と言い募り、猛烈な「婚約破棄反対」運動を始めた。
実は、父帝もその昔、婚約を破棄せざるを得ない事があった。
美貌も才覚も家柄も完璧な女王と婚約していたのだが、その女王は
「肺病」の気があると診断されたのだ。
その時、女王の父は黙ってそれを受け入れ、気の毒に思った帝は
素晴らしい縁を女王につけた。
そんないきさつもあり、まさか、こういう事になって「婚約破棄反対」を
言い出す宮がいるとは誰も思わなかったのだ。
宮は病床の天皇には何も言えないと思ったのか、皇后に直訴した。
「婚約を破棄されたら我が家の面目丸つぶれ。娘を殺して私も」
これには皇后も驚き、そしてそういう宮の態度を嫌悪し、女王に関しては
いいも悪いも思っていなかったが、突如「婚約反対」の立場に回った。
侍従が「そうかといって、一度決まったものを白紙に戻すのは」というと
皇后は
「私は聞いてない。政府が婚約したと勝手に言ってるだけです」と横を向く。
女王を選んだのは皇后であった筈なのに、どうしてこうなるのか。
事がこじれて行く事に周囲は困惑した。
女王の父宮は怪文書をばらまいてまで皇室を攻撃し始める。
蚊帳の外におかれた女王は日々、いたたまれない気持ちであった。
おりもおり、摂政宮はイギリスに留学する事になり、結果は保留に。
長い時間・・・女王はただただ笑顔で事の成り行きを見守った。
娘が諭したからといって、妻が怒ったからといって前言撤回するような父宮ではない。
宮家は不穏な空気に包まれた。
英国の空の下、ぼんやりと一度見ただけの女王の顔を思い浮かべ
「遺伝とはどの程度作用するのだろうか」などと考えつつ
「でも、不確定な事で婚約を破棄してもいいものだろうか」とも思い。
「我が英国にも遺伝病はございます。先代の女王の血筋で血友病が。
多分そのせいでロマノフ家の皇太子は・・・気の毒な事です。
我が家には血友病ではないが、少し知恵が遅れた身内もおりましてな。
しかし、そういう事はどこにもあるという事。高貴な血筋は深いもの。
しかし、その遺伝が必ずそうなるとは限らない。だから、我々は前向きなのです」
国王はそうやって迷っている摂政宮を諭した。
それで宮の心は決まった。
結局、摂政宮と女王は華燭の典を挙げた。
といっても、式の直前に前代未聞の大震災が起こり、延期につぐ延期だったのだが。
よいのか悪いのかわからないが、とりあえず二人は
幸せな日々をスタートさせた。
新婚旅行と称して、東北の湖のほとりの屋敷に1月程滞在。
毎日馬車で散歩。人前でも平気で手をつなぐ。
「宮」「お上」と呼び合う。
人目もはばからないその態度に、付近に住む農民たちはみな驚き
「天子様は普通の人とは違う」と目を丸くした。
生まれも育ちも皇族出身の摂政宮妃は皇后よりも血筋は上。
本人は気にしていなくても、回りは気を遣うし、皇后自身、多少の
居心地の悪さは感じていたろう。
それというのも、皇后と皇太子妃は水と油程性格が違っていたからだ。
皇后が当時の皇太子妃になったのは、ひとえに「体が丈夫」だったから。
婚約破棄した女王に比べると家柄も血筋も美貌も何もかも劣っていた。
そういう目で回りも見たのだろう。
皇后は人一倍努力を重ねて夫の愛を勝ち取り、立て続けに男子を産んだ。
負けず嫌いではきはきして気が利く皇后。
一方、宮家の長女として大事にかしずかれてそだった皇太子妃はしっかり者では
あったけれど、かなり「おっとり」していた。
病の天皇を皇太子夫妻が見舞った時、皇后は自ら看病し
熱の高い天皇の額を冷やしたり、体を拭いたりしていた。
皇太子妃は「ごきげんよう」と言ったきり、所在なく突っ立っている。
皇后は黙々と女官のように仕事を続ける。
「陛下自らがそのような事をなさらなくても」
さすがに皇太子も口を挟む。
「おたあさまのお体が・・・・」
「手ぬぐいっ!」と皇后が厳しい声を発した。
弾かれたように皇太子妃は金盥の中に手を突っ込んで手ぬぐいを冷やす。
けれど・・・・手袋をしたままだった。
「さっさとよこしなさい」
皇后は手ぬぐいを取り上げた。それはびしょびしょでちっとも絞れていなかった。
「おたあさま、それは私が」と皇太子が言いかけたが
「帝になられる方にそのような事はさせられません」と皇后は断り、
その場で手ぬぐいを絞った。
じょぼじょぼと水が床にしたたり落ちた。
それを女官達が大慌てで拭くのだった。
気が利かない所があるとはいえ、皇太子妃はそもそもが明るくて
教養が深く慈悲深かったから、皇后を恨んだり憎んだりする事はなかった。
やがて帝がお隠れになり、新しい帝と皇后が誕生した。
即位の大礼は京都で行われた。
古式ゆかしい即位の式。
まばゆいばかりの皇后は、美しい十二単に身を包み、それから
ローブ・デコルテにティアラの正装になる。
国民の祝福を受け、順調なスタートを切った。
しかし、それがなかなか順調ではなかったのだ。
なぜなら、二人の間には世継ぎが誕生しなかったからだ。
きっちり2年おきに出産を繰り返していた皇后だったけど、全て内親王だった為に
宮中内ではひそひそ陰口がきかれるように。
「皇后は女腹では?」
「皇太后さまは4人の男子に恵まれたというのに」
「やっぱり宮家出身の皇后では」
このまま世継ぎが生まれなかったら・・・・皇位は1歳下の宮になる。
兄天皇と違って、スポーツが大好きでさっぱりとした性格で
側近に愛されていた。
彼が後々「皇太弟」になるのも悪くはないと誰もが考えた。
いっその事、この宮が結婚すると同時に皇位を譲ってはどうか。
そんなたくらみさえ出てくる始末。
「それが嫌なら側室を」と望む声もあった。
天皇は大いに悩み、日々苦しんだ。
彼の脳裏にはイギリスの一夫一婦制が浮かぶ。
互いに尊重し合い、愛し合う夫婦の姿。それは理想だった。
男子を産まないからといって、皇后を悲しませるような事が
出来るだろうか。
近代的な結婚制度。それは一夫多妻ではない。
女性を道具のようには扱えぬ。
「私は側室を持つつもりはない」
その言葉に侍従は言葉を失った。
「世継ぎが生まれなければ皇統の危機になります」
「弟が3人もいるのだ。どこかには男子が生まれるだろう」
「世継ぎは天皇の義務でございます」
「義務とはいっても自分で選んで産むわけにはいかない。
それこそ天の采配ではないのか」
「私情を挟んではいけません」
最後はやはり皇太后が大宮御所から出てくる。
「そうはおっしゃっても皇太后陛下。先帝が側室を持たなかったのは
なぜでございますか」
「それは私がきちんとお務めを果たしたからですよ」
無論、そうであるが、それ以上に夫の愛を自分一人に集中させるため
側室を持たせなかったのは皇太后自身だった。
「男子を産むのは妃の務め。でも出来ないからといって責めたりはしません。
出来る人がすればいい事なのです」
若き天皇は一言も返せなかった。
 世の中厳しいなあ・・・・・
世の中厳しいなあ・・・・・



 TAROの塔
TAROの塔 




 期待してなかったのにすごいっ
期待してなかったのにすごいっ



 私、
私、 」とドン引きするような娘さん
」とドン引きするような娘さん




 愛人の方は勝手にかの子を美化してるし。
愛人の方は勝手にかの子を美化してるし。 いいわあ。あの目が。
いいわあ。あの目が。


 冬のサクラ
冬のサクラ 


 必死になるモナミには気の毒でした。
必死になるモナミには気の毒でした。

 女の敵だ
女の敵だ













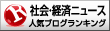


 この事件を仕組んだのは国家老の吉田で、ゆえにあだ討ちもさせず、事は
この事件を仕組んだのは国家老の吉田で、ゆえにあだ討ちもさせず、事は 臼井家の長子、六郎はあだ討ちを遂げようとするが、明治になり
臼井家の長子、六郎はあだ討ちを遂げようとするが、明治になり 六郎は山岡鉄太郎に弟子入りし、剣術を学び密かに下女のなかを使って
六郎は山岡鉄太郎に弟子入りし、剣術を学び密かに下女のなかを使って 果たしてこの事件は「あだ討ち」なのか「殺人」なのか。近代日本の価値観
果たしてこの事件は「あだ討ち」なのか「殺人」なのか。近代日本の価値観 もう最初の両親の殺され方からして惨くて。これであだ討ちを許さず、
もう最初の両親の殺され方からして惨くて。これであだ討ちを許さず、



 皇太子が誕生日会見で引用した東宮医師団の見解
皇太子が誕生日会見で引用した東宮医師団の見解 野田さんは「
野田さんは「
















