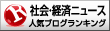外はかなりの暑さのようだった。
セミの声はいつまでも聞こえているし、日の長さも変わらない気がします。
病室から見える景色はいつも同じ。
今まで病気らしい病気をしたことのない「紀宮」(きのみや)はすっかり心が折れてしまっていた。
快適な個室とはいうものの、ベッドから降りてはいけないし、トイレに行く時も一々車椅子を使わないといけない。食事も妊婦の血圧が上がらない様に薄味になっている。
一体、お金がどれくらいかかるのかしら・・・「紀宮」(きのみや)は考えるだけで頭が痛くなって来た。今回の療養費は宮内庁の方から予算を組んでくれるとはいうものの、基本的に皇族に健康保険はない為、10割負担である。
差額ベッド代やら食事代やら考えると、こんな涼しい部屋の中であれこれ気をもむのは申し訳ない気になってくるが、それでも「紀宮」(きのみや)は心配せずにはいられなかった。
「今日は顔が青いようだけど」
見舞いに来た二宮が顔を覗き込む。
「紀宮」(きのみや)がご機嫌斜めの時はすぐにわかる。
まず無口になり、微笑みが消える。物言いは丁寧だけどその強さと言ったら。若い頃、喧嘩してもすぐに謝って来たほのぼの妃は消え、今や宮家のラスボスと呼ばれるだけある。
そう思って二宮は覗き込んだのだが不意をつかれた。
「紀宮」(きのみや)の瞳から大粒の涙がこぼれていたのである。
「どうしたんだい?どこか痛いのかい?具合が悪いとか」
「いいえ」
「だって君は泣いているうじゃないか」
「はい」
「何で泣いているの」
「わかりません」
「わからないって事はないだろう。お局に意地悪言われたのかい?」
「いいえ」
「いや、言われたんじゃないか?それとも大姫や中姫がここで何か悪いことでも」
「いいえ。何もございません。ございませんけれど、とにかく涙が止まらないのでございます」
二宮はすっかり困ってしまって
「何でだろうね。出産の事なら心配しなくてもとあれほど言ったじゃないか。東宮家の事も子供の性別も何も考えなくていい。ただ君は無事に産む事だけを考えていればいいのだから」
「はい。宮様の言葉はいつも心に刻んでおりますわ。でも・・・いえ、ベッドに縛り付けていられるととても不安になるのです。いくら本を読んでも読み切れない気がしますし、子供達の事も気になりますし。もしもの事を考えると」
「「紀宮」(きのみや)どうしてそんなに気弱に・・君らしくない」
二宮は怒ったように言った。いつもは「オールウェイズスマイル」と「物事は何とかなる」でどんな辛い事も乗り切って来た。それはいつも「紀宮」(きのみや)がおっとりと側にいてくれたからだ。
それなのに、今は誰よりも弱弱しく泣いている。まるで少女のような白い顔。
懐かしい表情をするんだな・・などと一瞬二宮は思ってしまったのだが。
「私達、間違ってはおりませんよね」
その言葉に思わず二宮は「紀宮」(きのみや)を抱きしめた。
「当たり前だろう。間違ってなんかいない。私達は絶対に間違っていない。誰かがそういって君を虐めるなら私が許さない」
ああ、夫の鼓動が聞こえる。「紀宮」(きのみや)は子供達が生まれる以前の、心ときめく恋物語を思い出していた。あの時はその胸に抱かれると外国製の煙草とコロンの薫りがしたものだった。
今は煙草をやめてずいぶん経つ。だけど変わらないその胸板の厚さ。
「紀宮」(きのみや)はほんのちょっと安心して泣きながらもちょっと笑った。
「君の辛さの半分もわからない私は自分に腹が立つ事がある。だから時々どうしたらいいかわからなくなる。どこへ行っても「紀宮」(きのみや)の事が気になる。気になるけど平気な顔をしている」
結婚して以来、こんなにロマンチックな告白を聞くことがあったろうか。
ようやく「紀宮」(きのみや)はニッコリ笑い、
「私も同じです。いつも殿下のことを思っております。誰よりも」
とんとんとノックの音がしてお局が顔を見せた。
「お取込み中でございましたでしょうか?」
「そんなことない。「紀宮」(きのみや)が泣いていたから。お局に泣かされたのかと聞いていたところだよ」
お局は向日葵の花瓶をサイドボードに起きながら心外という顔をした。
「どうして私がお妃さまを泣かしますの?女が泣くのは99%殿方のせいですわ」
お局は容赦なく言った。言い返せない二宮は立ち上がり
「そろそろ帰るよ。大姫と中姫の勉強を見てやらないと。それに明日の公務の準備もあるから」
「ご負担をかけますわ」
「いや。いい・・大丈夫。ではお局、あとはよろしく頼むよ」
「お任せ下さいまし」
お局は深々と頭を下げた。二宮は挨拶も早々に部屋を出て行った。
「まあ、綺麗な向日葵ね」
「そうでございましょう。もう向日葵の盛は過ぎているんですのに。今時のお花屋さんは季節を問わずにお花を置いてくれますから」
「私、殿下に愚痴を言って困らせてしまったわ。ここ何日かの鬱憤がほんとうに溜まっていたのね。申し訳ないことをしてしまった」
「どんどん愚痴でも悪態でもついてやったらよろしいんですよ。夫というものは年月が経つにつれて妻の気持ちに鈍感になるものでございますから。適当な時にガツンと雷を落としておけば楽ですよ」
「そうは思うけど。やっぱり言えないわ。本質を突くわけにはいかないもの」
お局は箪笥の中から「紀宮」(きのみや)の着替えを出し、揃え始めた。
「両殿下の目に嫌でも入る週刊誌や雑誌の見出しは日々過激になっていますわ。悲劇の主人公は東宮妃と女一宮さんで、すっかり「紀宮」(きのみや)様は悪者になってしまわれた。男女産み分けなどの策が弄せる程賢いお方であれば后の宮様の産児制限などに従ったりなさいませんわ。お好きに何人でもお産み遊ばしてそのお子が全員内親王でも平気で、次々旧宮家とでも縁談をまとめてしまわれるでしょうよ」
「まあ、お局。そんな事を考えていたの?」
「紀宮」(きのみや)はびっくりしてお局を見た。
「ああ、「紀宮」(きのみや)さま、その真正直さが国民にとっての癒しなのですわ。かの持統天皇しかり、光明皇后しかり、ご自分の目的の為なら平気で他人を蹴落とし、殺してしまう。皇室とはそういうところでございます。「紀宮」(きのみや)さまはお生まれになるのがもし内親王だったらとご心配されているのですか?」
「そんな事ないわよ・・・そんな事、考えてはいけないの」
「でも、母であれば生まれる子の性別は知りたいと思うものですし、お二人内親王が続いたのですから、次はぜひ親王をと考えるのが普通なんです」
「それはわかっているけど」
「恐れているのはもし内親王が生まれたら、それ見た事か、東宮妃に張り合って頑張って産んだのに結果的に女一宮様の皇位継承を確立する助けになっただけだと。2000年の伝統は破れ男系男子で継承してきた皇室の終焉と」
「・・・・」
「けれど「紀宮」(きのみや)さま。東宮様にあって二宮様にないもの。それは八百万の神の力ですわ。そもそも二宮様が「紀宮」(きのみや)さまをお妃に選ばれたことも、また皇祖神のお計らいだったのですから」
「そう・・かしら」
「紀宮」(きのみや)は不安そうな目でお局を見た。
「そうですとも。これは噂ですが本当は東宮家に生まれるのは親王様だったというお話はご存知?」
「え?どういうことなの?」
お局は支度をやめて、ベッドの脇にある椅子に座った。そしていかにも秘密を打ち明けるように声を潜めて話し始めた。
「これは女官達の間では有名なお話で。元々東宮妃さんはお若いころにおいたをやりすぎて石女だという噂が成婚の頃からありまして。また東宮さんも、男女のあれこれにひどく疎くていらっしゃり。まあ、そういうわけでお二人は結ばれたものの、お子の存在はどこか遠くに追いやっていらしたのです。そうはいっても東宮家の役割は後継ぎを産む事で、それをお妃さまにご納得頂くのが本当に大変で。ついに5年以上が経過した後、例の産婦人科では有名な先生をお招きして治療が始まったんだそうです。今は体外受精という方法がありますね。出来るだけ自然な形で医師も東宮さんも望んでいらしたから・・ところがやっぱり何度挑戦しても流れてしまう。
その理由がまあ、過去のおいたさん以上に今のこれ」
お局は煙草を吸う真似をした。
「この癖がどうしても抜けなかったと。喫煙は母体にとって最もいけない事です。低体重児や障害を持つ子供が生まれてしまうことがある程。それなのにお妃さんは治療中にも関わらずおやめにならず。
漸くご懐妊の運びとなった時には、お妃さまはそれを隠して飛行機に乗られた。しかも遠出をしてお酒を飲むなど無茶をやられて。またも流れてしまったのです。確かそれは親王さんでした。でも、お妃さまはご自分のミスとはお認めにならず新聞社のせいになさった。一方でお妃さまの御実家では、これは必ず親王が生まれると踏んだんですわ。それで究極の男女産み分け法を試す事にしたのです」
「そんなものがあるの?」
「紀宮」(きのみや)はびっくりしてお局に尋ねた。
「確かアルカリ性とか酸性とか・・・そういう話は聞くけれど」
「そんな方法もございますわね。でもそれは長い時間をかけて男子を産みやすい体にしていくとか、そういうお話でございましょう?東宮妃が2度目の懐妊をされたのは流産からほどなくでしたでしょ?」
「そうだったわ」
「お妃様は元々妊娠しづらいお方だったのですもの。それを流産してすぐに、しかも男子限定でとなると方法は科学に頼るしかございません。お妃様に施されたのは最先端の医療技術だったのですわ。しかも受精させた時から男子が生まれるという・・いわゆる産み分けの。だってあの先生はその道の権威でいらっしゃいますもの。めでたく懐妊された東宮妃はご自分がお産みになるのは親王殿下と疑っていなかったというお話です。そういうお約束が出来ていたとも。だから、内親王が生まれた時は国民よりも東宮様よりもご本人とコンクリート卿が驚いて大層お怒りになったそうです。今もってなぜ生まれたのが内親王だったのか、誰もおわかりにならないとか」
「でも生まれてくる子供の性別を特定するなんて元々無理なことじゃない?それは神様に挑戦するようなものでしょう?」
「そうですとも!」
お局は叫ぶように言った。
「そうなんですわ。人がいつ生まれてくるか、いつ死ぬか。生まれてくる子が男か女か。それは全て神様がお決めになることなんですよ。「紀宮」(きのみや)様のもとに最初に大姫が、そして中姫がお生まれになったのも、神様がお決めになった事です。つまりこれから生まれるお子も神様がお決めになるのです。それをあたかも人の手でどうにか出来るというような考えを持った時点で東宮様のところは見放されたんです。これは大きな声では言えませんけどね」
「結構、大きな声じゃなくて?」
「申し訳ありません。不遜なことを申しました。ただ、私が申し上げたいのは、今、やきもきしてもすでに運命は決まっているということです。皇統を見放すのかそれともお繋げになるのか、それは皇祖神がお決めになることで、宮様がただご自分のお役目を果たせばよろしいのですよ」
いつの間にかあたりは暗くなり、太陽が沈もうとしていた。
煩かったセミの声も減り、代わりに秋の虫の声が聞こえる。
「紀宮」(きのみや)は窓の外に広がる景色に思いをはせた。
それでも季節は変わって行くのだ。
「「紀宮」(きのみや)様、ご結婚された時、どれほど国民は喜び、そして宮様ご夫妻を敬愛したことでしょう。僅か15年でいわれのない中傷を受ける身になられたこと、この局は悔しくてなりません。でも、宮様のご苦労はいつかきっと報われる日がくると、私は信じております」
「紀宮」(きのみや)は微笑んだ。沈む日を背にしているその姿はどこまでも美しいとお局は思った。
「大御心を思えば、私の悩みなど大したことではないわね。わかったわ。もう泣かない。我慢します。退屈でもつまらなくても腰が痛くても食欲がなくても」
「その調子ですわ。ではシャワーの準備を」
お局の足取りは軽かった。