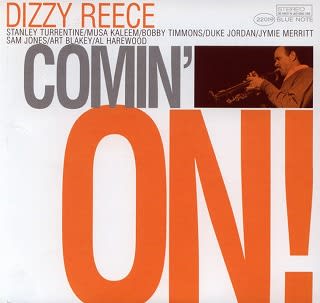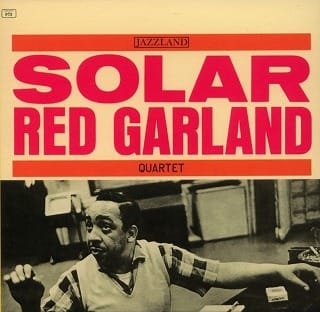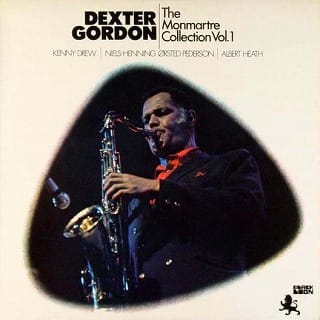■Easy Like / Barney Kessel (Contemporary)
バーニー・ケッセルはモダンジャズを代表する白人ギタリストのひとりですが、1960年代はスタジオの仕事がメインでしたし、ジャズの現場に本格復帰したのが1970年代でしたから、やはり全盛期は1950年代に吹き込まれた諸作でしょう。
まあ、「全盛期」をどうとらえるかは十人十色でしょうが、1951年にはオスカー・ビーターソンのトリオにレギュラーとして抜擢されながら、巡業嫌いで潔く辞め、西海岸に定着してからは多くの名演を残し、人気投票でもトップにあった実績は侮れません。それがあったからこそ、スタジオの仕事も途切れることなく続き、1960年代にはハリウッド芸能界で縁の下の力持ちとなったのでしょう。
さて、このアルバムはバーニー・ケッセルにとって、そうした時期の最初の成果を楽しめる名盤で、まずは10インチLPとして1954年頃に発売されたものですが、1956年になって12インチ盤へと拡大再発するにあたり、新録音を加えた経緯があります。
ですから1953年と1956年のセッションが混在しているのですが、流石は音の良いコンテンポラリーだけあって、違和感はほとんど感じられないでしょう。もちろん演奏そのものの味わいが同じというのは進歩が無いというよりも、不滅の完成度として結果オーライということだと思います。
メンバーは1953年のセッションがバーニー・ケッセル(g) 以下、バド・シャンク(as,fl)、アーノルド・ロス(p)、ハリー・ババシン(b)、シェリー・マン(ds) という如何にもの面々♪♪~♪ また追加された1956年のセッションにはバディ・コレット(as,fl)、クロード・ウィリアムソン(p)、レッド・ミッチェル(b) が交代参加しています。
A-1 Easy Like (1956年2月23日録音)
バーニー・ケッセルのオリジナルで、なかなかリラックスしたモダンジャズのビートが心地よい演奏です。グルーヴィな雰囲気の中にも軽いフィーリングが西海岸派の面目躍如でしょう。
バディ・コレットは黒人ですが、このフルートの軽妙な味わいは捨て難く、ほどよいファンキー節というクロード・ウィリアムソンも素晴らしいと思います。そしてバーニー・ケッセルのギターが、極力ごまかしを避けようと奮闘するのです。テーマ部分も含めて途中、何箇所かで聞かれる疑似オクターブ奏法みたいな弾き方は、ちょっと真似出来ない名人芸だと思います。
A-2 Tenderly (1953年11月14日録音)
多くのギタリストが名演を残しているスタンダード曲ですから、バーニー・ケッセルも油断は禁物ながら、シブイ解釈のテーマ演奏はギターの独演会からリズム隊を呼び込んでのメロディフェイクまで、素晴らしい味わいが楽しめます。倍音やチョーキングの使い方もニクイばかりですねぇ~♪ もちろんコード弾きの魔法も流石!
A-3 Lullaby Of Birdland (1953年12月18日録音)
ジョージ・シアリングが書いた魅惑のメロディがスマートに、そして力強く演じられていますが、ここで聞かれるような、ちょっと浮ついたようなスピード感が曲想にジャストミート! 私は大いに気にいっています。
と言っても、シェリー・マンとハリー・ババシンが作りだす真正のジャズビートはグイノリの悪魔性が顕在ですから、クロード・ウィリアムソンのピアノからバド・シャンクのフルートへと続く美しき流れ、また淀みないフレーズを積み重ねていくバーニー・ケッセルのアドリブパートは、快感以外の何物でもありません。
キメまくりのアンサンブルとアドリブの両立が、本当に見事だと思います。
A-4 What Is There To Say ? (1953年12月18日録音)
これまた私の大好きなスタンダード曲で、ビル・エバンスやレッド・ガーランドが演じたピアノバージョンがあまりにも有名ですが、ギターならば、これっ! でしょうかねぇ~♪
実際、ここでのバーニー・ケッセルは余計な色気は見せず、とことん素直に素敵なメロディをフェイクしていきます。う~ん、ほとんど出来すぎのアドリブですよ♪♪~♪
A-5 Bernardo (1953年11月14日録音)
ラテンリズムを上手く使ったバーニー・ケッセルのオリジナルは、バド・シャンクのフルートも楽しい快演です。この軽さ、この浮かれた調子は、まさに西海岸でしょうねぇ~♪
アドリブパートに入ってからの弾んだ4ビートも実に快適ですし、十八番のリックを出し惜しみしないメンバーのサービス精神の中で、ギターのボディをチャカポコ叩くバーニー・ケッセルが感度良好ですよ。
A-6 Vicky's Dream (1953年11月14日録音)
一転してクールスタイルのモダンジャズ曲で、猛烈なスピートでクネクネと紆余曲折のテーマアンサンブルが、一糸乱れぬ素晴らしさです。シェリー・マンのシャープなドラミングも絶品♪♪~♪
そしてバーニー・ケッセルのギターが思いっきりツッコミ鋭いアドリブに徹すれば、バド・シャンクのアルトサックスも青白く燃える炎です。アーノルド・ロスのピアノも精一杯、ビバップしていて好感が持てますよ。
B-1 Salute To Charle Christian (1953年12月18日録音)
これがアルバムの目玉演奏!
バーニー・ケッセル自身が大きな影響を受け、尊敬しているというエレキの天才ギタリストだったチャーリー・クリスチャンに捧げたオリジナル曲ですが、テーマメロディはディジー・ガレスピーの「Birk's Works」を焼き直したものですし、アドリブパートで連発されるフレーズは、明らかにチャーリー・クリスチャンの十八番を繋ぎ合わせた稚気がたまりません。
聞くほどに、思わずニヤリの名演ですよ♪♪~♪
B-2 That's All (1956年2月23日録音)
これも私が好きでたまらないスタンダード曲ですが、それにしても、このアルバムのプログラムは憎さあまって可愛さ百倍という、逆もまた真なりですね♪♪~♪
ここではバディ・コレットのフルートを上手く活かし、バニー・ケッセルの素晴らしいコードワークも冴えわたりの傑作トラックに仕上がっています。こういう素直さって、本当は一番難しいのでしょうねぇ、サイケおやじにしても、自惚れからコピーして挫折した前科を深く反省している次第です。
B-3 I Let A Song Go Out Of My Heart (1953年12月18日録音)
デューク・エリントンの楽しい有名曲を、ここでは室内楽風味も入れながら、粋に演奏するバンドが流石の名人揃いを証明しています。
とにかくアンサンブルとアドリブの対比が出来すぎというか、殊更にジャズっぽさを強調するピアノとアルトサックスの思いきりの良さが秀逸ですし、バーニー・ケッセルにしてもリラックスしながら、難しいことをサラリとやってのけるのです。
なんてことない演奏に聞こえながら、奥はどこまでも深いと思います。
B-4 Just Squeeze Me (1953年11月14日録音)
これもデューク・エリントン楽団の定番ヒット曲で、オリジナルメロディが持つグルーヴィなムードを白人的に解釈しながら、実はハードバップの味わいも滲む隠れ名演だと思います。
特にテーマのアンサンブル最終部分の怖い盛り上がりから、バーニー・ケッセルのアドリブに入っていく瞬間のスリルは絶大! 演奏が進むにつれて馬力を発揮していくリズムの存在感も凄いと思います。
相当にエキセントリック!?
B-5 April In Paris (1956年2月23日録音)
こちらはカウント・ベイシー楽団でお馴染みという和みのメロディが、ほとんど一人舞台というバーニー・ケッセルのギターで演じられます。あぁ、このハーモニーとコード選びの魔法は流石です。
そしてリズム隊が入ってからのパートでは、グイノリのグルーヴィなビートを活かしたアドリブが、これまた絶品ですよっ♪
B-6 North Of The Border (1956年2月23日録音)
そしてオーラスは、またまたラテンビートとビバップの美しき結婚ともいうべき、楽しいオリジナルですが、このあたりのムードこそが、如何にもウエストコーストジャズの真髄かもしれません。
シェリー・マンとレッド・ミッチェルは唯一無二のコンビネーションで、実に爽快! バーニー・ケッセルのギターはアンサンブルでの大活躍がアドリブパート以上の素晴らしさだと思いますし、とかにくメンバー全員の意思統一が見事!
ということで、短めの演奏ばかりですが、密度の濃さは天下逸品でしょう。
おそらくはEPやSPとしてジュークボックスでも使われたと推察しておりますが、実際、ここで聞かれる演奏が当時のホールやクラブ、ラウンジで流れてきたら、気分は完全にアメリカングラフティの前夜祭♪♪~♪ 白人が大いに威張りちらしながら、文化をリードしていた強いアメリカって、こういうものだったのかもしれません。
しかし基本のジャズは明らかに黒人色を否定しておらず、それはここでも顕著ですし、バーニー・ケッセル以下のメンバーが、それを強く意識していればこその名演集だと思います。