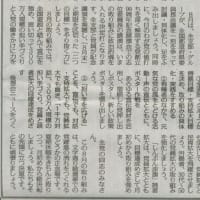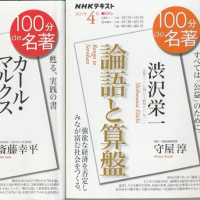東京でさえも侵略戦争の責任を曖昧にするようでは!
侵略戦争の責任と反省と憲法を活かすは切り離せない!
以下の東京新聞の社説は、産経とは違って、支持・共感する人は多いでしょう。しかし、愛国者の邪論は、微妙なところで、「反日」論に屈しているというか、戦争責任について、曖昧な東京新聞の立ち位置について、検証しておくことが必要不可欠だと思います。それは、このような視点が、憲法を活かす日本国になりきれない大きな障害になっていると思うからです。そこで、以下の視点を明らかにしておくことが必要不可欠だということで記事にすることにしました。ご覧ください。まず、以下の展開です。
1.戦争の「過去」をめぐる欧州と東アジアの事情は違う。ドイツはナチスによる侵略と大虐殺の事実を認め、欧州は共通の歴史認識づくりに大きな成果を挙げてきた。
2.これに対し、日中韓の間では歴史認識での隔たりは極めて大きい。
3.しかし、その中で、戦後五十年の村山富市首相談話で表明した「植民地支配と侵略」に対する反省とお詫(わ)びは、日本外交の基盤である歴史認識の根幹となってきた。
4.戦後七十年談話でも、これを曲げることなく明確に表明し、周辺国の理解を得た上で、歴史認識の溝を埋めていきたい。(引用ここまで)
「ドイツはナチスによる侵略と大虐殺の事実を認め、欧州は共通の歴史認識づくりに大きな成果を挙げてきた」という視点をどのように使うか。
東京は、この文章を「日本」にはあてはめず、「日中韓の間では」と話を飛躍させていくのです。愛国者の邪論なりに使えば、
「日本は天皇主権の政府による侵略と大虐殺の事実を認め、日中韓=東アジアは共通の歴史認識づくりに大きな成果を挙げてきた」となるべきです。しかも、
「日中韓の間では歴史認識での隔たりは極めて大きい」と、その責任が曖昧です。あたかも被害国にも責任があるかのような書き方です。
更に言えば、「しかし、その中で、戦後五十年の村山富市首相談話で表明した『植民地支配と侵略』に対する反省とお詫びは、日本外交の基盤である歴史認識の根幹となってきた」とありますが、「反省とお詫び」をしなければならない「植民地主義と侵略」の「原因と責任」は曖昧です。まるで「一億総懺悔」論の焼き直しです。
こうした視点が、一部政治家など、侵略戦争を正当化しようとしている勢力に対する「おもねり」「忖度」「逃げ腰」であると言われても仕方がないことは一目瞭然です。「反日」と言われるのが、怖いのでしょうか。
日本国憲法は「植民地支配と侵略」を反省したからこそ、天皇主権から国民主権に転換したのです。これは決定的なことです。この主権の在り様の大転換に立った憲法を使うかどうか、このことこそが、「植民地支配と侵略」の「原因と責任」「反省とお詫び」を具体的に果たすことになるのです。これは自国内のことだけではなく、国際公約です。
事実、いわゆる村山談話や小泉談話が発表されても、憲法9条を形骸化する策略は推進されてきました。国際法に違反したアフガン・イラク戦争を起こしたアメリカを支援してきたからです。国民の反論があったから、ギリギリのところで、既成事実化を謀ってきたことはその時強行された法律を視れば明らかです。それが、今日の集団的自衛権行使容認の閣議決定とそれに基づく安保法制議論になっていることは否定できないはずです。
同時に「植民地支配と侵略」の加害の事実を語り、教えることを「自虐史観」「反日」として煽る、いわゆる「自由主義史観」なる勢力が跋扈し、国際的には容認できないヘイトスピーチをまくし立てる勢力が跋扈してきたこと、これらの「思潮」「風潮」が戦争の加害の事実を「風化」させ、そのことを利用して憲法擁護の運動の様々な取り組みが「政治的」として黙殺される事態が創りだされてきたことを東京は知らないはずはありません。
また、こうした動きを背景にして、今自民党が侵略戦争の反省の上に制定された憲法を改悪しようとしているのです。これは否定できないはずです。
東京の視点が、こうした憲法改悪勢力の諸事実を受けたものであることは「日本の周辺国にも寛容さや自制を促したのは注目される」というメルケル首相の言葉を使って、被害国にも「歴史認識での隔たり」の責任を負わせていることに象徴的です。
こうした視点が、「ASEANの活用はEUに学ぶ点が多い」論になるのです。これは憲法9条の理念をより発展させようとして悪戦苦闘しているアセアンの努力を理解していないと言わざるを得ません。事実、アセアンの取り組みは、ほとんど国民には紹介していないのです。あるのは「中国脅威」論だけです。
こうした視点では、安倍首相の思う壺です。メルケル首相は、憲法9条を使った外交政策を求めてはいないのです。安倍首相の「地球儀を俯瞰する積極的平和主義」を評価しているのです。ただし、その場合は戦争責任問題で「けじめ」をつけていないと、ドイツのようにはできませんよ!と言っているだけなのです。その「ドイツのように」という条件がどのようなものか、そこが最大のポイントです。
「戦争放棄条約」締結を/インドネシア外相が提案/米中含め義務付け 2013年5月18日 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-05-18/2013051807_01_1.html
日米中含む戦争放棄条約を/インドネシア大統領が呼びかけ2013年12月14日 9時39分http://news.livedoor.com/article/detail/8347246/
アセアンの不戦条約を黙殺して対立を煽ったマスコミ!憲法を活かすの形骸化に加担! 2014-08-14 08:48:49 | 憲法を暮らしに活かすhttp://blog.goo.ne.jp/aikokusyanozyaron/e/05c46333e4f0862d9bc3442bc0ea95a1
しかも、東京の視点には、違法な戦争に加担してきたEUを美化し免罪する視点が含まれているのです。
このことは日米軍事同盟を容認する東京が陥っている「軍事抑止力」論があります。侵略戦争の責任と反省という立場に夏のであれば、「軍事抑止力」論=「武力による威嚇」と決別して「非軍事抑止力」論を土台としている憲法9条を徹底化していこうと言う立場に立たなければなりません。この視点に立てない最大の弱点、安倍派の口実を徹底して批判できない最大の欠点が、この社説に見られるのです。
このことが、戦争は二度と起こしてはならない、戦争はしたくないという国民感情に、「非軍事」でも紛争は解決できるという確信を与えられないでいるのです。このことは世論調査に出てくる国民世論を視れば一目瞭然です。ここにこのような視点が国民に大きな影響を与えていることが判ります。
だから、今必要なことは、中国によって「東シナ海、南シナ海における海上通商路の安全が海洋領有権をめぐる紛争によって脅かされている」現実に対して、「東南アジア諸国連合(ASEAN)の活用」と言うのであれば、このアセアンの取り組みが、あの国際法に違反して、また日米軍事同盟を使ったベトナム戦争の惨禍を踏まえて行われていることを再度確認することです。
そのためには、戦争放棄条約などを含めた非軍事的手段による解決と歴史問題についての各国の共通認識の構築、領土紛争を武力で解決することの無意味さと経済的損失の大きさを明らかにすることです。この討論の枠組みに中国を巻き込むことです。
更に言えば、こうした討論を行うことの方が中国国民の暮らしが改善されていくのだということを確認しながら、この平和的解決の方が中国の国内政治の安定化になることを、各国が知恵を出して説得することです。
このような取り組みの重要な位置にいるのが侵略戦争の反省の上に制定された憲法平和主義を戴く日本であること、しかも経済的に密接な関係を維持してきている日本の果たす役割が大きいことは明らかです。「対中脅威」論の思考回路で思考が停止している状況を憲法9条を使って打ち破っていくという視点が今ほど求められている時はないのです。
では以下、社説をご覧ください。
中日/東京新聞 メルケル独首相/語られた二つの反省 2015/3/12 10:00
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015031202000137.html
ドイツのメルケル首相が七年ぶりに来日した。大戦後の廃虚から経済大国となった日独両国。過去と向き合ったドイツを受け入れ、平和を築いた欧州の歩みを、戦後七十年を考える参考としたい。
ドイツは欧州連合(EU)の一員として、近隣諸国との強い信頼関係を築いている。これに対し、日本と中国、韓国との間には不協和音が目立っている。
メルケル首相は来日講演で、近隣諸国との関係について「ナチスの時代があったにもかかわらず、ドイツは国際社会に受け入れてもらえた。過去ときちんと向き合ったからだ」と説明した。
戦争の「過去」をめぐる欧州と東アジアの事情は違う。ドイツはナチスによる侵略と大虐殺の事実を認め、欧州は共通の歴史認識づくりに大きな成果を挙げてきた。これに対し、日中韓の間では歴史認識での隔たりは極めて大きい。しかし、その中で、戦後五十年の村山富市首相談話で表明した「植民地支配と侵略」に対する反省とお詫(わ)びは、日本外交の基盤である歴史認識の根幹となってきた。戦後七十年談話でも、これを曲げることなく明確に表明し、周辺国の理解を得た上で、歴史認識の溝を埋めていきたい。
メルケル首相はまた「独仏の和解はフランスの寛容な振る舞いがなかったら、可能ではなかった」と述べた。「東シナ海、南シナ海における海上通商路の安全が海洋領有権をめぐる紛争によって脅かされている」とも発言して中国をけん制、解決のため、二国間対話のほか、東南アジア諸国連合(ASEAN)の活用を呼び掛けた。日本の周辺国にも寛容さや自制を促したのは注目される。ASEANの活用はEUに学ぶ点が多い。
ドイツの脱原発政策への転換については「核の平和利用には賛成してきたが、福島の原発事故で考えを変えた。日本という高度な技術水準を持つ国でも事故が起きることを如実に示した。想定外のリスクがあることが分かった」と、事故の衝撃の大きさが引き金となったことをあらためて強調した。
安倍晋三首相は首脳会談後の会見で、原発再稼働を進める方針を重ねて明言した。しかし、最近でも、福島第一原発の汚染水の外海流出が明らかになるなど、メルケル首相が指摘する想定外の「リスク」は何ら解消されていない。ドイツが福島の事故を教訓としたように、日本もドイツの決断の意味を、いま一度しっかりと考えたい。(引用ここまで)