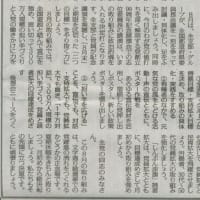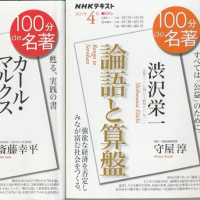児童相談所の実態と改善方向=第三者的論評に
無責任体制が浮き彫り!
何故第三者的になるか!
根底には
子どもの現状に対する
危機感と人権尊重主義への軽視がある!
安倍自公政権に対する追及の甘さがある!
一般的なことを書いてお茶を濁すな!
児相の負担軽減は喫緊の課題である。
虐待数の増加に加え、複雑で深刻な事案が多くなっているからだ。
虐待の防止や解消に向けてきめ細かく対応するためには専門職の増員や対応力の向上が求められる
行政だけでなく学校や地域など総力を挙げて根絶に取り組みたい
ただ対策全体としては、児相の負担が重過ぎるのではないか。
児相に加え市区町村や警察、学校、医療機関などの役割を明確にし、その上で連携して対処する仕組みが必要だ。
社会の総力を挙げて取り組まなければ現状の打開にはつながらない
児相の担当者任せでなく、事案ごとに関係機関が迅速に協議し、それぞれ責任を持ってどう動くかをはっきりさせるシステムの整備が不可欠だ。
児相はすでに「パンク寸前」と言われる。
児相の負担軽減は喫緊の課題である。
虐待数の増加に加え、複雑で深刻な事案が多くなっているからだ。
児相の負担軽減も急務だ。
だが、職場環境は過酷であり、人材確保は容易ではない。
専門知識を持つ職員の育成に、国も支援を強化させる必要がある。
市町村の体制強化にも踏み込んだ。責任の所在があいまいにならないよう、児相と市町村の明確な役割分担を進めてほしい。
しかし、多くの課題が山積みになっている。職場環境の過酷さは広く知られており、どう人材を確保していくか、詰めを急がなければならない。
さらに一時保護といった「強制措置」と家族の「支援」を児相が一手に担う仕組みに限界が指摘されるようになり、市区町村との役割分担を徹底するなど抜本的見直しが求められている。
福島民友 児童虐待/根絶へ兆し見逃さぬ体制を 8/21 10:05
http://www.minyu-net.com/shasetsu/shasetsu/FM20160821-102454.php
言葉による脅しや無視などの「心理的虐待」が急増し、半数近くを占めた。子どもの前で配偶者らに暴力を振るう「面前DV(ドメスティック・バイオレンス)」を心理的虐待と捉え、児相に警察が通告する事案が増えているという。子どもに危害を加える「身体的虐待」と、育児を放棄する「ネグレクト」がそれぞれ約25%あり、「性的虐待」が続いた。
専門家によると、子どもが面前DVに接した場合、トラウマを持つようになったり、性格が暴力的になったりする可能性があるという。虐待といえば、子どもが親らから直接、暴力を振るわれることを想起しがちだが、面前DVへの対応という新たな課題が突き付けられている。
増え続ける児童虐待に対応するためには、一層の相談体制の充実が求められる。特に、児相での養育相談や家庭環境の調査などを行う児童福祉司ら専門職の十分な確保が急務だ。
県内では現在、4児相に児童福祉司が41人配置されている。東日本大震災前の2010年度よりは9人増えたが、虐待の件数も震災前の約2.3倍に増えており、児童福祉司1人当たりの負担は確実に重くなっている。虐待の防止や解消に向けてきめ細かく対応するためには専門職の増員や対応力の向上が求められる。
ことし5月には、児童福祉法と児童虐待防止法が改正され、来年度から各市町村にも児童虐待に関する専門職の配置が義務付けられることになった。市町村と児相が連携して虐待の"芽"を初期の段階で摘み取ることが重要だ。
虐待を未然に防ぐための方策にも力を入れたい。県は今年から検診で産科を訪れた妊婦に、子育てへの不安や悩みなどを聞くアンケートを行っている。虐待につながるような兆しがあった際は、関係機関や市町村と情報を共有し、保健師を家庭に派遣して相談に応じるなど的確な対応を取るよう望みたい。虐待を巡っては、近所の目配りが早期対応につながり、子どもが救われるケースもあった。行政だけでなく学校や地域など総力を挙げて根絶に取り組みたい。(引用ここまで)
昨年度、児相が相談や通告を受けて対応した子どもへの虐待は過去最多の約10万3千件に上った。5年ほどの間に2倍近くに急増した。増加の要因として、社会に児童虐待に関する認識が広がり、通報が増えていることや、地域で家庭が孤立しがちな時代状況、貧困から保護者が受ける育児ストレスなどが挙げられる。
内容別では、子どもへの暴言や、他の家族に対する暴力などによる心理的虐待が最も多く、全体の半数近くを占めた。身体的虐待、育児放棄と続く。この数年、心中を除く虐待死は年に30〜50件程度起きている。各地で子どもが所在不明になっている問題も、虐待との関連が懸念される。保護者らと向き合い、子どもの安全確保から心のケアや自立支援まで担う児相職員には重圧がかかる。多数の事案を扱い、難問にも直面する。このため厚労省は児相で働く児童福祉司の増員やベテラン職員の配置などの対策を決めた。しかし課題はなお山積している。例えば、相模原市の中学生が養父から暴力を振るわれ、保護を求めながら自殺に追い込まれた事案の検証では、児相内部の情報共有の不十分さが指摘された。市の担当部門と児相や学校などの検討会議が開かれず、事態の緊急性が認識できなかったことも報告され、虐待対応に共通する弱点が浮かんだ。
児相の担当者任せでなく、事案ごとに関係機関が迅速に協議し、それぞれ責任を持ってどう動くかをはっきりさせるシステムの整備が不可欠だ。
もう一つ重要なのは、さまざまな事情で育児に悩む保護者が、子育て放棄や子どもへの暴行などへ追い詰められないよう、どう支えるかだろう。各地で育児体験を語り合うサークル活動、助産師や保健師への相談などの試みが行われている。妊娠から子育てまで続く悩みを保護者に抱え込ませないため、粘り強い支援が欠かせない。(引用ここまで)
増加の一途をたどる児童虐待には、早期発見と迅速な対応が欠かせないが、児相はすでに「パンク寸前」と言われる。
国は5月、児相の体制と権限などを強化する児童福祉法と児童虐待防止法の改正を行った。
虐待は子どもの命を危機にさらし、心にも大きな傷を負わせる。子どもを守ることを最優先に、児相を中心に学校、警察、自治体などが協力して対応を強化していかなければならない。
増加の要因の一つは、昨年7月から、相談を24時間受け付ける全国共通ダイヤル「189」の運用が始まったことだ。15年度に児相が受けた電話は、前年度比2.9倍の2万9000件に上った。
社会的な関心の高まりは、子どもを見守る目を増やすことにつながり、歓迎できる。一方で、児相の負担軽減は喫緊の課題である。虐待数の増加に加え、複雑で深刻な事案が多くなっているからだ。
5月の関連法改正で、児童心理司や、同僚らの指導・教育も担当するベテラン児童福祉司の配置が義務化された。子どもの安全を確認するために、強制的に家庭に立ち入る「臨検」の手続きも簡略化した。だが、職場環境は過酷であり、人材確保は容易ではない。専門知識を持つ職員の育成に、国も支援を強化させる必要がある。
虐待を受けている子どもの一時保護などの「強制措置」と、家族の「支援」を児相が一手に担う仕組みにも限界が指摘されている。
欧米では裁判所が保護を命令するが、日本では児相所長の権限となっている。「一行政機関の判断でしかなく、親との間でもめ事が起こりやすい」という声もある。
相模原市では、児相に保護を求めた中学2年の男子生徒が自殺した。児相側が保護者の言い分に重きを置いたことなどから、最悪の事態を招いてしまった事例であり、反省すべき点は多い。
厚生労働省の有識者検討会では、家庭裁判所が一時保護の必要性を審査する制度の導入も検討されている。家族の「支援」は市区町村が担うなど、役割分担の見直しも求められよう。それぞれの機能を整理し、実効性のある連携システムの構築が急がれる。(引用ここまで)
http://www.kobe-np.co.jp/column/shasetsu/201608/0009385879.shtml
言葉による脅しや無視などの「心理的虐待」が急増し、半数近くを占める。子どもの前で配偶者らに暴力をふるう「面前DV」を心理的虐待と捉え、警察が通告する事案が増えているという。24時間相談を受け付ける全国共通ダイヤル「189」への電話は、前年度の3倍に上った。
相談の経路は警察の通告が最多だが、近隣住民や知人、学校もある。子どもを守るため、虐待の兆しに敏感な社会でありたい。
国も、増加する児童虐待への対策強化に乗り出した。5月に成立した改正児童福祉法と改正児童虐待防止法は、経験豊かなベテランの児童福祉司や専門知識を持つ弁護士の配置を児相に義務づけ、強制的に家庭に立ち入る手続きを簡略化する。児相の体制と権限を拡充する内容だ。
相談件数は15年間で6倍以上に急増したが、支援などを担当する児童福祉司の数は約2倍にとどまる。国は児童心理司や保健師を含む専門職を19年度までに15年度の26%増の5430人程度に増員するという。だが過酷な職場環境などが指摘される中、人材をどう確保するのか。国は具体的な方策を示す必要がある。
児相はこれまで、親と対立してでも子どもを保護する一方、親と関係を築きながら親子関係の改善を支援するという矛盾した役割を求められてきた。児相の負担軽減も急務だ。
今回の法改正では、専門職の配置や児相から事案を引き継ぐなど、市町村の体制強化にも踏み込んだ。責任の所在があいまいにならないよう、児相と市町村の明確な役割分担を進めてほしい。
相模原市では、親の虐待を受けて児相に保護を求めていた中学2年生の男子生徒が自殺した。市がまとめた報告書は、保護者の言い分に偏った支援であったことや、児相内の情報共有の不十分さを指摘した。
何よりも優先すべきは、虐待を受けている子どもの保護である。端緒をつかみながら防げなかった悲劇の教訓を生かさなければならない。(引用ここまで)
http://ibarakinews.jp/hp/hpdetail.php?elem=ronsetu
児相は「パンク寸前」といわれる中、国は5月に児童福祉法と児童虐待防止法を改正。同僚らの指導・教育を担当するベテラン児童福祉司をはじめ、児童心理司や医師、弁護士の配置を義務化するなど児相の体制強化を進める。子どもの安全を確認するため強制的に家庭に立ち入る「臨検」の手続きも簡略化した。
しかし、多くの課題が山積みになっている。職場環境の過酷さは広く知られており、どう人材を確保していくか、詰めを急がなければならない。さらに一時保護といった「強制措置」と家族の「支援」を児相が一手に担う仕組みに限界が指摘されるようになり、市区町村との役割分担を徹底するなど抜本的見直しが求められている。
そんな折、相模原市の事例が波紋を広げている。養父の暴力を訴え、児相に保護を求めた中学2年の男子生徒が自殺を図り、死亡したことが明らかになり、児相の対応が厳しく問われた。市は今月、保護者の言い分に偏った支援になり、児相内の情報共有も不十分だったとする報告書をまとめ、厚労省に提出した。生徒は小学6年だった2013年に学校で養父の暴力を打ち明け「家に帰るのが怖い」と訴えた。連絡を受けた市は児相に通告し一時保護も含めた対応を提案したが、児相はそこまでの緊急性はないと判断。翌年には児相で通所の親子面接があり、生徒は施設で暮らすことを望んだという。
しかし児相側は「親子関係に苦労している」という養父の言い分に重きを置き、生徒の訴えが児相内で共有されることもなかった。生徒はその年11月に自殺を図り、入院。意識が戻らないまま今年2月に亡くなった。
保護を巡り、厚労省は判断基準に「子ども自身が保護・救済を求めている」を挙げ、これまで「保護者の反発を恐れて控えるのは誤り」とする通知を出している。だが現場では、親の意向に反し保護に踏み切った場合に、その後の支援が円滑に進まないことから、保護をためらうことも少なくないといわれている。加えて、相模原の事例では担当した児童福祉司の経験の浅さや、当時1人で90例も抱えていたという負担の大きさも指摘され、さまざまな問題点が浮き彫りになった。
こうした状況を踏まえ、例えば、児相の役割のうち支援などソフトな部分は市区町村が中心になり担うという案が提案されている。また厚労省有識者検討会で検討されている一時保護への「司法関与」の強化も、役割分担の一環といえる。これらも含め、安全網からこぼれ落ちる事例を一つでも少なくするために対応を急いでもらいたい。(引用ここまで)
http://www.sanin-chuo.co.jp/column/modules/news/article.php?storyid=560729033
児相は「パンク寸前」といわれる中、国は5月に児童福祉法と児童虐待防止法を改正。同僚らの指導・教育を担当するベテラン児童福祉司をはじめ、児童心理司や医師、弁護士の配置を義務化するなど児相の体制強化を進める。子どもの安全を確認するため強制的に家庭に立ち入る「臨検」の手続きも簡略化した。
しかし、なお多くの課題が山積みになっている。職場環境の過酷さは広く知られており、どう人材を確保していくか、詰めを急がなければならない。さらに一時保護といった「強制措置」と家族の「支援」を児相が一手に担う仕組みに限界が指摘されるようになり、市区町村との役割分担を徹底するなど抜本的な見直しが求められている。
厚生労働省の有識者検討会は、家庭裁判所が一時保護の必要性を審査する制度の導入なども検討。子どもを守るために何をすべきか。児相を中心に学校や警察、自治体などの関係機関が連携して知恵を絞り、速やかに施策に反映させていく必要がある。
そんな折、相模原市の事例が波紋を広げた。養父の暴力を訴え、児相に保護を求めた中学2年の男子生徒が自殺を図り、死亡したことが明らかになり、児相の対応が厳しく問われた。市は今月、保護者の言い分に偏った支援になり、児相内の情報共有も不十分だったとする報告書をまとめ、厚労省に提出した。生徒は小学6年だった2013年に学校で養父の暴力を打ち明け「家に帰るのが怖い」と訴えた。連絡を受けた市は児相に通告し一時保護も含めた対応を提案したが、児相は緊急性はないと判断。翌年には児相で通所の親子面接があり、生徒は施設で暮らすことを望んだという。しかし児相側は「親子関係に苦労している」という養父の言い分に重きを置き、生徒の訴えが児相内で共有されることもなかった。生徒はその年11月に自殺を図り、入院。意識が戻らないまま今年2月に亡くなった。
保護を巡り、厚労省は判断基準に「子ども自身が保護・救済を求めている」を挙げ、これまで「保護者の反発を恐れて控えるのは誤り」とする通知を出している。だが現場では、親の意向に反し保護に踏み切った場合に、その後の支援が円滑に進まないことから、保護をためらうことも少なくないといわれている。加えて、相模原の事例では担当した児童福祉司の経験の浅さや、当時1人で90例も抱えていたという負担の大きさも指摘され、さまざまな問題点が浮き彫りになった。
これを受け、児相の役割のうち支援などソフトな部分は市区町村が中心になり担うという案が提案されている。また厚労省有識者検討会で検討されている一時保護への「司法関与」の強化も役割分担の一環となる。安全網からこぼれ落ちる事例を一つでも少なくするために、対応を急がなければならない。 (引用ここまで)
http://www.kanaloco.jp/article/193899