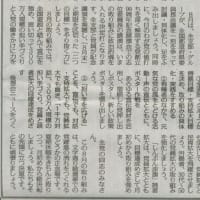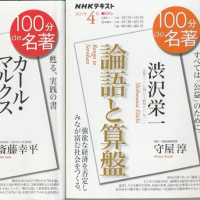これだけの問題が全国津々浦々で起こっているのに
児童虐待・いじめ・自殺・学校内暴力・非行・低学力など
それそれがバラバラに論じられているぞ!
ここに最大の問題がある!
思考回路を繋げていない!
場当たり・その場しのぎのアブハチ取らず!
http://www.saga-s.co.jp/column/ronsetsu/345701
内閣府の2015年版自殺対策白書によると、13年までの過去42年間で、18歳以下の子どもが自殺した日を日付別に調べたところ、9月1日が131人と突出して多く、9月2日94人、8月31日92人と続く。春休みと夏休み明けに顕著で、特に8月下旬からは連日50人を超えており、夏休みの終わりに危機に直面している子どもが多いことが分かる。
なぜ自殺してしまうのか。白書によると、小学生の自殺の原因・動機は「家族からのしつけ・叱責(しっせき)」「親子関係の不和」など家庭生活に起因するものが多い。中学生は「学業不振」や「学校の友達との不和」、高校生では「学業不振」「進路」「うつ病」が挙がる。また白書は、長期の休み明け直後は、「大きなプレッシャーや精神的動揺が生じやすい」と指摘している。
自殺を理解するには「準備状態」と「直接の契機」の関係を知る必要がある。さまざまな問題を抱え、時間の経過とともに蓄積していく自殺の「準備状態」と、自殺の引き金になる「直接の契機」。直接の契機は、ごくささいなものである場合が多く、夏休みの終了が契機となり、自殺してしまうこともある。
一方で、子どもの自殺は遺書などが少なく、予兆が見えにくいのが特徴という。「親の前では普通に明るかった」「学校では元気だった」という事後の証言も少なくない。また、不安や悩みを抱えても、親や教師に話したがらない傾向もある。それでも「なんらかの予兆はある」と、佐賀県精神保健福祉センターの相談員。「やる気が出ない」「イライラしている」「体の不調を訴える」など、身近な人が「いつもと違う」と感じたら、子どもに寄り添って、子どもの声に耳を傾けることが大切という。もし変化に気付いた時は、保護者だけで抱え込まず、同センターなど専門機関への相談を勧めている。
また、子どもたちに対しては「1人で悩んでいないで周りの人に相談してほしい。もし、打ち明けにくかったら、電話相談してほしい」と話す。
今年4月に施行された改正自殺対策基本法は、子どもの自殺対策に力を入れ、学校現場に自殺予防教育の強化を求めている。保護者や地域住民と連携し、児童や生徒の心の健康を保つ教育や、啓発を行う努力をすることなどを盛り込んだ。いじめや悩みを1人で抱え込まないよう「SOSの出し方」なども教え、子ども自身が問題を解決する力を育むよう促している。
夏休み明けのクライシス(危機)対策として、まずは、起床や就寝、食事の時間をきちんと決めて十分な睡眠を取り、規則正しい生活を送ることから始めたい。その上で、子どもの様子をしっかり見守り、万が一のことがないようにしたい。(田栗祐司)(引用ここまで)
http://www.ehime-np.co.jp/rensai/shasetsu/ren017201607196552.html
防止法は付則で施行後3年をめどに現場の状況を踏まえ、法改正を含めた「必要な措置を講じる」と明記している。国の協議会で見直し議論が始まった。法が機能していない現実を重く受け止め、徹底検証して改善を急がなければならない。
防止法は2011年に大津市の中2男子が自殺したのをきっかけに制定。柱として、各学校に防止対策基本方針の策定と対策組織の設置を義務付けた。今年3月までに全小中高校が方針の策定を終えたが、内容にはばらつきがあり、自治体が示した基本方針をひな型に文言を踏襲しただけの学校も少なくない。
弁護士やジャーナリストらで構成するNPO法人「ストップいじめ!ナビ」の全国主要自治体基本方針調査によると、カウンセラーなど外部の専門家や一般の教員も参画すべき校内の対策組織の多くが、従来通り校長や生徒指導担当者で構成されている。松山市の方針に関しては校外講師による学習会や子ども主体の意見交換への支援など啓発施策を高く評価した一方で、教職員間の情報共有体制や、外部専門家の校内組織参入の義務付けが示されていないことを指摘し、改善を促している。
学校内外の風通しを良くし、担任の「抱え込み」を防ぐために組織の見直しが不可欠だ。ただ、形を整えても実効性が伴わなくては意味がない。昨年の岩手県矢巾町の中2男子自殺では学校で基本方針を定めていたが校長が把握しておらず、生徒がいじめを繰り返し訴えても担任以外に伝わっていなかった。方針策定にとどまらず、実行の義務化や運用状況をチェックする仕組みづくりも求めたい。
法はまた、心身に重大な被害を受けたり、長期欠席を余儀なくされたりした場合を「重大事態」と定義。学校に文部科学省や自治体への報告や調査組織の設置、被害者側への情報提供を義務付けた。だが、学校ごとのいじめへの認識には差がある。
矢巾町の事件は「トラブル」と見なされ、いじめと認知されていなかった。重く見た文科省が全国の小中高校に14年度のいじめ認知件数調査のやり直しを指示。その結果、報告が当初よりいきなり約3万件増え、18万8千件を超えた。だが、その後も認知されないまま自殺につながる事件が起きている。「いじめゼロ」を良しとするあまり、実態から目を背ける傾向も依然残っていることを危惧する。
いじめはどこでも起こり得ると社会全体で意識し、余裕ある教職員配置や相談窓口の充実、相手を尊重する教育を進めることが重要だ。児童生徒を守るために防止法を見直すとともに、形骸化しないよう、きめ細かな日々の取り組みによって法に魂を入れ続けなければならない。(引用ここまで)
小学校の校内暴力件数が過去最高の1万605件!
対応に問題はないか?
Posted:09/17/2015 06:36 am|Updated:09/17/2015 06:36 am

shutterstock
2年連続の1万件超え
文部科学省の発表によると、小学校内で起きた暴力行為の発生件数が過去最高を更新したことが分かった。
平成26年度に学校内で発生した暴力行為の件数は次の通り。
小学校:1万605件(前年比+527件)
中学校:3万2986件(同-3883件)
高等学校:6392件(同-888件)
調査方法が変わったこともあり、一概に言えないものの、高校内での暴力行為は、平成19年度(9603件)をピークに減る傾向にある。中学校内では、まだまだ多いものの、平成21年度(3万9382件)から減少傾向にありそうだ。

文部科学省
小学校の調査を開始した平成9年以降の推移を見ると、当初1000件台だったのが、平成17年度には2018件、平成20年度はは5996件、平成24年度はは7542件と増加ペースがアップ。
平成25度に1万78件と、初めて1万件を突破すると、26年度と合わせて、2年連続で1万件を超えた。
また学校外においても、高校生や中学生の暴力行為発生件数は減少しているものの、小学生による件数は増えつつある。
小学校の対応は指導や相談が大半
加害児童への対応では、小・中・高で大きく分かれている。
高校で多いのは、退学・停学・転学などの対応だ。中学校では、そうした措置はグッと少なくなる。出席停止も、暴力行為の件数ほど多くない。多いのは警察の補導、家庭裁判所の保護措置、保護観察など、学校以外の機関の対応だ。
小学校で多いのは、担任を始めとした教職員、養護教諭などの指導や、スクールカウンセラーによる相談などだ。
もちろん中学校や高校でも、暴力行為の件数に比例した形で、教職員等による対応がある。
しかしながら小学校では退学・停学・転学などや、警察の補導、家庭裁判所の保護措置、保護観察などがごく少ないことから、言うなれば「緩め」の対応に留まっている様子が伺える。
現在の対応で十分か
資料では、加害児童の学年をグラフにしてある。

文部科学省
中学生が多いのは一目瞭然だが、これまでの傾向から今後を推測すると、小学校高学年あたりが、もっと増えそうだ。
そもそも厚生労働省の人口統計などで明らかなように、年少人口は減っている。にもかかわらず小学生の暴力行為が増えているのは、どこに原因があるのか。
……などと考えている間にも、被害者は出ているはずだ。さて現在の対応で十分なのだろうか。