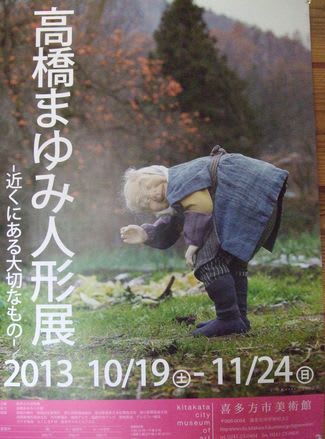2013年11月18日(月)晴 9.5℃~1.8℃
街道観光って何? 人間の交流手段であり、またその場である「街道を歩き、その交流の原点に触れると共に、沿道の景観・町並みや街道周辺に形成された文化の事蹟を訪ねる琴などによって人的交流を図る観光」:須田寛著「観光」より。
このモニターツアーは“観光再生と現在の地域情勢との観点から・・・
野岩羽鉄道構想は潰えたが、その構想は陸路の国道121号大峠道路、そして地域高規格道路『会津縦貫道』として新しい形で実現しようとしている。交流人口の拡大は会津地域の緊急課題であり、会津全域の自治体や商工会議所など経済団体が地域振興の為その早期整備実現を永年要望活動している。
昨年度は会津ー日光での連携を模索したが、さらに歴史的側面で結ばれる米沢へと縦軸をつなぎ、街道観光の観点で地域間連携を拡大。世界文化遺産・日光から北へ向かうルートを充実させ、外国人客を受け入れる拠点でもある会津若松市の魅力増加に資する。
商工会議所のこのような取り組みが会津若松の観光の起爆剤になり発展につながればと願っている。このモニターツアーの条件としてアンケート提出があったので積極的に賛同する意思表示をして記入した。何しろ前回も書きましたが米沢牛のステーキのうまさは最高でしたから・・・・・・(笑 笑 笑)

ステーキをビールを飲みながら5切れも食べてしまった写真です。写真を撮る前につい食べてしまったのでこんな肉の少ない写真になってしまいました。
街道観光って何? 人間の交流手段であり、またその場である「街道を歩き、その交流の原点に触れると共に、沿道の景観・町並みや街道周辺に形成された文化の事蹟を訪ねる琴などによって人的交流を図る観光」:須田寛著「観光」より。
このモニターツアーは“観光再生と現在の地域情勢との観点から・・・
野岩羽鉄道構想は潰えたが、その構想は陸路の国道121号大峠道路、そして地域高規格道路『会津縦貫道』として新しい形で実現しようとしている。交流人口の拡大は会津地域の緊急課題であり、会津全域の自治体や商工会議所など経済団体が地域振興の為その早期整備実現を永年要望活動している。
昨年度は会津ー日光での連携を模索したが、さらに歴史的側面で結ばれる米沢へと縦軸をつなぎ、街道観光の観点で地域間連携を拡大。世界文化遺産・日光から北へ向かうルートを充実させ、外国人客を受け入れる拠点でもある会津若松市の魅力増加に資する。
商工会議所のこのような取り組みが会津若松の観光の起爆剤になり発展につながればと願っている。このモニターツアーの条件としてアンケート提出があったので積極的に賛同する意思表示をして記入した。何しろ前回も書きましたが米沢牛のステーキのうまさは最高でしたから・・・・・・(笑 笑 笑)

ステーキをビールを飲みながら5切れも食べてしまった写真です。写真を撮る前につい食べてしまったのでこんな肉の少ない写真になってしまいました。