10年ほど前に出会った森博嗣著『すべてがFになる』。
初めて読んだ理系ミステリィに衝撃を受け、この著者の小説にはまってしまった。
理系の思考回路をまったく持ち合わせていないわたしは、
この不思議なタイトルを見てもその意味するところがわからず。
…というか考えもせず、そのままの文字を受け止めていただけだが、
理系オットは、それは15ということだよ、と即答したと思う。
1,2,3 ・・・ 9, A B C D E F
Fは、16進法でいうと15なのだそうだ。
これまた理系次男にこの本のことを教えると、たいそう興味を持ち、
ふたりして森博嗣の本を読み漁った。
著者は、しばらくすると、欲するところの印税をたくさんいただけるようになり(!?)
最初の職業、大学の助教授はその前に辞めていたけれど、
いよいよ小説を書くのも止め、
庭園鉄道や模型飛行機など趣味の世界に生きるというようなことを書かれていたので
寂しいなあと思い、また、何て羨ましいとも思った。
その後、時々新書などで新しい本を出しておられるのに気付いたけれど、
ちょっと難しそうで手に取ることはなかった。
最近、文庫で面白そうなのを見つけ、買ってみた。
『つぼねのカトリーヌ』…日頃思っていることを綴った100のショートエッセイ。

タイトルは著者一流のことば遊びで、
『つぶやきのクリーム』『つぼやきのテリーヌ』とシリーズ化されて3冊目のようだ。
なるほど!と膝を打ちたくなるような珠玉のエッセイ。
ひとつのことを逆から見るとこうなるのかという斬新さと知的ユーモア。
思いついたことを思いついたまま書き飛ばしているようでいて、
たぶん森博嗣の頭脳の中では綿密な計算がされているんだろうな。
森博嗣熱が再燃した瞬間。
ちなみに解説は御茶ノ水女子大学名誉教授の土屋賢二氏。
共著もあるのでふたりはオトモダチだと思うのだけど、
解説の方が本文よりも面白いというウワサも・・・。
そして、『喜嶋先生の静かな世界』。
これは著者の自伝的小説ということだけど、
理系ミステリィの生まれたベースがここにあると納得。
面白いと同時に過ぎ去った青春の切なさがベースに流れていてとても深い。
大学を卒業し、修士、博士と大学院に進み、大学の助手になる主人公。
理系の学部を卒業後、修士課程に進み、
実験やら論文やら国内外の学会出席やら、
それなりに頑張ってきた次男とちょっと重なる。
次男はその後民間企業に就職したわけだけれど、
研究職も次男には合っているんじゃないかなぁと密かに思っていたが、
この本を読むと、大学に残るのがいかに大変かと気づきこれでよかったんだと納得。
この本を離れて暮らす次男のところに持って行った時に、
彼は同じ著者の『科学的とはどういう意味か』という新書を持っていたので交換した。

次男と森博嗣、または、『すべてがFになる』に出てくる犀川先生とは
ちょっと似てるなあと常々思っていて。
例えば、
次男は時報を聞いて腕時計の秒針まできっちりと合わせるのだけど、
『すべてが ~ 』の犀川先生もそうだ。
話すことは無駄な修飾なく理路整然と簡潔にして明快だ。
「歴史なんかは、記憶いているかしていないかの違いでしょ」
などと、以前次男が言っていたのだけど、
『科学的とは ~ 』で森博嗣がまったく同じことを語っているのには、
驚いたと同時に感動もした。
それは理解したということではなく、ただ言葉を記憶しているにすぎない。
数学や物理は、方法であり、そこから発展させるシステムだ。
『科学的とは ~ 』では、
「科学とは他者によって再現できるもの」と繰り返し書いているけれども、
今年最大の日本科学界のミステリィ、STAP細胞論文騒動とリンクして、
なるほどなぁと思った。
そして、自分の実験は常に疑えとも書かれている。
科学者は謙虚であるべきとも。
なぜあのような論文が世に出たか?不思議だ。
この本が書かれたのは2011年(しかも3日間で書いたらしい)。
今年読んだわたしは、
「科学とは他者によって再現できるもの」という一文の意味がとてもよくわかる。
森博嗣は、作家デビューして18年、著作が260冊余り、大変多作だ。
しかも絶版した作品は0。
締切に遅れたこともないそうだ。
あふれ出る旋律を楽譜に書きとめることが追い付かなかった
と言われる天才音楽家モーツァルトのように、
文章が泉のようにこんこんと湧き出すイメージ。
しっかり印税もらっちゃったから、筆を折る…なんてことないように、
どんどん趣味にお金を使って、
文章の泉をいつまでも枯渇させることなく、わたしたちを楽しませてほしい。
わたしもこれから数字にアレルギーを持たず、数字の意味を考えてみたい。
感情をもって判断せずに、
頭の中の交通整理をして合理的、論理的に物事を考えてゆきたい。
と新しい年の訪れを目前にして思うのであります。
次男から、
「お母さんってよくわかってないのに
『これってすごいよね~~!』って言っちゃうタイプでしょ。」と言われないように。
とにかく文系のわたしには目からウロコのような金言にあふれているエッセイたち。
この正月休みに他のエッセイも読みたいと思っている。
初めて読んだ理系ミステリィに衝撃を受け、この著者の小説にはまってしまった。
理系の思考回路をまったく持ち合わせていないわたしは、
この不思議なタイトルを見てもその意味するところがわからず。
…というか考えもせず、そのままの文字を受け止めていただけだが、
理系オットは、それは15ということだよ、と即答したと思う。
1,2,3 ・・・ 9, A B C D E F
Fは、16進法でいうと15なのだそうだ。
これまた理系次男にこの本のことを教えると、たいそう興味を持ち、
ふたりして森博嗣の本を読み漁った。
著者は、しばらくすると、欲するところの印税をたくさんいただけるようになり(!?)
最初の職業、大学の助教授はその前に辞めていたけれど、
いよいよ小説を書くのも止め、
庭園鉄道や模型飛行機など趣味の世界に生きるというようなことを書かれていたので
寂しいなあと思い、また、何て羨ましいとも思った。
その後、時々新書などで新しい本を出しておられるのに気付いたけれど、
ちょっと難しそうで手に取ることはなかった。
最近、文庫で面白そうなのを見つけ、買ってみた。
『つぼねのカトリーヌ』…日頃思っていることを綴った100のショートエッセイ。

タイトルは著者一流のことば遊びで、
『つぶやきのクリーム』『つぼやきのテリーヌ』とシリーズ化されて3冊目のようだ。
なるほど!と膝を打ちたくなるような珠玉のエッセイ。
ひとつのことを逆から見るとこうなるのかという斬新さと知的ユーモア。
思いついたことを思いついたまま書き飛ばしているようでいて、
たぶん森博嗣の頭脳の中では綿密な計算がされているんだろうな。
森博嗣熱が再燃した瞬間。
ちなみに解説は御茶ノ水女子大学名誉教授の土屋賢二氏。
共著もあるのでふたりはオトモダチだと思うのだけど、
解説の方が本文よりも面白いというウワサも・・・。
そして、『喜嶋先生の静かな世界』。
これは著者の自伝的小説ということだけど、
理系ミステリィの生まれたベースがここにあると納得。
面白いと同時に過ぎ去った青春の切なさがベースに流れていてとても深い。
大学を卒業し、修士、博士と大学院に進み、大学の助手になる主人公。
理系の学部を卒業後、修士課程に進み、
実験やら論文やら国内外の学会出席やら、
それなりに頑張ってきた次男とちょっと重なる。
次男はその後民間企業に就職したわけだけれど、
研究職も次男には合っているんじゃないかなぁと密かに思っていたが、
この本を読むと、大学に残るのがいかに大変かと気づきこれでよかったんだと納得。
この本を離れて暮らす次男のところに持って行った時に、
彼は同じ著者の『科学的とはどういう意味か』という新書を持っていたので交換した。

次男と森博嗣、または、『すべてがFになる』に出てくる犀川先生とは
ちょっと似てるなあと常々思っていて。
例えば、
次男は時報を聞いて腕時計の秒針まできっちりと合わせるのだけど、
『すべてが ~ 』の犀川先生もそうだ。
話すことは無駄な修飾なく理路整然と簡潔にして明快だ。
「歴史なんかは、記憶いているかしていないかの違いでしょ」
などと、以前次男が言っていたのだけど、
『科学的とは ~ 』で森博嗣がまったく同じことを語っているのには、
驚いたと同時に感動もした。
それは理解したということではなく、ただ言葉を記憶しているにすぎない。
数学や物理は、方法であり、そこから発展させるシステムだ。
『科学的とは ~ 』では、
「科学とは他者によって再現できるもの」と繰り返し書いているけれども、
今年最大の日本科学界のミステリィ、STAP細胞論文騒動とリンクして、
なるほどなぁと思った。
そして、自分の実験は常に疑えとも書かれている。
科学者は謙虚であるべきとも。
なぜあのような論文が世に出たか?不思議だ。
この本が書かれたのは2011年(しかも3日間で書いたらしい)。
今年読んだわたしは、
「科学とは他者によって再現できるもの」という一文の意味がとてもよくわかる。
森博嗣は、作家デビューして18年、著作が260冊余り、大変多作だ。
しかも絶版した作品は0。
締切に遅れたこともないそうだ。
あふれ出る旋律を楽譜に書きとめることが追い付かなかった
と言われる天才音楽家モーツァルトのように、
文章が泉のようにこんこんと湧き出すイメージ。
しっかり印税もらっちゃったから、筆を折る…なんてことないように、
どんどん趣味にお金を使って、
文章の泉をいつまでも枯渇させることなく、わたしたちを楽しませてほしい。
わたしもこれから数字にアレルギーを持たず、数字の意味を考えてみたい。
感情をもって判断せずに、
頭の中の交通整理をして合理的、論理的に物事を考えてゆきたい。
と新しい年の訪れを目前にして思うのであります。
次男から、
「お母さんってよくわかってないのに
『これってすごいよね~~!』って言っちゃうタイプでしょ。」と言われないように。
とにかく文系のわたしには目からウロコのような金言にあふれているエッセイたち。
この正月休みに他のエッセイも読みたいと思っている。










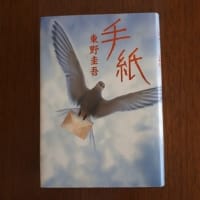









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます