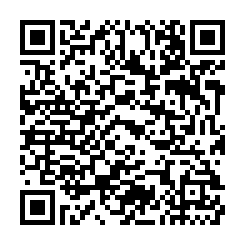ギターを弾けるようになり、独りで弾き語りするようになると、すぐにそれに飽き足らず、バンドを組もうと考えるのがギター少年の常だ。
私も例外ではなかったが、九州の辺境の田舎町では、そんな人材などいなかった。
京都の大学のフォークソング同好会に入って、初めて組んだバンドが、2人組のサイモン&ガーファンクルのコピーバンドだった。
しかしすぐにフォークに飽きて、4人組のロックンロールバンドを組んだ。
ビートルズやキャロルの曲を演奏していた。
それから間が空いて、社会人になった30代の時に3人組のロックバンドを組んだ。
それから、またまた間が空いて、50代の時に、たそがれオヤジーズというなんでもありの3人組のバンドを組んだ。
どのバンドも短命に終わった。
原因は音楽的志向の違いで、メンバーが同じ方向を向いて突っ走ることの難しさを痛感した。
音楽を志す人間は、多かれ少なかれ、オレがオレがの主張が強く、協調性が薄いという事だ。
その点、ローリングストーンズは、50年以上もほぼ同じメンバーでやっている。
生ける伝説のバンドと言われるのも頷ける。
私は今では、ひとりウクレレのワンマンバンドだ。
これでいいのだ。
私も例外ではなかったが、九州の辺境の田舎町では、そんな人材などいなかった。
京都の大学のフォークソング同好会に入って、初めて組んだバンドが、2人組のサイモン&ガーファンクルのコピーバンドだった。
しかしすぐにフォークに飽きて、4人組のロックンロールバンドを組んだ。
ビートルズやキャロルの曲を演奏していた。
それから間が空いて、社会人になった30代の時に3人組のロックバンドを組んだ。
それから、またまた間が空いて、50代の時に、たそがれオヤジーズというなんでもありの3人組のバンドを組んだ。
どのバンドも短命に終わった。
原因は音楽的志向の違いで、メンバーが同じ方向を向いて突っ走ることの難しさを痛感した。
音楽を志す人間は、多かれ少なかれ、オレがオレがの主張が強く、協調性が薄いという事だ。
その点、ローリングストーンズは、50年以上もほぼ同じメンバーでやっている。
生ける伝説のバンドと言われるのも頷ける。
私は今では、ひとりウクレレのワンマンバンドだ。
これでいいのだ。