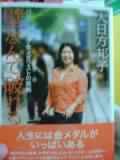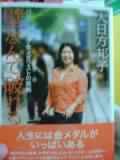
今日は本のご紹介
教えてくれたのは東京のリハビリセンターの義肢装具士さん
さっそく購入して読んでみた
「壁なんて破れる」(パラリンピック金メダリストの挑戦)
NHK出版
大日方邦子
1400円
チェアスキーの金メダリストのNHKディレクターである大日方さんが語るパラリンピックへの思い、障害を持った人の思い、社会へのメッセージ
一人の頑張りやさんの人生を追体験させてもらえたような不思議な気分になった
障害者という視点を抜きにしても、とても考えさせられた
少し本から抜粋してみよう
「小学校入学を「歩けるから」という理由で許可された私は、車いすを使うということは、自分の行動を制限することにしかならない、と思っていた」「義足をつけて、杖も使わずに歩くことこそ、「普通」に暮らすための唯一の方法だと思いこんでいたのだ」
「私にとって車いすは、「自転車」に近い乗り物だといえる」
「街を歩いていて、入りたい店を見つけたとき、入り口に段差があったり、店内の通路が狭かったりすれば、ひょいと車いすを降りてしまうこともある」
「私のような車いすの使い方をする人は少数だろうけれど、「私と同じようにすればもっと楽に動き回れるのになぁ」とついおすすめしたくなる人を街で見かけることは多い」
「障害者の代表にはだれもなれない」「わかった気になってはいけない。押しつけ、思いこみは禁物」「考えてみれば、…他人を思いやる想像力は人と人とがコミュニケーションをとる際の、基本中の基本ではないだろうか」
「障害の意味を、私は「不便を感じること、行動しにくいと感じること」だと思っている」
「私は、なるべく「障害者」といわず、「障害のある…」「障害を持っている…」と表現することにしている」
「ちなみに「障害」があることをポジティブに捉えるときには「持っている」、ありのままの事実として使うときには「ある」という使い分けをしている」
「職場での仕事ぶりを評価されなくて落ち込んでも、家庭で子供から「最高のお父さん」と評価してもらえるならば、それは十分に立派なことではないだろうか」
いやぁ…しっかり読ませていただいた
娘にも読ませてあげたいな
みなさんもどうぞ
 「よーく考えよ~お金は大事だよ~うーうーううぅ~」
「よーく考えよ~お金は大事だよ~うーうーううぅ~」