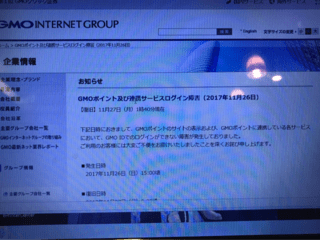民法改正
債権関係の民法が改正大改正されたらしい。
施行は2020年とか。
ニュースになっていたから、備忘録。
なにせ、一応宅地建物取引士なので。
気になります。
ざっと読んだ感じだと、あまり改悪の要素はなさそうに見えるけど。
えてして、そうしたことは密やかに変えられている場合もあるから、注意が必要。
是非、パブリックコメントに有識者の皆さまがたくさんの意見を送っていただけることを願いたい。
賃貸借契約
子供達が独り立ちするときに通る道。
ちょうど上の娘が大学になる頃には、施行後かな。
いつか時間があれば。
そんなことを思いながら。
大切だと思うから備忘録。
皆さまもどうぞ覚えておいてください。
こういうのは、皆が意見しないとろくなことになりませんからね。(^。^)
以下、WEBより抜粋
https://www.homes.co.jp/cont/press/rent/rent_00456/
1896年(明治29年)に制定された民法のうち、債権関係の規定が約120年ぶりに改正された。これまでも細かな見直しはあったが、大幅な改正は初めてのことであり、改正点はおよそ200項目に及ぶ。
当初、民法改正法案が通常国会へ提出されたのは2015年3月31日だが、国民生活への影響も大きいだけに審議は長期化し、可決・成立は2017年5月26日、公布は同年6月2日となった。十分な周知期間を設けるため施行は「公布から3年以内」とされ、2020年になる見込みだ。
それでは、今回の民法改正が住宅などの賃貸借契約にどのような影響を及ぼすのだろうか。その主なポイントを改めて整理しておくことにしよう。
賃貸借契約に関わる改正点は細かな部分まで含めると10項目以上になるが、おさえておきたいのは次の3つである。
□ 敷金および原状回復のルールの明確化
□ 連帯保証人の保護に関するルールの義務化
□ 建物の修繕に関するルールの創設
民法の改正を踏まえて、国土交通省は「賃貸住宅標準契約書」の再改訂を検討している。その案を公開し、2017年7月24日から9月10日までパブリックコメント(意見募集)を実施したところだ。改正法の施行まで3年ほどある段階で検討を始めたのは、それだけ賃貸住宅市場への影響が大きいと考えてのことだろう。
「賃貸住宅標準契約書」は1993年に作成され、反社会的勢力の排除や明渡し時における原状回復内容の明確化などを盛り込んで2012年2月に改訂されている。この雛形(モデル)の使用が法律などで義務付けられているわけではないが、紛争防止の観点から国土交通省が普及に努めているものだ。
この「賃貸住宅標準契約書」を実際に使用するかどうかはともかくとして、賃貸住宅を取扱う不動産会社は契約書の内容を見直し、改正後の民法に沿ったものにすることが欠かせない。とくに連帯保証人の保証限度額を定めることは民法上の強行規定であり、この欄を設けなければ保証契約自体が無効となる。他の項目についても、条件などを明確に記載することが必要になる。