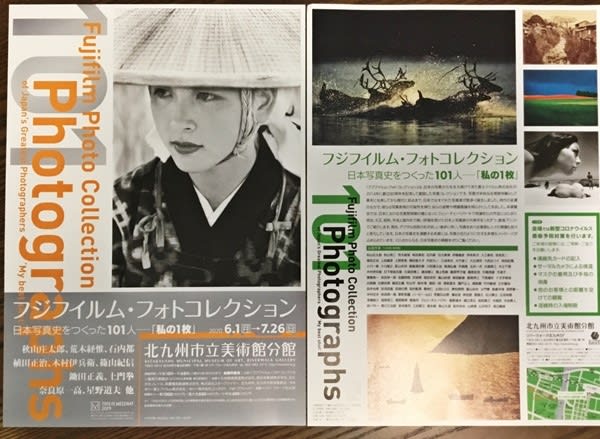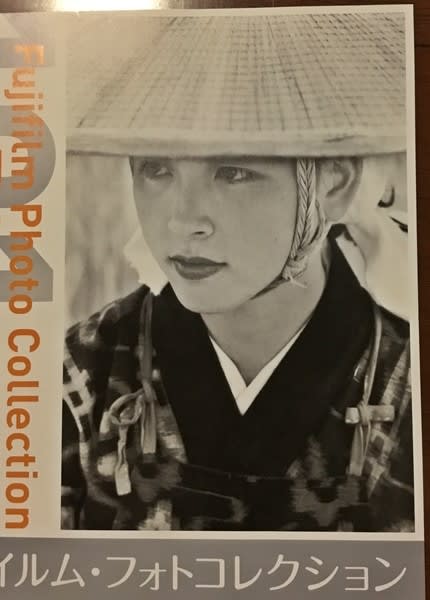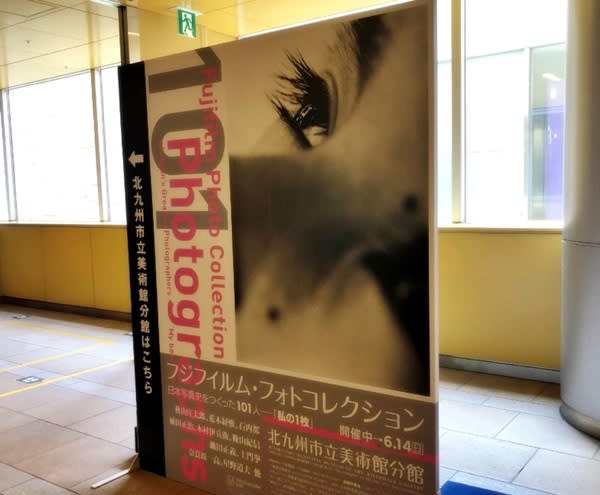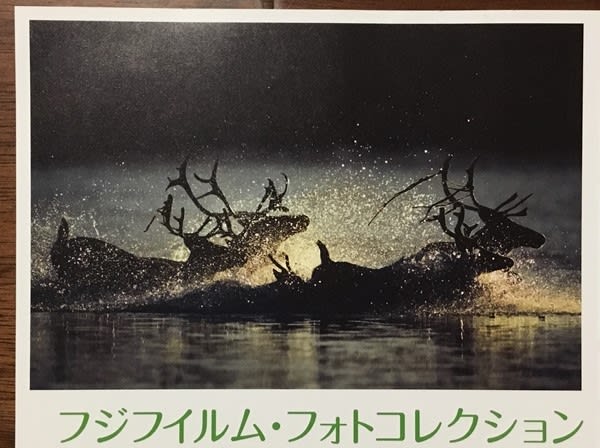ある統計によれば、日本で腰痛に悩んでいる人は2800万人もいるそうです。ということは、日本人の4人に一人は腰痛持ち。もはや国民病と言っても過言ではありませんね。
実は私も、若いころから頑固な腰痛に悩まされてきました。整形外科はもちろん、整骨院やカイロプラクティックなどに通った時期もありましたが、一時的に楽になることはあっても効果は長続きしないんですよね~
それでも、一番しんどかった時期(約20年前)に比べればかなり楽になってきていますので、日常生活は普通に過ごしています。ところが、私の腰は自他ともに認める「ガラスの腰」で、ときどき腰に「ガツン」と衝撃が走ることがあり、一旦そうなってしまうともう身動きがとれません。ただ多くの場合、まったく突然くるのではなく、今にもガツンときそうな気配(=予兆)があります。この一触即発状態のときに不用意に腰に負担をかけようものなら、間違いなく本家本元「ガツン」がきてしまうので本当に気を遣います。
つい先日も、そんな「ガツン」半歩手前の状態になってしまったので、しっかり腰を支え固定するため、取り急ぎ腰用サポーターを購入することに……。試着品をいろいろ試した結果、一番がっしりと腰を支えてくれる「中山式ボディフレーム腰用ハードW(ダブル)」を選びました。

最大20㎝と幅の広いベルト自体で、まず腰まわり全体を固定。さらに、腰に当たる位置に3本(上に2本、下に1本)の補助ベルトがあり、更に腰部をがっしり支える構造となっています。(「サポーター」と書きましたが、メーカーはこの製品を「コルセット」と分類しています)

この補助ベルトをギュッと引くことで締め付け効果を調整します。補助ベルトは、上部が2本になっているのが「ダブル」で、シングルは上下1本ずつ。私は少しでも強力にサポートするためダブルを選びました。やはりこれが正解。過去に使ったことのある腰痛サポーターに比べて、腰を固定し支える機能がずっと強力で安心感が違います=(^.^)=

裏側中央部分に幅広の腰部ボーンが2本。これが腰部が不用意に屈曲するのを抑制してくれるんですね〜
メッシュ素材で通気性も確保されているので、長時間着けていても大丈夫でした。

カミングアウトついでに、膝用サポーターも紹介します (^-^)ゞ
去年の春から初夏にかけて、右膝が痛み始めたのに「そのうち治るだろう」と高をくくって運動を続けていたところ、とうとうある日、膝がパンパンに腫れて歩けないほどの痛みに……。ナメちゃいけませんね。おかげで半年ほど整形外科に通う羽目になりました(◞‸◟)
このサポーターは、スポーツクラブのレッスンを再開できるまでに回復した頃、膝を保護し動きをサポートするために購入したものです(左が表、左は裏返したところ)。膝まわりは思いのほか汗をかくので、洗い替えとして二つ使っています。1年近く使っているので、どちらもくたびれてきました(^^;;

裏側(内側)の丸く分厚いでっぱりで膝関節を固定。更に、両サイドに入っている芯が、膝の屈曲を抑え、延ばすのをサポートしてくれるので、膝の曲げ伸ばしが少し楽になります。エアロやズンバ、ボクシングエクササイズなど、膝に負担がかかる運動では必需品です。

これは、運動するときに足首をガードするためのサポーター。(膝・足首ともに米国3M社のサポーターブランド、FUTURO)
近ごろ時々、捻ったりグキッとした覚えはないのに足首が痛むことがあるので、念のため予防用として使っています。歳とともに足首関節が弱ってきてるんでしょうか……情けない話です(^^;;

見苦しい足で恐縮ですが……、丸い穴の中に踵を入れて、足の甲から足の裏を通し、この後、足首をぐるっと巻いて固定します。素材に伸縮性があり、がっちり固定する訳ではないので、運動時に装着していてもそれほど支障にはなりません。

腰痛とは長い付き合いですが、膝・足首などの関節痛や先日書いた足指のモートン病は割と最近の症状です。はっきりした原因はわかりませんが、体の経年変化も否定できないのかもしれませんね。特効薬はないので、用心しながら日常生活やスポーツを楽しんでいこうと思います(^-^)v
サポーターのCMみたいになってしまいましたが、メーカーから謝礼や便宜供与は一切受け取っておりません(笑)
実は私も、若いころから頑固な腰痛に悩まされてきました。整形外科はもちろん、整骨院やカイロプラクティックなどに通った時期もありましたが、一時的に楽になることはあっても効果は長続きしないんですよね~
それでも、一番しんどかった時期(約20年前)に比べればかなり楽になってきていますので、日常生活は普通に過ごしています。ところが、私の腰は自他ともに認める「ガラスの腰」で、ときどき腰に「ガツン」と衝撃が走ることがあり、一旦そうなってしまうともう身動きがとれません。ただ多くの場合、まったく突然くるのではなく、今にもガツンときそうな気配(=予兆)があります。この一触即発状態のときに不用意に腰に負担をかけようものなら、間違いなく本家本元「ガツン」がきてしまうので本当に気を遣います。
つい先日も、そんな「ガツン」半歩手前の状態になってしまったので、しっかり腰を支え固定するため、取り急ぎ腰用サポーターを購入することに……。試着品をいろいろ試した結果、一番がっしりと腰を支えてくれる「中山式ボディフレーム腰用ハードW(ダブル)」を選びました。

最大20㎝と幅の広いベルト自体で、まず腰まわり全体を固定。さらに、腰に当たる位置に3本(上に2本、下に1本)の補助ベルトがあり、更に腰部をがっしり支える構造となっています。(「サポーター」と書きましたが、メーカーはこの製品を「コルセット」と分類しています)

この補助ベルトをギュッと引くことで締め付け効果を調整します。補助ベルトは、上部が2本になっているのが「ダブル」で、シングルは上下1本ずつ。私は少しでも強力にサポートするためダブルを選びました。やはりこれが正解。過去に使ったことのある腰痛サポーターに比べて、腰を固定し支える機能がずっと強力で安心感が違います=(^.^)=

裏側中央部分に幅広の腰部ボーンが2本。これが腰部が不用意に屈曲するのを抑制してくれるんですね〜
メッシュ素材で通気性も確保されているので、長時間着けていても大丈夫でした。

カミングアウトついでに、膝用サポーターも紹介します (^-^)ゞ
去年の春から初夏にかけて、右膝が痛み始めたのに「そのうち治るだろう」と高をくくって運動を続けていたところ、とうとうある日、膝がパンパンに腫れて歩けないほどの痛みに……。ナメちゃいけませんね。おかげで半年ほど整形外科に通う羽目になりました(◞‸◟)
このサポーターは、スポーツクラブのレッスンを再開できるまでに回復した頃、膝を保護し動きをサポートするために購入したものです(左が表、左は裏返したところ)。膝まわりは思いのほか汗をかくので、洗い替えとして二つ使っています。1年近く使っているので、どちらもくたびれてきました(^^;;

裏側(内側)の丸く分厚いでっぱりで膝関節を固定。更に、両サイドに入っている芯が、膝の屈曲を抑え、延ばすのをサポートしてくれるので、膝の曲げ伸ばしが少し楽になります。エアロやズンバ、ボクシングエクササイズなど、膝に負担がかかる運動では必需品です。

これは、運動するときに足首をガードするためのサポーター。(膝・足首ともに米国3M社のサポーターブランド、FUTURO)
近ごろ時々、捻ったりグキッとした覚えはないのに足首が痛むことがあるので、念のため予防用として使っています。歳とともに足首関節が弱ってきてるんでしょうか……情けない話です(^^;;

見苦しい足で恐縮ですが……、丸い穴の中に踵を入れて、足の甲から足の裏を通し、この後、足首をぐるっと巻いて固定します。素材に伸縮性があり、がっちり固定する訳ではないので、運動時に装着していてもそれほど支障にはなりません。

腰痛とは長い付き合いですが、膝・足首などの関節痛や先日書いた足指のモートン病は割と最近の症状です。はっきりした原因はわかりませんが、体の経年変化も否定できないのかもしれませんね。特効薬はないので、用心しながら日常生活やスポーツを楽しんでいこうと思います(^-^)v
サポーターのCMみたいになってしまいましたが、メーカーから謝礼や便宜供与は一切受け取っておりません(笑)