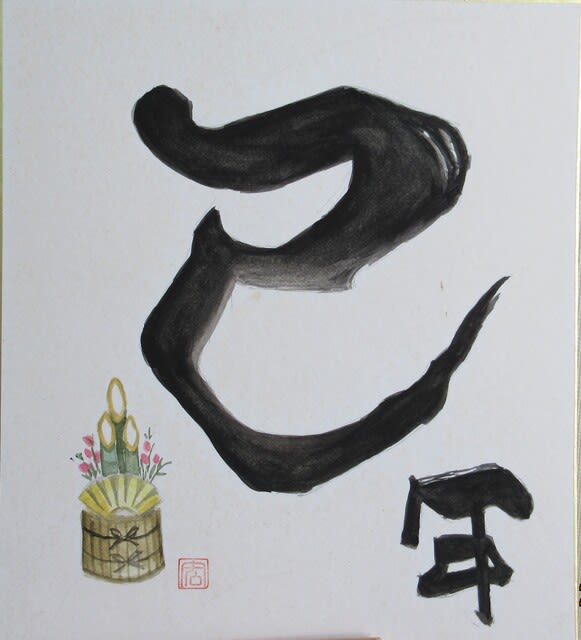先週見た「室町無類」が「動」とすれば、今回の映画は「静」といえます。
どちらの映画も、歴史上実在の人物であるということ、時代は違うが、当時の社会的な問題を多くの反対や抵抗にあいながらも成し遂げてゆくという共通点がある。
そして、違うところは、その目標に達するやり方が、その時代に即した行動をしたのでしょうか!
でも、やはり時代劇には日本の四季やなつかしい風景が似合います。今回の映画でも美しい風景を見てなにかホッとしました。


江戸時代の末期、死に至るとして恐れられた疱瘡(天然痘)が猛威を振るい、多くの命を奪っていた。
その中、福井藩の町医者で漢方医の笠原良策(松阪桃李)は、患者を救いたくとも何もすることが出来ない自分に無力感を抱いていた。
自らを責め、落ち込む良策を、妻の千穂(芳根京子)は明るく励まし続けます。


どうにかして人々を救う方法を見つけようとする良策は、ひょんなことから大聖寺藩の町医者の大武了玄(吉岡秀隆)から京都の情報を得、京に向かう。
京都には、蘭方医・日野鼎哉(役所広司)が海外の治療法に詳しいとの情報を得、さっそく教えを請うことになり京都に向かう。


日野鼎哉の塾でも、疱瘡の治療法を探し求めいるなか、異国ではでは種痘(予防接種)という方法があると知るが、そのためには「種痘の苗」を海外から取り寄せる必要があり、それには、幕府の許可も必要であり、実現は極めて困難と思われていましたが・・・
諦めない良策の志は、藩の重心、藩主から幕府も巻き込んでゆきます。


笠原良策(1809~1880)後白翁と名乗る 笠原の碑(福井市足羽山にある)
この無名の地方の町医者が、どのようにして日本をすくったのか、あらゆる困難を乗り越え諦めず人に寄り添いながら、熱意をもって成し遂げてゆく・・・この映画には、悪人はいません。みな普通の人です。それだけに物語に大きな変化がなく、結論に向かって淡々と進んでゆく中で、吹雪のなか、京都から福井に種痘の苗を運ぶところが、一番の力の入った画面でした。
又、噂や言いがかりなど多くの未知の庶民は、それに翻弄され、一時は石を投げられたり、いやがらせをされるが、それでもそれに耐え、説得に努めます。
ひとたび決意したことは、いかに苦難があっても成し遂げる熱意が、多くの庶民の心を動かします。
又、その後、藩主から御典医を命ぜられますが、それを固辞します。
どちらにしても、あまり知られていない話だけに、良い話を見せてもらったという感じです。
他に、三浦貴大、沖原一生、山本 学、益岡 徹、三木理紗子他・・・