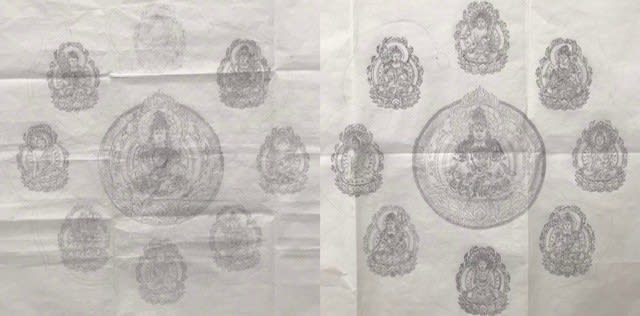海を眺めていると、優しい波の音が聞こえてくる。
心地よい風が体をとおり抜けていく。
時として、想像を絶する自然の怒りのようなものが襲ってくる。
東日本大震災11年。震災による直接の死者は1万5900人。いまだ行方不明者が2523人という。命が無残にも奪い取られた。こんなことが現実に起こり得る。あれから丸10年の月日が流れた。二度と、いや絶対に、このような事が起こらないことをただただ祈るのみ!

奇跡の一本松
こんな折に、人間の欲によって起こされた、ロシアのウクライナ侵略戦争。戦争は人が人を殺す。あってはならないことが行われている。守らなければならない民族の尊厳よりも、人の命の尊厳の方がはるかに大きいはずなのに。すべてが過去を清算できてないが故に、いまも、そしてこれからも浅はかなことが繰り返されていくのだろうか。
震災11年目の今日、黙とうしながら亡くなられた方々や行方不明者の方々のご冥福を祈り、手を合わせた。雑念ながら頭によぎったのが、ウクライナの人たちの悲しみの表情である。
一日でも早く戦争が終わり、穏やかな音や風を感じることができますように!
※トップのイメージ写真は、尾道出身のカメラマン、栗山主税氏が撮影した尾道鳴滝山からの日の出
リポート/ 渡邉雄二 写真/ 栗山主税(尾道出身のカメラマン) 奇跡の一本松の写真/ ネットのフリー画像を転載 Reported by Yuji Watanabe Photos by Chikara Kuriyama
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
尾道・文化紀行 https://asulight0911.com/hiroshima_onomichi/