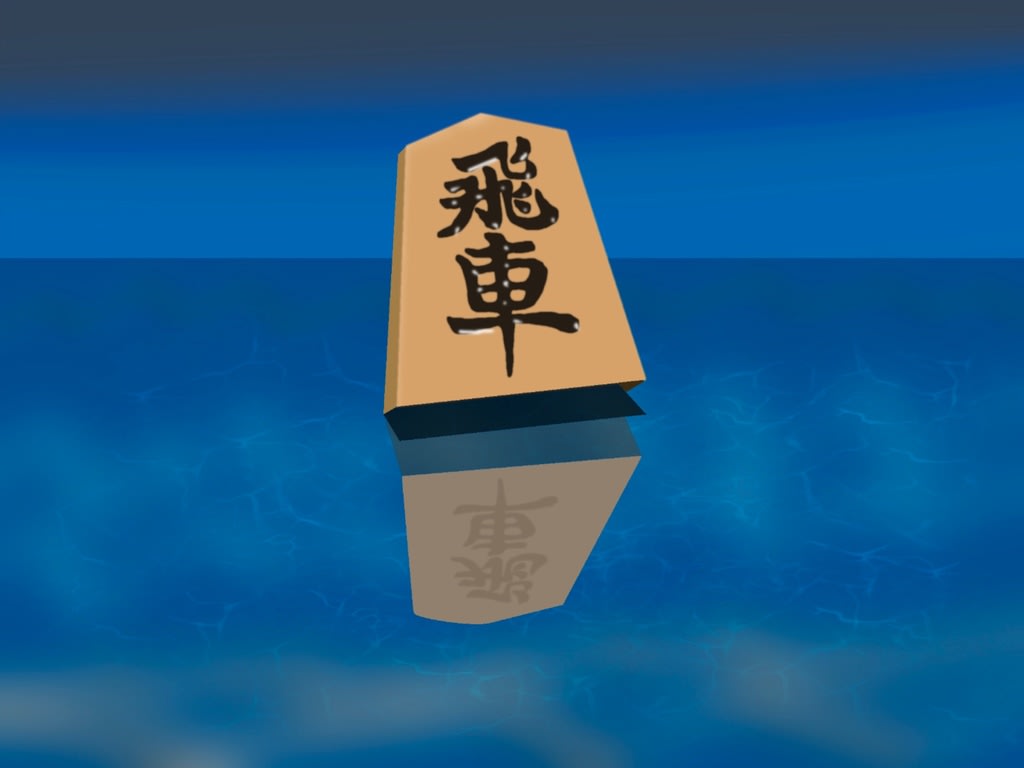
「あらゆる合駒を考える」
詰将棋の中でも合駒問題は難しい。詰将棋のルールでは玉方は盤上に存在しない残り駒全部を使える。(何という戦力差!)実戦ではまずそのような状況にはならないはず。しかし、実戦では詰将棋にはない攻防の要素が加わる。その複雑さを考えれば、あらゆる合駒をすべて考えるということは、実戦を見据えた読みの訓練にもなる。慣れてくれば条件によって読みを飛ばせるようになるだろう。(強い駒では駄目だとか、頭の丸い駒でないと駄目だとか、金以外は無効だとか)合駒に中合いの要素が加われば、更に読みは複雑化する。中合いも実戦では滅多に現れないが、それ故に詰将棋でしか研究できないとも言える。
「作者の物語を読む」~ギリギリ詰まないという罠
難解な作品では、初形から詰み形を描くことが難しい時がある。有力な王手をかけていく内にギリギリ詰まないという変化に突き当たる。詰将棋を解いていて非常にもやもやとする瞬間だ。
(何か見落としがあるのではないか)あと一歩で詰みそうなだけに、自分の読みの深さや精度に疑いをかける。実際、読み直す内にやはり詰んでいたということもないわけではない。
もしも、それが紛れ筋の方だとすると、どこかで読むことを止めねばならない。それには不詰めを読み切るという方法と、変化に見切りをつける方法とがある。(まあ、この先はあっても詰みはないなという推測)
不詰みを読み切ることも、「読む」という訓練においては、詰みを読み切ることと同じ価値がある。その時間も決して無駄ではない。
ところが速解きの競技/選手権に参加するという場合、事情は大きく変わる。詰将棋には、直線的な読みを磨くという面と、作者の描いた物語を読むという面がある。訓練の中では紛れ変化に深入りすることも不詰め変化を読み切ることも意義があるが、スピード競争においては時間を無駄に使うだけ損と言える。(詰み筋/正解筋のみを発見すればよい)
作者の用意した偽のストーリーを見破り、本筋のみを読み切ることが正解への近道になる。その時、あなたの真の敵は周りにいる選手ではなく、目の前にある問題そのものということだ。
「本当は読まされていた」
紛れ筋に見切りをつけることを躊躇った場合、納得がいくまで変化手順を読むことになる。不詰みに行き着くことを読み尽くしてしまえば、もはや自分の読みを信じる他はない。
ようやく初形にかえって改めて局面を眺めてみると……。
あなたは至って「シンプル」なことに気づく。
そして、合駒も、中合いも、紛れ一つない、詰み筋が現れる。
なんだ、簡単じゃないか。
「難解なのはサイド・ストーリーの方だった」
長い回り道の末に、幻を読まされていたことに気づくのだ。















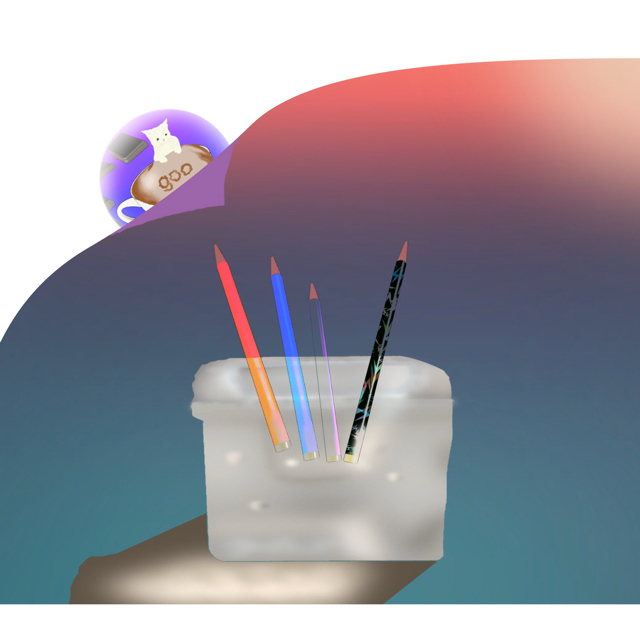

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます