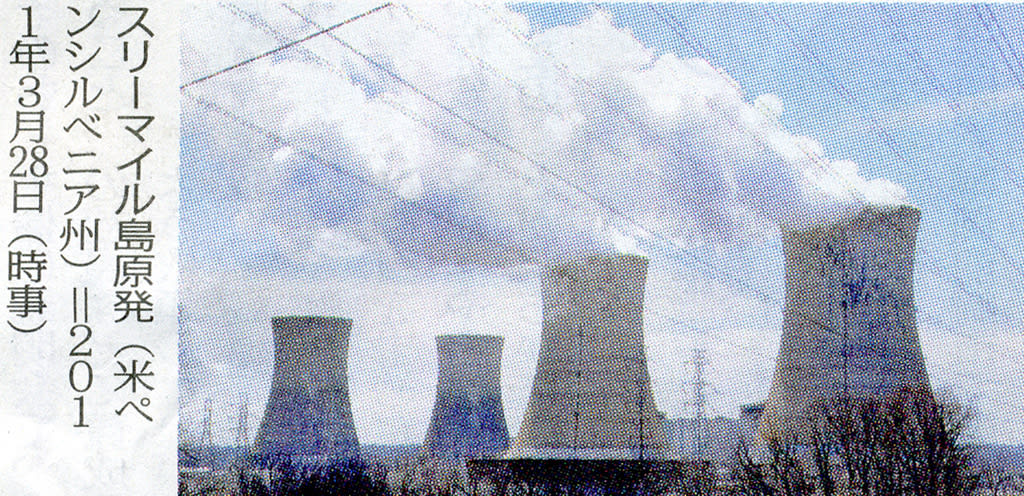続・原発の源流と日米関係⑨
米国の「核の支配」 いまこそ脱却のとき
この連載で検証してきたように、日本の原子力政策は一貫して米国の支配下に置かれてきました。この問題は、日本のエネルギー自給率の極度な低下と密接に関連しています。
自給率は4%
経済産業省によれば、国民生活や経済活動に必要な1次エネルギー(石油、石炭など)のうち、自国内で確保できる比率を示すエネルギー自給率はわずか4%です。
1960年には、主に石炭や水力といった国内天然資源によって58%あったエネルギー自給率はそれ以降大幅に低下。1980年には約10分の1の6%にまで落ち込みました。
その要因は、米国への経済的な従属を盛り込んだ日米安保条約の下で、石炭から石油への転換を強行するとともに、原発導入にまい進したからです。
戦後復興期に「傾斜生産方式」によって増産が図られた石炭は、1950年代後半から1960年代に相次いで炭鉱が閉山され、米石油メジャーが支配する石油にエネルギー源を転換。1970年代は、原発の新規立地を住民運動が許さなかったものの、2度の石油ショックを口実に「石油依存度を低下させる」として、既存発電所での原子炉増設が加速しました。
現在、石炭や石油だけでなく、液化天然ガス(LNG)や原子力の燃料となるウランもほぼ全量が輸入です。
一方、日本のエネルギー自給率4%の内容は、水力、地熱、太陽光、バイオマスなどです。化石燃料や原子力依存から脱却し、再生可能エネルギーヘの転換を図れば、自立したエネルギー政策を築くことができます。

米国の新政策
米国は、核の力=核分裂による巨大なエネルギーで戦後世界を支配してきました。1945年8月、広島と長崎に投下した原爆で圧倒的な軍事力を示す一方、数十力国に濃縮ウランを提供して、エネルギー分野での支配網をつくりました。
しかし今、それが揺らいでいます。欧州ではドイツなどで「原発撤退」の方向が示されました。当の米国ではどうでしょうか。
オバマ政権は原発推進を掲げる一方、3月30日に発表した新エネルギー政策で、「2035年までに電力の80%をクリーンエネルギーから得る」として、原子力に加えて風力、太陽光、天然ガスを挙げています。
地中の岩に含まれる「シェールガス」は米国が埋蔵量世界一です。原発に代わりうるエネルギー源として注目が高まっています。
「米国は、最後は損得で物事を決める。原発からの撤退もありうる」。原子力業界の関係者は、真顔で心配しています。
◆
「ドッカーン」。3月12日と14日、福島第1原発からの巨大な爆発音が響きわたりました。やがて「死の灰」が降り注ぎ、すべてを汚染しました。
福島県南相馬市の詩人・若松丈太郎さんは言います。「広島、長崎、福島…。核分裂による巨大なエネルギーと人類は、本当に共存できるのだろうか」
日本は、米国の「核の支配」から脱却するときを迎えています。
(おわり)
(この連載は榎本好孝、竹下岳が担当しました)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年8月4日付掲載
オイルショックの時はスペインが化石燃料から自然エネルギーへ転換。チェルノブイリの原発事故の時はドイツが原発から自然エネルギーへ・・・。
時々のターニングポイントがありながら、日本は化石燃料依存、原発依存から脱却できませんでした。
それは日本の政治が、財界主導、アメリカ主導に縛られていることによります。
その根本的打開のためには、日本を経済的にも軍事的にも縛りをかけている日米安全保障条約の廃棄、それと日本の労働運動や住民運動を主体として「ルールある経済社会」への転換が今求められていると思います。
米国の「核の支配」 いまこそ脱却のとき
この連載で検証してきたように、日本の原子力政策は一貫して米国の支配下に置かれてきました。この問題は、日本のエネルギー自給率の極度な低下と密接に関連しています。
自給率は4%
経済産業省によれば、国民生活や経済活動に必要な1次エネルギー(石油、石炭など)のうち、自国内で確保できる比率を示すエネルギー自給率はわずか4%です。
1960年には、主に石炭や水力といった国内天然資源によって58%あったエネルギー自給率はそれ以降大幅に低下。1980年には約10分の1の6%にまで落ち込みました。
その要因は、米国への経済的な従属を盛り込んだ日米安保条約の下で、石炭から石油への転換を強行するとともに、原発導入にまい進したからです。
戦後復興期に「傾斜生産方式」によって増産が図られた石炭は、1950年代後半から1960年代に相次いで炭鉱が閉山され、米石油メジャーが支配する石油にエネルギー源を転換。1970年代は、原発の新規立地を住民運動が許さなかったものの、2度の石油ショックを口実に「石油依存度を低下させる」として、既存発電所での原子炉増設が加速しました。
現在、石炭や石油だけでなく、液化天然ガス(LNG)や原子力の燃料となるウランもほぼ全量が輸入です。
一方、日本のエネルギー自給率4%の内容は、水力、地熱、太陽光、バイオマスなどです。化石燃料や原子力依存から脱却し、再生可能エネルギーヘの転換を図れば、自立したエネルギー政策を築くことができます。

米国の新政策
米国は、核の力=核分裂による巨大なエネルギーで戦後世界を支配してきました。1945年8月、広島と長崎に投下した原爆で圧倒的な軍事力を示す一方、数十力国に濃縮ウランを提供して、エネルギー分野での支配網をつくりました。
しかし今、それが揺らいでいます。欧州ではドイツなどで「原発撤退」の方向が示されました。当の米国ではどうでしょうか。
オバマ政権は原発推進を掲げる一方、3月30日に発表した新エネルギー政策で、「2035年までに電力の80%をクリーンエネルギーから得る」として、原子力に加えて風力、太陽光、天然ガスを挙げています。
地中の岩に含まれる「シェールガス」は米国が埋蔵量世界一です。原発に代わりうるエネルギー源として注目が高まっています。
「米国は、最後は損得で物事を決める。原発からの撤退もありうる」。原子力業界の関係者は、真顔で心配しています。
◆
「ドッカーン」。3月12日と14日、福島第1原発からの巨大な爆発音が響きわたりました。やがて「死の灰」が降り注ぎ、すべてを汚染しました。
福島県南相馬市の詩人・若松丈太郎さんは言います。「広島、長崎、福島…。核分裂による巨大なエネルギーと人類は、本当に共存できるのだろうか」
日本は、米国の「核の支配」から脱却するときを迎えています。
(おわり)
(この連載は榎本好孝、竹下岳が担当しました)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年8月4日付掲載
オイルショックの時はスペインが化石燃料から自然エネルギーへ転換。チェルノブイリの原発事故の時はドイツが原発から自然エネルギーへ・・・。
時々のターニングポイントがありながら、日本は化石燃料依存、原発依存から脱却できませんでした。
それは日本の政治が、財界主導、アメリカ主導に縛られていることによります。
その根本的打開のためには、日本を経済的にも軍事的にも縛りをかけている日米安全保障条約の廃棄、それと日本の労働運動や住民運動を主体として「ルールある経済社会」への転換が今求められていると思います。