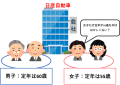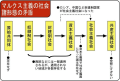「わが左翼論」の続きだが、今回と次回は番外で、自分の若い頃の話である。内容的には「非左翼論」という方が近いかもしれない。僕は中学生の頃から、本や映画に接してきた。中学一年の夏頃に突然「文学少年」になったのである。まあ、自意識の目覚めみたいなもんだろう。小学生時代にも、「小学○年生」みたいな雑誌の付録で『坊ちゃん』を読んだりしたと思う。
面白かった記憶があるが、それで終わりである。ただ面白い本を読んだというだけのことだ。ところが中学一年の夏に芥川龍之介を読んだ。学校で紹介販売していた旺文社文庫だったと思う。判りやすい『鼻』『芋粥』『蜘蛛の糸』などから始め、面白いから『河童』『歯車』『或阿呆の一生』と最晩年のものまで読み進んだ。それで世の中には「ブンガク」があると気付いた。
この「ブンガク」というのは、功利性(成績が良くなるとか)とは全く関係なく、むしろ「自分」や「世界」に関わって「譲れないもの」だった。そこでさらに読み進みたかったが、当時は「ヤング・アダルト」的な本がなかった。高い本は買えないし、町の本屋には新潮文庫と角川文庫しかなかった。(岩波文庫は普通の本屋にはなく、講談社文庫、集英社文庫、文春文庫などはまだ無かったのである。)文庫には、戦後の「大家」と言われる作家、例えば丹羽文雄とか石川達三などがいっぱい入っていた。
それらの本はちょっと古い感じがしたから、もっと新しい作家の本を買いたいと思った。当時はまだ文庫には定評ある純文学作品が収録されるものという意識が強かった。それが三島由紀夫、安部公房、大江健三郎などだった。半世紀前に死んだ三島とつい最近死んだ大江では、全然違う世代のように思われるかもしれない。だけど、70年に自衛隊に乱入したとき三島は45歳だった。僕はその前から読んでいて、ノーベル賞有力な若手作家と言われていたのである。
何にでも興味を持つタチなので、中学2年の夏に「毛主席語録」を読んでみたことがある。当時中国の映像で、みんなが持っていた赤い小さな本である。読んでみたら、意外なことに革命への熱い呼びかけを感じられず、統制ばかりを説く自由のない押しつけ的な内容だった。最初に素直に読むと、そう思うはずである。僕はすでに「文学少年」だったから、毛沢東に圧倒されずに「左翼党派性」に違和感を持ってしまったのである。
高校時代になって、もっといろいろな作家を読むようになった。三島は事件以後、何となく敬遠するようになったが、主な傑作は中学時代に読んでいた。前から良く読んでいた井上靖の歴史小説に加えて、遠藤周作も良く読んだ。だがなんと言ってもたくさん読んで、影響もされたのは、安部公房と大江健三郎だった。当時世界最先端と言っても良い文学者だったのだから、若い僕が魅惑されたのも当然だろう。
 (安部公房)
(安部公房)
そこから近代文学者をさかのぼって読んで行くようになった。高校だけでなく浪人時代も読んでいた。受験勉強するより小説読んでいたかもしれない。志賀直哉の『暗夜行路』を読んだのも、浪人時代だった気がする。中野重治、佐多稲子、野間宏、椎名麟三、武田泰淳などを大学前半までに読んでいた。ところで、この中で安部公房、中野重治、佐多稲子、野間宏は日本共産党を除名された作家である。別にそんなことは文学性に関係はない。中野重治が書いた素晴らしい詩の数々は、日本文学史に残り続ける。
 (中野重治)
(中野重治)
だが当時は、今じゃ信じられないだろうが、「誰それはトロツキスト」だとか言ってる人がいたのである。トロツキストとはスターリンに追放、暗殺されたトロツキーを支持することを指すはずだが、そんなことを考えて使ったわけではなく、もはや共産党系の人が使う悪罵の常套句だったのだろう。共産党は除名、離党された人を認めなかった。今はどうか知らないけれど、元ソ連大統領のゴルバチョフの訃報を赤旗は報じなかったそうである。当時からソ連のペレストロイカを批判していたんだそうだが、やはり触れちゃマズいものがあるんだろうか。
共産党系の「多喜二・百合子賞」というのがあったけど(1969年から2005年まで)、受賞作家をWikipediaで見るとほぼ知らない作家ばかりである。まあ、僕は数人(松田解子、江口渙、霜田正次、あるいはハンセン病作家だった冬敏之など)は知っているけど、一般的な知名度は除名された作家の方が高いだろう。だからどうだというのではなく、僕は自分の読む本は自分で決めたい。「禁書」を指示されたくない。何にしても「党派」というのは面倒だ。それが「プチブル」的な感性だろうと、自分は「自由」を手放したくないなあと思ったわけである。続いて映画の話を。
面白かった記憶があるが、それで終わりである。ただ面白い本を読んだというだけのことだ。ところが中学一年の夏に芥川龍之介を読んだ。学校で紹介販売していた旺文社文庫だったと思う。判りやすい『鼻』『芋粥』『蜘蛛の糸』などから始め、面白いから『河童』『歯車』『或阿呆の一生』と最晩年のものまで読み進んだ。それで世の中には「ブンガク」があると気付いた。
この「ブンガク」というのは、功利性(成績が良くなるとか)とは全く関係なく、むしろ「自分」や「世界」に関わって「譲れないもの」だった。そこでさらに読み進みたかったが、当時は「ヤング・アダルト」的な本がなかった。高い本は買えないし、町の本屋には新潮文庫と角川文庫しかなかった。(岩波文庫は普通の本屋にはなく、講談社文庫、集英社文庫、文春文庫などはまだ無かったのである。)文庫には、戦後の「大家」と言われる作家、例えば丹羽文雄とか石川達三などがいっぱい入っていた。
それらの本はちょっと古い感じがしたから、もっと新しい作家の本を買いたいと思った。当時はまだ文庫には定評ある純文学作品が収録されるものという意識が強かった。それが三島由紀夫、安部公房、大江健三郎などだった。半世紀前に死んだ三島とつい最近死んだ大江では、全然違う世代のように思われるかもしれない。だけど、70年に自衛隊に乱入したとき三島は45歳だった。僕はその前から読んでいて、ノーベル賞有力な若手作家と言われていたのである。
何にでも興味を持つタチなので、中学2年の夏に「毛主席語録」を読んでみたことがある。当時中国の映像で、みんなが持っていた赤い小さな本である。読んでみたら、意外なことに革命への熱い呼びかけを感じられず、統制ばかりを説く自由のない押しつけ的な内容だった。最初に素直に読むと、そう思うはずである。僕はすでに「文学少年」だったから、毛沢東に圧倒されずに「左翼党派性」に違和感を持ってしまったのである。
高校時代になって、もっといろいろな作家を読むようになった。三島は事件以後、何となく敬遠するようになったが、主な傑作は中学時代に読んでいた。前から良く読んでいた井上靖の歴史小説に加えて、遠藤周作も良く読んだ。だがなんと言ってもたくさん読んで、影響もされたのは、安部公房と大江健三郎だった。当時世界最先端と言っても良い文学者だったのだから、若い僕が魅惑されたのも当然だろう。
 (安部公房)
(安部公房)そこから近代文学者をさかのぼって読んで行くようになった。高校だけでなく浪人時代も読んでいた。受験勉強するより小説読んでいたかもしれない。志賀直哉の『暗夜行路』を読んだのも、浪人時代だった気がする。中野重治、佐多稲子、野間宏、椎名麟三、武田泰淳などを大学前半までに読んでいた。ところで、この中で安部公房、中野重治、佐多稲子、野間宏は日本共産党を除名された作家である。別にそんなことは文学性に関係はない。中野重治が書いた素晴らしい詩の数々は、日本文学史に残り続ける。
 (中野重治)
(中野重治)だが当時は、今じゃ信じられないだろうが、「誰それはトロツキスト」だとか言ってる人がいたのである。トロツキストとはスターリンに追放、暗殺されたトロツキーを支持することを指すはずだが、そんなことを考えて使ったわけではなく、もはや共産党系の人が使う悪罵の常套句だったのだろう。共産党は除名、離党された人を認めなかった。今はどうか知らないけれど、元ソ連大統領のゴルバチョフの訃報を赤旗は報じなかったそうである。当時からソ連のペレストロイカを批判していたんだそうだが、やはり触れちゃマズいものがあるんだろうか。
共産党系の「多喜二・百合子賞」というのがあったけど(1969年から2005年まで)、受賞作家をWikipediaで見るとほぼ知らない作家ばかりである。まあ、僕は数人(松田解子、江口渙、霜田正次、あるいはハンセン病作家だった冬敏之など)は知っているけど、一般的な知名度は除名された作家の方が高いだろう。だからどうだというのではなく、僕は自分の読む本は自分で決めたい。「禁書」を指示されたくない。何にしても「党派」というのは面倒だ。それが「プチブル」的な感性だろうと、自分は「自由」を手放したくないなあと思ったわけである。続いて映画の話を。