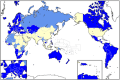萩原延壽「遠い崖ーアーネスト・サトウ日記抄」を延々と読み続けている。「アーネスト・サトウと幕末」の続き。途中でやめずに、ようやく最後の14巻まで来た。5月半ばに読み始めて、6月全部を使っても終わらない。「遠い崖」に関してもう少し書いてみたい。
アーネスト・サトウに「英国策論」というものがある。1866年に横浜の英字新聞ジャパン・タイムズに無署名で寄稿した3つの論文を集めたものである。というか、「英国策論」は本人が出したのではなく、その匿名英語論文が勝手に訳されて日本中に散布されたのである。事実上英国の政策と同一視され、幕末の政局にも大きな影響を与えたらしい。イギリス軍艦に乗って宇和島に寄った時、幕末の4賢侯の一人伊達宗城(だて・むねなり)も読んでいた。

外国から見たら、江戸の将軍って何なんだ?という疑問があった。外国人は長崎に行けと言われて長崎に行くと、江戸は遠いから連絡に時間が掛かると言われる。ペリーが江戸湾に直接現れたことで、幕府との間に日米和親条約を結ぶことに成功した。次は貿易ができるような通商条約を結びたいと幕府と交渉し、話がまとまった。そうしたら「勅許」(ミカドの許し)が出ないと言われる。江戸幕府が最高権力だと思っていたら、日本には幕府の上があったのか。
これは英国外交官にとってとても深刻な疑問だった。何故なら徳川将軍と英国女王(ヴィクトリア女王)との間に条約が結ばれた以上、将軍の上に天皇がいるなら「天皇は英国女王より上」になってしまうから。この問題は外国外交官にとって大疑問だったのである。幕府は将軍は天皇に任命されているが、全国統治権は完全に幕府のもとにあると主張していた。だから薩摩藩が起こした英国人殺傷事件(生麦事件)の賠償金も幕府が払った。でも事件の責任者の処罰という要求を幕府に突き付けても、どうも解決の見込みが立たない。
そこに若き英国外交官サトウが現れ、日本語を自在に操り反体制派人士にも多くの知人を得た。文語も読めるから、国学者の文献なんかも読んでみる。日本書紀、古事記など古来の史書にあたれば、天皇の方が古いということが確認できる。どうも幕府の言い分の方がおかしいのではないか。サトウはそう思うようになっていったわけである。そこで「英国策論」では「将軍は主権者ではなく諸侯連合の首席にすぎない」という認識が語られる。
さらに「現行条約を廃し、新たに天皇及び連合諸大名と条約を結び、日本の政権を将軍から諸侯連合に移すべきである」といった主張も展開している。匿名とはいえ、外交官としては踏み込み過ぎだろう。サトウの「若気の過ち」である。この論文が全国にばらまかれて、サトウが書いたのも知れ渡る(日本語力から他の人には書けない)。サトウは「倒幕派」の論客とみなされ薩長の情報が集まりやすくなった。サトウはこうして、幕末政局に事実上の反体制派支援者としてデビューしたのである。
サトウの認識は現実の政治に影響した。徳川慶喜が将軍になり、外国外交官との謁見が行われたとき、英国以外は「陛下」(His Majesty)と呼んだのに対し、イギリスだけは「閣下」(His Excellency)と呼んだのである。幕府の外務官僚はその意味を理解して、わざわざ遣欧使節が英国本国に抗議している。将軍は当時外国では「タイクン」(大君)と呼ばれた。一方、天皇は「ミカド」である。タイクンとミカドの関係をどう理解するべきか。
 (徳川慶喜)
(徳川慶喜)
徳川幕府が亡びたことは、今では「それが歴史の流れ」と思ってる人ばかりだろう。日本人で将軍制度に戻すべきだという主張をする人は0%だ。現在もそうだし、明治時代も同じだろう。西欧文明を受け入れて日本を中央集権国家にする。それ自体は必然だったと今じゃ誰もが思っているだろう。ただ薩長中心に天皇が主権を持つ国家を作る以外に歴史のコースはなかったか。
今サトウの論をみると、当時最大の勢力を誇る大英帝国の目が無意識に入り込んでいたように思う。つまり、「君臨すれども統治せず」の立憲君主制を絶対視し、それを日本に投影して日本の主権者を天皇だと考える。そういう傾向がないとは言えない。現実に幕府が倒された後は、イギリスの政策はむしろアメリカと対立するようになる。
日本を開国させたアメリカだが、1860年代半ばは南北戦争によって関係が薄れた。明治初頭になって条約改正などでアメリカは日本の主張を支持した。最大の貿易関係にあった英国は、アメリカを共和制国家の「過激派」とみなし、日本にアメリカ流の考えが入り込まないように忠告している。しかし、その頃から日本政府はイギリスではなく、ドイツの憲法を目標にするようになる。もう歴史の中で解決済みの問題なんだけど、その時代を生きている人にはそのことは判らない。幕末の日本に来たサトウも、自らタイクンとミカドの関係を考察せざるを得なかった。
アーネスト・サトウに「英国策論」というものがある。1866年に横浜の英字新聞ジャパン・タイムズに無署名で寄稿した3つの論文を集めたものである。というか、「英国策論」は本人が出したのではなく、その匿名英語論文が勝手に訳されて日本中に散布されたのである。事実上英国の政策と同一視され、幕末の政局にも大きな影響を与えたらしい。イギリス軍艦に乗って宇和島に寄った時、幕末の4賢侯の一人伊達宗城(だて・むねなり)も読んでいた。

外国から見たら、江戸の将軍って何なんだ?という疑問があった。外国人は長崎に行けと言われて長崎に行くと、江戸は遠いから連絡に時間が掛かると言われる。ペリーが江戸湾に直接現れたことで、幕府との間に日米和親条約を結ぶことに成功した。次は貿易ができるような通商条約を結びたいと幕府と交渉し、話がまとまった。そうしたら「勅許」(ミカドの許し)が出ないと言われる。江戸幕府が最高権力だと思っていたら、日本には幕府の上があったのか。
これは英国外交官にとってとても深刻な疑問だった。何故なら徳川将軍と英国女王(ヴィクトリア女王)との間に条約が結ばれた以上、将軍の上に天皇がいるなら「天皇は英国女王より上」になってしまうから。この問題は外国外交官にとって大疑問だったのである。幕府は将軍は天皇に任命されているが、全国統治権は完全に幕府のもとにあると主張していた。だから薩摩藩が起こした英国人殺傷事件(生麦事件)の賠償金も幕府が払った。でも事件の責任者の処罰という要求を幕府に突き付けても、どうも解決の見込みが立たない。
そこに若き英国外交官サトウが現れ、日本語を自在に操り反体制派人士にも多くの知人を得た。文語も読めるから、国学者の文献なんかも読んでみる。日本書紀、古事記など古来の史書にあたれば、天皇の方が古いということが確認できる。どうも幕府の言い分の方がおかしいのではないか。サトウはそう思うようになっていったわけである。そこで「英国策論」では「将軍は主権者ではなく諸侯連合の首席にすぎない」という認識が語られる。
さらに「現行条約を廃し、新たに天皇及び連合諸大名と条約を結び、日本の政権を将軍から諸侯連合に移すべきである」といった主張も展開している。匿名とはいえ、外交官としては踏み込み過ぎだろう。サトウの「若気の過ち」である。この論文が全国にばらまかれて、サトウが書いたのも知れ渡る(日本語力から他の人には書けない)。サトウは「倒幕派」の論客とみなされ薩長の情報が集まりやすくなった。サトウはこうして、幕末政局に事実上の反体制派支援者としてデビューしたのである。
サトウの認識は現実の政治に影響した。徳川慶喜が将軍になり、外国外交官との謁見が行われたとき、英国以外は「陛下」(His Majesty)と呼んだのに対し、イギリスだけは「閣下」(His Excellency)と呼んだのである。幕府の外務官僚はその意味を理解して、わざわざ遣欧使節が英国本国に抗議している。将軍は当時外国では「タイクン」(大君)と呼ばれた。一方、天皇は「ミカド」である。タイクンとミカドの関係をどう理解するべきか。
 (徳川慶喜)
(徳川慶喜)徳川幕府が亡びたことは、今では「それが歴史の流れ」と思ってる人ばかりだろう。日本人で将軍制度に戻すべきだという主張をする人は0%だ。現在もそうだし、明治時代も同じだろう。西欧文明を受け入れて日本を中央集権国家にする。それ自体は必然だったと今じゃ誰もが思っているだろう。ただ薩長中心に天皇が主権を持つ国家を作る以外に歴史のコースはなかったか。
今サトウの論をみると、当時最大の勢力を誇る大英帝国の目が無意識に入り込んでいたように思う。つまり、「君臨すれども統治せず」の立憲君主制を絶対視し、それを日本に投影して日本の主権者を天皇だと考える。そういう傾向がないとは言えない。現実に幕府が倒された後は、イギリスの政策はむしろアメリカと対立するようになる。
日本を開国させたアメリカだが、1860年代半ばは南北戦争によって関係が薄れた。明治初頭になって条約改正などでアメリカは日本の主張を支持した。最大の貿易関係にあった英国は、アメリカを共和制国家の「過激派」とみなし、日本にアメリカ流の考えが入り込まないように忠告している。しかし、その頃から日本政府はイギリスではなく、ドイツの憲法を目標にするようになる。もう歴史の中で解決済みの問題なんだけど、その時代を生きている人にはそのことは判らない。幕末の日本に来たサトウも、自らタイクンとミカドの関係を考察せざるを得なかった。