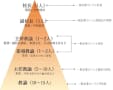谷崎潤一郎原作「細雪」は今までに3回映画化されている。以下の3つの作品である。
①1950年 新東宝 阿部豊監督 145分 キネマ旬報ベストテン第9位
②1959年 大映 島耕二監督 105分
③1983年 東宝 市川崑監督 140分 キネマ旬報ベストテン第2位 アジア太平洋映画祭作品賞、監督賞
この3本を神保町シアターで見たので、それも一週間以上前のことになるけど、何とか3月中にまとめ。もう上映もしてないし、誰にも無関係ながら自分の備忘という意味である。3本全部前に見ていて、随分しばらくぶりに見直したことになる。今までは原作を読んでなかったので、今度原作を読んでみたところ、なるほどなあと思うことが多かった。長大な原作をたった2時間ほどの映画にまとめなければならない。映画製作にはお金も時間も掛かるから、ある程度は女優中心に「商業映画」として成立させなくてはならない。そこでどこをどう切り取り、どう入れ替えるか。シナリオの勉強になる。
では、どのように女優中心になっているか。蒔岡家の四人姉妹を上からキャストを紹介すると、以下の通り。
①花井蘭子・轟由起子・山根寿子・高峰秀子
②轟由起子・京マチ子・山本富士子・叶順子
③岸恵子・佐久間良子・吉永小百合・古手川祐子
第一作のキャストは今ではもう判らないかもしれない。当時としても山根寿子より、4女の高峰秀子の方が大スターである。一方、②③の山本富士子、吉永小百合は、誰もが認める大女優。だから①は「こいさん」(妙子)が中心になり、②③は三女雪子が中心になる感じがする。原作は雪子の方が重要だと思うが、最初の映画化で四女妙子の奔放な恋愛が強調されたのは、時代の影響が大きいと思う。高峰秀子だからという以上に、敗戦と占領という時代相が反映されていると考えられる。
 (1950年の「細雪」、左から高峰・山根・轟・花井)
(1950年の「細雪」、左から高峰・山根・轟・花井)
簡単に各作品に触れていきたい。①は原作完結後すぐの映画化で、これだけがモノクロ映画になっている。それだけに今見ると、ロケなどにまだ敗戦直後の貧しさが見える。しかし、驚くべきことに原作のクライマックスとも言える「阪神間大水害」が描かれるのは①だけなのである。映画では特撮を駆使しているが、今となってはちょっとしんどい。それでも「完全映画化」に一番近いのは①なのである。ただ和服や花見シーンがカラーじゃないのは、やはり寂しい。雪子の山根寿子は戦前から活躍した女優で、50年代末日活の石坂洋次郎作品によく出ていた。電話にも出られずモジモジして縁談を断られる感じは一番出ているかな。
 (阿部豊監督)
(阿部豊監督)
①の監督阿部豊(1895~1977)は無声映画時代から長く活躍した監督で、1926年の「足にさはつた女」がキネマ旬報の日本映画ベストテンの最初の1位になった。その前にハリウッドに行って俳優として活躍し、映画技術を学んで日本に戻った。最初の頃は「ジャック」名で活動していて昔の文献には「ジアツキ阿部」なんて出ている。戦時中には「燃える大空」「あの旗を撃て」などの戦争映画を作った。ものすごく作品数が多いが、戦後は東宝、新東宝、日活で娯楽映画を量産している。「細雪」は戦後唯一のベストテン入選。特に悪くもないのだが、まあ全体的に評価すれば9位は妥当なところか。
 (1959年の「細雪」)
(1959年の「細雪」)
1959年の②は大映製作で、驚くべきことに原作を製作当時の1959年に変えている。その結果、当時の町並みなどをロケ撮影することが出来るので、貴重ではある。冒頭では啓ぼんがこいさんを車で送ってくるし、次女の幸子は自らカレーライスを作ると腕を振るっている。次女京マチ子と三女山本富士子は、大映を支えた看板女優で、「夜の蝶」ではバーのマダムの壮絶な争いを演じた。当然「細雪」でも山本富士子の縁談が話の中心になる。しかし、山本富士子が結婚出来ないなんておかしいので、かつてまとまった縁談があったのだが、デートするその日に交通事故死した過去がトラウマかになって、30を過ぎたとされる。そんなバカなという感じだが、山本富士子との縁談を断る男がいるはずがないので、そんな設定を作ったのである。
 (島耕二監督)
(島耕二監督)
島耕二監督(1901~1986)は戦前の日活映画を支えた俳優だったが、39年から監督に転身した。「風の又三郎」(1940)、「次郎物語」(1941)が高く評価された。映画史的に残るのもこの2本。戦後は「幻の馬」(1955)が一番かと思うが、「銀座カンカン娘」「有楽町で逢いましょう」「情熱の詩人啄木」など多くの作品がある。「細雪」は可もなし不可もなしか。
 (1983年の「細雪」)
(1983年の「細雪」)
1983年の③は明らかに一番優れている。映画的には脚本と撮影、照明などの技術が洗練の極みに達していて、四人姉妹に配する長女の夫が伊丹十三、次女の夫が石坂浩二と安定感がある。ただし、原作を読んでいると、実に驚くべき改変をしていてビックリ。②は時代そのものを変えたから他は気にならないが、③は本家の東京移転を最後に持って行っている。だから途中までの映画化かというと、三女雪子の縁談は最後まで描いているのである。原作では本家と一緒に雪子も上京するのに対し、③では縁談が決まった雪子は本家を見送る側である。しかも、そのお相手の華族の次男(原作は庶子なのだが、映画はただ次男とする)が、元阪神タイガースの江本なので唖然とする。そして驚くべきことに、次女幸子の夫(石坂浩二)が雪子(吉永小百合)に思いを寄せているという設定である。いや、これは面白いけど無茶でしょう。
そもそも冒頭の豪華な花見シーンだが、原作では本家は加わらない。しかし、映画では長女岸惠子も参加して四人姉妹の豪華絢爛たる花見シーンになる。何だか映画に影響されてしまっていたが、原作を読んだら全然違うので驚き。さらに凄いのは、「こいさん」(四女妙子)が啓ぼんを振ってカメラマンの板倉に思いを寄せるきっかけの「大水害」がない。特撮がないのではなく、セリフにもないのである。これも時代を正確に再現する意味では無茶だろう。自立して生きている板倉の方が、母親頼りの啓ぼんより立派というのは、現代人の感覚だ。階級的にこれほど格差がある相手に好意を寄せるには、生命の危機を助けて貰ったという設定は不可欠のはずである。しかし、こう変えたことで現代映画になったことは間違いない。脚色の手腕である。
ちなみに啓ぼんと板倉のキャストを比べると。
①啓ぼん=田中春男、板倉=田崎潤 ②啓ぼん=川崎敬三、板倉=根上淳 ③啓ぼん=桂小米朝(現米團治)、板倉=岸部一徳 原作のイメージには①が合っている。
 (市川崑監督)
(市川崑監督)
市川崑(1915~2008)は、さすが巨匠の風格である。長生きしたので、訃報では「犬神家の一族」「細雪」などが代表作などと書かれてしまった。真の代表作は50年代から60年代初期の大映で作った「野火」「おとうと」「破戒」などだろう。50年代初期に東宝で作ったコメディ、1961年の「黒い十人の女」などブラックユーモアも再評価されつつある。角川で横溝作品を映画化して大ヒットしたというのは、おまけというべきだろう。
①1950年 新東宝 阿部豊監督 145分 キネマ旬報ベストテン第9位
②1959年 大映 島耕二監督 105分
③1983年 東宝 市川崑監督 140分 キネマ旬報ベストテン第2位 アジア太平洋映画祭作品賞、監督賞
この3本を神保町シアターで見たので、それも一週間以上前のことになるけど、何とか3月中にまとめ。もう上映もしてないし、誰にも無関係ながら自分の備忘という意味である。3本全部前に見ていて、随分しばらくぶりに見直したことになる。今までは原作を読んでなかったので、今度原作を読んでみたところ、なるほどなあと思うことが多かった。長大な原作をたった2時間ほどの映画にまとめなければならない。映画製作にはお金も時間も掛かるから、ある程度は女優中心に「商業映画」として成立させなくてはならない。そこでどこをどう切り取り、どう入れ替えるか。シナリオの勉強になる。
では、どのように女優中心になっているか。蒔岡家の四人姉妹を上からキャストを紹介すると、以下の通り。
①花井蘭子・轟由起子・山根寿子・高峰秀子
②轟由起子・京マチ子・山本富士子・叶順子
③岸恵子・佐久間良子・吉永小百合・古手川祐子
第一作のキャストは今ではもう判らないかもしれない。当時としても山根寿子より、4女の高峰秀子の方が大スターである。一方、②③の山本富士子、吉永小百合は、誰もが認める大女優。だから①は「こいさん」(妙子)が中心になり、②③は三女雪子が中心になる感じがする。原作は雪子の方が重要だと思うが、最初の映画化で四女妙子の奔放な恋愛が強調されたのは、時代の影響が大きいと思う。高峰秀子だからという以上に、敗戦と占領という時代相が反映されていると考えられる。
 (1950年の「細雪」、左から高峰・山根・轟・花井)
(1950年の「細雪」、左から高峰・山根・轟・花井)簡単に各作品に触れていきたい。①は原作完結後すぐの映画化で、これだけがモノクロ映画になっている。それだけに今見ると、ロケなどにまだ敗戦直後の貧しさが見える。しかし、驚くべきことに原作のクライマックスとも言える「阪神間大水害」が描かれるのは①だけなのである。映画では特撮を駆使しているが、今となってはちょっとしんどい。それでも「完全映画化」に一番近いのは①なのである。ただ和服や花見シーンがカラーじゃないのは、やはり寂しい。雪子の山根寿子は戦前から活躍した女優で、50年代末日活の石坂洋次郎作品によく出ていた。電話にも出られずモジモジして縁談を断られる感じは一番出ているかな。
 (阿部豊監督)
(阿部豊監督)①の監督阿部豊(1895~1977)は無声映画時代から長く活躍した監督で、1926年の「足にさはつた女」がキネマ旬報の日本映画ベストテンの最初の1位になった。その前にハリウッドに行って俳優として活躍し、映画技術を学んで日本に戻った。最初の頃は「ジャック」名で活動していて昔の文献には「ジアツキ阿部」なんて出ている。戦時中には「燃える大空」「あの旗を撃て」などの戦争映画を作った。ものすごく作品数が多いが、戦後は東宝、新東宝、日活で娯楽映画を量産している。「細雪」は戦後唯一のベストテン入選。特に悪くもないのだが、まあ全体的に評価すれば9位は妥当なところか。
 (1959年の「細雪」)
(1959年の「細雪」)1959年の②は大映製作で、驚くべきことに原作を製作当時の1959年に変えている。その結果、当時の町並みなどをロケ撮影することが出来るので、貴重ではある。冒頭では啓ぼんがこいさんを車で送ってくるし、次女の幸子は自らカレーライスを作ると腕を振るっている。次女京マチ子と三女山本富士子は、大映を支えた看板女優で、「夜の蝶」ではバーのマダムの壮絶な争いを演じた。当然「細雪」でも山本富士子の縁談が話の中心になる。しかし、山本富士子が結婚出来ないなんておかしいので、かつてまとまった縁談があったのだが、デートするその日に交通事故死した過去がトラウマかになって、30を過ぎたとされる。そんなバカなという感じだが、山本富士子との縁談を断る男がいるはずがないので、そんな設定を作ったのである。
 (島耕二監督)
(島耕二監督)島耕二監督(1901~1986)は戦前の日活映画を支えた俳優だったが、39年から監督に転身した。「風の又三郎」(1940)、「次郎物語」(1941)が高く評価された。映画史的に残るのもこの2本。戦後は「幻の馬」(1955)が一番かと思うが、「銀座カンカン娘」「有楽町で逢いましょう」「情熱の詩人啄木」など多くの作品がある。「細雪」は可もなし不可もなしか。
 (1983年の「細雪」)
(1983年の「細雪」)1983年の③は明らかに一番優れている。映画的には脚本と撮影、照明などの技術が洗練の極みに達していて、四人姉妹に配する長女の夫が伊丹十三、次女の夫が石坂浩二と安定感がある。ただし、原作を読んでいると、実に驚くべき改変をしていてビックリ。②は時代そのものを変えたから他は気にならないが、③は本家の東京移転を最後に持って行っている。だから途中までの映画化かというと、三女雪子の縁談は最後まで描いているのである。原作では本家と一緒に雪子も上京するのに対し、③では縁談が決まった雪子は本家を見送る側である。しかも、そのお相手の華族の次男(原作は庶子なのだが、映画はただ次男とする)が、元阪神タイガースの江本なので唖然とする。そして驚くべきことに、次女幸子の夫(石坂浩二)が雪子(吉永小百合)に思いを寄せているという設定である。いや、これは面白いけど無茶でしょう。
そもそも冒頭の豪華な花見シーンだが、原作では本家は加わらない。しかし、映画では長女岸惠子も参加して四人姉妹の豪華絢爛たる花見シーンになる。何だか映画に影響されてしまっていたが、原作を読んだら全然違うので驚き。さらに凄いのは、「こいさん」(四女妙子)が啓ぼんを振ってカメラマンの板倉に思いを寄せるきっかけの「大水害」がない。特撮がないのではなく、セリフにもないのである。これも時代を正確に再現する意味では無茶だろう。自立して生きている板倉の方が、母親頼りの啓ぼんより立派というのは、現代人の感覚だ。階級的にこれほど格差がある相手に好意を寄せるには、生命の危機を助けて貰ったという設定は不可欠のはずである。しかし、こう変えたことで現代映画になったことは間違いない。脚色の手腕である。
ちなみに啓ぼんと板倉のキャストを比べると。
①啓ぼん=田中春男、板倉=田崎潤 ②啓ぼん=川崎敬三、板倉=根上淳 ③啓ぼん=桂小米朝(現米團治)、板倉=岸部一徳 原作のイメージには①が合っている。
 (市川崑監督)
(市川崑監督)市川崑(1915~2008)は、さすが巨匠の風格である。長生きしたので、訃報では「犬神家の一族」「細雪」などが代表作などと書かれてしまった。真の代表作は50年代から60年代初期の大映で作った「野火」「おとうと」「破戒」などだろう。50年代初期に東宝で作ったコメディ、1961年の「黒い十人の女」などブラックユーモアも再評価されつつある。角川で横溝作品を映画化して大ヒットしたというのは、おまけというべきだろう。