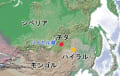集英社新書4月刊の三宅香帆『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』という本が評判になっていると聞き、読んでみた。これはある種「読者論」の体裁を取って、働き方について提言をしている本だった。帯には「疲れてスマホばかり見てしまうあなたへ」とある。現代人なら誰しも思い当たるようなキャッチコピーだろう。若い時は読書家だったけど、働くようになったら難しい本、大長編小説などを読めなくなったと嘆く人は多いはず。この問題設定に僕もちょっと書きたくなった。

最初に2021年の映画『花束みたいな恋をした』(土井裕泰監督)を取り上げたことも共感を呼んでいるらしい。その映画については、当時『映画「花束みたいな恋をした」と「あの頃。」ー魅力の青春映画』を書いた。読み直してみたら、2020年にコロナ禍で大ヒットしたアニメ『鬼滅の刃』の興収トップ記録を初めて破った映画だった。『怪物』でカンヌ映画祭脚本賞を受けた坂元裕二の脚本。ふと出会った麦(菅田将暉)と絹(有村架純)は本や映画のテイストが似ていて話が合った。恋に落ちて一緒に暮らすようになるが、大学を卒業すると麦は仕送りがなくなる。イラストレーターになる夢を捨て本格的に働き始めたが、そうすると二人の距離が大きくなっていく。本屋に行っても麦は自己啓発本みたいなものを手に取るようになっていく。
 (『花束みたいな恋をした』)
(『花束みたいな恋をした』)
これはよくあるような話だろう。僕はそれを麦が「おじさん文化」に取り込まれていくと書いたが、本書では二人の階級的背景を重視している。これは就職後の必然とまでは言えないと思う。麦と絹は一緒にアキ・カウリスマキの『希望のかなた』を見たが、麦は今ひとつ乗れない。だけど、僕はずっと夫婦でカウリスマキ映画を見てたんだから。映画は見ている間は受動的に鑑賞出来るので、エンタメ系だけではなくアート映画でも結構見続けられると思う。問題は長時間労働で疲弊していると、集中力が失われることだ。その意味で20世紀の教師は、夏休みや考査期間中などに自分の趣味に時間を使いやすかったのだ。
だけど、僕もかつて『大江健三郎を読まなくなった頃ー大江健三郎を読む①』という記事を書いた。若い頃からずっと読んできた大江文学だが、1987年に出た『懐かしい年への手紙』を某私立高校の学校説明会に行くバスの中で読んでいて、今はこれは読めないなと思った。そして2021年に改めて読んで、ものすごく面白い本だったことに驚いた。大江作品は「純文学度」が高いので、仕事をしていた間は読めなかった。村上春樹なら読めたので、小説全部を読まなかったわけではない。むしろ仕事に関係する本は読み続けていた。社会科教員といっても専門の歴史もどんどん新しい知識が必要だし、地理や政治経済になると不得意分野も多い。
僕はずっと本を読み続けてきたが、現職中は仕事に関する本がどうしても多くなる。それはつまらない本をガマンして読んでいたのではない。中にはつまらない本もあるが、基本的には授業に役立つものを楽しんで読んでいた。その意味では読書全般が仕事のノイズということはない。仕事にもよるだろうが、「読書」が仕事に必須な職場はかなりあると思う。それでも「純文学」(的な本)を読むのは現職バリバリの時は難しい。もちろんどんなに忙しくても『失われた時を求めて』を読み切れた人がいないとは言えない。しかし、やっぱり短期的に集中するべき課題を幾つか抱えていると、あまりに長い本には入れ込めないもんだ。
この本で触れられているが、現代では「映画を早送りして見る」ような「ファスト教養」を求める人が多いという。それが良いのか悪いのか僕には決められない。これは決して批判の意味で書くのではないが、この本の半分以上を占める近現代読者論はまさに「ファスト教養」のお手本である。有名な研究書を簡潔にまとめながら書かれている。例えば前田愛先生の『近代読者の成立』とか、僕も取り上げた本では福間良明『「勤労青年」の教養文化史』、小熊英二『日本社会のしくみ』なんかである。
一般向けに書かれた新書などを使いながら、大胆に時代を分析していく。明治大正期は僕も知らないから通説通りで納得したが、80年代、90年代になると、これでいいのかなと思うところも多い。今は詳しく触れないけど、後の世代から見るとこんなもんだったのかという感じ。著者の三宅香帆氏は1994年生まれで、京都大学大学院前期課程修了の文芸評論家とある。1994年生まれというと、もちろん地下鉄サリン事件や阪神淡路大震災は記憶にない世代。「3・11」(2011年の東日本大震災)には高校1年生だったはず。そうすると僕が最後に教えていた世代なので、何となく判る気がする。もちろん人様々だが読書大好きはいつでもいる。
 (三宅香帆氏)
(三宅香帆氏)
ただこの人の「読書できないから仕事を辞めた」みたいなことは真に受けない方が良いと思う。「京大大学院」という背景があって、その後の幾つもの本に関わる仕事に結びついた。もちろん「本」だけでなく、「音楽」「演劇」「ダンス」なども同様だが、それで一生生きていける人は少ない。多くの人は多少似通った分野で定職に就くことが多いはず。それでもやりようによっては、かなり読めると思う。それは三宅氏が言う「半身の働き方」である。それは最近必要になったのではなく、今までもずっと「身を守る」ためにやられて来た方法だ。我々はまず自分と家族を守っていく必要がある。
最後に三宅氏はいくつかのコツを書いている。例えば「iPad」が良いと言うけど、僕は今後どうなるかわからないけど、今のところ「紙の本」に執着している。内容と同時に、「本」の匂いや感触が好きなのである。それでも視力面で小さな字は難しくなるから、拡大できる機能がある方が良いとも思う。「書店に行く」というのも大事で、そうすることで意外な本に出会える。そして僕が言いたいのは、ネットで買うのもやむを得ないが(本屋では求めにくいタイプの専門書などもある)、そうすると向こうから勝手に勧めてくる本は買わないことである。AIかなんかで自分の買いたい本を決められては困る。
そして、三宅氏にはまだ遠い先だけど、やがて長時間労働をしたくてもやれない年齢がやってくる。そうなると、今度は「純文学」系の本を読む自由と内的必然性が出て来る。若い時に「生きる目的は何だろう」と思って小説に心惹かれたように、今度は「自分が生きてきた目的はなんだろう」と小説や思想書、宗教書を求めるようになる。そういう時代まで生き抜くために、それまで取っておく本があっても良い。

最初に2021年の映画『花束みたいな恋をした』(土井裕泰監督)を取り上げたことも共感を呼んでいるらしい。その映画については、当時『映画「花束みたいな恋をした」と「あの頃。」ー魅力の青春映画』を書いた。読み直してみたら、2020年にコロナ禍で大ヒットしたアニメ『鬼滅の刃』の興収トップ記録を初めて破った映画だった。『怪物』でカンヌ映画祭脚本賞を受けた坂元裕二の脚本。ふと出会った麦(菅田将暉)と絹(有村架純)は本や映画のテイストが似ていて話が合った。恋に落ちて一緒に暮らすようになるが、大学を卒業すると麦は仕送りがなくなる。イラストレーターになる夢を捨て本格的に働き始めたが、そうすると二人の距離が大きくなっていく。本屋に行っても麦は自己啓発本みたいなものを手に取るようになっていく。
 (『花束みたいな恋をした』)
(『花束みたいな恋をした』)これはよくあるような話だろう。僕はそれを麦が「おじさん文化」に取り込まれていくと書いたが、本書では二人の階級的背景を重視している。これは就職後の必然とまでは言えないと思う。麦と絹は一緒にアキ・カウリスマキの『希望のかなた』を見たが、麦は今ひとつ乗れない。だけど、僕はずっと夫婦でカウリスマキ映画を見てたんだから。映画は見ている間は受動的に鑑賞出来るので、エンタメ系だけではなくアート映画でも結構見続けられると思う。問題は長時間労働で疲弊していると、集中力が失われることだ。その意味で20世紀の教師は、夏休みや考査期間中などに自分の趣味に時間を使いやすかったのだ。
だけど、僕もかつて『大江健三郎を読まなくなった頃ー大江健三郎を読む①』という記事を書いた。若い頃からずっと読んできた大江文学だが、1987年に出た『懐かしい年への手紙』を某私立高校の学校説明会に行くバスの中で読んでいて、今はこれは読めないなと思った。そして2021年に改めて読んで、ものすごく面白い本だったことに驚いた。大江作品は「純文学度」が高いので、仕事をしていた間は読めなかった。村上春樹なら読めたので、小説全部を読まなかったわけではない。むしろ仕事に関係する本は読み続けていた。社会科教員といっても専門の歴史もどんどん新しい知識が必要だし、地理や政治経済になると不得意分野も多い。
僕はずっと本を読み続けてきたが、現職中は仕事に関する本がどうしても多くなる。それはつまらない本をガマンして読んでいたのではない。中にはつまらない本もあるが、基本的には授業に役立つものを楽しんで読んでいた。その意味では読書全般が仕事のノイズということはない。仕事にもよるだろうが、「読書」が仕事に必須な職場はかなりあると思う。それでも「純文学」(的な本)を読むのは現職バリバリの時は難しい。もちろんどんなに忙しくても『失われた時を求めて』を読み切れた人がいないとは言えない。しかし、やっぱり短期的に集中するべき課題を幾つか抱えていると、あまりに長い本には入れ込めないもんだ。
この本で触れられているが、現代では「映画を早送りして見る」ような「ファスト教養」を求める人が多いという。それが良いのか悪いのか僕には決められない。これは決して批判の意味で書くのではないが、この本の半分以上を占める近現代読者論はまさに「ファスト教養」のお手本である。有名な研究書を簡潔にまとめながら書かれている。例えば前田愛先生の『近代読者の成立』とか、僕も取り上げた本では福間良明『「勤労青年」の教養文化史』、小熊英二『日本社会のしくみ』なんかである。
一般向けに書かれた新書などを使いながら、大胆に時代を分析していく。明治大正期は僕も知らないから通説通りで納得したが、80年代、90年代になると、これでいいのかなと思うところも多い。今は詳しく触れないけど、後の世代から見るとこんなもんだったのかという感じ。著者の三宅香帆氏は1994年生まれで、京都大学大学院前期課程修了の文芸評論家とある。1994年生まれというと、もちろん地下鉄サリン事件や阪神淡路大震災は記憶にない世代。「3・11」(2011年の東日本大震災)には高校1年生だったはず。そうすると僕が最後に教えていた世代なので、何となく判る気がする。もちろん人様々だが読書大好きはいつでもいる。
 (三宅香帆氏)
(三宅香帆氏)ただこの人の「読書できないから仕事を辞めた」みたいなことは真に受けない方が良いと思う。「京大大学院」という背景があって、その後の幾つもの本に関わる仕事に結びついた。もちろん「本」だけでなく、「音楽」「演劇」「ダンス」なども同様だが、それで一生生きていける人は少ない。多くの人は多少似通った分野で定職に就くことが多いはず。それでもやりようによっては、かなり読めると思う。それは三宅氏が言う「半身の働き方」である。それは最近必要になったのではなく、今までもずっと「身を守る」ためにやられて来た方法だ。我々はまず自分と家族を守っていく必要がある。
最後に三宅氏はいくつかのコツを書いている。例えば「iPad」が良いと言うけど、僕は今後どうなるかわからないけど、今のところ「紙の本」に執着している。内容と同時に、「本」の匂いや感触が好きなのである。それでも視力面で小さな字は難しくなるから、拡大できる機能がある方が良いとも思う。「書店に行く」というのも大事で、そうすることで意外な本に出会える。そして僕が言いたいのは、ネットで買うのもやむを得ないが(本屋では求めにくいタイプの専門書などもある)、そうすると向こうから勝手に勧めてくる本は買わないことである。AIかなんかで自分の買いたい本を決められては困る。
そして、三宅氏にはまだ遠い先だけど、やがて長時間労働をしたくてもやれない年齢がやってくる。そうなると、今度は「純文学」系の本を読む自由と内的必然性が出て来る。若い時に「生きる目的は何だろう」と思って小説に心惹かれたように、今度は「自分が生きてきた目的はなんだろう」と小説や思想書、宗教書を求めるようになる。そういう時代まで生き抜くために、それまで取っておく本があっても良い。