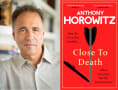まあ書かなくてもいいんだけど、趣味的な記事を数回。まずはアメリカのミステリー作家、ローレンス・ブロック(1938~)の話。僕はこの人のマット・スカダー・シリーズが大好きで、翻訳が出るたびに楽しみに読んできた。もっとも最初から読んでいたわけではない。5作目の『800万の死にざま』(1982)でブレイクし、その映画化を見て面白かった。ハヤカワ文庫に入っていたので読んだら面白かった。その後は二見書房から刊行されたので、大体ハードカバーで読んできた。
90年代が絶頂で、『墓場への切符』『倒錯の舞踏』なんか最高に面白かった。作者と主人公が一緒に年をとっていくシリーズなので、17冊目の『償いの報酬』で終わりかなと思っていた。と思ったら18作目の『マット・スカダー わが探偵人生』(二見書房)という「自伝」が出た。(他に短編をもとにした『石を放つとき』が出ている。これは老境心理小説みたいなもの。)
この「自伝」はもうミステリーとは言えない。このシリーズが好きだった人に向けたボーナスである。しかし、ある種文学史上に残る奇書である。シャーロック・ホームズもエルキュール・ポワロも自伝なんか書かなかった。架空の人物なんだから当然である。もちろんマット・スカダーも作者ローレンス・ブロックが作り出した架空の人物である。だけど、実に長い間にわたって作者はマット・スカダーという人物を書き続け、またニューヨークの町のたたずまいを見つめてきた。だから、まるで実在の人物のようにマット・スカダーに「自伝」を書かせることが可能になる。そして、マットは作者に言われて自伝に取り掛かり、時々作者に見せる。そこで作家ローレンス・ブロックが登場してあれこれアドヴァイスするという趣向である。
ほとんど「前衛」的手法とも言えるような書き方じゃないか。「劇中劇」というか「メタ文学」というか。まあ、それが面白いかと言えば、シリーズを読んでた人にしか意味ないと思う。その上に題名は「偽り」がある。マット・スカダーが警官を辞めて、「私立探偵」(みたいなもの)になった後の「秘話」みたいなものはほぼ出て来ない。警官時代の思い出がほとんどなのである。そして、それがある種のアメリカ社会論になっている。また、「ある事件」によって警官を辞めて離婚もするが、それ以前から結婚生活に問題があったことが告白されている。子どものために遠い地区に家を買い、そのため市内にアパートを借りることになってしまい、捜査で遅くなると帰らなくなってしまった。そのうち飲んでいて遅くなってもアパートがあるからいいやとなっていった。
マットの元妻はイタリア系とドイツ系の両親のもとに生まれた。そこでマットは最初に出会った時に「日本人のおばさんがいたりして」なんて軽口をたたいて、これは失言だったかなと思う。つまり、「日独伊三国同盟」にちなむジョークである。しかし、笑って受け流してくれて、結婚まで行く。しかし、このジョークを忘れていたわけじゃないことは、何十年も経ってニューヨーカーが「スシ」を食べることが当たり前になったときに判明する。ローレンス・ブロックの世代だと、やはりニューヨークを代表するプロスポーツはヤンキースで野球の話題が多い。何の作品だか覚えてないが、ブルックリン・ドジャーズを西海岸に移してしまったオーナー、ウォルター・オマリーをニューヨーカーに一番憎まれてる人物と表現していたことも忘れられない。
ところで都営地下鉄新宿線菊川というところに、「Stranger」という小さな映画館がある。そこでハル・アシュビー監督特集が行われ、『800万の死にざま』(8 Million Ways to Die)も上映された。時間が合わなくてこれしか見られなかったが、ハル・アシュビー監督(1929~1988)は、『帰郷』『ウディ・ガスリー わが心のふるさと』などの名作を作った人である。僕は昔『800万の死にざま』を見てると思うんだけど、その時点では原作を知らなかった。だから何も思わなかったんだけど、オリバー・ストーンが加わった脚本は何とロサンゼルスの話になってた。これって黒川博行の原作を東京で映画化するようなもんじゃなかろうか。ま、それはともかくスカダーはジェフ・ブリッジス、敵役がアンディ・ガルシア、ヒロインがロザンナ・アークエットの佳作。
ローレンス・ブロックは実に多彩な作品を送り続けた名手だが、年齢的にもう新作は望めないかもしれない。マット・スカダー・シリーズと同じぐらい人気だったのが、泥棒バーニーシリーズや殺し屋ケラーシリーズだ。特にケラーものは短編集ながら、面白さは絶品で楽しみに読んでいた。ほとんど訳されていると思ったら、2024年になって文春文庫から『エイレングラフ弁護士の事件簿』が刊行され、「このミス」6位に選出された。いや驚き。しかし、このシリーズはやり過ぎでしょ。必ず無罪にしてくれる弁護士である。法廷で無罪判決になるのではなく、いつの間にか起訴が取り下げられたりする。エイレングラフが何をしたかよく判らないけど、結果的に依頼人は自由になるのである。恐ろしいシリーズである。ちょっと後味が悪いなあ。