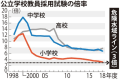中公新書から2020年4月に出た詫摩佳代「人類と病」を読んだ。2020年のサントリー学芸賞(政治・経済部門)を受賞した本で、帯で大きく宣伝している。サントリー学芸賞は1979年から始まって、政治・経済、芸術・文学、社会・風俗、思想・歴史の4部門で毎年10名前後に授賞している。一般向けの新書でも受賞することが多く、人文・社会科学系の学者にとって論壇デビュー的な役割を果たしている。昨年度ではここで書いた小山俊樹「五・一五事件」も受賞している。

読んでみて、内容が事前の予想と少し違っていた。題名からは「医学史」の本のような感じを受ける。広く「科学史」という学術分野があって、自然科学の一部門だけど社会史的な研究でもある。そんな本かと思ったら、これは国際政治学の本だった。著者の詫摩佳代氏は東大法学部で学んだ北岡伸一門下の国際政治学者だった。(現在は都立大学教授。)2014年に安田佳代名で「国際政治のなかの国際保健事業 国際連盟保健機関から世界保健機関、ユニセフへ」(ミネルヴァ書房)という本を出している。この題名が問題意識を表わしている。
ペスト、コレラから出版直前の新型コロナウイルスまで触れられている。第1章の「二度の世界大戦と感染症」では第一次世界大戦後の「国際連盟保健機関」が取り上げられる。ILO(国際労働機関)は第一次大戦後に発足しているが、WHOはまだなかったのである。非政府組織との協力には国際連盟内でも消極的な国が多かったという。そこで赤十字を中心にして国際協力が始まる。1923年に国際連盟保健機関が常設の機関として認められた。
僕も全く知らなかったが、この国際連盟保健機関は世界に支部を設け、アジア支部はシンガポールに置かれた。日本が国際連盟を脱退した後も、保健機関との協力は持続されたという。この国際連盟保健機関では、ビタミンや性ホルモンの「標準化」も行った。大戦前に、医学、化学が一番発達していたのはドイツだったが、大戦に負けて当初は国際連盟に入れなかった。一方、アメリカは経済や科学が発展して医学用語も統一されていなかった。
第2章「感染症の『根絶』」ではではWHOの設立に始まり、天然痘、ポリオ、マラリアとの闘いが描かれる。第3章「新たな脅威と国際政治の変容」では、エイズ、サーズ、エボラ出血熱、新型コロナウイルスが扱われる。第4章「生活習慣病対策の難しさ」では生活習慣病、喫煙とたばこ規制の問題を取り上げる。感染症に関しては、2月に「ポリオ、アフリカで根絶ーWHOの成果」を書いた。この本はその時に持っていたので、早く読めばもっと詳しく書けた。
 (ジュネーブのWHO本部)
(ジュネーブのWHO本部)
それよりも印象的だったのは、アメリカは特に生活習慣病に関してWHOを敵視し、予算を削ると脅してきたという歴史だ。「生活習慣病」の対策で、肥満、糖尿病のリスクを減らすために「糖分を控える」という問題がある。しかし、アメリカの大企業はそれに大反対してきた。名前は挙っていないが、清涼飲料やチョコ、ビスケットなどのお菓子メーカーはすぐに思い浮かぶ。糖分の摂取量低減目標など決められたら、大損害なんだろう。また煙草でもアメリカには世界的大メーカーがあり、銃規制に対するライフル協会と同じく、一大圧力団体となってきた。煙草会社が禁煙運動を目の仇にしてつぶそうとする映画が何本も作られている。
最後の第5章「『健康への権利』をめぐる闘い」では、医薬品アクセスをめぐる問題、顧みられない熱帯病が取り上げられる。特許をめぐって貧困国では高い薬が入手できない。医療へのアクセスが「市場メカニズム」に左右される問題がある。また「先進国」に多い病気の方が医学研究でも優先されやすい。新薬を開発するための膨大な開発費は、先進国で売れる薬を作って取り返すしかない。そのため熱帯の貧困国に多い感染症が後回しにされる。そういう「国際政治学的な問題」が保健分野でも存在するのである。
新型コロナウイルスで判ったことは、コロナウイルスといった特に珍しくないウイルスの研究が遅れていた現状だ。サーズもマーズも重大だったが、すぐに終息したために研究できるほどの事例がなかった。何よりも大切な「国際保健協力」を世界がどのように進展させてきたか。その現状と問題点を考えるために一読の価値がある。

読んでみて、内容が事前の予想と少し違っていた。題名からは「医学史」の本のような感じを受ける。広く「科学史」という学術分野があって、自然科学の一部門だけど社会史的な研究でもある。そんな本かと思ったら、これは国際政治学の本だった。著者の詫摩佳代氏は東大法学部で学んだ北岡伸一門下の国際政治学者だった。(現在は都立大学教授。)2014年に安田佳代名で「国際政治のなかの国際保健事業 国際連盟保健機関から世界保健機関、ユニセフへ」(ミネルヴァ書房)という本を出している。この題名が問題意識を表わしている。
ペスト、コレラから出版直前の新型コロナウイルスまで触れられている。第1章の「二度の世界大戦と感染症」では第一次世界大戦後の「国際連盟保健機関」が取り上げられる。ILO(国際労働機関)は第一次大戦後に発足しているが、WHOはまだなかったのである。非政府組織との協力には国際連盟内でも消極的な国が多かったという。そこで赤十字を中心にして国際協力が始まる。1923年に国際連盟保健機関が常設の機関として認められた。
僕も全く知らなかったが、この国際連盟保健機関は世界に支部を設け、アジア支部はシンガポールに置かれた。日本が国際連盟を脱退した後も、保健機関との協力は持続されたという。この国際連盟保健機関では、ビタミンや性ホルモンの「標準化」も行った。大戦前に、医学、化学が一番発達していたのはドイツだったが、大戦に負けて当初は国際連盟に入れなかった。一方、アメリカは経済や科学が発展して医学用語も統一されていなかった。
第2章「感染症の『根絶』」ではではWHOの設立に始まり、天然痘、ポリオ、マラリアとの闘いが描かれる。第3章「新たな脅威と国際政治の変容」では、エイズ、サーズ、エボラ出血熱、新型コロナウイルスが扱われる。第4章「生活習慣病対策の難しさ」では生活習慣病、喫煙とたばこ規制の問題を取り上げる。感染症に関しては、2月に「ポリオ、アフリカで根絶ーWHOの成果」を書いた。この本はその時に持っていたので、早く読めばもっと詳しく書けた。
 (ジュネーブのWHO本部)
(ジュネーブのWHO本部)それよりも印象的だったのは、アメリカは特に生活習慣病に関してWHOを敵視し、予算を削ると脅してきたという歴史だ。「生活習慣病」の対策で、肥満、糖尿病のリスクを減らすために「糖分を控える」という問題がある。しかし、アメリカの大企業はそれに大反対してきた。名前は挙っていないが、清涼飲料やチョコ、ビスケットなどのお菓子メーカーはすぐに思い浮かぶ。糖分の摂取量低減目標など決められたら、大損害なんだろう。また煙草でもアメリカには世界的大メーカーがあり、銃規制に対するライフル協会と同じく、一大圧力団体となってきた。煙草会社が禁煙運動を目の仇にしてつぶそうとする映画が何本も作られている。
最後の第5章「『健康への権利』をめぐる闘い」では、医薬品アクセスをめぐる問題、顧みられない熱帯病が取り上げられる。特許をめぐって貧困国では高い薬が入手できない。医療へのアクセスが「市場メカニズム」に左右される問題がある。また「先進国」に多い病気の方が医学研究でも優先されやすい。新薬を開発するための膨大な開発費は、先進国で売れる薬を作って取り返すしかない。そのため熱帯の貧困国に多い感染症が後回しにされる。そういう「国際政治学的な問題」が保健分野でも存在するのである。
新型コロナウイルスで判ったことは、コロナウイルスといった特に珍しくないウイルスの研究が遅れていた現状だ。サーズもマーズも重大だったが、すぐに終息したために研究できるほどの事例がなかった。何よりも大切な「国際保健協力」を世界がどのように進展させてきたか。その現状と問題点を考えるために一読の価値がある。