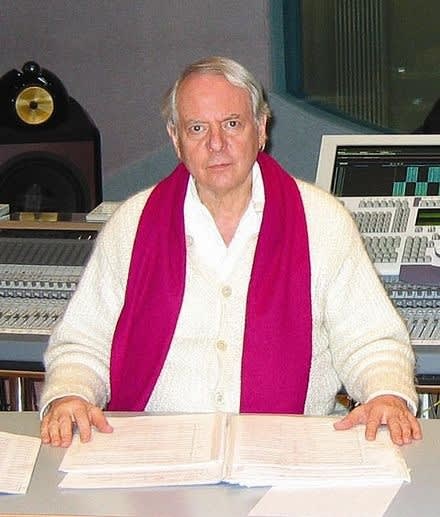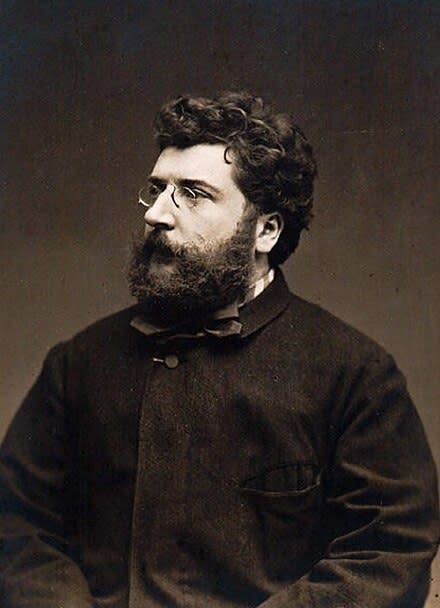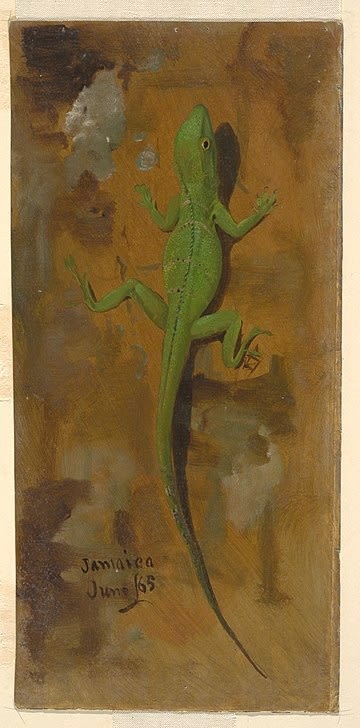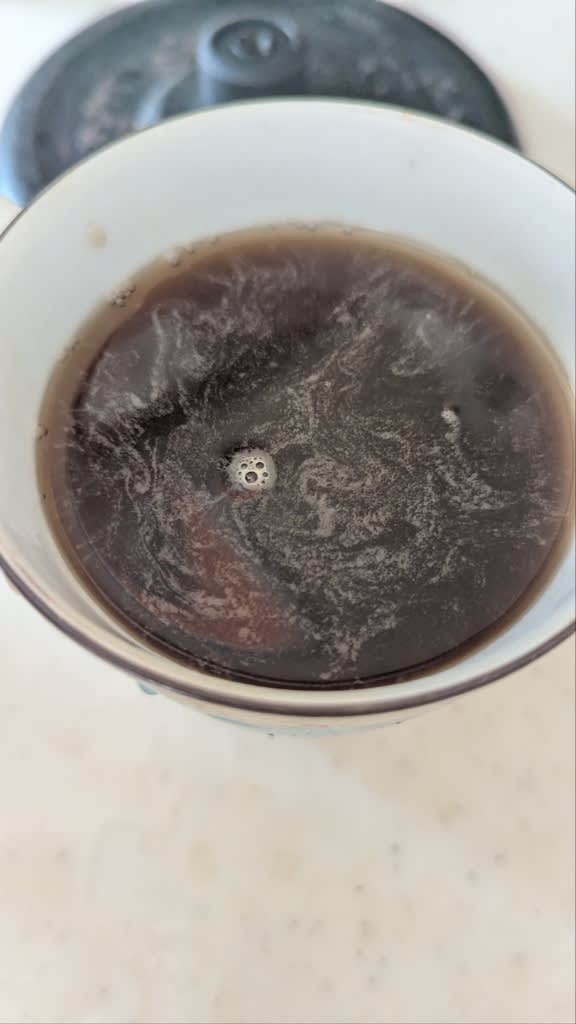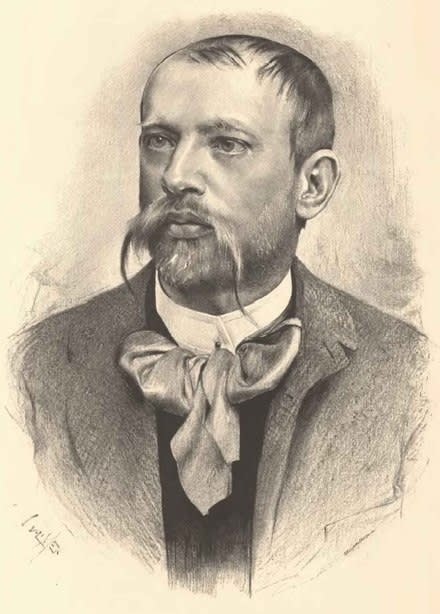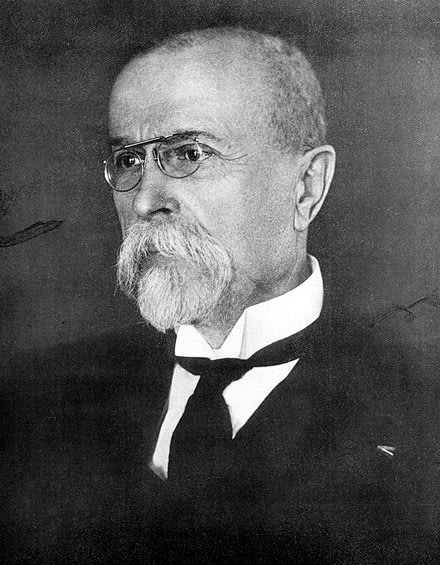自力洗髪洗顔禁止なので、介護用品のコーナーで買った洗顔ペーパータオルで顔を拭いて、ついでに髪のホコリを拭いてしのいでいましたが、7日目ともなるといよいよ気持ち悪くなってきました。
ご近所の美容院に行くと、干支飾りの巳年のパズルや
お花で大にぎわい。
「かわいいもの好きなスタッフがいるんです。」
きれいにシャンプーしてもらって、せっかくなのでカットもしてもらってすっきり。
「シャンプーだけでも来てくださいね。」
シャンプー上手かったです。
ほぼ自分でカット、毛染めも自分ですが、たまにはこういう時間もいいものですね。
理容は先史時代からあり、考古遺物としては青銅器時代にあたる紀元前3500年頃の剃刀が発見されているそうです。
また、『旧約聖書』「エゼキエル書」にも理容のことが書かれています。
エゼキエル書 釈迦十大弟子の一人であるウパーリは、出家前は釈迦族の理髪師であったことが知られています。
マケドニア人(アレクサンドロス3世(大王)時)に征服される前の古代ギリシアでは、主人の調髪や、頭髪、髭、指の爪などのスタイルを整えていました。
整髪は、古代ギリシアの植民地で当時の技術的最先端地域であったシチリア島から紀元前296年に共和政ローマに渡り、間もなく人気を博しました。
古代ギリシア 古代ローマの自由市民は髭を剃らなければいけませんでしたが、一方、男性奴隷は髭を伸ばすことと決められていました。
朝、公衆浴場と共に理髪師を訪れて身を正すことは習慣となり、また、青年が生まれて初めて髭を剃ること (tonsura) は青年と見なされるための通過儀礼の一部となっていました。
ローマ人理髪師の中には裕福になって栄えた者もいました。
彼らは店先の通りにスツール(椅子)を並べ、クォドランス(当時の硬貨、通貨単位でクォーター)の料金で髭を剃っていました。
鋳造硬貨。表はヘールクレースの頭部と3つのペレット、裏面はガレー船の船首と3つのペレットが描かれている。 剃刀による剃髪が嫌いな客には脱毛も行いました。
紀元前54年、共和政ローマのガイウス・ユリウス・カエサル(紀元前100-紀元前44年)
が軍を率いてグレートブリテン島に上陸したときには、先住民であるブリトン人は唇の上部以外の顔の髭を剃っていました。
イングランドでは歴史的に、シェービング(剃髪、髭・髪に関わらず)は法律で義務づけられていました。
中世以降
イングランドにおいて、ノルマンディー公ギヨーム2世(イングランド王ウィリアム1世)によるノルマン・コンクエスト(ノルマン征服)1066-1071年
イングランド兵と戦うノルマン騎兵 の時代には、敵方であり最後のアングロ・サクソン系イングランド王となったハロルド2世(1022-1066年)
とその家来は顎髭(あごひげ)を剃っていました。
中世の欧米諸国では理容師は外科的処置を行う外科医、歯科医師でもありました。
その頃、医学は内科学主流とされていたため、怪我の処置や四肢の切断等に至るまで、理容師がこれを行っていました。
「瀉血(血抜き)」、吸角法、ヒル療法、浣腸、抜歯を行いました。
そのため、彼らは "barber surgeon(理髪外科医)" と呼ばれ、1094年に最初の組合を作りました。
イングランドにおける理容師は、イングランド王エドワード4世(1442-1483年)
によって1462年、ギルド(職業組合)として法定化され、外科医はその30年後にギルドができまし。
1540年にヘンリー8世(1491-1547年)
により、"The United Barber Surgeons Company"(理髪・外科医組合)とされました。
エリザベス1世(1533-1603年)
は「生活が活発でないことの証明だから」という理由によって2週間以上髭を伸ばした者に税金を課していました。
17 - 18世紀のロシア皇帝ピョートル1世(ピョートル大帝)(1672-1725年)
は、1699年、西洋化改革の始まりを示すべく、ロシア正教上の習慣に逆らって口髭・顎鬚を剃り落とすよう全国民に強要し、違反者には身分上の貴卑の別なく課税しました。
ロシアの民衆版画であるルボークにもこの様子は描かれています。
ルボーク( 民衆 版画 ) 『床屋の髭切り』 17世紀末のロシア帝国にて、勅令に従って“髭刈り”を執行する床屋(理容師。右)と、抵抗の意志を見せながらも応じざるを得ない古儀式派の大貴族(左)を描いた戯画。18世紀初頭の作
ジョージ1世時の1745年、外科医は理容と分けることが法定されました。
18世紀、オスマン帝国の理容師のエプロン 音楽史上最も有名な理髪師と言えばジョキアキーノ ロッシーニ(1792-1868年)教皇領ペーザロ生まれ、教皇領ボローニャ没
の歌劇「セビリアの理髪師」のフィガロ。
1816年、フランスの劇作家ボーマルシェ(1732-1799年)の戯曲(Le barbier de Séville ou la précaution inutile 「セビリアの理髪師あるいは無用の用心」)を題材に作曲した2幕のメロドランマ・ブッフォ(Almaviva o sia L'inutile precauzione、一般には Il Barbiere di Siviglia )の中の主人公フィガロです。
セヴィリャの理髪師
あらすじ
18世紀、スペインのセヴィリャ
【第1幕】
時は18世紀、舞台はセヴィリャの医師バルトロ邸。
若くして親から莫大な遺産を継いだロジーナ
ジュヌヴィエーヴ・マテュー・ルッツ(ロジーナ役)、1907 年
は、後見人である医師バルトロ
の家に身を寄せていましたが、一方のバルトロは、ロジーナと結婚できれば美女と財産を一気に手に入れることができると目論んで、他の男が言い寄らないように監視しています。
スペインの貴族アルマヴィーヴァ伯爵
はロジーナを見そめて、窓の下からセレナードを歌いますが、バルトロ邸の監視が厳しく二人は会うことができません。
そこに「セヴィリャの理髪師」のフィガロ
が通りかかったので、伯爵は、報酬をはずむから協力するよう依頼します。
そのとき、ロジーナは窓からこっそり「身分と名前を教えて」というメモを落としました。伯爵は彼女の誠実な気持ちを試すため、貧しい学生リンドーロと名乗ることにします。
理髪師としてバルトロ邸に入り込んだフィガロは、ロジーナにリンドーロ宛の手紙を書くように勧めます。
彼女はすでに書き終えていて、それをフィガロに託します。
ロジーナはフィガロに手紙をアルマヴィーヴァ伯爵に渡す。ヴィルヘルム マーストラン
その後、伯爵が酔っぱらった兵士に変装してバルトロ邸にやって来てロジーナと話をしようとしますが、この作戦はバルトロに怪しまれて失敗します。
【第2幕】
伯爵は、今度はバルトロの腹心の音楽教師バジリオの「弟子」に変装しました。
しかし、それでもバルトロに怪しまれたので、仕方なくロジーナが書いたリンドーロ宛の手紙を、伯爵の手から盗んだと言って渡し、味方だと思い込ませます。
伯爵とロジーナは音楽のレッスンをしている間に、二人で今夜駆け落ちすることを約束します。
このときフィガロは、バルトロの髭を剃りながら、バルコニーの鍵を手に入れていました。
伯爵とフィガロが去ったあと、バルトロはロジーナに例の手紙を見せ、リンドーロはお前を伯爵に売ろうとしているのだと言います。
怒ったロジーナはバルトロとでも誰とでも結婚すると言い出します。喜んだバルトロは公証人を呼び寄せておきました。
その夜、伯爵とフィガロがバルコニーから忍び込むと、ロジーナは怒っています。伯爵が身分を明かして説明すると一件落着。
ちょうどそこへバルトロが呼んでおいた公証人がやって来たので、その場で二人は結婚してしまいました。
バルトロが現れたときはすでに時遅し。それでも伯爵がロジーナの財産はいらないと言ったので、バルトロはとりあえず満足できたのでした。
セビリアの理髪師 フィガロがやってきて「おれは街のなんでも屋」と歌います。
みんな俺を必要としている。人生は楽しい!
VIDEO