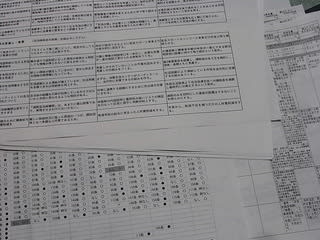朝起きて、新聞を読んで、P-WANのセレクトニュースをアップして、
コーヒーを飲んで、洗濯物を干して・・・・していると、すぐにお昼になってしまう。
このところ、週末にせまった「議員と市民の勉強会」の準備でけっこういそがしい。
勉強会の参加者から届いた、レジメを元にオリジナル資料を作成。
できた資料を持ち寄って、連れ合いと当日のセッションの、
分担とタイムスケジュールを詰めていく。
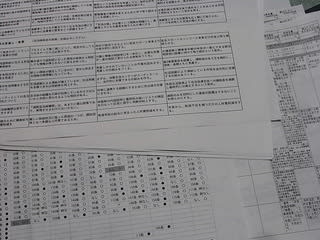
資料を見ながらどんなすすめ方にするのか相談するのだけど、
10年ほど続けている勉強会なので息はあってて、タイムテーブルは問題なく決まった。
あとは、当日に向けて、それぞれ分担のところで何を話すか詰めるだけ。
もう一息、がんばろう。
人気ブログランキング(社会・経済)に参加中 
応援クリック してね
してね 

 本文中の写真をクリックすると拡大します。
本文中の写真をクリックすると拡大します。
鶏を育てているまどかくんが、卵を持ってやってきた。
えさを少し変えたので、色と味をみてほしい、ということ。
ここ10日間くらいの卵に、一日ごとにマジックで産んだ日付が書いてある。
いろいろ調べて、鶏の健康のために、アスタキサンチンと酵素を取り寄せて
やりはじめたとのこと。
ヒヨコは米で餌付けしているので、卵黄の色が薄かったのだけど、
アスタキサンチンは、蟹やエビに含まれるカロテノイドの一種なので、
卵黄の色もよくなる、という効果もある。
日付けの順番に割ってみたら、確かに黄身の色は濃くなっているが、
カボチャや人参もやっているので、予想よりも、ずっと濃い。
見た目「黄身」というよりは「オレンジ身」、「卵黄」ならぬ「卵紅」(笑)。
アスタキサンチンをえさに加えると、米やぬかをたくさんやっている鶏は
卵黄がピンク系になるのが特徴のようだけど、「ピンク卵」よりはよい。

本人は、「いろが濃い方がおいしそう」といっているが、
「下の段の5日目くらいの色がいいんじゃない(笑)」とわいわいがやがや、
白身と黄身の味がよく分かる、目玉焼きにしてみた。

味付けは何もなし。
よい香りがしてきたので、こげた白身の端を食べてみたら、
ほんのり塩味とうまみが感じられる。

元の順番に並べて、品評会のように、白身と黄身を、
味が混じらないように順番にスプーンですくって食べてみた。
目隠しして食べたりした結果、黄身の色が濃いものほど味も濃厚でおいしい。
まどかくん作の卵は、いままで、生臭みがなくて香りがよいさっぱり系だったのだけど、
むかし、わたしたちが飼っていた卵の味がする。
とはいえ、あとでいり卵にしてみたら、黄色というよりオレンジだったので、
緑餌をたくさんやってることだし、アスタキサンチンをもう少し減らした方が、
卵としては自然な色だと消費者は思うかも知れない。
まっ、巷で売っている卵は、緑餌はやらずに、配合飼料に着色料を添加して
黄身の色を濃くしているだけれど、「自然卵」は季節によっては餌によって
卵の色にばらつきが出るのは仕方ないかな。
試行錯誤して、安全でおいしい卵を追求してほしい。
「平飼い自然卵」は、餌に発酵飼料や野菜、海草を入れるので、
コレステロールが低いと、前からいわれていたのだけど、
調べてみたら、アスタキサンチンはもっといろんな作用がありそうだ。
アスタキサンチン
アスタキサンチンは、自然界が生み出す代表的な色素の1つカロテノイドの一種で、キサントフィル類の仲間です。ヘマトコッカスなどの藻類に含まれるアスタキサンチンは、食物連鎖によりオキアミやサクラエビやサケの体に蓄えられ、イクラや筋子を美しく彩っています。
●カロテノイドの一種
β-カロチンなどと同じカロテノイドの仲間で、サケ・エビ・カニや海藻などの魚介類に多く含まれる赤い色素です。その抗酸化力はビタミンEの1000倍にも達し、「史上最強のカルテノイド」と言われています。つまり血中脂質の活性酸素を抑え、血管を若々しく保ったり、免疫細胞を活性酸素から守ることで免疫力を高めます。またアスタキサンチン自体がガンの増殖を抑制することも知られています。さらに、脳関門を通過することができるため、目の病変の予防と治療に効果があるとされています。
魚介類に多く含まれるアスタキサンチンや緑黄色野菜に多いルテイン・リコペン・β-カロチンといった抗酸化物質としてのカルテノイドは、生物が活性酸素から自分を守るために身につけたと考えられます。
またトコトリエノール・ビタミンC・ビタミンEなどは細胞膜が酸化されるのを防いでくれます。さらにウコン(クルクミン)・ローズマリー・セレンなどにも抗酸化作用があります。これらの水溶性・脂溶性の抗酸化物質を上手に組み合わせることでその効果が相乗的に高まり、また持続性も向上するといわれています。
アスタキサンチンの主な効用
メタボリックシンドローム
アスタキサンチンに、内臓脂肪から分泌されるホルモン[アディポネクチン]を増やす効果があることをヤマハ発動機が突き止めた。20代~60代の男女16人に、アスタキサンチン16mgを毎日、3ヶ月間摂取してもらった。血液中のアディポネクチンは最高で18%増加していた。
また血糖値を調整するインスリンが効かないようにする物質が、約29%減少したことも確認した。
アディポネクチンは脂肪を燃焼し血糖値を抑える働きがあると言われていて、分泌量が増えるとメタボリック症候群が改善すると見られている。2007年8月
眼球に対する作用
一部がビタミンAに変換され、ビタミンA活性を示す
・光障害による網膜保護
・毛様体機能調節
抗酸化作用
脂質の酸化防止
紫外線による皮膚の酸化損傷防止、炎症の抑制(活性酸素を抑える)
その他
抗炎症作用
サーカディアンリズム調節作用
悪玉コレステロール(LDL-コレステロール)の低下
動脈硬化の予防・改善
糖尿病性白内障の進行抑制
免疫賦活作用
ストレス等による皮膚の免疫力低下の抑制(抗ストレス作用) |
アスタキサンチン(『ウィキペディア(Wikipedia)』より)
ふつうは黄色いけれどオレンジ色、といったら、
卵だけじゃなくて、サツマイモも。
一週間ほど追熟させた安納芋を食べようときったら、なかはオレンジ色。
ふかし芋よりは焼き芋がよいということなので、
水分が多いのだろうと、乱切りにして、素揚げしてみた。

何も味付けしてないのに、食べてみたら、すごく甘い。


←鳴門金時のレモン煮。
まどくんが、コスレタスのおいしい食べ方を教えてほしい、ととれたてを持ってきたので、
魚肉ソーセージとコーンを入れて強火でさっと炒めた。

コスレタス(立ちチシャ)は、シーザーサラダによく使われる、歯ごたえのしっかりしたレタス。
エーゲ海のコス島うまれなので、この名がついた。
炒めてもゆでても、歯ざわりがしゃきしゃきして、おいしい万能レタス。
無農薬でも育てやすいので、まだだれもコスレタスを知らない頃から、
わが家ではよくつくっていた。
最近たべてなかったので、ほろ苦くて、なつかしい味がした。
最後まで読んでくださってありがとう 


 クリックを
クリックを
 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね 



 してね
してね 




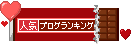 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ  クリックを
クリックを 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。








 クリックを
クリックを 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。