先日、玄関先に植えたばかりのヒヤシンスがもう咲いています。
ドアを開けるとよい香りがします。



このところ雨が近いのですが、名前の通り水が好きな水仙が
つぎつぎに開花しています。
一か月ほど前まで影も形もなかったところに、
黄色い花が並んで咲いています。










応援クリック してね
してね 


本文中の写真をクリックすると拡大します。
昨日の続きの、毎日新聞の「こうのとり追って:第4部・出生前診断」。
後半の3と4を紹介します。
最後まで読んでくださってありがとう
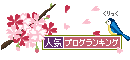
 クリックを
クリックを
 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね

ドアを開けるとよい香りがします。



このところ雨が近いのですが、名前の通り水が好きな水仙が
つぎつぎに開花しています。
一か月ほど前まで影も形もなかったところに、
黄色い花が並んで咲いています。










応援クリック



本文中の写真をクリックすると拡大します。
昨日の続きの、毎日新聞の「こうのとり追って:第4部・出生前診断」。
後半の3と4を紹介します。
| こうのとり追って:第4部・出生前診断/3 治療、対策 速やかに ◇母体を介し手術も 自治体超えた態勢整備必要 どうしても踏ん切りがつかなかった。一人は助かるけれど、もう一人は助からないかもしれない……? どうしてそんな決断を迫られなくてはいけないのか。 横浜市の会社員、佐藤浩生(ひろみ)さんは、おなかの双子が「双胎間輸血症候群」と診断されていた。双子の一方に血流と羊水が過剰になり、もう一方には少なくなる。「このままだと、2人の命にかかわります」と手術を勧められた。血流のアンバランスを改善するため、胎盤の表面でつながった双子の血管をレーザーで遮断するという。 佐藤さんを悩ませたのは「少なくとも1人が助かる割合は90%。2人とも生存は60%」という治療成績だった。夫は「打つ手があるんだから」と前向きだったが、「2人とも助けたい。他に選択の余地はないのか」と自問し続けた。 病室の机に置かれた手術の同意書は、何日も置きっぱなしになった。考えた末、決断してサインした。 手術は、内視鏡(直径最大4ミリ)を腹部に挿し入れ、モニター画面に映った胎盤表面を見ながら行われた。血管の接合部が見つかると医師たちが確認し合い、レーザーで焼いていく。下半身麻酔を受けた佐藤さんは、祈りながら画面を見つめていた。おなかの子に何が起こっているのか、自分の目でしっかりと見ておきたかった。 手術は成功し、羊水の量は正常に戻った。今年1月、帝王切開で双子の男児を出産。2人の顔を見て、やっと落ち着いた。「よく生まれてきてくれた。病気が早くみつかり、手術を受けてよかった」。結果がよかったからこそ言える、とも思う。金融機関に勤める佐藤さんはこれまで仕事中心の生活だったが、子どもの世話は楽しい。今度は双子の女の子がほしいと考えている。 ◇ ◇ 胎児の病気を生まれる前に治す「胎児治療」は、出生前診断によってもたらされた。1960年代に行われた胎児への輸血が最初といわれる。80年代の超音波診断装置の発達によって、胎児の画像を見ながら手術することも可能になった。 胎児治療の対象になるのは、放置すれば胎児が亡くなる場合や、生まれてからの治療では手遅れになったり、重い障害を残す場合に限られる。母体を介しての治療で、母親にもリスクが生じるためだ。 佐藤さんの受けたレーザー手術は、国内では10年前に始まった。11年末までに約750件が行われた。有効性が認められ、これまで自己負担だった手術費(約40万円)が胎児治療では唯一、4月から保険適用になる見通しだ。ただし、経験を積む必要があり、レーザー手術できるのは7施設にとどまっている。 250件以上のレーザー手術の実績がある国立成育医療研究センターの左合治彦・周産期センター長は「出生前診断の意義の一つとして胎児治療は重要。治療できる病気は限られているが、今後も新しい治療に取り組みたい」という。 ◇ ◇ 100人に1人と言われる先天性の心臓病が、出生前診断でみつかるケースも年々増えている。 横浜市の寺島美奈子さん(38)は4人の子どもの母親だ。次男(5)は生後3週間、3カ月、1歳半と3度にわたる心臓手術を受けた。外出に携帯の酸素ボンベが欠かせない時もあった。寺島さんは「毎日薬を飲み続ける必要はあるけれど、運動の制限もなく普通の生活を送れる。将来を考えられるようになった」とほほ笑む。 妊娠7カ月での健診。パクパク動く心臓を指さし、医師は「赤ちゃんの心臓が右寄りにある」と指摘した。寺島さんが見ても右寄りにあるとわかった。 小児病院で詳しいエコー検査を受け、重い心臓病と診断された。「おなかの中で死んでしまったら」と不安に襲われた。病気の状況や治療方針、術後の生活について説明を受け、「手術がうまくいけば元気になれるんだ」と、前向きに受け止められるようになった。看護師らも心配事の相談にのってくれた。 「事前に病気が分かって本当によかった。病気の知識や医療費の助成制度について出産前に情報を得られたし、病院に付き添う間に上の子どもたちをどうするかなど、家族の生活についても考えることができた」。寺島さんは振り返る。 胎児の心臓病診断に詳しい神奈川県立こども医療センター新生児科、川滝元良医師によると、同病院で心臓病が出生前に見つかったケースは93年に10人以下だったが、10年では140人以上だ。生後24時間以内の緊急手術も増え、救えなかった命も助けられるようになった。 しかし、妊婦健診で異常を見つける技術を持った医師が少ない地域もあれば、見つかっても、精密検査できる態勢が十分にない地域もある。「見つけるだけでは妊婦を不安にさせるだけ。県単位を超えて、精密検査できるネットワークづくりが必要だ」と指摘する。=つづく ◇優れた日本の超音波診断装置 エコー検査は形の異常を見つけるのに優れている。専門医によると胎児の病気では、腹壁破裂、小脳の萎縮や水頭症など脳の異常、消化管閉鎖などの診断ができる。 超音波診断装置は日本が世界をリードしてきた。1960年に日本メーカーが世界に先駆け装置を製品化した。76年に鹿児島県で誕生した五つ子の診断にも使われた。 80年代以降、血流の向きや速度が分かるようになった。これにより心臓病の診断精度が向上したほか、胎児の貧血を血流速度から診断できるようになった。メーカーの東芝メディカルシステムズは「人体の機能が分かるようになったのは画期的だった」という。 出生前診断で分かるのは、胎児の異常の50~60%といわれる。例えば腎臓の大きさが正常でも、尿をきちんとつくれるかは判断できない。精神の発達具合もわからない。 ============== ■ご意見お寄せください 感想、意見を募集します。郵便は〒100-8051(住所不要)毎日新聞生活報道部宛て、メールは表題を「こうのとり」としkurashi@mainichi.co.jp、ファクス03・3212・5177へ。 毎日新聞 2012年3月29日 |
| こうのとり追って:第4部・出生前診断/4 長く生きられなくても ◇染色体異常、根本治療なく 「がんばれるところまで」 じきに生まれる赤ちゃんの姿を、お兄ちゃんにも見てもらいたかった。2年前の8月の暑い盛り。妊娠28週だった東京都八王子市の公務員、吉武麻紀さん(38)は、地元クリニックで1時間にわたるエコー検査を受けた。夫の泰三さん(38)と長男の広太くん(12)が笑顔で囲んだ。だが医師の表情は曇っていた。「髄液が頭にたまる水頭症です。死産の可能性もある」。別室で宣告された。 羊水検査をすると13番染色体の一部が欠けていた。「運良く生まれても、産声をあげるかどうかわかりません」と言われた。麻紀さんはそれでも「がんばれるところまでがんばろう」と決意した。子宮外妊娠の経験から妊娠しにくい体質。この機会を大切にしたかった。 10月、都立小児総合医療センターで帝王切開手術。「あー」。か弱い産声が響いた。「良かった。息をしている」。立ち会っていた泰三さんの目から涙があふれた。 小さな命を「美紀」と名付けた。水頭症に加え、心臓にも病気を抱えていたが、頭部の手術を経て1カ月後にはNICU(新生児集中治療室)からGCU(回復期治療室)に移り、人工呼吸器も外された。夫婦は毎日欠かさず病院に通った。麻紀さんは冷凍母乳を届け、泰三さんは毎晩30分美紀ちゃんを抱っこするのが楽しみだった。仕事疲れで抱っこしたまま眠ってしまうこともあった。 体調のよい日は笑ったり怒ったり、表情が豊かだった。看護師からは「ミラクル美紀ちゃん」と呼ばれた。麻紀さんも泰三さんも「家に帰れるのでは」と奇跡を願ったが、容体は悪化した。 昨年3月18日。家族が病院に集まった。美紀ちゃんに触れるのを禁じられていた広太くんは、初めて妹を抱っこした。美紀ちゃんは兄の顔をじーっと見て、最後は眠るように息を引き取った。出産時2732グラムだった体重は、6キロ近くになっていた。 麻紀さんはまた赤ちゃんが欲しいという。でも「羊水検査はもう受けないと思う」。中絶のために調べているような気がするからだ。「命は奇跡。子供が生きていればそれだけで幸せだとわかった。美紀は5カ月しか生きなかったけど、一生分のことを教えてくれた」 同センター臨床遺伝科の吉橋博史医師は「染色体異常は根本的な治療法がないので、プロセスが大切になる。手術などの重要な決定を自分たちで行ったという思いがあると、お子さんを亡くしたあとでも立ち直りにつながりやすい」と話す。 ◇ ◇ 1歳2カ月の長女は、体重がまだ3500グラムしかない。栄養剤や薬を混ぜたミルクを、鼻から胃に通された管に少しずつ流す。「心臓に負担をかけないように、ミルクの量は制限されている。早く大きくなってほしいのですが」。群馬県高崎市の女性(37)は言う。 女児は13番染色体が1本多い「13トリソミー」と診断され、約2000グラムで生まれた。退院後は自宅で過ごしている。成長はゆっくりだが状態は安定しており、元気な泣き声を上げ、笑うこともある。 妊娠8カ月のとき。エコー検査で「あれ?」と声を上げた産婦人科医は、申し訳なさそうな顔をするだけで何も言わない。紹介された小児専門病院で、染色体異常の可能性を指摘された。毎晩、インターネットで情報を集め、涙が出た。「産まない」という選択肢はなかったが、周囲から「看護師の仕事を続けられなくなる」と言われると動揺した。 次の診察で、延命治療の意向を尋ねられた。生まれても自力で呼吸できない可能性があるという。人工呼吸器をつけるか、強心剤を使うか、心臓マッサージを施すか。出産予定日が迫り、重い選択に結論を出さなければならなかった。 女性には長男(4)がいるが、複数の流産経験があった。「生まれてこられるのなら、その子ができるところまでがんばってほしい」。医師から「この病気の1年生存率は10%」と聞かされていた。「長く生きられないのに苦しい思いをさせるのは」と考え、呼吸器をつけない選択をした。夫(38)も同意した。 昨年1月、帝王切開で出産。女児は呼吸していた。長くは生きられないと覚悟していたが、1歳の誕生日を迎えられた。しかし、まだ首は据わらない。「泣いていると長男があやしてくれたり、かわいがってくれるので、家に連れて帰れたのはよかった。でも先が見えない不安もある。家のローンもあるし、働きに出られれば気分的にも違うのですが」と漏らす。預け先はなく、「何かあったら怖い」と話す実母にも頼れない。 昨年、通院先の子供病院が、トリソミーの子がいる親のグループをつくってくれた。「同じ立場の親に会って、少し吹っ切れた」 同じく1年生存率が10%程度とされる「18トリソミー」では、10年以上生きている人もいる。「18トリソミーの会」の桜井浩子代表は「その子に応じた治療が受けられるようになり、退院できる子も増えている。しかし親子だけでは行き詰まる。医師、訪問看護師、患者会などが支援する態勢をつくることが必要だ」と指摘する。=次回は4月2日 ◇新生児の0.6%に発生 人の精子や卵子には、染色体が1本多かったり少なかったり、一部に欠損や入れ替わりがあるものが含まれている。こうした精子や卵子が受精すると、染色体異常が起こる。だれにでも起こる可能性があり、流産の原因になる。新生児の0・6%に発生するとされている。 数の異常で知られるのが、21番染色体が1本多い21トリソミー(ダウン症)で、1000人に1人の割合で生まれる。 13トリソミーは1960年に初めて確認された。発育不全で生まれ、生後1カ月以内で約半数、1年以内に90%以上が亡くなるというデータもある。脳や目の異常など症状は多様で、心臓病を合併していることも多い。 ============== ■ご意見お寄せください 感想、意見を募集します。郵便は〒100-8051(住所不要)毎日新聞生活報道部宛て、メールは表題を「こうのとり」としkurashi@mainichi.co.jp、ファクス03・3212・5177へ。毎日新聞 2012年3月30日 東京朝刊 |
最後まで読んでくださってありがとう

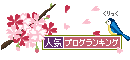
 クリックを
クリックを 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。明日もまた見に来てね




























































