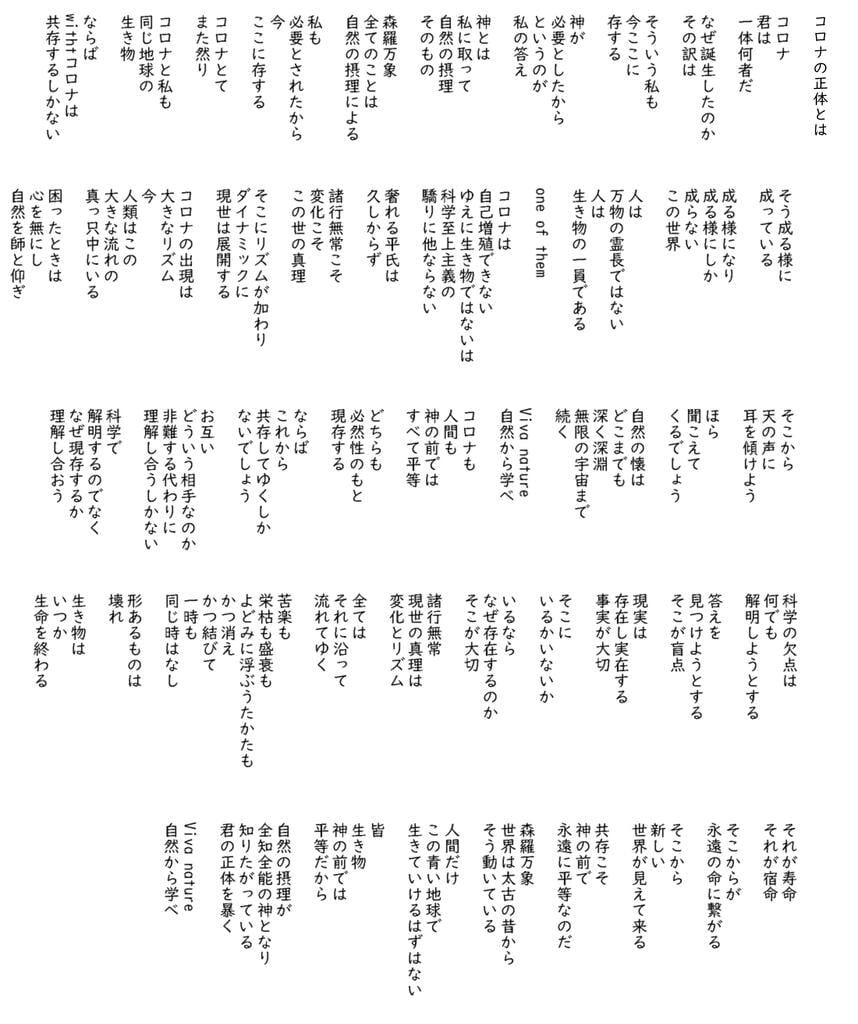
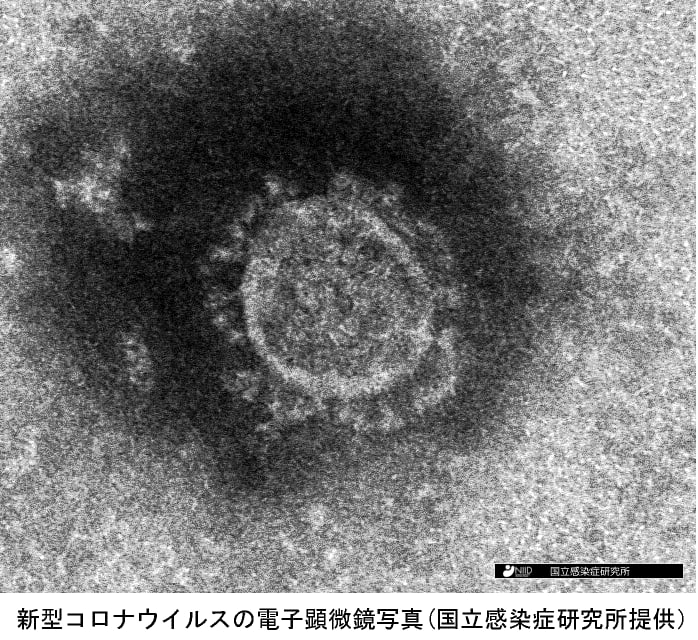
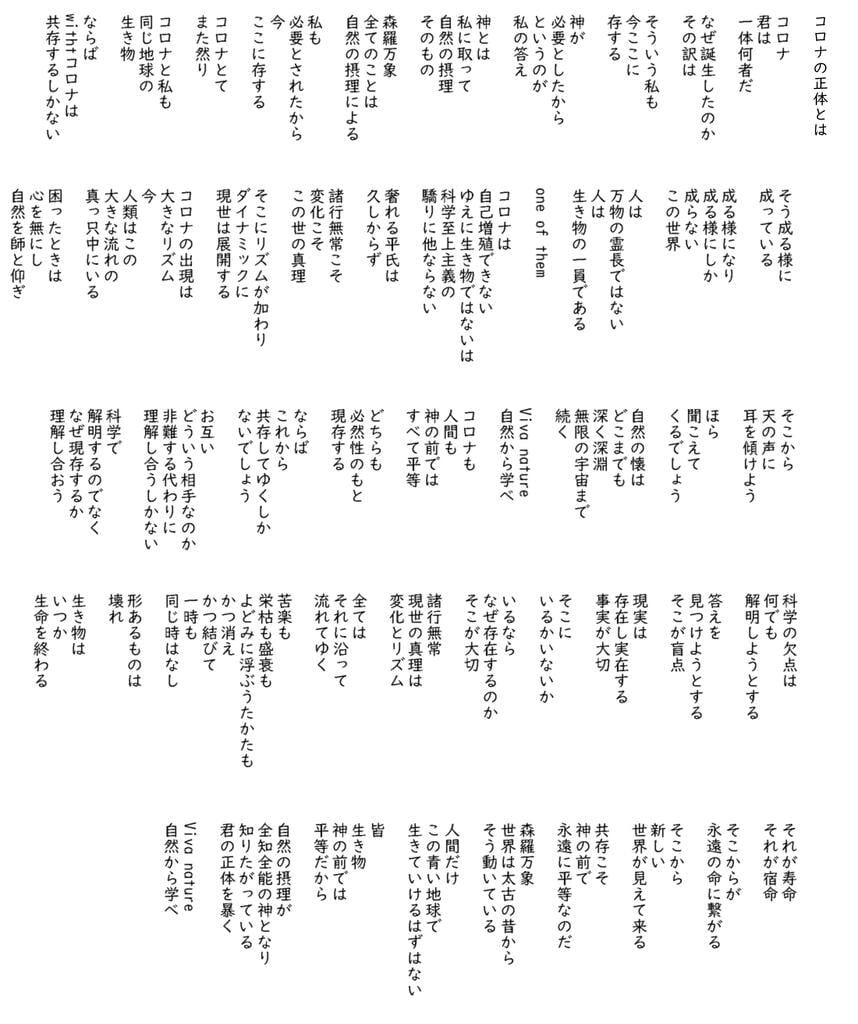
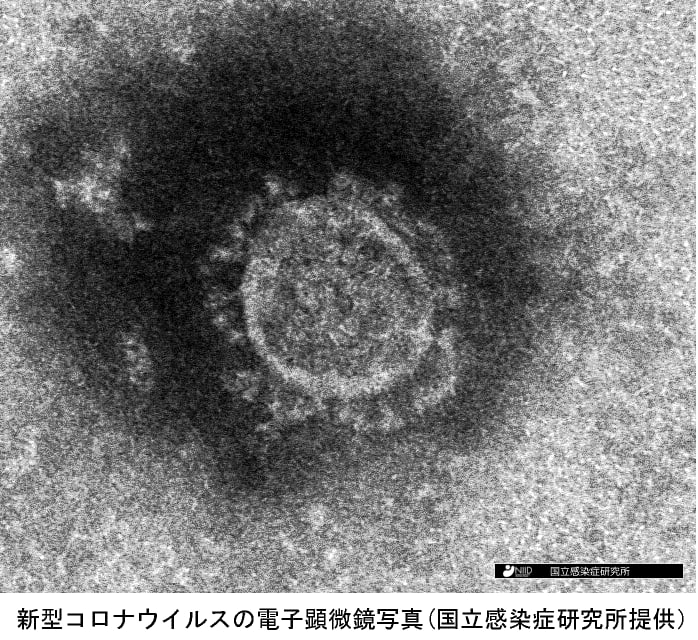
コロナ元年10月7日
平井大臣は会見で、先週、河野行革担当大臣と萩生田文部科学大臣とオンライン教育に関する意見交換会を行ったことを明らかにした。この中で平井大臣は、小中学校でパソコンやタブレットなどが1人につき1台普及するようなデジタル環境が整った段階で、教科書制度を見直してデジタル教科書の導入を提起した。
コロナ元年10月6日
先日、中国から直接輸入した胡蝶蘭の種が発芽しました。と、ブログに書いたと想いますが、それは、どうも種が偽りものだったようで、私が調べた範囲では、国内では発芽は殆ど難しいと書いてありました。ですので、中国なら種から育てるのかと想っていましたが、やはり案の定、発芽したのは、違う種だったようです。ですから、胡蝶蘭ではない種を胡蝶蘭と偽って販売していたようです。悪質ですね。
下の写真を載せておきましたので、百聞は一見に如かずですが、胡蝶蘭の葉ではないことが、よくわかります。土に植えてあるものを写真に撮りましたので、参考に見ていただけるとわかりますが、これは、ジャーマンアイリス類の葉っぱではないかと想われます。中国輸入は気をつけないと、このような偽物を送られてくる場合もあります。今回は見事騙されました。
幸い、200円でしたので、いい勉強になりました。地に植えてありますので、いまとなってはどんな花が咲くか楽しみです。中国輸入はくれぐれもご注意ください。
※ヒオウギという花も葉がよく似てます。どう見ても、胡蝶蘭には見えませんね。

コロナ元年10月3日
WITHコロナの真っ只中、ここ数日、学問の自由の危機が叫ばれ始めています。日本学術会議の推薦した6人が菅総理から任命されなかったのです。学問の一大事と学術会議が色めいたのも致し方ないことだと想います。
学術会議は科学に関する重要事項を審議したり、研究の連絡をすることを目的にした科学者の組織です。政府に対して提言をするのが役割の一つで、210人の会員は非常勤特別職の国家公務員です。この210人の半数の105人が3年ごとに入れ替わります。
今まではすんなり推薦が通っていたのに6人だけが今回落とされました。しかも、その理由は現状では、何も明らかになっていないようです。そこがまず、問題です。
学問研究についてはその性質からは本来は自由に委ねられるべきです。明らかに反倫理的な人体実験や人類の将来に対する危険となる事等は一定の規制が必要だという事はわかります。
憲法、「第二十三条学問の自由は、これを保障する。」と、あります。この憲法の精神を守って欲しいと想いますが、今回の処置を見ていますと、まさに学問の危機的状況だと想います。
これでは、本来、自由であるはずの学問も時の政権に都合のいい研究ばかりをすることになってしまい、学問でいう真理の追究が危うくなってしまいます。
法律では総理から任命されることになっていますから、この法律がある限り法的には任命権を総理大臣が握っていますので、法の趣旨に照らして任命されないこともありうるでしょうが、こと、憲法ではしっかり保証されていますので、最高裁まで争うことになれば憲法論から、倫理面で問題のある研究等を除いては任命がOKとなるはずだと想いますが、今回はまだ、理由を知らせれてないので、どこの研究で落とされたかは定かではありません。
いずれにせよ、この法律では理由により違法となることも、十分ありますので、最終的には裁判で争われることになるでしょう。それにしても、しっかり理由を言うべきだと想います。
コロナ元年10月2日



デジタル化は、コストもかかるのも事実であるが、やると決めたらそこをクリアーしてやらないと、いつまでたってもできない。戦後の農地改革を思い起こすとそれが分かる。GHQの命令で小作人はなくなった。これくらいの覚悟で取り組まないと、また、もとの木阿弥になってしまう。国際社会で先進国とお付き合いしていく上で万難を排してこれを乗り越えるしかないだろう。
だから、やることを前提に、どう、やっていくかのハウトゥーを考えるべきだ。時代を変える時はこんなこと言っていたら、いつまで立っても変わっていかない。変えていく中で変えてはいけない不易なものを求めていくのだ。芭蕉の不易流行はこんなところに生きている。不易と流行は一体だと芭蕉もいっている。ここが大事。
やっていく中で課題は何なのだ。一つずつクリーしていくしかない。そして、落ちこぼれていく国民をどう手当てしていくかである。ここでは、公助が生きてくる。ペーパーの教科書がなくなることはないのだから。まさに、今はそういう時代になっているのだと、国民は認識すべきだ。そう、国民を追い込む施策も考えたい。
男子の育休も同じだ。いつの時代も変えてゆくことには抵抗がある。だから、尻込みしていてはだめだ。その根底には考え方も変えてゆく必要がある。広くビジョンを俯瞰し、その方向性を見定めて、歩きながら考えてゆかないと変革はすすまない。その時、弁証法的考え、すなわち正反合が生きてくる。弁証法は動的に物事を考える時には不可欠な行動理念なのだ。弁証法=共産主義の亡霊から脱却してもっと、広く考えてほしい。
デジタル化時代は、心配するな。却って人間とは何かを問われる時代になる。人間の本来持つ素晴らしさがあらためて具現化してくる時代でもある。不易流行はいつの時代でも真理である。
広いビジョンを持ってデジタル化を進めていってほしい。この時大切なことは、必ず乗り遅れる保守的な人間はいるので、そこをどう救済していくかが思いやり社会では問われるキーワードだ。国としてそこは十分考えていきたい。今は読み書きそろばんから、読み書きITの時代に変化しつつあるのだ。
銀行でも、ネット取引の重要性が増している。大手銀行ではネット取引に移行させる仕組みができつつある。変化の時代は先行性が有効だ。誰よりも早くこのことに気づいて変化して行く必要がある。年齢は関係ないのだ。シニアこそ長い経験をそこに注いて行ってもらいたい。不易流行は真理ですぞ!