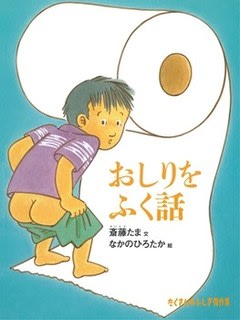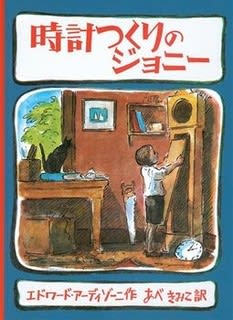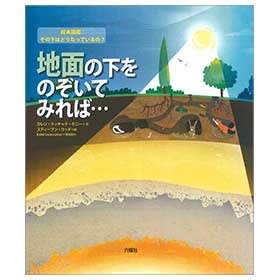この話もいくつかのバリエーションがあるが、治病の薬として、猿の生肝を取りに竜王から遣わされた海月が、猿を騙して帰る途中、その目的を洩らしたため、猿に生肝を樹の上に置き忘れたと騙されて逃げられるという話。
古代インドの説話集パンチャタントラにも類話が見えるという。
・サルの心臓(オクスフォード世界の民話と伝説10 アフリカ編/キャスリーン・アーノット 矢崎源九郎・訳/講談社/1978年改訂)
東アフリカ、スワヘリ族の話であるが、ここでは生肝が心臓になっている。
サルが木の実を海にほうりこんでサメの餌にしてあげ、サルとサメは仲良くなり、かわりに海の自分の家に招待する。
ところが途中でサメの王さまが死にそうで、病気をなおすためにはサルの心臓が必要だということを話してしまう。
驚いたサルは、陸の木の上に心臓をおいてあると嘘をつき、難を逃れる。
親切にしてあげたのに、心臓が欲しいと言われたサルはどれだけ驚いたことか。
・サルの心臓(アンドルー・ラング世界童話集12 ふじいろの童話集/西村醇子監修/東京創元社/2009年初版)
同じ「サルの心臓」でも、ラングの世界童話集では、二つの話があわさっているようで、大分長い話になっている。
サルがサメにイチジクの実を木の枝から落としてあげるが、このときのサメの言い分が「50年ものあいだ魚ばっかり食べているといいかげん、ちがうものが食いたくなる。塩っ辛い味にはもうほとほとあきてしまったよ」ともっともらしい。
・サルのきも(子どもに聞かせる世界の民話/矢崎源九郎編/実業乃日本社/1964年初版)
タイの話ですが、オチが楽しい。
ワニが、奥さんの病気を直すため、サルの生き肝をいただこうとして、サルを川にさそいこむ。しかし、サルはきもを忘れてきたといって、山へもどっていくが、イチジクをもってきて、これが生き肝だよと言ってワニにわたす。そのイチジクを食べるとワニの奥さんの病気がけろりと治ってしまう。
信じる者は救われるというが、イチジクを食べると病気が治るというオチは、ほかの国にはみられないようだ。
・くらげ骨なし(ちゃあちゃんのむかしばなし/中脇初枝・再話 奈路道程・絵/福音館書店/2016年)
同様の話が日本各地でもみられます。
高知県の話で、くらげに骨がないという由来話にもなっています。
竜宮のお姫さまが病気になって、直すためにはサルの生き胆より薬がなく、くらげがサルを連れにでかけます。
竜宮につれていかれたサルが、生き胆を岩の上に干してきたといって、陸へあがって、木の上にのぼります。
サルを陸までつれていったのはくらげ。くらげがサルに逃げられ、命の代わりに骨を抜かれてしまいます。
いずれも川や海が舞台というのが共通しています。