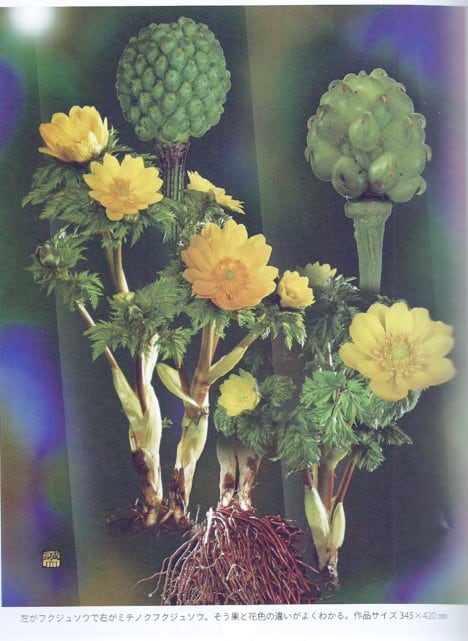(上と下)隋身門(ずいしんもん):国指定重要文化財(平成14年12月指定)、宮城県重要文化財指定(昭和34年)。三間楼門で、銅板葺き、朱塗り。
この門は、国道45号線からの表参道である表坂(男坂)とも呼ばれている参道の社号標「東北鎮護鹽竈神社」や石鳥居が建つ所から202段あるという石段を登ると到着する門である。
元禄2年(1689)5月9日(新暦6月25日)早朝、芭蕉はこの石段を登って鹽竈神社に詣でたそうです。
http://www.kankoubussan.shiogama.miyagi.jp/jinja/shiogamajinja.html [志波彦神社・鹽竈神社~鹽竈神社:御祭神ならびに御由緒:塩竈市観光物産協会]




(上と下)唐門及び廻廊(国指定重要文化財):「唐門」とは通常、唐破風をもつ門を指すが、当神社の唐門は切妻造りの四脚門で、唐破風をもたない。重要文化財指定名称は単に「門」となっている。門と左右に接続する廻廊ともに銅板葺き、朱塗りとする。


(上)鹽竈神社の手水舎


(上と下)文化灯籠:文化6年(1809)伊達9代藩主周宗公が蝦夷地警護の凱旋の後奉賛として寄進したものだそうです。塩釜市指定文化財。



(上と下)左右宮拝殿(廻廊・端垣と併せて平成14年12月、国の重要文化財に指定)

(左側)右宮拝殿:経津主神(ふつぬしのかみ)を祀る。(右側)左宮拝殿:武甕槌神(たけみかづちのかみ)を祀る。安産守護・延命長寿・海上安全・大漁満足・家内安全・交通安全・産業開発の神として、全国から信仰されているそうです。

(上)鹽竈神社左右宮本殿:全国的にも珍しい三本殿二拝殿という社殿構成、壮大で整然とした配置等が江戸中期の神社建築として高く評価され、昭和34年に宮城県重要文化財に指定され、平成14年12月には左右拝殿、左右幣殿、廻廊と共に国の重要文化財に指定されたそうです。

(上)右宮拝殿側から見た左右拝殿&(下)左宮拝殿側から見た左右拝殿(左右本殿はこの裏側に鎮座する)。



(上)左宮本殿・左宮拝殿の隣にあるいぼ神の鎮座する所。(下)桜の木がありましたが、未だ堅い蕾でした。



(上2つ)文治の灯籠:文治3年(1187)7月10日、奥州藤原三代秀衡の三男泉三郎忠衡により寄進されたものとのこと。説明碑は奥の細道紀行300年記念建立。
松尾芭蕉「奥の細道」塩竈の章、原文:早朝、塩がまの明神に詣。 国守再興せられて、宮柱ふとしく、彩椽(さいてん)きらびやかに、石の階(きざはし)九仞に重り、朝日あけの玉がきをかゝやかす。かゝる道の果、塵土の境まで、神霊あらたにましますこそ、吾国の風俗なれと、いと貴けれ。(中略)神前に古き宝燈有。かねの戸びらの面に、「文治三年和泉三郎奇(寄)進」と有。
五百年来の俤(おもかげ)、今目の前にうかびて、そゞろに珍し。渠(かれ)は勇義忠孝の士也。佳命(名)今に至りて、したはずといふ事なし。誠(まことに)「人能道を勤、義を守べし。名もまた是にしたがふ」と云り。
(上記 奥の細道 現代文は 下記のとおり)。
翌朝早く塩釜の明神を詣でた。この神社は 藩主が再建なさって、宮柱が太く、彩りをつけた垂木は輝いている。石の階段は長く、差し込む朝日が玉垣をきらきら輝かしている。このような、道の果てのような辺境の地まで神の霊験があらたかでいらっしゃることこそ、わが国の古来からの風習なのだと、大層尊く思われる。(中略)神前に古い素晴らしい灯篭がある。鉄の扉に「文治三年 和泉三郎 寄進」と、書いてある。500年もの前の面影が、今もこうして目の前に浮かび上がって珍しい。彼、和泉三郎は、勇気、忠義、孝心を全て備えた立派な人物である。その高名は今にまで至って、慕わない者はない。人は道にかなった生き方をして義理を守るべきである。そうすれば「名声もついて回る」と古人も言っている。
和泉三郎とは、平泉の藤原秀衡三男、忠衡のこと。妻は信夫荘司・佐藤基治の娘。異母弟は泰衡。庶長兄は国衡。平泉中尊寺の北西「泉ヶ城」が居城。文治3年7月は、奥州藤原氏に対して 鎌倉幕府から、義経を引き渡すよう求められていたころである。
忠衡による塩釜神社へのこの燈篭寄進は、平泉の平穏と 義経の無事を 懇願しての行為であったことが推測される、と習った。(妻のブログより転載)。

(上と下5つ)別宮拝殿(この裏側に本殿がある):朱漆塗入母屋造銅板葺きで、宝永以降20年に1度御屋根葺替の式年遷宮の制度が設けられ現在に至っているとのことです。幣殿、廻廊と共に昭和34年に宮城県重要文化財に指定され、平成14年12月には国の重要文化財に指定されたそうです。鹽老翁神(しおつちおぢのかみ)をお祀りしているそうです。



(上と下)別宮拝殿:朱漆塗りの柱などが真新しい。テレビでこの塗り替えの模様が紹介されたそうです。私たちは昇殿しませんでしたが、「漆塗りたて」の注意書きがありました。






http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BD%E7%AB%88%E7%A5%9E%E7%A4%BE [鹽竈神社:Wikipedia]