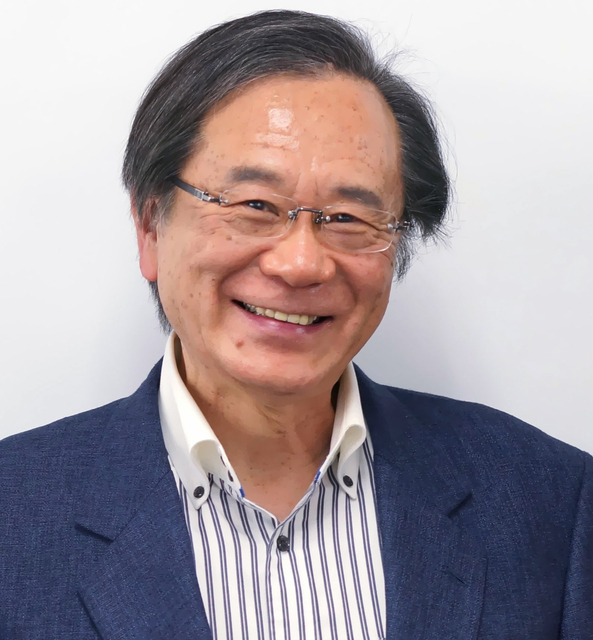若手の第二ヴァイオリンのほかは、みな著名なソリストや教師である「ミケランジェロ弦楽四重奏団」の銀座王子ホールでのベートーヴェン、
作品130(13番)は、1826年の初演時、あまりに長大で難解なフィナーレの6楽章=「大フーガ」が不評で、別のフィナーレをつくり改定し、大フーガは独立させて作品133としたわけですが、きょうのミケランジェロ四重奏団は、ベートーヴェンの意図通り、フィナーレ(第6楽章)を大フーガに戻しての演奏でした。
外から形として見れば、大フーガは、全体とのバランスを欠いているように見えますが、1楽章の四人の親密な対話、2楽章のウキウキする推進、3楽章の優しい色香、4楽章の懐古ないし再会のよろこび、5楽章のなつかしき陶酔と耽美の後、痺れるほど強靭な大フーガが来なくては、やはりこの曲(13番)は終わりません。
ベートーヴェンの到達した世界がいかに前人未到のものか、人間の内的精神の豊穣、もうなんの囚われもない自然の極みです。それにしても、最晩年になってもベートーヴェンは枯淡などとは無縁で、ますます色っぽい。深い精神とは色香を伴うものと分かります。芸術とはまさしくエロースそのものです。
強烈なフィナーレの大フーガ、王子ホールに虹がかかり、ムゥサがエロースと共に降りたったよう。昨年12月17日、ポール・ルイスによるピアノソナタ32番のときの再現です。
演奏は、第一ヴァイオリンが主導するオーソドックスなスタイルで、その音の強さと鋭さが6番の時にはかなり気になりましたが、13番では慣れもあり、曲想の違いもありで、全体の名演の前にはさほど気にならなくなりました。実演ならではの熱演で痺れましたが、粗野になる部分は全くなく、熟達の音楽家ならではの感動の名演奏。 うれしくてたまらない。
それにしても315席の王子ホール、弦楽四重奏にはピッタリです。贅沢の極みですが(妻と交代で、前から6番目の真ん中と、後ろから4番目の中央少し右寄りで聴きましたが、どちらもよい)。
武田康弘
写真は、演奏後のサイン会で。
あまりにも暗い場所で、iso6400での撮影 ソニーRXー1R